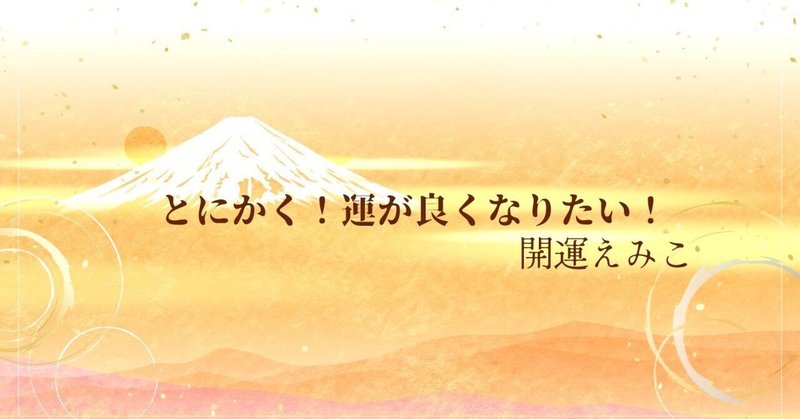
神仏さまとのお付き合い(基礎)
「プレゼント記事」のリメイクです
どこかで読んだ方ももう一度どうぞ^^
1「マイ神社」のススメ
◇一番最初はご先祖様
パワースポットを巡っても
「見えない世界に味方」は出来ません。
一番最初に手を合わせるところは!
まずはご自分の「ご先祖さま」です!!!
ご先祖さまも神様です
古神道では、人は亡くなった後
「遠津御祖神(とおつみおやがみ)」になり、
その家系の「護り神」になるとされています。
でも、近いご先祖さまは
まだまだ「護り神」までにはなっていません。
だからこそ仏道の
「ご供養」が必要になるわけです。
「お墓参り」や「先祖供養」です
これらを心を込めて行うことで、
ご先祖さま達の魂を慰め、
苦しみから解放し、
そのうえ自分も功徳を得ることが出来、
しかも
亡くなった方は「護り神」さまへの道を創るという
スグレモノです。
神道も仏教もきちんと関連しているのです^^
まずは「マイ神社」を作りましょう。
同時進行で「先祖供養」ですね。
*****
◇大事な「産土さま」
「産土さま」は生まれた場所、
産院の「土地神さま」
「初宮参り」の神さまなどになります。
住んでいるところと生まれた場所が違う
というのはよくあることです。
どこで生まれたのかわからなくなってしまった、
などもあるかもしれません。
そんな時は
「今住んでいる地域の土地神さま=管轄の神社」でも大丈夫です。
産土の神さまも、土地神さまも
そこに住んでいる人を護ってくれるだけでなく、
「願いの事の総合受付窓口」になってくれる神さまです。
パワースポット巡り、ではなく
「生まれた土地の神社」
「今住んでいる土地の管轄の神社」
に足しげく通いましょう。
これが「マイ神社」ですね。
お引越しをされたら
その土地の神さまにきちんと挨拶をすることもお忘れなく。
産土さまはご実家の近くであることが多いですね。
小さなころ「初宮参り」にも行っているかもしれません。
「初宮参り」の神さまは
あなたが最初にご縁をいただいた特別な神さま。
古神道では「三歳までは神の内」と言われ、
産土さまに護られて過ごすと言われます。
あなたに記憶が無くても、「魂」は覚えている。
それが「産土の神さま」なのです。
産土神社がわかっている方は、
近くなら頻繁に行きましょう。
遠くて通えないのであれば
産土さまと「同じ神さまを祀っている近くの神社」に
通うとよいですよ
*****
◇次は土地神さま
地域の土地神さまの役割は
「地域の土地一帯を守護」です。
神さまにも「護れる範囲」のようなものがありまして、
土地神さまは言うなれば
「支店の窓口」のようなもの。
一番近くで聞いてくれる存在です。
土地神さまのその上に「総鎮護」などといわれる
ちょっと大きな範囲を護ってくださる神さまがいます。
そしてなんといっても日本の神社のトップは
「伊勢神宮」です。
ただしこちらは「国家」の繁栄を祈る場所。
個人のお願い事には不向きな神社です

*****
◇崇敬神社(すうけいじんじゃ)
昔からなんとなく通っていた、とか、
「その神さまが好き」
ご縁を感じる神様仏様
こちらは本当に「好き」の気持ちでお詣します
そして、神さま方にも
「ザイオンス効果(単純接触効果)」が有効です
お好きな神社であれば、
最低でも年に2回は行きましょう。
年に一度であれば、
正式参拝や奉納をしてくださいね。
(奉納とはお酒や縁起物などの物的なものをささげることです。)
*****
見えない世界に味方を作り、
神さまのご利益をいただきたいのであれば、
1・まずは自分のご先祖さま方への感謝の気持ちを持つ
2・産土さまや土地神さまへ通い詰める
3・縁(えにし/えんよりも濃い関係性)と感じた崇敬神社
へ定期的なご挨拶をする
ことが大事です。
大前提です。
それとともに「ご祭神ネットワーク」を使いましょう。
伏見稲荷であれば、
出先のお稲荷さんには必ず顔を出す、
出雲大社であれば、
「スサノオノミコト」の祀られている神社に通う
などですね。
あなたも「マイ神社」へ通い詰めて、
見えない世界に味方をつくり、
「ご利益をいただける関係性」の土台を作っていきましょう(^^♪
観光で1回行った神社、
パワースポット巡りでいった神社の神さま
有名だから、
皆行くから、
そこが良いとは限りませんよ。
*****
◇神社と仏閣は役割が違う
神さまも仏さまもわたし達の祖先であると考えてください。
神さまは神話の時代
仏さまはそれ以降
日本の神さまと呼ばれる存在が神社です。
こちらは「空港の窓口・違う世界への入り口」のようなもの
次元の違う「大いなる何か」とのつながりを
感じるための場所であり、存在です。
「生かされている自分」を感じ
「生かしていくれている何か」への感謝を
わかりやすく、やりやすくシステム化している場所です。
人生の大きな夢や大きな目標を叶えるには
やはり神社への参拝がオススメです。
仏さまは寺院、仏閣ですね。
こちらは「市役所の窓口」のようなものです。
「肉体を持って三次元で人としていかに生きるかの指針」
これらを教え、諭し、導いてくださる存在です。
病気平癒、現世利益などは寺院の方が得意です。
ご先祖さまへの感謝は基本は仏閣
「菩提寺」(先祖が生前崇拝していた教え)でします。
お寺やお墓がわからない、という場合は
ご自宅でもな可能です。
神社も仏閣も
「生きている人間には必要な場所」であり
「大切な護りの力」です。
どちらが上、下、ではなく役割の違いです。
日本はもともと「神仏習合」でした。
時の明治政府の「神仏分離令」で分離がおこります
これにより、神道国教化が表明され、
古代から続く神仏習合が禁止されました。
神道が保護される一方で、
廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)という
仏教弾圧の風潮が生まれ、
各地で寺院や仏像が破壊されるなどしたそうです。
なにしてくれてんねん、って感じですね。
第二次世界大戦後に日本の力がそがれた云々の
陰謀論があります。
わたしも勉強不足の時は
「第二次世界大戦」からゆがんだんだ、と思ってましたけど
いろいろ弁上していくと
そうやら「明治維新」からですね。
ここからもう
日本の方向性は決められていたのではないか?
と思います。
陰謀論もどこかで書きたいわ・・・。

*****
2「神社仏閣参拝」の基本のお作法
「形式」よりも「素」が大事。
普段のあなたの「在りよう」が大事です。
参拝の服装は
「とても尊敬している目上の方、
偉い(と自分が思っている)方
そのお宅にお邪魔する時の服装」にしておくと間違いないです。
地元の神さまへのご参拝だとしても
「失礼のない身だしなみ」で行きましょう。
マナーとして
人のお家の前やお庭で大声でおしゃべりしたりもしません。
庭のモノを家主の赦しなしに持ってきたりもしない。
参道のど真ん中を騒ぎながら歩いたりもしない。
庭の木にいきなり抱き着いたりもしませんねww
「普段のあなたの在りよう」とは
つまり、そうゆうことですww
*****
◆参道
「真ん中は神さまの通る場所なので端を歩く」
これも良く聞きますが、
わたしはどちらでも良いと思っています。
「歩道」を歩くとき、
「ど真ん中」を歩いたらちょっと迷惑では無いですか?
「すれ違いやすいように道なりに脇を」歩きますよね?
それと同じことです。
お祭りや、お正月の人がたくさんいる時に
真ん中が歩けないとか、困るじゃない?
その時々に
「道なりに」「流れに沿って」進めばよろしいと思います。
◆手水舎
手水舎と鈴祓いは
コロナ後の今は場所によってはあったり、無かったりです。
手水舎の作法は神社でも仏閣でも同じ。
右手、口、左手、柄杓の順で心身を清めます。
まずは一礼を捧げてから手と口を清めます。
右手に柄杓を持って左手に水をかけたら、
左手に持ち換え
右手と口をすすぎ
右手に持ち換え左手
柄杓の柄
この順で清めます。
この一連の動作を、
最初に汲んだ一杯の水で行います。
口をすすぐ際には柄杓に直接口をつけません。
右手に水を注いで行います。
濡れた手は拭いても拭かなくても良いです。
拭く場合であれば
「それ用」のハンカチなどを用意しておきます。
トイレで使うハンカチと同じハンカチで良いのか?
せっかく清めたのに、
自分のハンカチでまた汚れを憑けて良いのか?
という話があるんですよ。
わたしは「パタパタ」っとしてますwww
*****
◆神社の基本の参拝
神社の参拝は14時までに
なるべく午前中にうかがいます
鳥居を境に、境内は神域とされています。
くぐる前には必ず一礼して入りましょう。
進むときは道なりに端を歩きます。
場所によっては「右側通行」など指定されていますので
そのように、進みましょう。
鳥居をくぐったら、
「来ましたよー」の挨拶やお願い事などを心の中でしていきます。
そして、手水舎があれば手と口を清めます。
拝殿に着いたらお賽銭を入れ、鈴(鐘)があれば鳴らし
お賽銭を入れます。
神社では、「二拝二拍手一拝」が基本の参拝方法です。
神さまへの敬意を込めて深いお辞儀を2回した後、
胸の前で2回柏手を打ちます。
古神道では八拍手、または四拍手とされます。
わたしは四拍手をおススメ。
二拍手は神さまに、
残りの二拍手は自分の胸の前で小さく打ちます。
住所や名前を一緒に添えるとも言われますが、
初めての場所なら「歩いてる最中に」自己紹介してください。
住所氏名+
「近くに参りましたのでご挨拶に立ち寄りました」ですね。
通われている場所であれば必要ありません。
拝殿の前では、
道々相談やお願いしたことに
「そんなわけで、がんばりますので応援よろしくお願いします」
などの決意表明をしていきます。
帰りも鳥居ごとに振り返り一礼しながら戻ります。
*****
◆仏閣の基本の参拝
寺社に参拝するときも、
ふさわしい服装で午前中の時間帯に行きます。
お寺の入り口には山門があります。
山門とは俗世との境を表す門です。
山門をくぐるときは敷居を踏まないようにします。
山門の前では、合掌とともに一礼。
合掌とは、胸の前で手を合わせる作法のことです。
宗派によって形式は異なりますが、
お寺で礼拝する際の基本となり、
仏さまと一体になることを表しています。
仏閣では手を合わせるときには、音を立てません。
山門を通ったら「来ましたよー」と心の中でご挨拶、
お願い事も心の中でしていきます。
本堂へ着いたら、用意したお賽銭を入れ、
合掌しながら一礼し決意表明などを念じます。
その後、再度一礼して、本堂を後にします。
その後お線香やろうそくを所定の場所に供えます。
たいてい50~200円です。
基本お気持ちで、しなくても良いのですが、
「煙を悪いところに当てると良くなる」などの場合は
きちんとお線香を購入しましょう。
お寺を出る際も、山門の前で一礼します。

◆お賽銭にも相場がある
お賽銭とは、
願望成就のお礼や日ごろの感謝を伝えるために、
神社やお寺に納めるお金のことですね。
お賽銭の「賽」には「神仏へのお礼参り」
という意味があり、
神仏から受けた恩恵のお礼に、
お供えをする行為を指しています。
古くはお米や布を納めていたのですが
時代の流れとともに金銭に変化しました。
神社へのお賽銭は、
神さまに日頃の感謝を伝えるために納めるお金。
仏閣・寺院へのお賽銭は、
自分の欲を捨てる修行の意味をもち、
お布施だと考えられています。
またお賽銭を入れることで、
穢れを払い、身を清める「浄財」の意味もあります。
そして「お賽銭は5円」と思われている方、
それはちょっと間違いなのです。
「ご縁」と「5円」をかけたはじまりは、
明治時代だったと言われています。
当時の5円は、現在の10万円くらいの価値だったそうです。
その後も、5円は「ご縁がある」、
「二重にご縁があるように」と25円、
「始終ご縁があるように」と45円、
「先が見通せるので」50円
115円は「良いご縁」、
「これ以上の硬貨(こうか=効果)はない」ので500円はNG
など言われるようになりました。
お賽銭は日本の「ダジャレ文化≒言霊文化」の賜物(笑)
実際のお賽銭は神仏さまに対して
真摯な気持ちでお祈りをし、お願いをし、
その気持ちをもって日々の生活を送る「決意の金額」です。
あなたの決意をお金で表すとしたら、
おいくらですか?ということなのです。
そう考えると、
「たまにしか行かない神社仏閣に5円で願いを叶えてもらおう」って
どうですか?「そりゃ無理でしょ」と思いませんか?WWW
金額はこれくらいで良い、
というのは人それぞれ違います。
お札なら良い、というわけでもありません。
あくまでも「気持ちを表すモノ」なのです。
◇参考までにわたしの例(神棚にお札をいただいているところ)
※産土と土地神さま(わたしの場合は同じです)
月に6~9回ほど参拝しています。
本殿、靖国社、稲荷社の3つあります。
1回のお賽銭は基本「555円」で無い時は
「155円・115円」です。
※崇敬神社
江の島神社 年に4・5回ほど参拝しています。
3つの宮があり、各555円と御朱印をいただきます。
島内のお不動様も555円と御朱印です。
大山阿夫利神社(下社)は年に2・3回
1000円と御朱印と清め塩。
大山寺も1000円と御朱印を頂戴いたします。
伏見稲荷大社(年に1回か2回)
年末に参拝する時は基本お札です。
毎年お供えしてお願いする場所では
3000円のお供えとまあまあな金額です。
ちなみに「お賽銭」をお札数枚、
1万円で出す場合は白い封筒に入れましょう。
出来れば「ピン札」で、前もって用意しておくのがよろしいです。
◆お供え物の注意点
お供えは「撤下神饌」(てっかしんせん)として
後で全部いただくのが基本です。
自宅で神棚や仏間にあげたものも
後で食べてOKです。
お供え物を参拝時に購入する場合
自分が後で食べられないものがあった場合は
金額ではなく「全部食べられるお供え」を選びます。
「捨てる」のが一番NGなのですよ。
*****
◆神仏さまはお賽銭の金額を気にするのか?
神仏さまにはお金は必要ありませんし
金額の大小も気にならないようです。
ですが、三次元的に
神社仏閣を維持するためには「お金」が必要です。
その場所をキレイに維持するためには当たり前ですが
まだ「現金」が必要なのです。
現金でなければ「ご奉仕」が必要です。
奉賛会ですね
あなたのお賽銭や浄財やご奉仕で
「土地神さまや崇敬神社」がキレイに維持される。
あなたのお賽銭や浄財やご奉仕で
キレイになった土地神さまや崇敬神社にまた人が集まり、
その神さま方のパワーが増していく
そして増した分こちらに返ってくる
わたし達日本人と日本の神仏様との関係性です
「神は人の敬によりて威を増し、
人は神の徳によりて運を添ふ」
とは鎌倉時代に制定された
「御成敗式目」の第一条に記された言葉です。
まさに
「神さまは人間の敬う心によってそのお力を増し、
人間は神さまの徳をいただいてその運を開く」
ということが書かれています。
たくさんの人が来れば、
神仏さまのエネルギーは大きく成り、
それを支えるわたし達にもたくさん「徳」が返ってくる
見えない世界とのエネルギーの循環システムですよ!
ですから、
「懇意の神社仏閣へ通いつめましょう」と
言っているわけです
*****
◆参拝の時間やマナーなど
神社仏閣とも基本的には午前中、
遅くとも14時までに参拝を終わらせます。
お寺、仏閣は特に、16時以降はNG
憑きやすい人は特にダメですね。
とはいえ、夜間の行事などもありますので
自分が無理の無い明るい時間で、
行事なら行事の時間で大丈夫。
そしていわゆる「パワースポット巡り」ですが、
観光で1回行った神社、
パワースポット巡りでいった神社の神さま
ほんのごあいさつ程度なので
ご縁は繋がらないですよね。
そして、本当にマナーが悪い(苦笑)
最初の「基本のお作法」でも書きましたが
「形式」よりも「素」が大事。
普段のあなたの「在りよう」が大事です。
神仏様のお家で何しますか?ってことですよ。
人様のお家でしないことは
神社仏閣でも、もちろんしません。
・数人で拝殿の前で長時間お祈りをしている
・拝殿前で大きな声で話をする
・仲間内で道をふさいでしまっている
・境内の木から葉や実を取っている
・ご神木に抱きついている などなど・・・
人に対するマナーと同じです
周囲の人に気を使えない、
神社仏閣側に気を使えない、
そんな人たちに神仏さまたちは力を貸してくれません。
行くだけ無駄。
経済効果はあるから、行ってもいいけどww
神社仏閣の参拝だけでなく
「普段から、どんなふうに過ごしていますか?」
「自分以外の人にどう接していますか?」
それらも問われるということです。
神社仏閣とのお付き合いにも
「素の自分」がとても大事になるのですよ。
あなたが、今生きているその場所で
満足して、幸せを感じられているのか?
そのことの方が大事な事なのですよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
