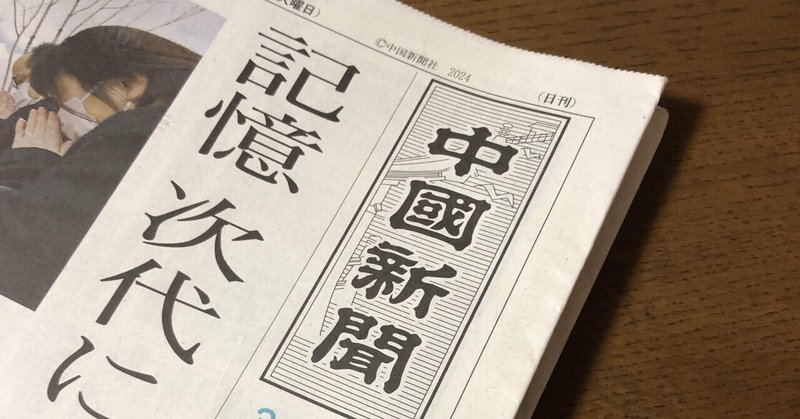
新聞のコラム連載を終えて
3/12(火)中国新聞文化欄のコラム「緑地帯」の連載が無事終わりました。
読んでくださり、ありがとうございました。
県外にお住まいの方はデジタル版を読んで下さったようです。感謝します。
新聞、それもコラムの連載というなかなか出来ない経験をさせてもらったのでこの数ヶ月を振り返りつつ書いてみます。
掲載のきっかけ
2023年秋、ノーベル文学賞発表の様子をライブ配信で見守るという「村上春樹ナイト」の夜。会場は近くのカフェバーNICOさん。
恒例の新聞取材が入っていました。その年も、スクリーンに映るノーベル財団の方の発する言葉に「ああ、またか。残念」と言いながら杯を重ねようと思ってました(若干盛りましたが私は外でお酒を飲みません)バーの店主は、以前同じコラムを書かれたこともあり、その時に文化部の方から依頼があったのです。
バタバタと写真を撮ってもらい(初回に顔写真が載る)、その場で解散。後日メールが届きました。
何を書こう
メールの内容は、
8回掲載されること
基本的に内容は自由
ではあるが、一貫して一つのテーマに沿って書くこと
指定の文字数
締め切り
と、こんな感じでした。
せっかく店をやっているので本屋のことを書くことにしました。1回目から8回目まで、だいたいの内容を組み立てて書き始めました。
文章を書く時の癖なのか、つい筆が走り過ぎてしまうので、とにかく読者のことを考えながら書きました。仕事は半分くらい接客業でもあるので、他者のことを想像する姿勢は自然と身に付いていたようです。
文体について
文章は「ですます」でも「である」でもどちらでも良く、「である」調の中に「ですます」調が挟まっても大丈夫だと言われたので、自分の文体にしっくりくる「である」調を選択しました。少ない文字数に色々入れたいこともあり、そこは悩みませんでした。
昔から、少なからず装飾の多い文章を書く傾向がありましたので、今回は徹底的に「読みやすさ」を考え、出来るだけ平易な言葉を使い小中学生にも理解できる文章を心がけました。
書くこと見せること調べること
この連載は、8回分の原稿をまとめて送るので約5000字近い文章を書かなくてはなりません。朝刊を楽しみにしてもらえるように、毎日内容を変えました。まったりした回があるかと思えば一気に読ませる回、情報量の多い回と出来るだけ読み飽きないように緩急を付けました。
一番楽しみだったのは、担当の方の添削です。どんな風に変わるんだろうと期待していました。
年末に原稿を送った後、初回の原稿に「もっと具体的でいい」と指摘があり初稿では明記してなかった店の場所を書き足しました。それ以外では文章の長短を指示されたくらいで、大きな修正はしていませんでした。
当初の予定では年明けの掲載でしたが、それよりもかなり掲載時期がずれてしまったため、文学フリマについての修正が入りました。それから新聞の原稿と並行してリトルプレスを制作していたので、父のことを書いた回では本に収録したエッセイと同じにならないようにエピソードを変えて書きました。
2月に掲載日が確定し、一気に文化部から連絡が増えました。校閲のチェックが入ったためです。読みにくい漢字にルビを振ったり、父の話の回では出身校の沿革まで調べて正しい表記に直して下さいました。「これが噂に聞く校閲か」と感激したものです。私もそこまで調べて書けばいいものを、怠っていました。反省しました。そのあたりから、「本当に私の文章が新聞に載るんだ」という実感が湧いてきました。
チェックは毎回ありました。漢字のルビが意外と多かったです。そんなに難しい語句を使っていないのにも関わらず、です。新聞表記のルールに従って、漢数字がアラビア数字になったり細かいところまで見られるのだなと思いました。今後どこかで書く時の参考になりました。
反響について
コラムの掲載後はかなりの反響がありました。今までも様々な媒体で紹介されたことがありましたが、やはり自分の文章というものはより読者にダイレクトに伝わるのだなと実感しました。
父のことでは、教え子の方も含めて色んな方に声をかけていただきました。今年の9月に回顧展を予定していますし、父についてはどうしても書きたかったことなので、書けて良かったと思います。
今回まとまった文章を書くことにより、自分の頭の中を整理出来て良かったです。今年に入って日記を真面目に書き始めたのも同じ効果があります。書き足りなかったことや、あえて外したことなどまだネタはあるので、またどこかで。
最後になりましたが、中国新聞社様、文化部の担当者の方、読んでくださった皆さん、ありがとうございました。
コラムはこちらから読めます。
※無料登録が必要。月に10本まで読めます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
