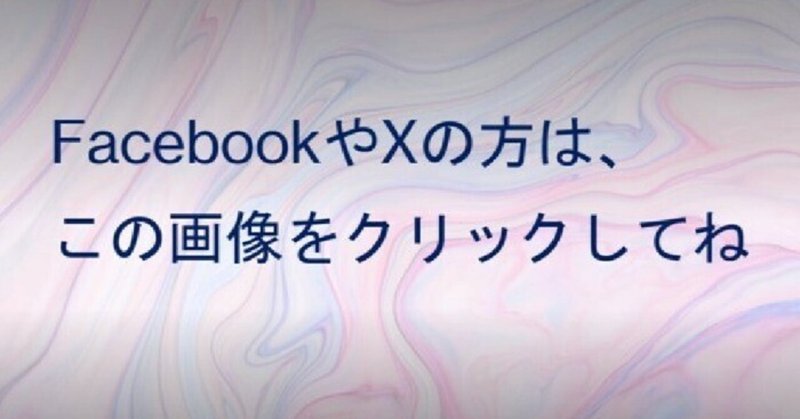
チンゲン革命(11)
【前回までのあらすじ】
テレビ芸人で笑ってしまった若本は、無意識に創価的な価値観を相対化した。これにより、池田氏に対する敬意は薄まった。
この相対化を意識させる、別の出来事があった。それは受験である。
【読者への事前注意】
今回は、学歴ネタや偏差値ネタをイヤな感じで取り上げます。「〇〇大よりも△△大の偏差値が高い/低い」の類の話です。
その手の話題が嫌いな方は、今回は飛ばして頂いて、次回を読んでくださいね。
さて、創価要素の相対化に大きな役割を果たしたものがある。受験だ。
隠してもしょうがないので書くが、私は創価学園を受験し、一度失敗している。
私の学力と受験の履歴は次の通りだ。
・創価中学
小6の終わりがけに受験を思い立ち、受験はしたが思い切り落ちた。そりゃそうだ。中学受験なんて、遅くても小5から準備しなきゃスタートラインにすら立てない。
・創価高校
当時の創価高校は合格ライン偏差値が70前後だった。共学の都内私立高校としてトップクラス。私は偏差値が60くらいしかなかったし、過去問を一目見て合格は無理だと理解できた。数学とかエグかったわ。何だあの問題。難しすぎだろ。解けるやつは頭がおかしい。そんなわけで受験自体を断念。
・創価大学
河合塾の偏差値で、創価大学の合格ラインは当時52.5-55.0くらいだった。私は高校でも偏差値が60くらいだったので、創価大学の合格可能性はそこそこ高かった。が、この頃には創価学会そのものから気持ちが離れていたので受験しなかった。
たったこれだけのことなのだが、私の心理や、創価学会を客観視・相対化するためのプロセスとして重要だったのでもう少し詳細に書き残しておく。
創価中の受験は、私はもちろんのこと、親も中学受験の何たるかを全く分かっていなかった。
家族メンバーの誰もが「先生の作られた学校だからチャレンジしてみよう」くらいの軽い気持ちでいた。
スポーツみたいなもので、「参加することに意義がある」という感じ。
でも、落ちたのが事実なので「さすが創価学園は凄いね。難しいね。」のような意識は残った。
中学受験は親子して何も分からないままだったのだが、高校受験は事情が異なる。
学校側の進学指導も始まるため、親子して偏差値などの意味を理解する必要に迫られた。
そこで知った創価高校の偏差値は70。これは公立中学ではオール5の生徒でも到達するか微妙な値だ。
要するに、めちゃくちゃ優秀な人間が行くのが創価高校だった。
私は偏差値60なので「ちょっとだけ優秀」という程度の頭だ。
数字は残酷なもので、私の頭では創価高校の合格など夢のまた夢であることを証していた。
受験をしても受からない、そのことを親も私も分かっていた。
ここでの家族的な認知は「やっぱり創価学園ってレベルが高くて凄いのね」といった辺りだ。
この感じ、伝わるだろうか?
「創価中・創価高に入学できない」というのは、単に私の成績が不足しているということを意味するのではない。
「自分の実力では入学できないほどの難関校」という現実を目の当たりにすることで、創価学園の偉大さを認知することになるのだ。
創価が偉大であれば誰が嬉しいのか?
それは他でもない、私が嬉しいのだ。
創価そのものを偉大だと思いたいからだ。
入試での敗北の結果、そこに残るのは組織賛美である。
そんなことをしろとは創価学会の誰も言っていないのに、潜在意識にはそのような歪んだ屈服感が残るのだ。
この頃は親子揃って
「優秀・偉大なる創価学園様、はっはーm(_ _)m」
のような心持ちである。
ところが、大学入試ではそこにおける大きな変化があった。
「大学は中堅なのに、中学高校は超ハイレベル」というのは入試で良く見る構造なのだが、創価大学も同様だったのだ。
高校入学後に模擬試験を受けさせられた際に、創価大学の判定ラインを自分の偏差値が上回ったのだ。
小中学生の間はひたすら見上げる一方だった創価を、数字によって見下ろすことになったということだ。
私は偏差値云々で人間が測れるなどと思っていない。
しかし、偏差値教育の文脈を是認していた当時の私にとって、意味が大きかった。
前述の通り、「創価中・創価高はレベルが高すぎて手が出ない」というのは、創価を賛美する文脈であると同時に、無意識のコンプレックスにもなっていたわけだ。
それが逆転し、コンプレックスが解消されたのだから、これはなかなか衝撃的だった。
創価学園は、「私を選ぶ側」から「私に選ばれる側」になったわけだ。
絶対視し賛美する対象でしかなかった創価的な要素について、自分の努力の結果として相対化したということだ。
これは私にとって、創価を客観視するための突破口になった。
正直、この点では日本に一般入試制度があったことに感謝している。
私に広布の使命を託した母は、「創価大学に行けると良いね!」とよく口にしていた。
創価中や創価高はダメだったけれど、創価大学には何とか入って欲しい…そんな願いだったのだろう。
しかし、前述の模試の結果を見てからは、そのようなことを言わなくなった。
そこに私は、学歴と社会における闇や現実を見たし、創価学園への憧れがどの程度のものなのかを見た気がする。
創価大学で創価学会を測れる訳では無いのだが、偏差値やら大学ブランドを気にしていた私は、そこで創価学会の夢から覚めた。
覚醒したというよりは、気持ちが冷めた、という感じだった。
何が言いたいかというと、外部的な価値観が信仰的な価値観より重視されることがあるということだ。
例えば私の場合は、異性への欲情が信仰的価値観を上回った。
前回の内容と合わせると
・テレビ的なお笑い
・偏差値的ヒエラルキー
・性欲
これらを覆すほどの魅力や価値を創価学会に見出だせなくなったということだ。
この、創価離れ/信仰離れを決定的なものにしたのが、私にとって初めての折伏であった。
次回、チンゲン革命 最終回
「初めての折伏★初めての敗北」
お楽しみに!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
