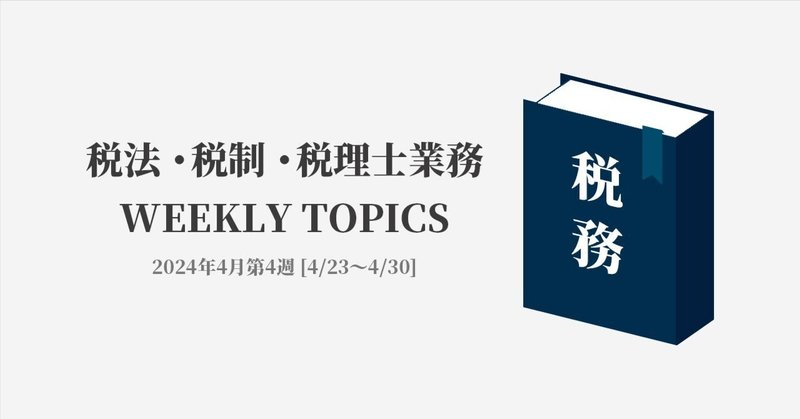
税務WEEKLY TOPICS:2024年4月第4週
2024年4月第4週(2024年4月23日〜4月30日)に話題になったことや税務に関する重要発表を紹介します。
連休前ということもあり、多くの情報が公開されていました。
法律・施行令・施行規則・基本通達を相互に繋ぐ、税理士・企業の税務担当などの税務専門家向けの六法アプリ「税務法規集」を開発しています。e-Govの最新法令データと国税庁の基本通達を毎月更新して常に最新の状態で利用できます。ぜひ一度利用してみてください。
1. 法令・通達・制度関係
1-1. 「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」及び「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を公開(国税庁・4/30)
定額減税に関する以下の2点の PDF 資料が公開されました。
1-2. 給与支払者向け定額減税説明会の開催予定を追加(国税庁・4/30)
税務署で実施されている参加費用無料の「給与支払者向け定額減税説明会」について、以下の開催予定が追加されたとのことです。
札幌中・厳原・人吉・沖縄・名護
各地の詳細な情報は以下にまとまっています。
1-3. 「個人番号を利用した税理士の登録事務等の利便性の向上」についての施行日を公表(国税庁・4/26)
令和6年度税制改正で措置された「個人番号を利用した税理士の登録事務等の利便性の向上」について、令和6年5月27日に施行されることを受けて、書式等が公表されました。
対象となる書式は以下のとおりです。ただし、税理士試験関係(以下の2,3)については来年(令和7年度・第75回)から適用されることとなります。
① 税理士試験受験資格認定申請書(第一号様式) (PDF/89KB)
② 税理士試験受験願書(第二号様式) (PDF/139KB)
③ 研究認定申請書(第三号様式) (PDF/111KB)
④ 税理士試験免除申請書(第五号様式) (PDF/100KB)
⑤ 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書(第六号様式) (PDF/119KB)
1-4. 「令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載(国税庁・4/23)
最新版のパンフレットとなる「令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし」が掲載されました。
源泉所得税関係についての改正に関してまとめられた資料で全4頁の PDF ファイルです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf
1-5. 文書回答事例「収益事業を行う青色申告法人である公益法人等の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について(収益事業以外の事業の取引に関する電子取引の取引情報について)」を公表(国税庁・4/24)
質問の概要は以下のとおりです。
公益法人等は電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が必要とされているところ、この保存については、収益事業を行う青色申告法人に保存が義務付けられている帳簿書類である、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しと同様、収益事業を含む全ての事業の取引に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が必要と考えるべきか。
法文としては、電帳法第7条と同第2条第5号が関係したものとなります。
【電帳法第7条】
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
【電帳法第2条第5号】
五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
1-6. 「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」についての特設ページを公開(国税庁・4/26)
表題のとおり、特設ページが新たに公開されました。本ページの趣旨は以下のとおりです。
社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となりますが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となります。
このページでは、障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いなどに関する情報を入手・閲覧できます。
項目としては、以下のようなものが公開されています。
障害者相談支援事業等に関する情報
消費税法令上の取扱い
社会福祉法令上の取扱い
関連Q&A
説明会資料
障害者相談支援事業等に関するご相談窓口
1-7. 令和5年9月21日付課法2-17ほか2課共同「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明を公表(国税庁・4/26)
令和5年9月21日現在の法令を前提とした法人税基本通達の改正についての趣旨説明資料が公開されました。
項目は以下のとおりです。
法人税基本通達関係(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設の経緯等)
1 寄附金【新設】9-4-9(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)
2 定義
【新設】18-1-1(企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定)
【新設】18-1-2(財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
【新設】18-1-3(連結の範囲から除かれる会社等)
【新設】18-1-4(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)
【新設】18-1-5(特定財務会計基準等に従って計算書類が作成されていない企業集団)
【新設】18-1-6(4対象会計年度の意義)
【新設】18-1-7(総収入金額の範囲)
【新設】18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)
【新設】18-1-9(事業が行われる場所とみなされるものの例示)
【新設】18-1-10(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)
【新設】18-1-11(国際的に広く用いられる方法により事業から生ずる所得の範囲を定める条約等の例示)
【新設】18-1-12(条約等の規定によっても所在地国が定まらない場合)
【新設】18-1-13(恒久的施設等を有する会社等の除外会社等の判定)
【新設】18-1-14(持分法が適用される会社等)
【新設】18-1-15(持分法が適用されることとなる会社等)
【新設】18-1-16(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
【新設】18-1-17(連結の範囲から除かれる会社等)
【新設】18-1-18(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)
【新設】18-1-19(出資者等が複数でない場合の取扱い)
【新設】18-1-20(会社等の持分)
【新設】18-1-21(直接又は間接保有の持分)
【新設】18-1-22(出資不動産の運用の範囲)
【新設】18-1-23(各種投資会社等の判定を行う場合の準用)
【新設】18-1-24(税引後当期純損益金額の計算)
【新設】18-1-25(最終親会社等財務会計基準の意義)
【新設】18-1-26(構成会社等の会計処理の基準が最終親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
【新設】18-1-27(共同支配子会社等の会計処理の基準が共同支配親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
【新設】18-1-28(構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い)
【新設】18-1-29(共同支配子会社等の決算日と共同支配親会社等の決算日が異なる場合の取扱い)
【新設】18-1-30(共同支配親会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い)
【新設】18-1-31(構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の換算)
【新設】18-1-32(最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合の例示)
【新設】18-1-33(独立企業間価格)
【新設】18-1-34(独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
【新設】18-1-35(いずれもが独立企業間価格である場合の取扱い)
【新設】18-1-36(独立企業間価格相当額の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
【新設】18-1-37(直接又は間接保有の持分)
【新設】18-1-38(会社等の持分)
【新設】18-1-39(持分の交付が省略されたと認められるものの例示)
【新設】18-1-40(恒久的施設等の個別財務諸表が作成されることとなる場合の準用)
【新設】18-1-41(各種投資会社等における資産又は負債の時価の例示)
【新設】18-1-42(第三通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額又は損失の額)
【新設】18-1-43(違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で費用の額としている金額の例示)
【新設】18-1-44(罰金等の例示)
【新設】18-1-45(定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しないものの例示)
【新設】18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)
【新設】18-1-47(課税所得の金額に含まれないことの例示)
【新設】18-1-48(利益の配当の額の範囲)
【新設】18-1-49(除外配当に係る費用の額)
【新設】18-1-50(所有持分に係る所有期間の判定)
【新設】18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)
【新設】18-1-52(裸傭船契約の期間の判定)
【新設】18-1-53(船舶に係る事業運営上の重要な決定及び事業活動の例示)
【新設】18-1-54(銀行業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
【新設】18-1-55(保険業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
【新設】18-1-56(構成会社等がその親会社の株式等を交付する場合の株式報酬費用額の取扱い)
【新設】18-1-57(時価評価調整加算額及び時価評価調整減算額における時価の例示)
【新設】18-1-58(ヘッジ処理の有効性の判定)
【新設】18-1-59(財務機能を果たす構成会社等が他の構成会社等が有する所有持分につきヘッジ処理を行っている場合の取扱い)
【新設】18-1-60(その他の事由による債務の消滅の意義)
【新設】18-1-61(債務者における資産の時価の例示)
【新設】18-1-62(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)
【新設】18-1-63(配当控除所得課税規定の例示)
【新設】18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)
【新設】18-1-65(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)
【新設】18-1-66(対象租税の範囲に含まれないものの例示)
【新設】18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
【新設】18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)
【新設】18-1-69(不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の例示)
【新設】18-1-70(利益剰余金に係る繰延税金負債の例示)
【新設】18-1-71(不確実性がある金額が支払われた場合の取扱い)
【新設】18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
【新設】18-1-73(3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないもの)
【新設】18-1-74(恒久的施設等への対象租税の額の配賦)
【新設】18-1-75(恒久的施設等への外国税額の控除額の配賦)
【新設】18-1-76(外国子会社合算税制の適用がある場合の対象租税の額の配賦)
【新設】18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦)
【新設】18-1-78(構成員課税型会社等への対象租税の額の配賦)
【新設】18-1-79(構成員課税型会社等への外国税額の控除額の配賦)
【新設】18-1-80(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等)
3 国際最低課税額
【新設】18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
【新設】18-2-2(有形固定資産及び天然資源の例示)
【新設】18-2-3(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)
【新設】18-2-4(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
【新設】18-2-5(構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
【新設】18-2-6(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の再計算繰越国別調整後対象租税額)
【新設】18-2-7(無国籍構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
【新設】18-2-8(共同支配会社等が共同支配会社等グループに属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
【新設】18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)
【新設】18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
【新設】18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)
4 経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期(1))
【新設】(経過的取扱い(2)…改正通達の適用時期(2))
【新設】(経過的取扱い(3)…国際最低課税額の計算に関する経過措置における国別グループ純所得の金額から控除する金額の取扱い)
1-8. 「輸出酒類に係る証明書の発行手数料について」を公表(国税庁・4/26)
表題の資料が公表されました。手数料自体は変更ありませんが、以下の点が昨年と大きく異なっている点かと思われます。
電子納付(ペイジー対応の ATM 又はインターネットバンキングによる支払い)は、一元的な輸出証明 書発給システムを通じて行います。他の納付方法としては、収入印紙による納付も可能ですが、円滑な 手続のために、原則、電子納付を御利用ください。
1-9. 「税務署の内部事務のセンター化について」を公表(国税庁・4/26)
納税者及び税理士向けに、以下の協力を求めるページが公開されました。
各国税局における「内部事務のセンター化」の実施に当たっては、次の事項について、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
① 業務センターへの申告書、申請書及び添付書類等の提出
② 業務センターから納税者・税理士の皆様への問合せ
③ その他の案内
1-10. 「振替依頼書」及び「ダイレクト納付利用届出書」のオンライン提出の利用制限について」を公表(e-Tax・4/25)
メンテナンスのため、以下の日程で表題の手続きができなくなるとのことです。
【対象手続】
- 振替依頼書オンライン提出
- ダイレクト納付利用届出書オンライン提出
【日時】
令和6年5月14日(火)1:00 ~ 6:00
(予備日:令和6年5月16日(木)1:00 ~ 6:00)
2. ブログ
2-1. 弥生、オンデマンド配信で定額減税セミナーを実施(弥生・4/30)
弥生が5月20日(月)よりオンデマンド配信で「定額減税セミナー」を実施するとのことです。
内容は、定額減税に対応するために、どのように業務を行えばいいか分からない給与計算の担当者や定額減税に対応した給与ソフトを探している人に最適なセミナーとのことです。
なお、視聴にはフォームからの申し込みが必要となるようです。
日時:2024年5月20日(月)より配信開始
参加費:無料
視聴方法:オンデマンド配信
申し込み方法:下記URLよりお申し込みください
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/seminar/teigaku-2405/form/
2-2. 納期の特例の要件である「常時10人未満」とは?(税務会計実務ノート・4/28)
源泉所得税を半年分まとめて年2回に分けて納める納期特例における「常時10人未満」について、基本通達を引用して解説されています。
2-3. 会社代表者の住所非表示措置(大阪勉強会からの税法実務情報・4/30)
令和6年10月1日より、登記事項証明書において、株式会社の代表取締役等の住所を申出等により非表示とすることができる措置が講じられるところ、非表示をした場合に発生する不利益等について解説されています。
2-4. 新しいNISA制度の利用者は13%、30代は19%(TabisLand・4/24)
野村アセットマネジメントが発表した「投資信託に関する意識調査」結果をもとに、NISA制度の利用状況が紹介されています。
2-5. 初任給30万円超えの企業も。「賃上げ」実現のために中小企業が知っておくべき3つの支援制度(税理士ドットコム・4/24)
賃上げを行う場合の助成金・税制優遇等が紹介されています。
2-6. AI導入でベテラン職員並の選定能力も?税理士が語る今どきの税務調査事情(税理士ドットコム・4/26)
「国税庁では現在、業務効率化を実現するためDXを推進している。税務調査においてはすでに全国の税務署にAI・データ分析を導入し、申告漏れの可能性が高い納税者等の判定を行っている。つまり税務調査の対象者になるかはAIが選定しているのだ。」とのことです。たしかに異常なものは機械学習で発見しやすいので、この流れは加速しそうに思います。
2-7. 「不安しかない」など切実な声ーー個人事業主に聞いた「消費税申告」アンケート調査(税理士ドットコム・4/26)
消費税申告を行なった個人事業主向けに行なったアンケートの結果に関する記事です。
3. SNS
3-1. 円安と iPad(4/27)
iPad の値段自体は大きく変わっていないものの、円安が大きく進んだせいで iPad が30万円未満にならないという問題をネタにしたポストが話題になりました。iPhone の高額機種も同じ問題がありますね。
私「1ドル166円67銭がラインだと思いなされ」
— mizuki @腰痛 (@mizukisa) April 27, 2024
友「何の?」
私「iPadが1800ドルとした時、買った年の経費にできなくなるライン」
友「あああっ」
私「166.67×1800=300006、少額減価償却30万未満を踏み抜く。頼みの綱は税抜経理じゃ」
3-2. フリーランスとインボイス(4/26)
「インボイス制度におけるフリーランス等の7000人 実態調査」という独自調査の結果が話題になりました。発起人自体が「STOP!インボイス」なので結果としてはネガティブになるのも当然そうな気もしますが、それを差し引いてもやはりネガティブに捉えている人が多そうです。
7000人中、91.9%の人がインボイスの「見直し・廃止を希望」
— STOP!インボイス (@STOPINVOICE) April 26, 2024
登録者の6割超が税負担分を値上げできず、貯蓄などを削って補填。納税のために借り入れした事業者は約1割
「インボイス制度におけるフリーランス等の7000人 実態調査」の結果が本日発表となりました。
調査結果の報告書は以下です。… pic.twitter.com/BD2NjVv4nk
3-3. 定額減税をなぜこの時期に?(4/30)
定額減税について、中途半端な時期にわざわざ実施させることについての怒りのポストが話題になりました。
税理士も社会保険労務士も、人事の給与担当も給与計算のシステムベンダーも全員激怒していて、なんで年末調整か確定申告で減税すればいいのに6月なのか理解できないって怒ってた。システム会社は二度と使わない機能のために数百万かけて開発してると思う。 https://t.co/fGUCtCWQUF
— 💃🏼💃🏼Alpaca🕺🏼🕺🏼 (@nanatea) April 29, 2024

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
