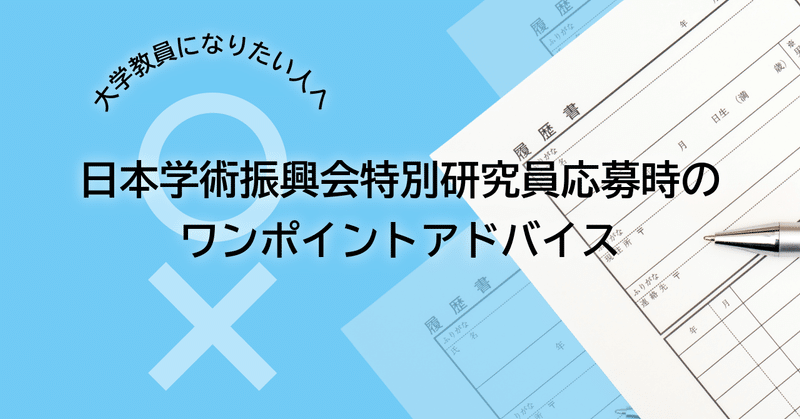
大学教員になりたい人へ Vol.5 ー日本学術振興会特別研究員応募書類のワンポイントアドバイスー
大学院生のみなさんから一番多く相談を受けるのは日本学術振興会特別研究員(通称、学振)についてです。まあ、4〜5月の相談が多いですよね。
もっと早くに相談してくれていれば戦略を伝えられるのにという場合が多いですが、そうは言っていられません。少しでもお役に立てればと思いアドバイス(というほど偉くもないですが)させていただいています。
今回は4〜5月にできるような少しでも評価を上げる可能性がある方法を紹介します。
これは私自身が自分の中で特に学振の書き方みたいな本(参考書)にはあまり書いていない部分(研究遂行力の自己分析であるとか目指す研究者像等)をどう書けば良いのかをまとめたものになっています。研究計画や人権の保護及び法令等の遵守への対応を書く際にもここで書く考え方は使えると思っていますし、実際にそのアドバイスをふまえて書いた申請書で学振が取れた方も一定数おられます。
本来は無料で書こうと思っていたのですが、色々と考えた結果、有料とすることにしました。
理由としては以下のような感じです。
審査員のみなさんが読まれることをできるだけ減らしたい(このアドバイスをふまえて書くことがマイナス評価になることは避けたい)
アドバイスを送った院生たちに止められた(全員が知るとノウハウではなくなる)
色々なノウハウを有料や本で提供してくださっている方々の商売を邪魔しないようにしたい
もちろん、指導している院生等には無料で教えていますが、お金が絡むことの情報なのでご理解ください。
院生(学生も)あるあるの「評価書(推薦書)の下書きを書くように言われたら?」についても書きましたので、そこが気になる方も読んでいただければと思います。
この学振について知らない方は以下を読んでください。今回は学振の説明は省略します。
学振採択のためのワンポイント
研究の価値は誰が決める?
学振に申請される院生はよく分かっておられると思いますが研究の価値は誰が決めるのか?という話です。それぞれ考えは異なるでしょう。自分自身が決めると思われている方もいるでしょうし、学会の偉い先生方が決めると思われている方もいるでしょう。ほかにも今や未来でその研究を知った誰かが決めると思われている方もいるでしょう。
研究は今の課題を解決するものであり、未来の課題を解決するためのものと私は信じていますし、誰かがいつかどこかで知ってくれたらそれで良いと思っています。
しかし、学振や他の研究助成費等は審査員が価値を決めるのです。審査員をしたことがある人は分かると思いますが胃が痛くなりながら審査をしたりします。
みなさんの心のこもった申請を評価するので誰が良くて誰が劣っているなどと考えて良いのかすら迷います。
だからこそ価値を分かりやすく示して欲しいのです。
特に審査員は、申請者の分野の専門ではない人もおられるので、学者が読んで分かるレベルで研究の価値を示す必要があります。
先生だけでなく、友人、先輩、後輩などに申請書を読んでもらおう
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

