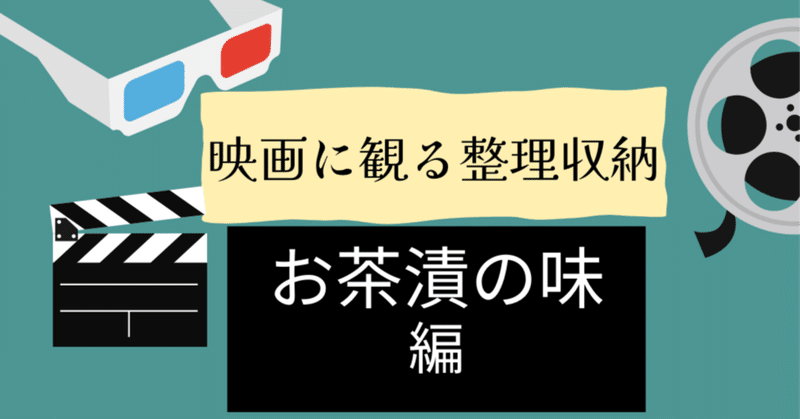
映画に観る整理収納Vol.12 「お茶漬の味」編
今年は小津安二郎生誕120周年です。
私が小津映画と出会ったのは約30年前。
その当時はこれほどの大監督だと知らず、ただ原節子の美しさと
整然とした印象の画面に心を奪われたことだけはよく覚えています。
今回は小津作品の中でも私が大好きな「お茶漬の味」と整理収納をリンクしてみたいと思います。
登場する店やオフィスには見た目スッキリのコツがある
冒頭に映るのは和光や教文館ビル。今でも銀座の街に残るシンボルです。
姪の節子(津島恵子)と一緒にタクシーに乗る妙子(小暮実千代)が友人(淡島千景)の経営するブティックへ向かうところから物語は始まります。
その話し方や、値段も見ずに「これ頂戴。包んでおいてね」と秒で買い物をするところを見ると、妙子は裕福な奥様であることが想像できます。
一方、丸の内に努める妙子の夫、佐竹茂吉(佐分利信)は地方出身の素朴で堅実な男性です。
亡き友人の弟の就職の心配をして、一緒にバーで飲んで話を聞いたりする面倒見の良いところもあります。
そのバーの様子。
棚には整然と酒瓶が並んでいます。
酒瓶だけでなく、店内の椅子や壁に飾られた絵も不自然なほど等間隔にならべられています。
余分なものは画面に映りこまず、(他のお客さんも誰もいません)必然的に画面の男性2人に視線が行きます。
「等間隔」や「揃っている」という状況はそれだけで無意識的にスッキリした印象を与えることがよくわかります。
例えばモノが少なくても雑然とした雰囲気があるというお宅は、アイテム別に分けて、整然と並べてみるだけでもずいぶんと印象が変わるはずです。
これはオフィスの映像でもわかります。
オフィスを引きで撮った画像が出るのですが、机、ネームプレート、ブラインドや書類棚、電気スタンドまでも全て直線でスッキリと合っています。そして仕事をしている人たちの椅子の引き具合まで揃っている!(普通はこんなことないですよね)
仕事中の机の上が映っていないという点もあるでしょうが、雑然としがちなオフィスなのにとってもスッキリとした印象があります。
小津映画は「ロー・アングル」の固定カメラで撮ることがとても有名ですが
この低さも安定感という意味でとても大きな意味があるでしょう。
佐竹家の居間のゾーニング
佐竹家はお手伝いさんが二人もいる裕福な家庭と思われ(途中、妙子が兄から送金を受けているであろう様子が伺えますが)家の中はいつもとてもと整っています。
妙子は家事という当時(映画制作時は1952年)の重労働がないためか、時間とお金があるためか夫に嘘をついて学生時代の友人と温泉旅行に行ったり、野球観戦に行ったりしているようです。聞いたことはあるけれど会ったことはない「有閑マダム」なのでしょうか?
あ、今気づきましたけど「有閑」って閑(ひま)が有るって書くんですね(笑)
佐竹家の居間は和室の二間続きで間仕切りの襖はいつも開いているため、奥の植え込みまで見えて広々とした印象です。
食事をとるのはその一間の中の端に作られた場所で、二人だけで食事をするからか小さめの座卓が置かれています。
部屋は広いのだし、座敷の真ん中に机を置いて食べても良いようなものだと思いますが、「食事をとる場所」という限定的な場所をコンパクトに作ることで他を広々と使えているとも言えます。
また、よく見るとそのすぐ横にはお茶が点てれられる場所や酒器を入れる小さな茶箪笥もあったりします。
すっきり片付いた座卓の上にはいつもお湯呑みが2つ出ていのるで、ここでよくお茶を飲むのかもしれません。
いずれにしてもこの空間は、「食に関わる場所」ということでまとめることができます。座卓の場所も台所からの動線がよさそうですし、このように「ゾーニング」しておくことでその場所に関するモノが集まった空間をつくり、管理しやすくなるという良い点もあります。
夫婦の違いが判る部屋の作りと会話の糸口
妙子の部屋はこの家で唯一の洋間で、シャンデリアがあり、花柄の壁紙やソファ、寝具はベッドが置かれ、洋風の家具が揃えられた他の部屋とはかなり趣が違います。
一方茂吉の部屋は純和風で小さな文机と火鉢、小机があり、多くの書物は一角にまとめて置かれ、書棚からあふれた本には埃除けなのか布がかぶせてあります。
茂吉はここでよく書き物や読書をして過ごしているようで、もっとも心が安らぐ空間になっているようです。
さてお手伝いさんがいて趣味や価値観が違うと夫婦がそれぞれの部屋を持つと会話の糸口がなかなか見つかりませんね。なんといってもお互いのテリトリーがぱっきりと分かれているのですもの。
夫婦だけの狭い家なら「こんなところにモノを置かないで」とか「この手紙はもう処分していいの?」とか「今日は何食べようか」などちょっとした会話になりそうなこともお手伝いさんとの間で全て解決してしまうのですから。
違いが判る夫婦は幸せなのかも
部屋からも普段の過ごし方からもわかるように二人はほぼ共通項がないどころか真逆な性格の夫婦と言えます。
妙子は自分の価値観に合わないことを茂吉がすることが許せません。
例えばお味噌汁をご飯にかけて食べる事や、たばこは朝日(多分安いたばこ)をたしなむ事、汽車は三等を望む事など茂吉のする事がことごとく気に入らず、「やめてくださいと申し上げたでしょ!」とたまにキレます。
一方茂吉は「インティメントなもっとプリミティブな遠慮や気兼ねのない気安い感じが好きなんだ」と自分の暮らしの好みは言いますが、妙子に対しては「君は今のままでいいんだ」と言っているし、実は妙子が嘘をついて遊びまわっていることもよくわかっていて何も言わないでいるのです。
物語の転換は急にきます。
仲違いしたまま妙子が友人の居る神戸へ旅行している時に急に茂吉のウルグアイへの出張が決まってしまいます。当時の海外出張は大変なことだったらしく、茂吉は妙子に帰るように電報を打ち、友人知人が総出でお見送りをするのですが、妙子はそれでも戻ってきません。
その後帰宅した妙子は、茂吉の居なくなった部屋で一人考え込みます。が、その日の夜中、飛行機の故障で茂吉が家に帰ってくるのです。
お腹が空いた二人はお手伝いさんの寝静まった台所でお茶漬けを作ります。
普段入らない台所で宝探しをするようにぬか漬けやご飯を探し、用意する様子が新婚のようにとても楽しそうです。
そして妙子はお茶漬けをすすりながら、茂吉の言っていた「遠慮や気兼ねのない気安い感じ」がやっとわかったと言って泣きながら謝ります。
嘘のない信頼があってこそ、お互いの違いを尊重し合える。
それが夫婦なんだということが妙子にもようやくわかったとても良いシーンです。
整理収納の現場ではご夫婦、親子間で「要る要らない」で意見が分かれることがあります。「こんなに古いモノ要らないでしょ」「なんでこんなものとってあるの?」といった言葉が飛び交います。
家族でも価値観はそれぞれで、誰が良い悪いではないのです。お互いの「違い」を知るためには相手がなぜそう思うのかを聞くことがまず第一歩です。違いを知ることができれば、今までよりももっとお互いを理解できます。
お互いを理解できれば、なぜそれが要るのか要らないのかも理解できるかもしれません。理解できなくても少なくとも自分との「違い」を理解して尊重することができます。
それが解ってくると、お片付けはグーンと進むのです。そして関係もとってもスムーズになります。
茂吉は妙子にまあまあ酷い言われ方をしても嘘をつかれても決して怒るようなことはありませんでした。
私なら「そんないい方しなくても!」と言い返すだろうなと思うような場面は結構あるのです。
ひたすら「君が嫌ならやらないよ」「僕はこう思っているからこれが好きなんだよ」と根気よく話します。
なんていう人格者なんでしょう茂吉さん。
相手を無理に変えるようなことはしないのです。
大きな器を感じさせる素敵なおじさまです。
茂吉の意図を理解した妙子は今や今まで嫌だったところも全部好きになってしまった様子。おやおや(笑)
自分と同じ考えを持つ人などこの世にはいない。自分と人とは「違う」ということがわかっていれば夫婦もお片付けもうまくいくのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
