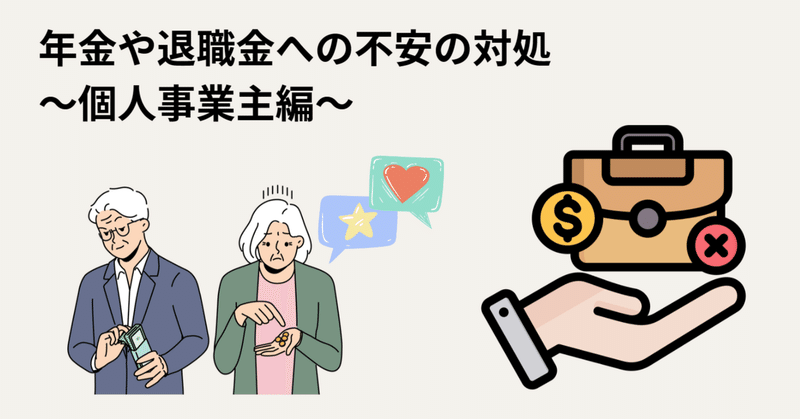
個人事業主の年金や退職金対策!国民年金や国民年金基金など制度理解
(1)はじめに
「自営業者・個人事業主はもらえる年金が少ない?」「年金が少ない場合、老後はどう過ごせば良い?」など、老後資金を不安に思っている自営業者・個人事業主は多いのではないでしょうか。
この、将来の年金に関する漠然とした不安は、起業への第一歩を阻害する大きなハードルの一つと言えます。
実際に、個人事業主がもらえる主な公的年金は、基礎年金(国民年金)のみとなり、会社員や公務員と比べると少ないです。しかし、個人事業主が利用できる任意加入の年金制度があるため、これらを活用することで将来もらえる年金を増やすことができます。

本記事では、老後資金に不安を持つ自営業者や個人事業主に向けて、知っておきたい年金制度の仕組みや対策について解説します。
(2)個人事業主の老後資金対策(年金対策)
個人事業主の年金対策は、公的年金と私的年金を組み合わせた多層構造が効果的です。また、年金以外にも、小規模企業共済などを活用し、老後資金を所得控除の税制メリットなどを活用しつつ積み立てることができます。

①国民年金(基礎年金)(公的年金)
基礎となる年金1階部分は、国民年金(基礎年金)です。
これは、全ての国民が加入する必須の公的年金制度で、老後の最低限の生活を保障するものです。
②「国民年金基金」や「付加年金」(公的年金)
年金の2階部分は、「国民年金基金」や「付加年金」です。
国民年金に上乗せ・追加する形で加入できる公的年金制度です。
これらの制度のうち、いずれかを選択して加入します。
③iDeCo(個人型確定拠出年金)(私的年金)
年金の3階部分は、iDeCo(個人型確定拠出年金)です。
iDeCoは、自助努力で積立てる私的年金制度です。
④小規模企業共済(退職金)
小規模企業共済は、個人事業主の廃業・退職時の生活資金を確保するための制度です。
このように、国民年金(基礎年金)を基礎として、国民年金基金/付加年金、iDeCo、小規模企業共済を組み合わせることで、"所得控除"という税制優遇を受け節税しつつ、多層的に老後資金を準備することができます。
早期から計画的に取り組むことが、老後生活に安心感を持つことにつながるでしょう。
(3)国民年金受給の平均年金月額は、約5万6千円
令和5年度の国民年金(基礎年金)は、満額で年間約80万円です。
会社員は、厚生年金も合わせて受け取れますが、個人事業主は、満額でも月額6万~7万円しか年金がありません。

また、厚生労働省が公表している「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和4年度)」によると、以下の通りです。国民年金受給者と厚生年金受給者の平均年金月額は、大きな差があることが分かります。
国民年金受給者の平均年金月額:56,428円
厚生年金受給者の平均年金月額:144,982円
(4)国民年金以外の年金対策の意義
特に個人事業主にとって、老後の年金に関する漠然とした不安は、起業への一歩を踏み出す際の大きな障壁です。
しかし、国民年金以外の制度、例えば国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済などに加入することで、追加で一定の老後資金の受給が約束されます。

事業が軌道に乗るまでは痛み分けの支出かもしれませんが、所得控除などの税制優遇措置を享受しつつ老後資金を積み立てる安心感は、仕事のパフォーマンス向上にも寄与する側面もあるはずです。
(5)各種年金制度等の解説
①国民年金(公的年金)
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入します。保険料は月あたり約17,000円で、原則として65歳から受給できます。
そして、令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、約66,000円(月額)です。
②国民年金基金
国民年金基金は、国民年金に上乗せして積み立てる公的年金制度です。
個人事業主と会社員の年金格差を解消するため、1991年に創設されました。
月額上限68,000円の掛金を拠出し、口数制で給付型を選択できます。
③付加年金
付加年金は、国民年金に追加して月額400円の付加保険料を納付することで、将来の年金を増額できる制度です。
将来の付加年金額は、「200円 × 付加保険料納付月数」で計算されます。
例えば、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)納付した場合、年額96,000(200円 × 480ヶ月)円が上乗せされます。この場合、納付済みの付加保険料の総額は19万2,000円(=400円 × 480月)のため、65歳から2年間付加年金を受け取れば元本が回収できるお得な制度です。
④iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、国民年金や厚生年金に上乗せして加入できる私的年金制度です。20歳~60歳未満の個人事業主は、月額5,000円~68,000円を上限に掛金を拠出し、自身で選択した運用商品で資産運用を行います。60歳以降、積立元本とその運用益を受取れますが、運用成績次第で受取額は変動します。
なお、掛金拠出限度額は、個人事業主の場合には月額68,000円ですが、これは、国民年金基金や付加保険料との合算で計算します。
将来の受取時は、一括受取りの場合は退職所得扱いになり、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いのため、税制優遇を享受できます。
⑤小規模企業共済
経営者が廃業した時の退職金代わりになるものです。
掛金は月額70,000円が上限で、月額1,000円~70,000円の範囲で500円単位で支出でき、お得な利回りで老後資金の準備ができます。
将来の受取時は、一括受取りの場合は退職所得扱いになり、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いのため、税制優遇を享受できます。
(6)何の制度に、いくら加入すべきか?
個人事業主にとって、どの年金制度にいくら加入すべきかは、年齢、収入、家族構成、事業の安定性、ライフプランなど、個々の状況によって千差万別です。画一的な答えはなく、自身の将来設計に合わせて、最適な制度設計を行う必要があります。
その際、ライフプランの策定は欠かせません。老後の生活費、必要な資金額、リスク許容度などを明確にすることが、年金制度の選択や拠出額の決定に繋がります。

時には、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談することも有効です。制度の特徴や注意点、税制優遇措置など、専門的な知見を踏まえたアドバイスを得ることで、より最適な年金対策を実現できるでしょう。
(7)おわりに
個人事業主の老後資金準備は重要な課題であり、将来の公的年金受給額を早めに確認し、老後の生活設計を立てることが大切です。
1階建て部分の基礎年金である国民年金のみでは、老後の生活費をまかなうことは難しく、公的年金に上乗せする形で、私的年金制度を活用しましょう。長期的な視点を持ち、計画的に準備を進めることが、安心できる老後生活につながります。
以上、起業時の参考にされてください。
X(Twitter)のフォローもお願いします!
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
