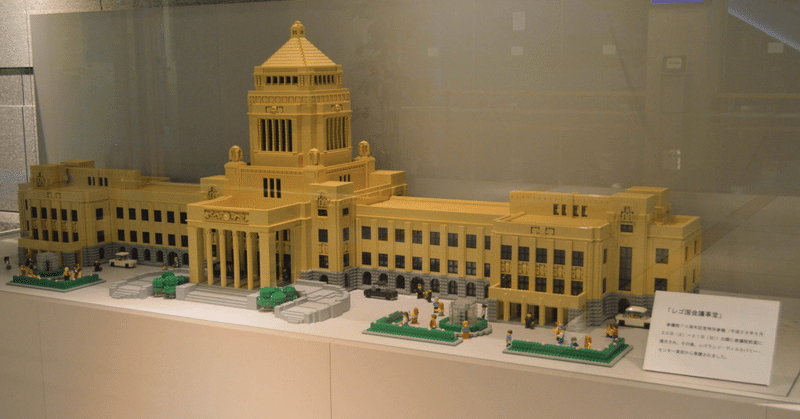
桂と原 ~太郎と敬という男~
どっちも一文字の名字ですが、
明治~大正を象徴する人物です。
桂太郎(かつらたろう)と
原敬(はらたかし)!
「桂太郎、と言えば、
明治時代の『日露戦争』の時の総理大臣で、
確か『ニコポン宰相』と呼ばれて、
ニコッと笑ってポンと肩を叩く人ですよね!」
「原敬、と言えば大正時代の総理大臣で、
確か『平民宰相』とも呼ばれて
「大正デモクラシー」のリーダー、でも
東京駅で暗殺されたんですよね…」
その通り。
…ただ、何となく、ですが
以下のようなイメージもありませんか?
◆桂太郎:薩長閥のリーダー
民主主義的でない独裁的な政治運営
◆原敬:本格的な政党政治の指導者
開明的で新時代のデモクラシー論者
私もそんなイメージでした。
桂太郎は、有名な桂小五郎(木戸孝允)と
同じ一族の桂家の出で、長州出身。
地縁や血縁を笠に着て、栄華を極めた…。
原敬は、東北、盛岡の出身で、
「一山いくら」と馬鹿にされたことから
「一山」と自ら称する反藩閥の闘士…。
『日露戦争指導者』VS『大正デモクラシー』
『薩長閥・藩閥政治』VS『平民宰相』
という対立しがちな言葉が先に来て、
どうしても対比されがち。
…ただ、当然ながら人間は
多角的な生き物ですから、光と影がある。
一面的な情報だけではわからない。
本記事では、桂太郎と原敬について、
少し詳しめに書いてみたいと思います。
(もちろん、評価は人それぞれなので、
読者の方に委ねたい、と思っています)
桂太郎。1848年~1913年。
有名な桂小五郎(かつらこごろう)とは
直接の親戚ではありませんが、
同じ桂一族の出身でもあります。
当然、小五郎に気に留めてもらった。
1868年、明治維新の頃には、まだ二十歳。
「海外を見て来たほうがいい」と思い、
1870年にドイツ留学。私費留学だったので
生活が苦しく、小五郎(木戸孝允)を訪ねて
官費留学に切り替えてもらったりしている。
…ですが、忙しい木戸が
手続きをしてくれたにもかかわらず、
1873年、留学を打ち切って帰国。
「日本に戻って実績を積んだほうがいい」
と思ったのでしょうか? このあたりは
幕末に英国に留学しながら
すぐ帰国した伊藤博文と似ています。
その伊藤博文にも重用されました。
1901年に総理大臣、初の組閣!
「小山縣内閣」「第二流内閣」と言われる。
小山縣、とは、時の実力者、山縣有朋の
二番煎じ、小間使いのような意味です。
ただ、この太郎が、なかなかやる。
外務大臣に小村寿太郎を起用して、
当時の超大国、英国と同盟を締結!
1902年「日英同盟」ですね。
1904年からの「日露戦争」を戦えたのも、
この同盟が効いている。
その後、公家出身の西園寺公望と交互に
政権を担い「桂園時代」とも言われました。
第三次、三回も内閣をつくります。
いわば、伊藤・山縣などの「維新の元老」、
偉大なる先輩たちからうまく
ソフトランディングさせようとした人…。
議会政治にも理解があり、
晩年は「桂新党」をつくろうとしました。
これは伊藤博文が作った「立憲政友会」、
いわば上からつくった政党の
良きライバルになるよう企図したもの。
「自由党」「立憲改進党」のように
在野から自由民権運動で作ったものとは違う。
一言で言えば『二大政党制』です。
『ちゃんとした野党』を作ろうとした。
でも、議会嫌いの山縣有朋ににらまれ断念。
1913年、死去。
…さて、ここまでが桂太郎。
ここからは原敬です。
原敬。1856年~1921年。
祖父は盛岡藩家老、上士の出です。
東北は明治新政府に逆らったほうなので、
戊辰戦争後、生活が苦しくなります。
家が盗難にも遭い、学費が払えずに
家に戻ってきたこともある。
元々は健次郎という名前でしたが、この時、
気分一新するために兄弟全員で改名する。
「敬(たかし)」は、この時に自らつけた。
再度上京した原は1876年、18歳頃に
司法省法学校を受験、合格します。
卒業後は新聞社、マスコミに進む。
…ただ、彼は現実主義者でした。
理想主義者では、ない。
単に批判さえすればいい、ではなかった。
現実に強い者の力を利用します。
「官民調和論」の男。
自由民権運動!民がイチバン!ではない。
そんな原に、政府の実力者が目をつけた。
井上馨。伊藤博文の盟友です。
原は政府系の新聞「大東日報」の
主筆に起用され、力をつけていきます。
井上馨、と言えば「鹿鳴館」の外務大臣。
後に、原は外務官僚、公務員になる。
1883年、薩摩藩出身の役人の娘と結婚して、
藩閥グループの一員になりました。
…このあたり、とことん現実主義者です。
対抗するのではなく取り入り、取り込む。
強者の力を利用して、のし上がっていく…。
ただ、そんな姿勢の彼を嫌う人もいます。
大隈重信。早稲田の人です。
彼とは生涯の政敵になります。
そのうちに、彼は切れ者と巡り合う。
1890年、農商務大臣になった陸奥宗光です。
和歌山出身、藩閥とは一線を画した人。
「かみそり陸奥(大臣)」とも呼ばれ、
凄腕の政治手腕を持っている男…。
彼の腹心となり、原は実力をつけます。
陸奥は1897年には病没しますが、
原は、事実上の外務大臣として活躍する。
1895年には『大阪毎日新聞』の編集長にもなり、
牛肉弁当を食べながら毎日遅くまで残業、
「ウシベン」という異名までもらった。
(漫画『鬼滅の刃』の煉獄さんみたい)
…と、このように、マスコミと官僚、
薩長閥と対抗勢力、民間の間を
行ったり来たりする中で、
彼は次第に恐ろしい力をつけていく。
実力者、山縣有朋さえ取り込む。
官界財界報道界「官民すべてに」パイプを持つ。
お公家さんの西園寺公望とは真逆、
血と汗にまみれ闘争する男…。
何度か爵位を与えられそうになりますが、
彼は「辞退」しています。
おそらくこれは「イメージ戦略」。
「平民」という看板を自分でブランディング。
こうして実力と人気をつけて、
政敵との闘争に勝ち残っていった原は、
1914年、立憲政友会の総裁に就任!
1918年「米騒動」の後には首相に就任します。
山縣はこの時、原の恐ろしさに気付いて
難色を示しましたが、抗しきれません。
彼は「本格的な」政党内閣をつくる。
「平民宰相」は流行語になる。
…ただ、1921年に暗殺されてしまうのです。
彼の死の2年後、
政友会は分裂し、政争に明け暮れ、
二大政党制が根付くことはありませんでした。
今でも、根付いていません。
彼の死を聞いた時、山縣有朋は
「凄い奴を失った」と熱を出し寝込んだそうです。
最後に、まとめます。
本記事では桂と原、二人の人物像と経歴を
少し詳しめに書いてみました。
イメージとちょっと
違う部分もあったのではないでしょうか?
解釈は、読者の皆様に委ねます。
もちろんこれも、私の取捨選択による
「一面的な」内容の記事、とも言えます。
気になった人は、ぜひ、
彼らを検索して調べてみてくださいね!
※明治~大正時代の有名人をつなげた
こちらの記事もぜひ!
『古河市兵衛という補助線』↓
合わせてどうぞ!
よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!
