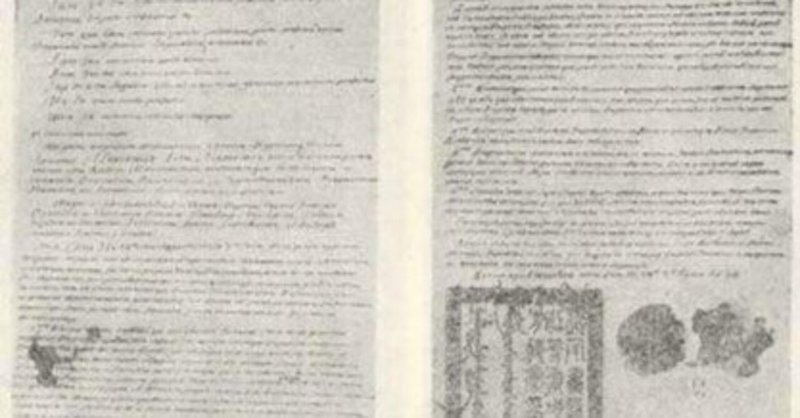
ネルチンスク条約ラテン語版を和訳してみた(第4回)
Rivulus nomine Kerbichi, qui rivo Chorna Tartaricé Vrum dicto proximus adiacet et fiuvium Sagalien Vla influit, limites inter utrumque Imperium constituet.
Item a vertice rupis seu montis lapidei, qui est supra dicti rivuli Kerbichi fontem et originem et per ipsa huius montis cacumina usque ad mare, utriusque Imperii ditionem ita dividet, ut omnes terrae et fluvii sive parvi sive magni qui a meridionali huius montis parte in fluvium Sagalien Vla influunt sint sub Imperii Sinici dominio, omnes terrae vero et omnes rivi qui ex altera montis parte ad Borealem plagam vergunt sub Euthenici Imperii dominio remaneant, ita tamen, ut quicunque fluvii in mare influunt et quaecumque terrae sunt intermediae inter fluvium Vdi et seriem montium pro limitibus designatam prointerim indeterminatae relinquantur.
今回は本文の第1条の一部を読んでいきます。
短い文が1つと長い文が1つあります。長い文は、分割して説明します。
なお、途中で比較のためにロシア語版や中国語版ネルチンスク条約の和訳を入れています。当方ロシア語は疎いため、DeepLに任せています。
Rivulus nomine Kerbichi, qui rivo Chorna Tartaricé Vrum dicto proximus adiacet et fiuvium Sagalien Vla influit, limites inter utrumque Imperium constituet.
ネルチンスク条約の一番根幹となる部分です。地名がラテン語表記なので、特定するのが困難でした……。間違えていたらご指摘お願いします。
「Rivulus nomine Kerbichi」は、「ケルビチという名前の小川」となります。
その後の「qui rivo Chorna Tartaricé Vrum dicto proximus adiacet et fiuvium Sagalien Vla influit」で、この川は「タタール語で「ウルム」と書くコルナ川に隣接し、サガリャン=ウラ川に流れる」川であることが分かります。
この川は「imites inter utrumque Imperium constituet.」、つまり「両帝国の境界として定められた」とされています。
よって、この川は世界史の知識で言えばアルグン川(黒竜江上流)となるのではないかと予想できます。しかし、このラテン語の文では「ケルビチ」川とされており、「ケルビチ」川=アルグン川なのかはまだ特定できません。そこで、調べてみました。
ロシア語版ネルチンスク条約の同じ箇所は、このように書かれています。
「チェルナヤ川の近くの左側でシルカ川に流れ込むゴルビツァという名前の川が、両州の境界を定めています。」
ここで、ケルビチ川=ゴルビツァ川だと分かります。しかし、ゴルビツァ川が何なのかは、調べても出てきませんでした。
そこで、ネルチンスク条約に関する論文を読んでみました。
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/255577/1/JOR_76_2_372.pdf
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/153888/1/jor042_1_62.pdf
両論文によると、アルグン川の上流がゴルビツァ川(=ケルビチ川)だと分かります。
ここが川としての国境の始点となるようです。
ところで、両論文とも「ケルビチ」ではなく「ゲルビチ」としています。しかし、ラテン語は日本語のローマ字と同じように読むため、「Kerbichi」はラテン語読みすれば「ケルビチ」となるはずです。なぜ「ゲルビチ」となるのかは、さらなる研究が必要になりそうです。
本記事では、「ケルビチ」と読んで進めます。
さて、この情報からサガリャン=ウラ川が黒龍江を指すのではないかと予想できます。この予想が正しいか、他の言語で書かれたネルチンスク条約から調べてみました。
ロシア語版には説明がありませんでした。
中国語版では、「北から黒龍江に流れ込むチョルナ川、つまりウルム川近くのゲルビチ川に囲まれることになる。」とあります。
ラテン語の文章と照らし合わせると、「北から黒龍江に流れ込むChorna川(Vrum川)の近くのケルビチ川」となります。よって、「サガリャン=ウラ川」=「黒龍江」と断定できます。
ちなみに、こちらの文章には誤字があります。「fiuvium」というラテン語は存在しません。おそらく、「fluvium(川)」の誤りではないかと思います。
よって、この箇所は
「ケルビチという名前の川(タタール語でウルムと書くシルカ川に隣接し、サガリャン=ウラ川に流れる)が、両帝国の境界として定められた」
Item a vertice rupis seu montis lapidei, qui est supra dicti rivuli Kerbichi fontem et originem et per ipsa huius montis cacumina usque ad mare, utriusque Imperii ditionem ita dividet,
カンマごとに区切って説明します。
「Item a vertice rupis seu montis lapidei」は「岩または石の山の頂上から」。
この岩がどこにあるのかは次の区切りで説明されます。
ちなみに、「lapidei」の原形は「lapideus(岩でできた、岩のような)」。「lapideus」は「lapis(石)」から来ています。「lapis lazuli(ラピスラズリ)」の「lapis」です。
「qui est supra dicti rivuli Kerbichi fontem et originem」は「その名をケルビチという川の源泉の上にある」となります。
次に「et(&)」が来るので一度区切ります。
ここまでを繋げて、「その名をケルビチという川の源泉の上にある岩または石の頂上から」となります。
「et per ipsa huius montis cacumina usque ad mare」は「この山の頂上を通って海まで」となります。
「utriusque Imperii ditionem ita dividet,」は「両帝国の権力を分かつ」となります。「権力を分かつ」だと日本語としておかしいので、「領域を分かつ」のほうがいいでしょうか。
ここまで繋げて訳してみると、こんな感じです。
「その名をケルビチという川の源泉の上にある岩または石の山の頂上からこの山の頂上を通って海まで、両帝国の領域を分かつ。」
世界史の教科書ではざっくりと「アルグン川が国境線である」と紹介されていますが、正確にはもっと細かく決められていたことが分かります。個人的には、岩が国境線の起点となっているのが面白いと思いました。よほど目立つ岩なのでしょうか……?侵食などでなくなったりしないのでしょうか……?など、思いを巡らせてしまいます。
ちなみに、ロシア語では「また、その川の最上流から始まる石山脈のそばから、その山々の最上流に沿って、海にまで広がって、両国の支配権を分割し、」となっています。「岩」という記述はなく、山脈のそばからその山々の上流に沿って……ということになっています。このように、ラテン語版とロシア語版で異なる点が多々あります。
ut omnes terrae et fluvii sive parvi sive magni qui a meridionali huius montis parte in fluvium Sagalien Vla influunt sint sub Imperii Sinici dominio,
分けて読むと、
「ut omnes terrae et fluvii」は「全ての土地と河川は」
「sive parvi sive magni」は「大きい方も小さい方も(=大小)」
「qui a meridionali huius montis parte」は「その山の南部から(quiは関係代名詞)」
「in fluvium Sagalien Vla influunt」は「サガリャン=ウラ川へ流入する」
「sint sub Imperii Sinici dominio」は「〜は清帝国の支配下である(sintは英語でいうbe動詞)」
となります。
合わせると、「山の南部から始まるサガリャン=ウラ川へ流入する大小全ての土地と河川は清帝国支配下となる。」となります。
omnes terrae vero et omnes rivi qui ex altera montis parte ad Borealem plagam vergunt sub Euthenici Imperii dominio remaneant,
「Euthenici」というラテン語は存在しません。前後の文から見て、おそらく「Ruthenici(ロシア)」だと思われます。ラテン語さんにも確認を取りました。
また分けて読んでみます。
「omnes terrae vero et omnes rivi」は「全土と全河川」となります。「vero」はおそらく「本当に、特に」という意味の副詞ではないかと思われます。和訳にはうまく落とし込めませんでした……。
「qui ex altera montis parte」は「山の反対側から(quiは関係代名詞)」
「ad Borealem plagam vergunt」「北側地域まで広がる」。「Borealem」は「meridionali」の対義語にあたると思われます。よって、「Borealem」は固有名詞ではなく、「B」と大文字になっているのは誤字ではないかと思います。
「sub Euthenici(Ruthenici) Imperii dominio remaneant,」は「ロシア帝国の支配下となる」です。「remaneant」は「残り」という意味ですが、うまく和訳に落とし込めませんでした。おそらく、南部は清帝国、残りの北部はロシア帝国の支配下にそれぞれなる、という意味ではないでしょうか。
ところで、第2回の記事で、ロシアは厳密に言うと現時点では「ロシア=ツァーリ国」であって「ロシア帝国」ではないという話をしました。しかし、ネルチンスク条約では「Ruthenium Imperium(ロシア帝国)」とされています。ここから、ピョートルが大帝と呼ばれる以前から、公式文書では「ロシア帝国」と呼ばれていたことが分かります。
ちなみに、「Ruthenium」という呼称はロシアのルーツである民族名「ルーシ」から来ているようです。化学物質の「ルテニウム(Ruthenium)」の語源でもあります。
合わせて。「山の反対側から北部に広がる全ての土地と河川は全てロシア帝国の領土とする」
となります。
ita tamen, ut quicunque fluvii in mare influunt et quaecumque terrae sunt intermediae inter fluvium Vdi et seriem montium pro limitibus designatam prointerim indeterminatae relinquantur.
また分けて読みます。
「ita tamen」は「しかし」という意味です。
「ut quicunque fluviiin mare influunt」は「海に流れるどの川も」。
「et quaecumque terrae」は「〜とどの土地も」。
「sunt」は英語で言うbe動詞です。
「intermediae inter fluvium Vdi et seriem montium」は「ウディ川と山脈の間」。
「ウディ川」は、「ウダ川」とも言います。変化系かとも思いましたが、詳しくは分かりませんでした……。
調べてみると、オホーツク海に流れ込む川で、スタノヴォイ山脈東部の南に源を発し、ほぼ東に流れる川のようです(Wikipediaよりhttps://en.wikipedia.org/wiki/Uda_(Khabarovsk_Krai))。
「pro limitibus designatam」は「境界として示された」。これは「montium」にかかっているので、合わせて「境界として示された山脈」となります。
明確には示されていませんが、この「山脈」が外興安嶺(スタノヴォイ山脈)であると考えられます。
「prointerim indeterminatae relinquantur」は「当分未確定として残す」。
合わせると、「しかし、ウディ川と境界として示された山脈の間にある海に流れる全ての河川、土地も未確定として残される」。
以上で第1条の前半が終わりました。すべてまとめると、
「ケルビチという名前の小川(タタール語で「ウルム」と書くシルカ川に隣接し、サガリャン=ウラ川に流れる川)は両帝国の境界として定められた。その名をケルビチという川の源泉の上にある岩または石の山の頂上からこの山の頂上を通って海まで、両帝国の領域を分かつ。しかし、ウディ川と境界として示された山脈の間にある海に流れる全ての河川、土地も未確定として残される」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
