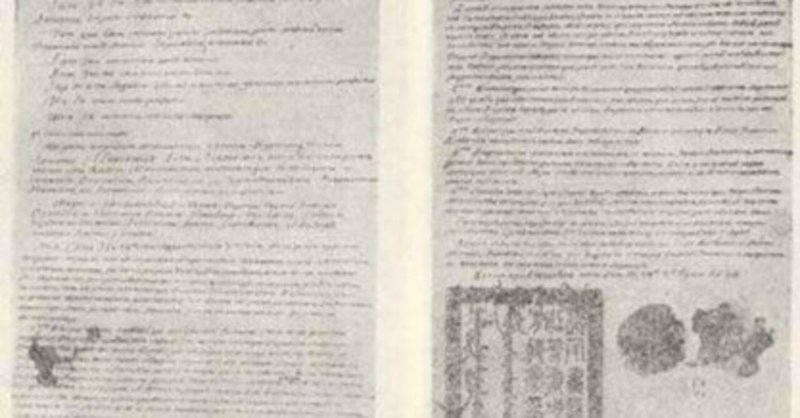
ネルチンスク条約ラテン語版を和訳してみた(第2回)
こちらの記事の第2回目です。
今回は、ロシア側の使節を列挙している部分を読んでいきます。
参考ページ:
ツァーリ
Dei gratia magnorum dominatorum Tzarum Magnorumque Ducum loannis Alexiewicz, Petri Alexiewicz totius magnae ac parvae, nee non albae Russiae Monarcharum, multorumque dominiorum ac terrarum Orientalium, Occidentalium ac Septemtrionalium, Prognatorum Haeredum, ac Successorum, dominatorum ac possessorum
「イヴァン=アレクセイヴィッチとピョートル=アレクセイヴィッチ
(神の恩寵による大君主、ツァーリ、大公、全大ロシア・小ロシア・白ロシアの専制君主、あまたの国および東方・西方・南方地域の王位継承者、統治者、君主)」
早速長くて複雑ですが、一つ一つほぐしていきます。
どの言葉も「 Ioannis Alexiewicz, Petri Alexiewicz」の説明です。彼らはロシアの君主ですが、君主として多くの称号を持っているため、長々とした説明になっているのです。
「Dei gratia」は直訳すると「神の恩寵」。ここでいう神は、ロシアの宗教であるキリスト教(正確に言うとギリシア正教)のGodです。
多分、清でも出てきた似たような言葉「神聖な」と同じように、枕詞だと思います。
実は、中世イギリスで成立した「マグナ・カルタ」にも、同じ表現が使われています。
Johannes Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie, dux Normannie et Aquitannie,
ネルチンスク条約とマグナ・カルタを両方読むことで気づくこともあるのだと学びました。なんでもラテン語で読んでみるものですね。
さて、このネルチンスク条約の文には、通常ではあり得ない不思議なことが書かれています。
それは、君主が2人いるということです。世界史の教科書には、ネルチンスク条約とはピョートル=アレクセイヴィッチことピョートル1世が結んだ条約であるとされています。
では、 Ioannis Alexiewicz(イヴァン=アレクセイヴィッチ)とPetri Alexiewicz(ピョートル=アレクセイヴィッチ)とはどのような人なのでしょうか?また、なぜ君主の名前が2つ書かれているのでしょうか?
手元にいい資料がないためWikipediaで調べた結果ですが、紹介します。
1676年、ロシアのツァーリ(君主)としてフョードル3世が即位しました。
彼は結婚し子どもも生まれましたが、幼くして亡くなってしまいます。
再婚するものの、彼自身病気ですぐに亡くなってしまいました。彼は世継ぎを残すことができないまま生涯を閉じたのです。
本来ならばフョードル3世の兄弟イヴァンが跡を継ぐはずでしたが、彼は生まれつき障害を持っていました。よって、フョードル3世の異母兄弟であるピョートルが選ばれ、ピョートル1世として即位しました。1682年のことです。
しかし、同じロマノフ家と言えどもイヴァンとピョートル1世は親戚としては遠い関係にありました。それにより、先代フョードル3世の家系からツァーリを排出したい派閥(ミロスラフスキー派)が不満を持っていました。
そこで、彼らはクーデタを起こしましたこれに乗じて、ミロスラフスキー派は自分達が本当にツァーリにしたかったイヴァンを即位させ、イヴァン5世としたのです。1682年のことでした。
しかし、ピョートル1世は死んだわけではありませ
ん。妥協案として、ピョートル1世はイヴァン5世の共同統治者に格下げされました。
さて、こうして成立したイヴァン5世政権ですが、先述の通り彼は障害を持っています。
よって、彼には摂政がつきました。それが彼の姉、ソフィヤでした。彼女は主席顧問ゴリツィンと手を組み、精力的に政治を行いました。
障害があるにもかかわらず、無理矢理ツァーリにさせられた挙句実権は姉に握られてしまったイヴァン5世。かなり可哀想だと思うのは私だけでしょうか……?
さて、そんなイヴァン5世(ほぼソフィヤ)政権はピンチを迎えます。
それはクリミア戦争の失敗です。クリミア戦争に敗れ領土を拡大できなかった政権は支持力を失いました。その代わりに期待されたのが、成長した共同統治者ピョートル1世でした。
そんな混乱の中で結ばれたのがこのネルチンスク条約でした。
この時はイヴァン5世が先に、ピョートル1世が後に書かれていることから2人が共同統治者であったことがわかります。
しかし、ネルチンスク条約はどちらかと言うと中国側に有利な条約となりました。ロシアは取りたかった領土を取らずに終わったのです。
こうして、イヴァン5世側の株は下がり、追い込まれることになりました。
ネルチンスク条約から約1ヶ月後、ソフィヤはピョートル1世にに政府を明け渡しました。そしてソフィヤは修道院に幽閉され、ゴリツィンは流罪となりました。
よって、ネルチンスク条約はイヴァン5世とピョートル1世の共同統治末期に書かれた文書、ということになります。
長くなりましたが、もう一つだけネルチンスク条約の上記の箇所の説明をさせてください。
それは肩書きについてです。この時期のロシアの君主は「ツァーリ」と呼ばれる、というのは世界史の教科書にも載っている話です。しかし、実は中国側に書いてある「Imperator(皇帝)」と全く同じ立場、というわけではないのです。
細かくいうと、モンゴルの「ハン」などと同じで、「ツァーリ」とはロシア固有の君主の名称なのです。
日本語にしてしまえば「皇帝」と言ってもいいのですが、本当は「皇帝(Imperator)」とは別の称号なのです。よって、正確に言うとこの時期のロシアは「ロシア帝国」ではなく「ロシア=ツァーリ国」です。ここまで私が「ロシア帝国」と敢えて言わなかったのはこれが理由です。
では、いつロシアは「ロシア帝国」になったのでしょう?それは、大北方戦争に勝利してからです。
詳細は省きますが、この戦争で大きな成功を収めたピョートル1世には、「ツァーリ」よりもさらに偉大な称号がふさわしいとされました。それが、「皇帝(Imperator)」だったのです。ここから、ロシアは「ロシア帝国」と呼ばれ始めます。
……まあ、ツァーリは皇帝と言えば皇帝なので、ネルチンスク条約本文でロシア側の君主は「Imperator」と呼ばれていますが。
たった1つの文章からでも、この時代のロシア情勢を窺い知ることができます。
Magnis ac plenipotentibus Suae Tzareae Majestatis Legatis Proximo Okolnitio ac locitenente Branski Theodoro Alexiewicz Golovin dapifero ac locitenente Iélatomski, loanne Eustahievicz Wlasoph Cancellario Simeone Cornitski
「強大で万能であるツァーリ国王陛下の大使、宮内官(オコリニチー)・ブリャンスク総督フョードル=アレクセイヴィッチ=ゴロヴィン・ブリャンスク総督、大膳職(ストリニク)・エラトムスキー総督イヴァン=オスタフェヴィチ=ウラソフ、書記官セニョン=コルニツキー」
ロシア側の大使の紹介です。3人います。
1人目はこの人です。
テオドロ、セオドロ、フョードルなどは全て同じ名前なんですね!(エリザベス、エリザベート、エカチェリーナなどが同じ名前なのと同じ関係)
はじめはWikisourceのミスかと思ってしまいました笑
「オコリニチー」とは官職・階級の名前です。
この頃のロシア貴族には階級がありました。
8個ある階級のうち、上から2番目がオコリニチーのようです。
……という以上はいまいち分かりませんでした。要するに、結構偉い貴族、だと思います。雑ですみません……。
「ブリャンスク」とは、地名です。
当時かなり栄えていた都市ではあったようですが、ネルチンスク条約に関わるにはあまりに遠い場所の気がします。重要な都市を任されるくらい偉い人だったから条約締結の場に呼ばれた、とかでしょうか……?
私の検索が間違えている可能性もあります……。
2人目はイヴァン=オスタフェヴィチ=ウラソフ。ロシア語版Wikipediaには記事がありました。
「ストリニク」とは、中位貴族の名称らしいです。先ほどの貴族の階級で言うと、上から4番目です。
条約文には書かれていませんが、彼は1684年ネルチンスク知事に任命されていたようです。そうした人物がネルチンスク条約締結に関わっているのは納得です。
条約に書かれている「エラトムスキー」は地名です。多分この場所ですかね……?ロシア語版ネルチンスク条約に出てきた地名を検索したら出てきました。
うーん、やっぱりネルチンスクからはかなり遠いですね。1人目と同じく、モスクワ近くを治めるくらい偉い人、ということでしょうか。
3人目はセミョン=コルニツキー。
詳しい情報は得られませんでした。
以上、ネルチンスク条約のロシア側大使の紹介部分でした。
全部まとめるとこんな感じでしょうか。
「イヴァン=アレクセイヴィッチとピョートル=アレクセイヴィッチ(神の恩寵による大君主、ツァーリ、大公、全大ロシア・小ロシア・白ロシアの専制君主、あまたの国および東方・西方・南方地域の王位継承者、統治者、君主)、
強大で万能であるツァーリ国王陛下の大使
・宮内官(オコリニチー)兼ブリャンスク総督フョードル=アレクセイヴィッチ=ゴロヴィン
・大膳職(ストリニク)兼エラトムスキー総督イヴァン=オスタフェヴィチ=ウラソフ、
・書記官セニョン=コルニツキー
という感じでしょうか。
次もネルチンスク条約前文の解説です。
乞うご期待!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
