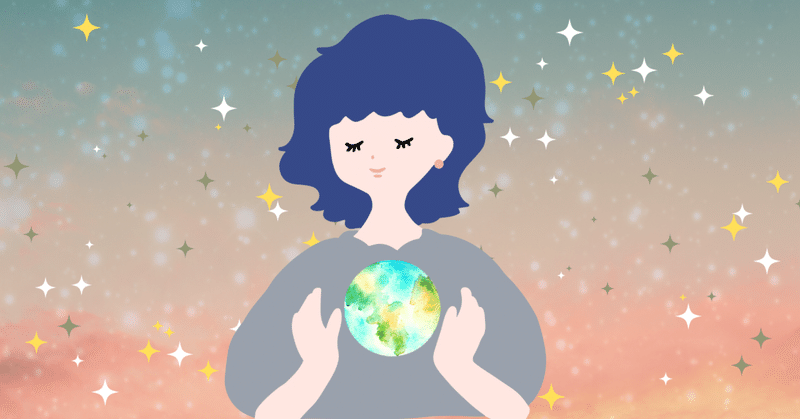
G7/G20の「脱炭素電源」の比率が高まる中で・・・出遅れる日本は、環境意識が低いから?
9/19の日経新聞の記事には「G7・G20の脱炭素電源比率高まる 10年以降7ポイント超」という記事が出ていました。ウクライナ侵攻などによって炭素電源に逆戻りしているのではと心配をしていましたが、世界においては、脱炭素電源である再生可能エネルギーおよび原子力発電所が増えているようです。
再生可能エネルギーと原子力発電を合わせた「脱炭素電源」の比率が高まってきた。主要7カ国(G7)と20カ国・地域(G20)の総発電量に占める比率は2010年以降、ともに7ポイントあまり伸びた。太陽光と風力がけん引役で、原子力は各国で温度差がある。出遅れる日本は対策を急ぐ。
「30年までに再生エネを3倍にする」。10日に閉幕したインドでのG20首脳会議の首脳宣言にはこう盛り込まれた。事前の閣僚会合の宣言は見送った野心的な目標だったが、気候問題への危機感が明記の背景にある。
今夏は世界で異常な高温が続いた。国連のグテレス事務総長は7月に「地球温暖化の時代は終わり、地球が沸騰する時代がきた」と表現した。
各国は温暖化ガスの排出量を減らそうと脱炭素電源を増やしてきた。石炭や天然ガスを輸出してきたロシアのウクライナ侵攻を受け、足元ではエネルギー安全保障の観点からも再生エネを導入する動きが加速している。
各国の電源比率を英オックスフォード大学などが運営する「Our World in Data」のデータで比べると、G7の脱炭素電源は10年の39%から22年の47%まで伸びた。
1)脱炭素電源が増えている日本
G7各国の発電比率についてのグラフがわかりやすく記事に載っていましたが、英国は風力発電を、ドイツは風力発電や太陽光発電を増やすことですでに50%を超えています。
しかし日本はこの12年間で、東日本大震災、そして福島第一原子力発電所の事故があったとはいえ、各国の中においてはむしろ石炭が増えており、大きく後退をしているという状況です。

2)英国において、脱ガソリン車5年延期
英国は前述した通り、この12年で大きく脱炭素電源へとシフトをしてきました。しかし9月22日の記事には、脱ガソリン車を5年延期とすることにしたという記事が掲載されていました。
いくら国が先導を切っても、企業がそこについていけないと目標を達成できないということですが、やはり国民が、そのような目標達成をできない企業を見捨てるような動きにならないと、企業も変わっていかないのではないか。この脱炭素という分野においては、いかに国民に理解し、動いてもらうのかという点が必要な気がしてなりません。
スナク英首相は20日、2030年としてきた英国内のガソリン車とディーゼル車の新車販売の禁止を35年まで先送りすると表明した。主要国の環境規制をけん引してきた英国の政策変更は、世界的な脱炭素の流れに影響を与えかねない。
ガソリン車の販売比率が大きい一部の自動車メーカーが「準備期間が短すぎる」などとして先送りを求めていた。
新築住宅のガスボイラー禁止なども見直す。温暖化ガス排出を50年に実質ゼロにする目標は維持する。
3)日本における環境意識が低い・・・
日本がG7の中でもっとも脱炭素電源の導入が後退している状況ですが、これが単純に福島第一原発事故によるものなのか。やはりここは国民の環境意識にもあるのではないか、と思ってWebで調べてみると興味深い調査がありました。
2022年6月30日に経営コンサルティングファームのボストン コンサルティング グループが、日本全国の消費者を対象に実施した「サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査」の最新の調査結果を公表していました。
私は自然が多くそして海に囲まれている、そしてゴミが少ないきれいな国という印象の日本では、諸外国に比べると意識が高いのではないかと思っていたのですが、諸外国よりも低いという結果に衝撃を受けました。こういうニュース、全く聞いたこともなかったので。。。
以下に一部を引用して掲載をしますが、今の日本において脱炭素電源の導入が増えないのは、この国民意識にあるのではないかと思いました。しかし、インドやブラジル、中国よりも低いというのはなぜなのでしょう。
日本の消費者の環境意識は調査対象の新興国(インド・ブラジル・中国)や欧米と比較して低い
今回の調査では、米国、英国、中国、インドなど世界各国で行われた調査を日本でも行い、日本と他国の消費者の気候変動問題に対する意識の違いを明らかにしました。日本の消費者は、さまざまな角度から見て環境意識が低いと言え、例えば、日常生活における自分の行動が気候変動に与える影響について「いつも気にしている」と答えた人は調査対象11カ国中最低の10%でした(図表1)。
日本の消費者は気候変動対策として消費を制限することに対しても消極的であり、「気候変動に与える影響を減らすために、自分の消費を制限することができる」と回答した人(完璧にできる、まあできると回答した人の合計)は、11カ国中最低の45%でした(他国はいずれも80%以上)。
また、周りの人が環境に配慮していなくても気にしない傾向が強く、「気候変動対策としての行動を全くしていない人やほんの少ししかしていない人たちに対して、あなたはどう思いますか」という質問に対し「多くの人にとって行動を変えることは難しいので、理解できる」と回答した人は76%と、中国の78%に次ぐ割合でした(図表2)。
先日に国民の意識を変える必要があると思って記事を書いたのですが、その時はすでに先頭の方にいて、という中でさらに他の国を引っ張ってというような意識があったのですが、まずは他の諸外国の意識に追いつくところから、なのですね。
この調査結果のページは以下のとおりです。
自分なりにもなにかできることを考え、具体的なアクションに繋げられればと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
