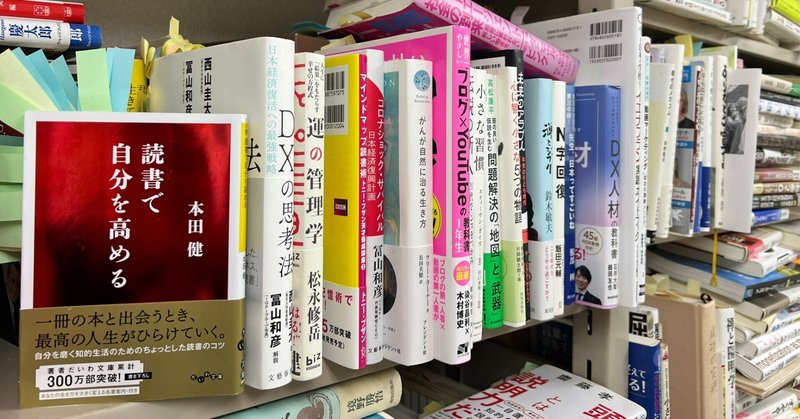
読書とボキャブラリー
今日のおすすめの一冊は、本田健氏の『読書で自分を高める』(だいわ文庫)です。その中から「孤独を愉しむ」という題でブログを書きました。
本書の中に「読書とボキャブラリー」という心に響く文章がありました。
本を読むと、自然とボキャブラリーが増えます。 ボキャブラリーには、2通りあります。アクティブ・ボキャブラリーと、パッ シブ・ボキャブラリーです。 アクティブ・ボキャブラリーは、ふだんあなたが使う言葉です。 パッシブというのは、受け身という意味で、ふだんは使わないけれど、理解はできるという言葉です。
この、聞いたらわかるという言葉が多い人ほど、ある意味で教養があるといえます。たとえば、「たおやかな女性」というと、一瞬で細身の美しい仕草の女性を想像する人もいるし、「??」となる人もいるでしょう。ひけらかす必要はありませんが、難しい言葉をよく知っている人は、人間的に奥行きがある空気感をまとうようになります。
そして、たくさん言葉を知らないと、自分のことを表現することができません。 たとえば、自分の感情を表現しようと思ったときに、本を読まない人ほど、ボ キャブラリーが少なすぎて、小学生のような感じになってしまいます。気分が悪いとか、イヤな感じがする、悪いなと思っている、ぐらいしか言えないのです。
言葉の裏には、世界が広がっているのです。 その感情を分析していくと、「罪悪感」という言葉が出てくるでしょう。その罪悪感にも種類があって、それが何なのかを見ていかないと、自分が何を感じているのか、はっきりすることができません。
それはたとえば、「自責の念」といった、自分を責めるような感情かもしれないし、「悔悟」というとりかえしのつかないことをしてしまったと後悔するような感情かもしれません。また、「良心の呵責」といった、モラル的なことかもしれないし、「後ろめたい」という気持ちかもしれません。
そういうボキャブラリーがなければ、自分のなかにあるモヤモヤした気持ちを、「イヤな気分だ」という言葉にしか集約できません。 それが明確にできないと、いつまでたっても、気持ちは晴れないままです。 言葉を知っていることで、自分のことが理解できるようになるとは、こういうことなのです。
ふだん、自分の教養をひけらかす必要はありませんが、言葉を知っていることで、自分のことがよりわかりやすくなるというのは、知っておいて損はないでしょう。 ボキャブラリーを増やすことで、内面だけでなく、世界に何が起きているかについても詳しくなります。それは、言葉を知ることが、あなたの認識能力を高めることになるからです。
◆「たおやか」とは「たわむ」からきている大和言葉だ。柳のようにしなやかに曲がるさまをいい、どんなことがあっても折れることなく、柔軟にやりすごす芯の強さのある人。
大事なことは、いくらボキャブラリーが増えたとしても、それをアウトプットしないと身に付かないということ。パッ シブ・ボキャブラリーもずっと使わなければ、忘れてしまう。
読書を通してボキャブラリーをふやしたい。
今日のブログはこちらから→人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
