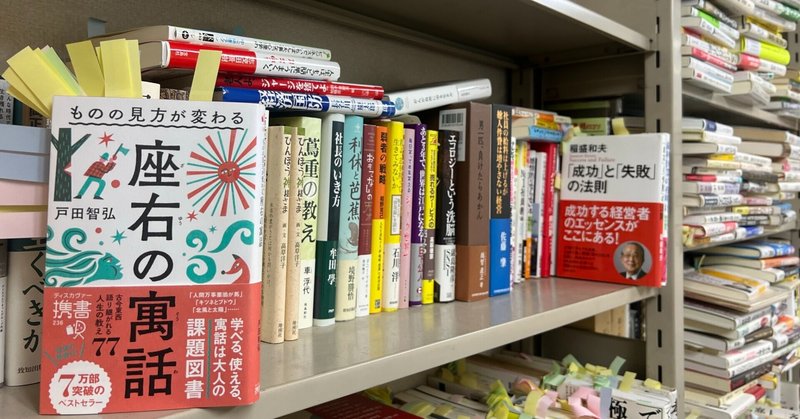
ましての翁
今日のおすすめの一冊は、戸田智弘氏の『座右の寓話』(ディスカヴァー携書)です。その中から「有難屋吉兵衛」という題でブログを書きました。
本書の中に「ましての翁(おきな)」という心に響く文章がありました。
以前、近江の国に仏教の篤信(とくしん)者がいた。その者は普段から何事につけても 「まして、まして」と言っていたので、近所の人たちは「ましての翁(おきな)」というあだ名をつけていた。
暑い日に道で会ったとき「本当に暑いですね」と挨拶すると、その老人は「暑いには違いない。人間の世界でもこのくらい暑いのだから、まして焦熱(しょうねつ)地獄ではどのくらい暑いかはしれない。それを思えば、このくらいの暑さは辛抱しなければなりません」と答えた。
寒い日に道で会ったとき「たいそう寒いですね」と挨拶すると、その老人は「寒いには違いない。人間の世界でもこのくらい寒いのだから、まして八寒(はっかん)地獄にでも落ちたら、どのくらい寒いかしれません。それを思えばこのくらいの寒さは我慢しなくてはなりません」と答えた。
老人はこのように何事についても、生涯不平不満を言わず、いつも人に対して「まして、まして」を連発し、いつもニコニコしながら生活していたという。だから、人は本名を呼ばないでこの老人のことを「ましての翁」と呼んでいたとのことである。
《基準値を下げて「ほどほど」でいく》
不平不満の多い人の特徴は、基準値が高いことである。逆に、不平不満の少ない人の特徴は、基準値が低いことである。「ましての翁」は極端に基準値の低い人だ。 基準値を下げるという心構えは、他人や会社に対する振る舞い方を考えるうえでも有効である。
他人や会社に対して不平不満をまくし立てる人は、例外なく他人や会社に求める基準値が高い。六〇点では満足せず、あくまでも一〇〇点を求める。一〇〇点と現状のギ ャップが不平不満を生む。
だが、待ってほしい。自分が満点の人間でないのと同様、他人も満点の人間ではない。 会社も同じで、満点の組織ではない。みんな一長一短を持っている。“ほどほどの人間”、“ほどほどの会社”なのである。完璧主義を捨て、ほどほど主義でいこう。「まあ、世の中、 こんなもんだろ」というような達観した態度でニコニコしながら生活するのが賢明である。
「基準値を下げて生きる」とは「下座(げざ)行」のことでもあります。森信三先生は下座行についてこう語っています。(師教を仰ぐ/森先生に導かれて)より
■そもそも一人の人間が、その人の真価より、はるかに低い地位に置かれていながらそれに対して毫(ごう)も不満の意を表さず、忠実にその任を果たすというのが、この「下座行」の真の起源と思われる。
■下座行とは、一応、社会的な上下階層の差を超えることを、体をもって身に体する「行」といえる。例えば「高慢」というがごとき情念は、自分の実力を真価以上に考えるところから生じる情念といってよかろうが、もしその人に、何らかの程度でこの「下座行」的な体験があったとしたら、その人は恐らく、高慢に陥ることを免れうるのではあるまいか。
下座行に徹している人は、威張ったり、偉そうにしたりすることはありません。逆にいうなら、下座行ができない人が、高慢になったり、不平不満を表す人だということです。
下座行に徹することのできる人でありたいと思います。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
