
コミュニティが苦手だったわたしが、コミュニティの世界を垣間見てきて思うこと。
このnoteは、コミュニティのカレッジ(コミュカレ)のアドベントカレンダー企画エントリーnoteです。
こんにちは、ひろのです。
第1期(2022.05)からコミュニティのカレッジという場に参加しています。
でも、本当は「コミュニティ」という響きが苦手でした。
そんなわたしが参加に至ったきっかけや、8か月たった今、改めてどんなことを受け取っているか言葉にしてみたいと思います。
「自然体」は1人では成り立たないのではないか
わたしは、昨秋(2021.10)からTHE COACH Academyにてコーチングを学んできました。応用コースでの統合心理学をベースにしたビジョンワーク・自分への問いかけによって浮かんできた言葉は「自然体で、ただそこに在る」。
言葉は妙にしっくりくるけれど、それってどういうことなんだろう。「自然体ってどんな状態?」「在るってどういうことだろう?」わたしが生きていくうえで大切なものがつまっていそうという直感のままに、頭の片隅にはいつも問いがある日々を過ごすことになりました。
その過程ではずっと自分の内面に焦点をあて続けていました。あらゆる自分の一面に気づき、向き合い、嬉しくなったり葛藤したり。そうして自己理解が深まるなかで、はたと思い至るのです。
「自然体」とは自分1人では成り立たない、”つながり”が前提となる概念ではないか、と。
そこで感じていたのは自分の内面だけに焦点をあてることの限界と、自然体というのはもっとスケールがおおきいものではないかという可能性。同時に、「個人の内面」と「社会やつながり」の構造の共通点や相互作用に対して、同じようにながれるもの(相関関係)があるのではないかという仮説も抱いていました。
そこで流れてきたのが、コミュカレの案内。「コミュニティ」という言葉には感覚的にしぶい反応がでましたが、コミュニティマネージャーやいろんな組織の方々が集い対話する場には”つながりの本質”があるのではないか、延いては”自然体の探究に直結しそう”という好奇心で申し込みをしました。
ゲストの方々が素敵で魅かれたことも言うまでもありません。
***
「コミュニティ」が苦手なわたし
わたしにとって、当時の「コミュニティ」という言葉のイメージは、閉鎖的な、密な集合体というイメージで、ネガティブなものでした。
昔をふり返ると、子供のころから人付き合いは広く浅くタイプでした。親友と遊ぶ姉をうらやましく思いつつ、それぞれのグループとほどよく仲良く孤立感は感じない。大人になってふり返ってもなかなか器用に付き合っていたように思います。
その中でも1つ、失敗した思い出もあります。中学時代、わたしの無自覚の許容距離感の内側に踏み込んできた友人を拒否してしまったこと。高校時代に訪れた2回目は、1回目の失敗から温和に対応できましたが、それでも感覚的に突然発動する黄色信号はなんなのだろう、というとまどいが残りました。
これらの程よい距離感は、ひとにとどまらず、もの・ことにも発揮され、偏愛な、職人なひとたちに憧れると同時に悩みのたねになっていました。そんな付き合い方は、内省の結果、「敵をつくりたくない」「衝突したくない」という防衛手段であったという意味づけに着地しています。
コーチングの学びの派生でゲシュタルト療法というセラピー領域のグループワークを体験した際、zoom越しの16人ほどの前で理性に反して涙がでるわたしに、「その涙は何と言っているの?」と問われ、思考が働かないなかで「危険だ」と答えた衝撃は強く印象に残っています。
取り乱しているその様を複数のひとに見られているこの状況こそ危険である。それは自覚なく、幼少期から身体的に染み込んでいる感覚なのだろうとはじめて認識することとなりました。
すべての行動の起点がここに集約するとは考えていませんが、バレー部時代にリベロやセッターにつき、副部長をし、吹奏楽時代に打楽器をし、バンド時代にドラムやPA卓をする。どれも全体が見渡せるポジションで、距離感がはかれるポジションで自分を活かしてきたことに、共通項を見出し「ああ、そうか~」と少し笑ってしまうわたしがいます。
(すこし寄り道してしまいましたが、)そんなわたしにとって、コミュニティとは敵となり得る因子が増えるものであり、コーチングに関わる以前のわたしにとって自ら新たなコミュニティに入るという選択肢は全く浮かばないほどに避けてきたものでした。
***
関係性の質と癒しの循環
そんなわたしが、コーチングを通してはじめて学校や会社とは異なる「コミュニティ」に属し、ワークショップに参加し、コミュカレでさまざまな組織のお話を聞いて、つながりについて気づいたこと・考えていることが2つほどあります。
①ひとつめは、こころのなかの亡霊のような他者の存在は、実存の他者によって癒される可能性があること。
亡霊のような他者とは、わたしの場合には「すべてのひとが敵になり得る」という固定観念といえます。それはもちろん、この社会を生きるうえで最低限必要なものでもありますが、無自覚に自分を制約していても生きづらくなります。
先のゲシュタルト療法ワークショップの体験で、インパクトが大きかったのは、一度に複数人のなかであっても理想的ではない、ありのままの自分でいても大丈夫だ(安全だ・大した問題はない)という身体感覚による実感がじわじわきいてきたことです。
わたしの性格上、なにか問題が発生したら自身に原因を追及しがちであり、そこにとらわれがあることも事実だけれど、一方で安心・安全な(評価・判断されない)小さな社会において、無防備な体験ができることは直接的な癒しになるのではないかと感じています。
それは、結果的に自分自身とのつながりに還元されることとなります。
評価・判断やラベリングをしないことは、日常をともにする近しい存在ほど難しいと感じています。だからこそ、コミュニティをはじめとした安心・安全を感じられる全くの他者の存在は大切なのだと実感しました。
はじめてコミュニティに複数属す1年を経験し、現実世界の幅が広がる感覚にうれしいおどろきがあります。
*
②ふたつめは、関係性の質がアウトプットの質をきめるということ。
わたしがこの1年で出会ってきた、すてきだなと感じる方たちには共通して「関係性の質=アウトプットの質」が感じられました。
これは、個人単位でも組織単位でも当てはまると感じています。組織は個人の集合体だからといって、全個人の問題が解決したとしてもすべては解決しなさそうなところが複雑で、個人の問題をそれぞれが抱えていても組織となるとエネルギーが発揮されうるところも面白いと感じています。
そしてそれは、個人と他者の関係性を多様に行き来することが大切なのだろうと感じています。
①と重なりますが、個人のなかで直接癒すことがむずかしいタイミングでは、他者との関係性に癒される。それがいつか個人に還元される。逆も然り。それは複数の関係性のなかで、直接的でなくとも関係性の質と癒しが相互作用しながら還元されていくということなのではないか、と感じています。
書きながら、それが本来の「社会」というものなのかもしれないな、と思いはじめたわたしがいます。
***
おわりに
コミュカレにて、eumoの新井さんがゲストにこられたとき、コミュニティというものをとらえるときに「濃度」という表現をされていたことが印象的でした。
コミュニティは境界をつくり、分断を生むものではない、濃度の濃淡で集っていたり集っていなかったりするだけだと。(記憶で書いており、わたしの解釈に変わっています)
そう受けとめると、素直にいまのわたしはどこに、どんなひとたちと集いたいのか考えられそうです。
ひとりではじめ、ひとりで完結して暮らすことは難しいから。わたしたちは遠いだれかと近しいだれかに生かされて今を過ごしているから。ときにつながりによって傷つくこともあるけれど、つながりをもって回復し、癒しが関係性の質となって循環していくといいな、と感じています。
自然体とはなにか、つながりとはなにか、これからは一緒に集いたい人たちとのつながりを深めながら探究していきたいです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
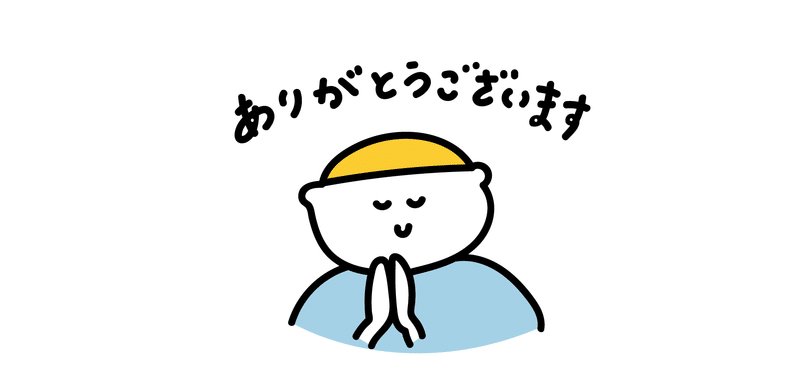
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
