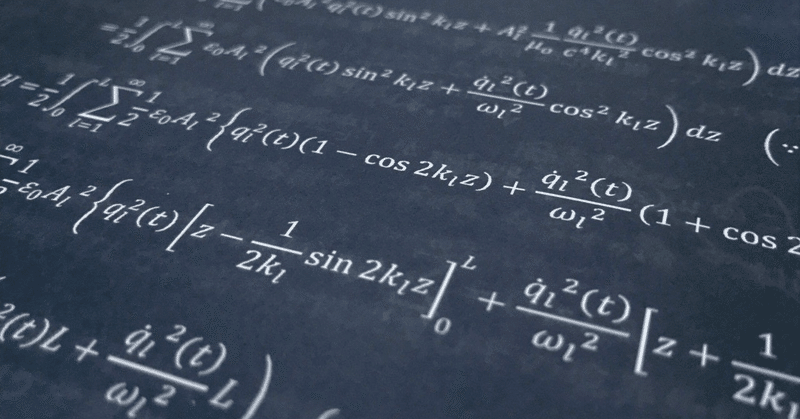
ゴールって、どれくらい決まりそうだったの?攻守のドラマを数値で読み解く「ゴール期待値」のすべて
こんな経験ありませんか?
チームが決定的なチャンスを作ったのに、シュートが枠外へ。
相手が危ない場面を切り抜けたと思ったら、次の瞬間あっさり失点。
そのシュートって難しかったの?そんなモヤモヤをスッキリ解決するかもしれない、サッカーの指標「ゴール期待値」について解説します。
短くわかりやすく解説できるように、全6回に分けて投稿する予定です。
今回は、基礎をテーマに書いています。
それでは早速見ていきましょう。
Q1.ゴール期待値とは?
・ゴール期待値(英語:Expected Goal、略称:xG)は、シュートがゴールになる確率を表した指標です。
・xGOALSという表記でも使用されることがあります。
(以後xGやxGOALSと表記することもあります。)
Q2.ゴール期待値は、なにを表すものなの?
・平均的な選手がシュートを打った場合のゴールになる確率を表した指標
・言い換えると、「チャンスの質を表す値」と言えます。
Q3.その指標は、どうやって表しているの?
・1本のシュートがゴールになる確率を0~1の範囲で数値化して表されます。
(0.02や0.85など、0~1の範囲と言っても小数点以下の数字が表示されることが普通です。)
Q4.ゴールになる確率が高いのは0に近い数字?1に近い数字?
・1に近いほどゴールになる確率が高く、0に近いほどゴールになる確率が低くなります。
・0.03と0.1だと、0.1の方がゴールになる確率が高いということです。
・示されている数字を100倍し%にした方がイメージしやすい気がします。
参考として、上記の例でやってみます。
0.03×100=3% , 0.1×100=10%
ゴールになる確率が高いのは、もちろん10%です。
%にした方がなんとなくイメージしやすい気がしませんか?
Q5.試合後に表示されるxGが1や2を超えるのはなぜ?
・1試合ごとのゴール期待値(xG)は、その試合の全シュートのxGの合計です。
なんとなく理解はできているでしょうか?
xGの基礎は大体このような感じです…
これからは、この基礎を元に実際に使われている図などを用いながら解説もしていきますので、完全に理解しなくても、読み進めていくことで理解できるかと思います。
例えば、
・チームと個人のxGってどうやって考えればいいの?
・そもそもxGは、どうやって算出しているの?
・xGが同じ値の場合はあるの?
・xGって、どうやって使われているの?
など、、
こういった疑問などを今後解説していきます!!
最後まで読んでいただけると幸いです。
また、わからないことなどは、コメントいただければと思います。わかる範囲で回答できれば…
それでは、さらに理解を深めていきましょう。
次の二つのシーンを想像してみてください。
①ゴールから約5mという近い距離から放たれるシュート
②ゴールから約35mという遠い距離から放たれるシュート
皆さんは、どちらの方がゴールになりやすいと思いますか?
きっと、①の方がゴールになりやすいと想像するのではないでしょうか。
しかし、各場面でのシュート状況は以下のようでした。
①ディフェンダー3人がゴールを死守しようと目の前に飛び込んできて、シュートコースがボール1個分もないように見える
②後半ロスタイムのカウンター攻撃でゴールから約35m離れた位置から放つシュートだけれども、ゴールとボールの間には相手が誰もいない状況
この場合、どちらのシュートの方がゴールになりそうでしょうか?
ゴールに近いから①の方がゴールになりやすそう。。
相手がいないから②の方がゴールするのは簡単じゃないだろうか。。
どっちの意見も正しいような気がします。。
このような時に、ゴール期待値が新たな知見を与えてくれます。
例えば、ゴール期待値(xG)が下記のような数字だったとします。
①:0.3
②:0.2
この場合、平均的なプレーヤーがゴールする確率として①は30%、②は20%という意味になります。(ゴール期待値を%へ変換して表示しています)
つまり、①の方がゴールする確率は高かったということになります。
(この場面のゴール期待値は解説するために割り当てた数字なので、実際とは異なるものになります)
このように、ゴール期待値は、数字として、各場面におけるゴールになる確率、つまりチャンスの質を示してくれるのです。
これらを言い換えると、①のシュートをゴールに結びつけた選手は、平均的なプレーヤーが10本シュートして3本しか入らないところをゴールしたという解釈もできますね。
とはいえ、これはあくまでも「ゴール期待値」をわかりやすく説明するための1つの事例です。
使用用途は選手獲得の指標やチームの評価などにも使われていたりと様々です。
ということで、今回は、ゴール期待値の基礎をできる限り簡単に解説しました。
次回は、『どうやって算出されているの?』をテーマにします。
これがわかると、観戦中にシュートを見て、ゴール期待値が予測できるようになるかも?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
