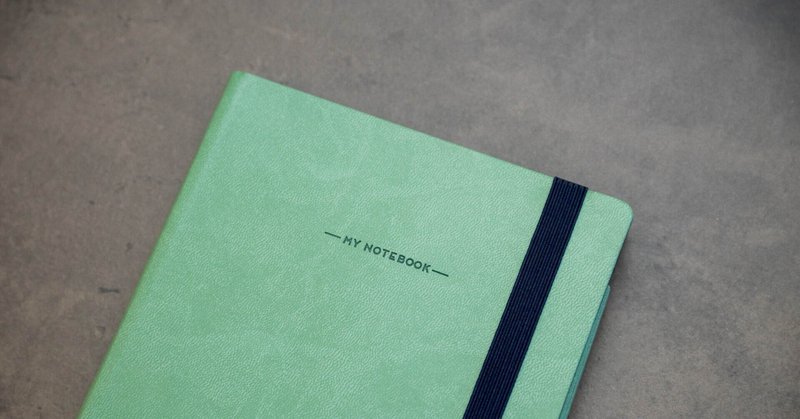
メモ書き M・ポランニー『暗黙知の次元』に寄せて(第Ⅰ章 暗黙知)①ポランニーの問題意識
[マイケル・ポランニー(高橋勇夫訳)『暗黙知の次元』(ちくま学芸文庫,2003)に必ずしも依拠しない私的メモ書きです。なお、「暗黙知」という概念が通俗的に誤って理解されて普及している部分があること(暗黙知を形式知と対置し、「暗黙知を言語化して形式知化しよう」という楽天的態度や、その反転として「現場の暗黙知」なるものを称揚して神秘主義に走る等)については各所で指摘されているので(例えば、矢守克也「〈書評〉マイケル・ポランニー(著)『暗黙知の次元』」災害と共生 3(1)2019,71-78頁.福島直人「暗黙知再考ーその由来と理論的射程」インターナショナルナーシングレビュー 32(4)2009,19-22頁)、この記事では述べない]
ポランニーの問題意識
ポランニーはなぜ「暗黙知」を提示したのか。何に対抗しようとしていたのか。
1 形式化はできない
第1に、知のすべてを形式化しようとする傾向、形式化できるという楽観的な、あるいは傲慢な傾向に、ノーと言うことであった。対象に対する暗黙的認識が機能している最中でなければ、形式知たる理論を使用することはできず、この関係性のなかにしか包括理解は成立しないし、その理論に関する知や認識も確立されないからである。実証主義運動は失敗する。
暗黙的認識をことごとく排除して、すべての知識を形式化しようとしても、そんな試みは自滅するしかないことを、私は証明できると思う。
—同書44頁
ある理論についての真の認識が初めて確立されるのは、それが内面化され、経験を解釈するために縦横に活用されるようになってからだ・・・
—同書45頁
掛かり合いの行為を形式化しようとすると、内容を台無しにする類の「明示性」を持ち込むことになる。科学哲学における実証主義運動が失敗した原因は、まさにその点にあったのだ。実証主義が唱える客観性という理念に代わるべき確固たるものを見つけ出すのは、至難の業である。これこそ紛れもなく、腹を据えて取り組むべき課題として、暗黙知の理論が私たちに求めずにはいられないものなのである。
—同書53頁
*ポランニーが「知識は全領域・全側面にわたって一切形式化できない」と言ったと短絡しないこと。彼はきちんと識別的に表現している。暗黙知の理論は、ある事柄やある知識を言葉によって、あるいは数式によって表現し伝達可能な状態にすること、広くいえば「形式化」することに全く敵対的ではない。そのような形式化ができない側面(=次元)すなわち「暗黙の次元(tacit dimension)」があり、それを忘れてはならないと言ったのだった。
2 個人的要素を排除できない
第2に、近代科学は私的なものを完全に排し、客観的な認識を得ることを目的とするが、それは誤れる理想なのだ、ということである。
しかし、もしも暗黙的思考が知全体の中でも不可欠の構成要素であるとするなら、個人的な知識要素をすべて駆除しようという近代科学の理想は、結局のところ、すべての知識の破壊を目指すことになるだろう。
—同書44頁
彼は、自らの認識行為として、個人的な判断を下し、徴候を外界の実在に関係づける。
—同書52頁
*ここでいう「個人的」は「パーソナル」であり、個人的知識は人格的知識という意味合いである。ただ、人格的であるということは、人間という諸個人に普遍的である内面性という意味合いを持ちうるので直ちにイコールではないが、結局はその人独自の内面世界を浮かび上がらせずにはおかないであろう。
3 明示的統合の限界、暗黙的統合
第3に、全体を個別要素に分解し、各個別要素を一点の曇りもなく明瞭に認識して把握しようとしても、結果的には各諸要素の意味自体が色あせてしまい、統合的な理解にも失敗することになる。要素還元主義は誤っており、同主義が帰結する明示的統合による対象理解は、暗黙的統合の理解の深さには及ばない、ということである。
・・・あけすけな明瞭性は、複雑な事物の認識を台無しにしかねないのだ。包括的存在を構成する個々の諸要素を事細かに吟味すれば、個々の諸要素の意味は拭い取られ、包括的存在についての概念は破壊されてしまう。
—同書41頁
個々の諸要素はより明白なのだから、それらをきちんと認識すれば、事物全体のほんとうの姿を捉えることができる、と信じ込むのは根本的に間違っている。
—同書42頁
しかしこれまでの実例ではっきり分かるように、一般に、明示的統合が暗黙的統合に取って代わることはできない。
—同書43頁
ただし、個々の諸要素の吟味が、次の段階の統合へ向かうために寄与し、新しい意味をもたらす局面があることを看過してはならない。
もっとも、こうした意味や全体像の破壊は、個々の要素をもう一度内面化し直すことで、修復が可能だろう。言葉が適切な状況下で再び発せられ、音楽に集中したピアニストの指が躍動し、人相の個々の特徴や模様の詳細がある距離を保って眺め直されるなら、それらはみんな息を吹き返し、自らの意味と自らの包括的な関係を回復させるだろう。
—同書41-42頁
この場合における意味の修復は、もとの意味を単に復元させるものではなく、意味に改良を施す。暗黙知は不断に「新しい意味」を志向し形成しようとする(同書の訳者解説参照)。
4 私たちは実在を感知している
第4に、ポストモダニズムが称揚する言葉の恣意性、差異に「過ぎない」言葉と意味の分離、意味の浮遊(やがては「意味」それ自体の希薄化・無価値化)、こうした動態に腰を下ろして知の遊戯にふけっている傾向に対して、それは違うのだ、ということである(主に同書の日本での受け止め、受け入れ方についてではあるが。同書の訳者解説参照)。
実在なるものは難しすぎて手におえず、認識できたとしても人様には伝わらない。「そうであれば」として突如反転し、実在から切り離された恣意的虚構物である言葉やその織り成しを「テクスト」として即自的に捉えてこれを肯定し、その構成・再構成、解釈・再解釈と楽しめばよく、そこから生まれたようにみえる価値を人が価値と感じ取れば価値があるのである、というふてくされた開き直りは、人から実在との接点を見失わせ、実感していた意味をその手から引き離して浮遊させ、やがては意味の希薄化を招くだろう。しかし、私たちは知っているはずである、実在を感知しているはずである。
しかし、私たちは問題を認識することはできるし、その問題がそれ自身の背後に潜んでいる何かを指し示しているのを確実に感じ取ることもできる。したがって、科学的発見に潜む含意を感知することもできるし、その含意の正しさが証明されると確信も持てるのである。どうしてそんな確信が持てるかと言えば、その発見についてじっくり検討を重ねているとき、私たちは問題それ自体を見ているのではないからだ。そのとき私たちは、それに加えてもっと重要なもの、問題が徴候として示しているある実在への手掛かりとして、問題を見つめているのだ。・・・(中略)・・・すなわち、私たちは、初めからずっと、手掛かりが指示している「隠れた実在」が存在するのを感知して、その感覚に導かれているのだ。
—同書49-50頁
ここにポランニーの認識論と存在論の統合的視点がみられる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
