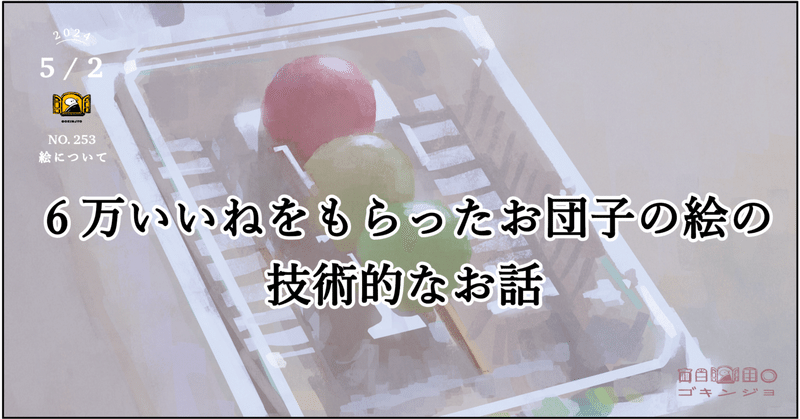
6万いいねをもらったお団子の絵の技術的なお話
ーーーーーー
24・5・2
絵について
6万いいねをもらったお団子の絵の技術的なお話
ーーーーーー
太陽が昇る時間が早くなったので朝の起床時間が早くなったヒロです(6時)
先日投稿した絵にものすごい数のいいねをいただきました。
朝のスケッチ。
— ヒロ/Hiro(ゴキンジョ) (@hiro_gokinjyo) May 1, 2024
描くのがめんどうくさいところを描かないと絵にならないんだなと思いました pic.twitter.com/WrwYxTnOpi
いいねをいただくというのは、鑑賞者の心が動いた結果、手を動かすという行動に繋がるということで、人の心が動くと行動に繋がる事実の表れで、それはすごいことです。ありがたいことです。
お団子の絵の何に心が動いているのかは人それぞれです。それについて考えるのも重要なのですが、今回は絵について、具体的な技術、何を考えながらお団子を描写していたかについての共有です。
お団子の絵は朝スケッチ配信の時に描いたもので、描写プロセスも残っていますので、よければ合わせて見ていただけたらと思います。
▼ 「実感」を描かないといけない
お団子の絵で主な描写ポイントが2つあると考えています。
・お団子の実感
・反射から見えるパッケージの構造
この2つが鑑賞者に伝わるように描けたら、絵としては成立するのではと考えていました。
「お団子の実感」とは、僕らの現実世界のお団子、「事実としてのお団子」です。
日本では団子は概念としてよく登場します。団子三兄弟、みたらし団子、お月見団子など日本人にとって団子という概念は特別なものなんだと思います。
そういった多くの人にとって特別なものは概念化、「記号化」されやすいものです。
今回気をつけたのは、訓練としてのスケッチ、目の前にあるものをキャンバス上に描写するという訓練でもあるので、なるべく「嘘をつかない」=「記号化しない」ということに気をつけました。
特によくあるのは三色団子の色を概念で描いてしまうことで、これは無意識のうちに行われます。

これが完成ですが、この団子を例えば概念で描くと、

こうなります。
概念とは「ラベリング」であって、僕たちが生きる現実世界の情報量が多すぎるので、人は情報を圧縮して物事を認識しています。
この情報の圧縮とはつまり「情報量の削減」なので、概念で絵を描くと絵に乗る情報が少なくなってしまいます。
なので絵を描く時の「概念で描かない」というのは「情報を圧縮しない」、「見たままを描く」ということです。
情報を圧縮するにしても完成の絵のような見え方をもとに団子の色を簡略化、記号化すると、
ここから先は
ゴキンジョマガジン『絵について、仕事について / 長砂ヒロ』
「絵について」と「仕事について」の記事を週2回お届けします。 ///////////// 日本では社会に出てから自分の好きなことを学び直す…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
