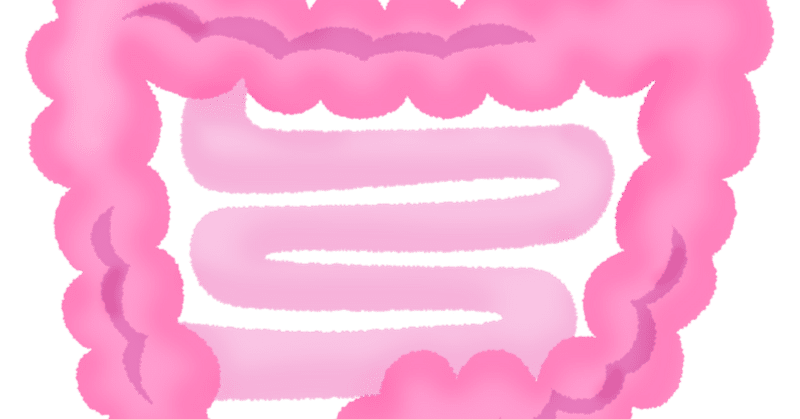
腸とは何か
はじめに
消化器官の内、排泄器官に近い大腸、小腸について調べてみます。消化器は胃、小腸、大腸とつながり、腸は栄養の吸収と水分の吸収と便にして排泄すさせます[3]。なぜこんなに長いのか(長さについては後述します)、また、なぜ便にして固めるのかです。
腸の構造
小腸
十二指腸:胃の幽門につながる25cmの小腸の最初の部分で、指12本分の長さからそう称されています。輪状のひだはありません。膵管と総胆管の出口があります[1]。それぞれ膵液と胆汁が分泌されます。
空腸と回腸: 十二指腸側の2/5が空腸、3/5が回腸と呼ばれます。小腸管の太さは成人で3cm~5cmで、長さは約6メートルですが、お腹の中では約3mほどに縮まっています。小腸の内側はヒダ状になっており、表面積を大きくして効率的に栄養を取り込めるようになっています。高さ0.5~1.2mm程度の突起である腸絨毛があります。これは1mm2あたり30本もの密集状態にあり、小腸全体では500万本以上が存在します[1]。
多くの食物は、小腸で4〜8時間かけて消化されます。

大腸
結腸とS状結腸: 大腸は直径は5cm~8cm、約1.5メートルの長さで、便を作るためにドロドロになった食べ物の水分の吸収や、便を肛門へと運ぶ役割を果たしています[3,4]。小腸にある輪状のひだは,ありません。小腸(回腸)側から盲腸、結腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸)、直腸と呼ばれています。なお、大腸については、日本人とアメリカ人のその長さに違いはないと言われています[5]。

腸の働き
消化、栄養素吸収機能:小腸は食事から取り入れた栄養素を吸収する役割を担っています。タンパク質はアミノ酸に、糖質はブドウ糖とガラクトースと果糖などの単糖に、脂肪はグリセロールと、脂肪酸と、コレステロールなどに分解され、小腸壁から吸収されます。
水分吸収機能:大腸では、食べ物のカスから水分が吸収され、液体から半固形状へ変換され(このとき食物のカスは大腸菌によって発酵され)、最終的には固形状の便が作られます。便は肛門の手前(直腸)まで運ばれ、刺激が脳に伝わり便意を催します。なお、水分は門脈から肝臓を運ばれて静脈に吸収されます。ただ直腸からは門脈から肝臓に運ばれずに静脈に吸収されます(そのため、坐薬が効くそうです)。
免疫機能: 小腸にはからだの免疫細胞の半分以上が存在しており、外敵(最近やウイルス)に対するバリア機能や抗炎症機能を持っています[5]。
脳とのつながり: 腸は脳とつながっており、「第二の脳」とも呼ばれています。ストレスなどが腸の状態に影響を与えることがあります。
まとめ
小腸が長い理由
管として長くすることで表面積を大きくすることで、消化酵素との接触面積が広がり、栄養素の吸収効率が上がるからです。
大腸で便が固まる理由
大腸では水分と電解質(塩分)の再吸収が行われ、便が濃縮されます。大腸内の腸内細菌により、カスが発酵された便が移送されながら形状が固まります[4]。
つまり、小腸の長さは消化と吸収を効率化し、大腸は水分調節と発酵、形状形成により、水分の吸収と排泄の両立を可能にする役割があります。
参考資料
[1]小腸 - Wikipedia
[2]小腸|からだとくすりのはなし|中外製薬 (chugai-pharm.co.jp)
[3]腸 - Wikipedia
[4]大腸 - Wikipedia
[5]健腸長寿②:健康の要、「腸」 | ヤクルト健康コラム | ヤクルト中央研究所 (yakult.co.jp)
[6]日本人とアメリカ人の大腸の長さは違うのか?―大腸3D-CT(仮想内視鏡)による1,300名の検討― | CiNii Research
変更履歴
Rev.1.0 2024.5.4 初版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
