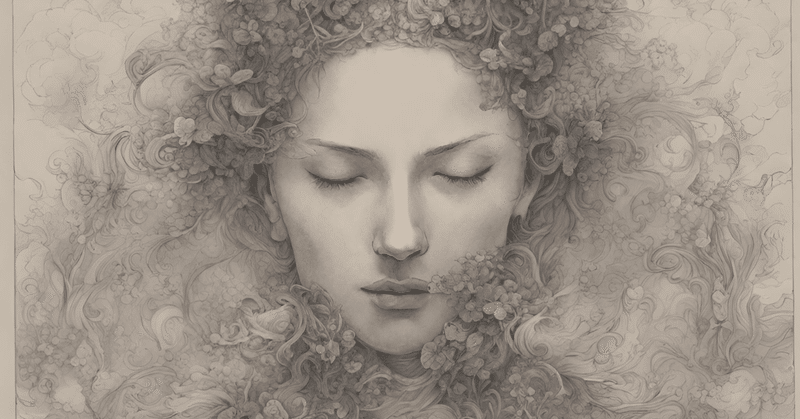
20240429 この身に言葉をたたえて
太田省吾さんが『小町風伝』を書いたとき、劇場となった矢来能楽堂の下見に行った際に舞台に立ってみて「俺が書いた台詞はこの舞台に蹴られる…」という直感を得、急遽書いた台詞を発語せず、俳優はその台詞をもった(覚えた)まま、無言でその台詞を表現するという演出に変えた、という話があった。
▼後に太田省吾さんは台詞のない『水の駅』などの沈黙劇と呼ばれる作品群を発表するようになる訳だけれども、その劇作家の直感というのはとても興味深いなと思う。俳優が発語すればなんでもいいというわけではなくて、舞台の空間から言葉が”蹴られる”というイメージは、なんというかものすごく劇作家っぽい感覚だなと思ったりする。
(そして太田さんはその発語されなかった台詞を含んだ『小町風伝』で岸田國士戯曲賞を受賞される。)
▼たとえば舞踊家の方は音楽を聴くともうそこに動きのイメージが見えるという。演劇だと、テクストを読んだときにその言葉がどう響くかをなんとなくイメージする、という感覚が(少なくとも私には)ちょっとある。もちろん「どうやって発語するか」というビジュアルのイメージもあるのだけれど、それ以上に「俳優と観客との間でその言葉がどう響くか」という聴覚先行のイメージ、とでもいおうか。
▼太田省吾さんのことで思い出したのでついでに書いておくと、太田さんが京都造形大学で演劇を教えられていたときに、とにかくゆっくり真っ直ぐ歩くというワークを学生たちと一緒にやっていたらしく、ずっと「ゆっくり歩く」ということをやりまくった果てに学生の一人があるとき「ゆっくり歩くことが演劇になるのなら、歩くこともまた舞踏になるのではないのか?」というスパーク(?)を起こして一念発起し舞踏の道に進まれた、という話を聞いたことがある。いい話だな、と思うと同時に沈黙劇、そしてゆっくりのテンポの動作というのは真に発明だったのだなと思う。
▼今回の作品は堀田善衞さんの長編小説(文庫で700ページ弱)を60分の演劇にする、という趣向なので、とてもではないけれども全文を演劇にすることはできない。なのでまず俳優がそれぞれテクストを取捨選択し、自分が発語するべきところを選び取ることから創作はまずスタートしている。
▼基本的には選んだ言葉を発語することになるわけだけれども、元のテクストが小説であるために、その間の地の文や会話などの文章は舞台上で発語されることこそないものの決して”なくなりはしない”。それらの膨大なテクストを引き受けるのが、ほかでもない俳優の身体だということになる。六人なら六人の俳優が堀田善衞さんの書かれた言葉をどう我と我が身に湛えて舞台上に立ち続けることができるか。楽に立つことなんて、どうやらできそうもないのだった。
*****
◆本日もご清覧頂きありがとうございます。もしなにかしら興味深く感じていただけたら、ハートをタップして頂けると毎日書き続けるはげみになります!
◆私が主宰する劇団、平泳ぎ本店/Hiraoyogi Co . では向こう10年の目標を支えて頂くためのメンバーシップ「かえるのおたま」(月額500円)をはじめました。
メンバーシップ限定のコンテンツも多数お届け予定です。ワンコインでぜひ、新宿から世界へと繋がる私たちの演劇活動を応援していただければ幸いです。
→詳しくはこちらから。https://note.com/hiraoyogihonten/n/n04f50b3d02ce
◆コメント欄も開放しています。気になることやご感想、ご質問などありましたらお気軽にコメント頂けると、とても励みになります。どうぞご自由にご利用ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
