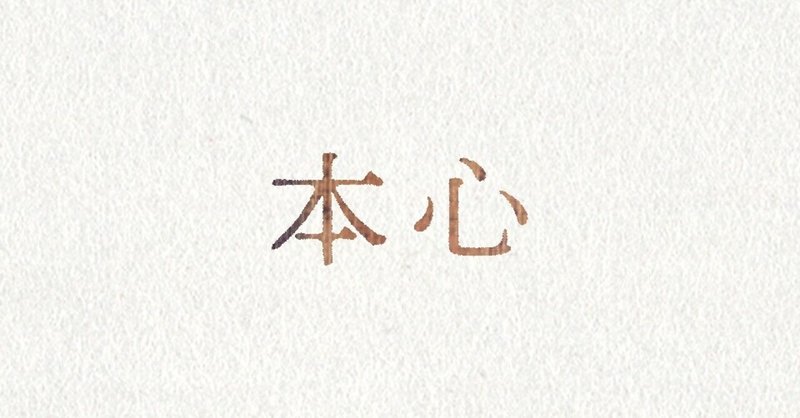
【5月26日刊行予定!】第一章 「〈母〉を作った事情」【試し読み】
『マチネの終わりに』、『ある男』に引き続き、愛と分人主義の物語であり、その最先端となる平野啓一郎の最新長篇『本心』(文藝春秋社)を、5月26日(水)に刊行いたします。🎊
発売記念に、プロローグから第三章まで、noteでも試し読み公開!
それでは、平野啓一郎の3年ぶりの新作『本心』をお楽しみください。
目次
プロローグ 5月17日(月)公開
▶︎▶︎ 第一章 〈母〉を作った事情 5月19日(水)
第二章 再会 5月21日(金)公開予定
第三章 知っていた二人 5月24日(水)公開予定
第四章 英雄的な少年
第五章 心の持ちよう主義
第六章 〝死の一瞬前〟
第七章 嵐のあと
第八章 転落
第九章 縁起
第十章 〈あの時、もし跳べたなら〉
第十一章 死ぬべきか、死なないべきか
第十二章 言葉
第十三章 本心
第十四章 最愛の人の他者性
第一章 〈母〉を作った事情
「──母を作ってほしいんです。」
担当者と向き合って座ると、たった数秒の沈黙に耐えられず、僕の方から、そう口を開いた。
もっと他に言いようがあったのかもしれない。
メールで既に、希望は伝えてあったので、確認程度のつもりだった。しかし僕は、それだけのことさえ最後まで言い果せずに、途中で涙ぐんでしまった。
なぜかはわからない。母を亡くして、半年間堪えていた寂しさが、溢れ出してしまったのだろうが、その挙げ句がこれかと、何となく惨めな気持ちになった。
それに、その不可能な単語の組み合わせが、単純におかしかったのだとも思う。──おかしくて泣いて悪い理由があるだろうか?
僕は、二十九歳になったところだった。
僕と母は、どちらかが死ねば、遺された方は一人になるという、二人だけの家族だった。そして僕は、二〇四〇年代の入口に立って、時々後ろを振り返りながら、まだ呆然としているのだった。
もう母は存在しない。その一事を考えれば考えるほど、僕は、この世界そのものの変質に戸惑う。
簡単なことが、色々とわからなくなった。例えば、なぜ法律を守らなければならないのか、とか。……
用心していても、孤独は日々、体の方々に空いた隙間から、冷たく無音で浸透してきた。僕は慌てて、少し恥ずかしさを感じながら、誰にも覚られないように、その孔を手で塞いだ。
僕たちを知る人は多くはなかったが、誰からも仲の良い親子だと見られていたし、僕は母親思いの、大人しい、心の優しい青年だという評判だった。
話を簡単にしてしまえば、母の死後、僕がすぐに、VF(ヴァーチャル・フィギュア)を作るという考えに縋ったように見えるだろうが、実際には、少なくとも半年間、母のいない新しい生活に適応しようとする、僕なりの努力の時間があったのだった。
それは、知ってほしいことの一つである。
僕は、六月一日生まれで、それが、「朔也」という名の由来になっている。「一日」を、古い言葉で「朔」ということを、僕は母から何度となく聞いていた。
母に祝われることのない初めての誕生日から数日を経て、僕は不意に胸に手を当て、言いしれぬ不安に襲われた。
自分では、その都度うまく蓋をしたつもりだった体の隅々の孔が、結局、開いたままで、僕の内側に斑な空虚を作り出していた。僕は、外からの侵入者を警戒するあまり、僕自身が零れ落ち続けていたことに、気づいていなかったのだった。
体が軽くなる、というのは、大抵は何か快さの表現だが、僕はその腐木のような脆い感触に、これはいけない、と初めて自覚し、その解決策を考えた。
それが、僕が今、渋谷の高層ビルの中にいる理由だった。
死は勿論、平凡な出来事だろう。誰もがある時、この世に生まれてきて、いつか死ぬ。これは、絶対に例外のない事実だ。取り分け、親が子供よりも先に死ぬというのは、まったく平凡なことに違いない。逆よりずっといい。そして、平凡なことを受け容れられない人間は、周囲を苛立たせる。──それはわかっている。僕の経験は平凡だ。ただ、ふと、どうしてそんなにみんな、何でも平凡なことだと思いなすようになったのだろうとは、考えることがある。決して口には出さないけれど。
僕は結局、感情生活の落伍者なりの手立てに頼ろうとしている。
ありがたいことに、そういう人向けのサーヴィスに目をつけた人もいるのだった。
担当者は、野崎という名の、僕よりも恐らく、一回り年上らしい女性だった。白いブラウスを着ていて、髪を短く切っている。メイクの仕方から、外国生活が長いのではないか、という感じがした。
ここに来る客では、泣き出すことも珍しくはないのか、彼女は、理解に富んだ表情で、僕が落ち着くのを待った。一重まぶたの小さな目が、よくわかりますよ、という風にこちらを見ていたが、観察されている感じもした。誇張でなく、僕は一瞬、彼女は受付用のロボットなのではないかと疑った。
ネットで済むはずの手続きを、わざわざ対面で行うのが、この会社の「人間味溢れる」特徴で、彼女はつまりは、そういう仕事に恵まれる人物なのだった。
「お母様のVFを製作してほしい、というご依頼ですね。」
「はい。」
「VFについては、おおよそ、ご存じですか?」
「──多分、一般的なことくらいしか。」
「仮想空間の中に、人間を作ります。モデルがいる場合と、まったくの架空の人物の場合と、両方あります。石川様の場合は、いる方、ですね。姿かたちは、本当の人間と、まったく区別がつきません。たとえば、わたしのVFとわたし本人とが、仮想空間で石川様にお会いしても、まず、どちらが本物かは見分けられないと思います。」
「そこまで……ですか?」
「はい。あとでお見せしますが、その点に関しましては、ご信頼ください。話しかければ、非常に自然に受け答えをしてくれます。──ただ、〝心〟はありません。会話を統語論的に分析して、最適な返答をするだけです。」
「それは理解しています。」
「興醒めかもしれませんが、どれほど強調しても、お客様は途中から、必ずVFに〝心〟を感じ始めます。もちろん、それがVFの理想ですが、その誤解に基づいたクレームが少なからずありますので、最初に確認させていただいてます。」
半信半疑だったが、想像すると、喜びというより不穏なものを感じた。彼女の口調は、製品の説明というより、僕自身の治療方針の確認のようだった。
「お母様は生前、VFの製作に同意されてましたか?」
「はい、……」と噓を吐いた。そんな話は決してしなかったが、本人の同意がないと言うと、製作を拒否されるか、面倒な手続きを求められるのではと思ったからだった。
「他のご家族は同意されてますか?」
「母一人、子一人の母子家庭でしたので。……母の両親は、既に亡くなっています。」
「承知しました。ご親族の間で、トラブルになることもありますので、一応。──失礼ですが、石川様は、生前のお母様とのご関係は、良好でしたか?」
僕は、最初の涙の印象を打ち消したくて、
わざわざ嫌な母親のVFを作る人がいるんでしょうか?」と笑ってみせた。
彼女はしかし、当然のように頷いた。
「いらっしゃいます。──ただ、理想化しますが。」
「ああ、……そういうことですか。」
「生前から、実際の家族とはまったく違った、理想的なVFの家族を作られる方もいらっしゃいます。片思いの相手を作られる方も。石川様の場合は、出来るだけ実物のお母様に似せる、ということでよろしかったでしょうか?」
「本物そっくりにして下さい。……本物に近ければ近いほど理想的です。」
彼女は、「──かしこまりました。」とだけ言うと、傍らのモニターに目をやって、聴き取られた会話が、自動的に整理されてゆく具合を確認していた。
たったこれだけのやりとりで、僕は疲労を感じた。彼女に好感を覚えたが、ピンと張ったピアノ線のような緊張の上で、期待と警戒とがゴムボールのように跳ねて、胸の裡で、素っ頓狂な音を立てていた。
「株式会社 フィディテクス」という社名のロゴが、至るところから、僕を見ている。ここは現実で、あなたは、我が社にいることをお忘れなく、としつこく念押しするように。
オフィスは広く、背の高い鉢に植えられた観葉植物が、木製の棚と組み合わされて、空間を機能的に仕切っている。ハンモックも見え、職場と言うより、自由なカフェのような雰囲気だった。さもなくば、今時、わざわざ出勤する意味もないのだろう。
バッサイアやフィカス、ガジュマルなど、僕でもAR(添加現実)を頼らずに名前を言える木が、目立って生い茂っていて、それが夏の光を心地良く遮っている。
よく手入れが行き届いていて、枝にも葉にも張りがあり、生気が感じられた。
「──石川様は、現在、二十九歳ですね?」
あまり長く窓の方を見ていたせいで、振り返った時、僕は野崎の姿を見失った。
「……そうです、先月が誕生日でした。」
「いつ頃のお母様をご希望ですか? 直近の事故に遭われる前のお母様か、それとも、もっとお若い頃か。」
思いがけない質問に、僕は即答できなかった。
この半年というもの、僕の脳裡を去来したのは、幼少期に見上げた、まだ四十代半ばの若々しい母の笑顔から、一年ほど前に、玉ねぎを切っていて人差し指の爪を削ぎ落としてしまった時の痛々しげな表情まで、一時も同じではなかった。
これから一緒に生活をするとして、いつ頃の、どんな顔の母が理想的なのか?──遺影は、葬儀会社の薦めに従って、時期の異なる五枚ほどの写真を選んで、切り替わるようにしてあった。しかし、VFとなると、そうはいかないのか。
「オプションで、複数の時期を選んでいただくことも出来ます。その分、お手間と費用がかかりますが。お子さんを亡くされた方などは、未来の姿を選ばれることもあります。」
「──未来?」
「はい。成人後の姿を、かなり正確に予想できます。」
僕は、どうして正確に予想できたなどと言えるのだろうかと、その言葉に引っかかった。
成長や老化は、ある程度、予想がつくのかもしれない。しかし、その子がいつか看板に額をぶつけて作る傷のかたちを、どうして予測できよう? 正解は、永遠に失われているというのに。
「今日、決めていただかなくても結構です。ゆっくりご検討ください。ただ、複数のヴァージョンを作られても、結局、みなさん、一体に絞っていかれますね。」
「……そうですか。──ただ、まだ、購入するかどうかを決めてないんです。どの程度、母を再現できるのかを知りたいのですが。」
「精度は、ご提供いただける資料次第です。写真と動画、遺伝子情報、生活環境、各種のライフログ、ご友人や知人の紹介、……サンプルとして、弊社で製作したVFに実際に会っていただくと、色々ご理解いただけると思います。」
そう言うと、野崎は立ち上がって僕を別室に誘った。
*
体験ルームは、意外と平凡な応接室だったが、外部からは遮蔽されていて、壁には闘牛をモティーフにしたピカソのエッチングが飾られていた。かなり古色を帯びていて、しみもある。最近の精巧なレプリカなのか、二十世紀に刷られたものなのかは、わからなかった。
ヘッドセットを装着しても、何の変化もなかった。僕は、これから対面するVFが、AR方式で、現実に添加されるのか、それともヘッドセット越しに見ている部屋が、既に仮想的に再現された応接室なのか、本当に区別できなかった。
黒いレザーのソファの前には、コーヒーが置かれている。座って、それを飲めば、わかることだろうが。……
野崎が、二人を連れだって戻って来た。
一人は、薄いピンクの半袖シャツを着た、四十前後の瘦身の男性。よく日焼けしているが、僕とは違い、長い休暇中に、ゆっくり丁寧に時間をかけて焼いたらしい肌艶だった。
もう一人は、紺のスーツを着て、眼鏡をかけた白髪交じりの小柄な男性だった。
「初めまして、代表の柏原です。」
日焼けした男の方が、白眼よりも更に白い歯を覗かせて腕を伸ばした。
僕は握手に応じたが、ウィンド・サーフィンでもやっているんだろうか、といった眩しい想像を搔き立てられた。
続けて、隣の男性を紹介された。
「弊社でお手伝いいただいている中尾さんです。」
「中尾です。どうぞ、よろしく。暑いですね、今日は。──お手伝いと言っても、ただここでお話をさせていただくだけなのですが。」
彼は、額に皺を寄せて、柔和に破顔した。落ち着いた物腰だったが、こちらの人間性を見ているような、微かな圧力を感じさせる目だった。「お手伝い」というのがよくわからなかったが、僕と同じVFの製作依頼者なのだろうかと考えた。
同様に握手を求められたので、応じかけたが、その刹那に、ハッとして手を引っ込めた。実際には、それも間に合わず、僕は彼に触れ、しかも、その感触はなかったのだった。
「私は、VFなんです。実は四年前に、川で溺れて亡くなっています。娘がこの会社に依頼して、私を製作してくれたんです。」
僕は、物も言えずに立っていた。〝本物そっくり〟というのは、CGでも何でも、今は珍しくないが、中尾と名乗るこのVFは、何かが突き抜けていた。それが、僕の認知システムのどこをどう攻略したのかはわからない。誇張なしに、僕には彼が、本当に生きている人間にしか見えなかった。柏原と見比べても、質感にはまったく差異がなかった。
僕は、半ば救いを求めるように野崎を振り返った。彼女は特に、「どうです!」と誇らしげな様子を見せるわけでもなく、「気になることがあれば、何でも質問してみてください。」とやさしく勧めた。恐らく、彼女がVFに接する態度も、これを人間らしく見せている一因だろう。
彼の額に、うっすらと汗が浮いているのに気がついて、僕は驚いた。僕の眼差しを待っていたのか、それは、目の前で、静かにしずくになって垂れ、こめかみの辺りに滲んで消えた。そのベタつくような光沢を、中尾は痒そうに、二、三度、搔いた。
僕は、反射的に目を逸らした。彼の足許には、僕たちと同じ角度で、同じ長さの影まで伸びていた。
「ちゃんと、足は生えてますよ。」と中尾は愉快そうに笑って、「そんな、幽霊を見るみたいな顔をしないで下さい。」と、腹の底で響いているような篦太い声で言った。
「すみません、……あんまりリアルなので。」
「中尾さんは、実は収入もあるんですよ。」と野崎が言った。
「──収入ですか?」
「これが仕事なんです。」と中尾が自ら引き取った。「ここでこうして、自分自身をサンプルに、新しいお客様にVFの説明をしているんです。それに、データの提供も。お金を受け取るのは、家内と大学生の一人娘ですがね。……かわいそうなことをしましたから、まあ、親として出来るせめてもの孝行ですよ。」
そう説明する彼の目には、憂いの色があった。しかも彼は、「親として出来るせめてもの孝行」と言うだけでなく、その手前で、「まあ、」と一呼吸置いてみせたのだった。
僕は、自分の方こそ、出来の悪いVFにでもなったかのように、不明瞭な面持ちで立っていたと思う。「話しかければ、非常に自然に受け答えをしてくれます。ただ、〝心〟はありません。」という、野崎の最初の説明が脳裡を過った。
彼はつまりAI(人工知能)で、その言葉のすべては、一般的な振る舞いに加えて、彼の生前のデータと、ここでの、何十人だか、何百人だかの新規顧客との会話の学習の成果なのだった。ただ、「尤もらしい」ことを言っているに過ぎず、実際、こうしたやりとりは、大体いつも、似たり寄ったりなのだろう。
第一、それを言うなら、柏原や野崎の言動こそ、僕が誰であろうと、そう大して変わらない、パターン通りの内容だった。彼らとて、一々、僕の心を読み取り、何かを感じ取りながら話をしているわけではなく、「統語論的に」応対しているだけに違いない。
「お母様を亡くされたと伺ってます。きっと、あなたのお母様も、私と同じように、VFとして立派に再生しますよ。娘はね、私と再会した時、本当に涙を流して喜んでくれました。もちろん、私も泣きましたよ。──心から。」
僕は、中尾の姿に母を重ねようとした。しかしそれは、どう努力しても止めることの出来ない、破れやすい、儚い幻影だった。それでも、母とまた、こんな風に会話を交わす日が来るという期待は、僕の胸を苦しみとしか言いようのない熱で満たした。
わかった上で欺されることを、やはり欺されると言うのだろうか? もしそれで幸福になれるなら? 僕は絶対的な幸福など、夢見てはいない。ただ、現状より、相対的に幸福でさえあるなら、残りの人生を、歯を喰い縛ってでも欺されて過ごしかねなかった。……
その後、ソファに座って、面会の続きをしたが、僕はほとんど上の空で、話の半分程度しか頭に入らなかった。
ヘッドセットを外した途端、VFの中尾は目の前から消えた。しかし、僕の中に残った、人と会ったという余韻は、実のところ、代表の柏原よりも、遥かに彼の方が強かった。
「……実際に、VFをお渡ししてからも、石川様ご自身にお母様を完成していただく必要があります。機械学習ですから、出来るだけ長く、頻繁に会話を交わしていただくことで、少しずつ違和感が修正されていきます。」
「シラケませんか、その間に?」
「いえ、逆です。みなさん、感動されます。ご家族のVFを望まれる方は、ご病気で意思疎通が出来なくなったり、死別されたりというケイスが多いですから。少しずつ、以前同様のコミュニケーションが回復してゆくことが、大きな喜びになります。──それは、本当に。ご病気が治ったり、生き返ったりした感じがするようです。ちょっと違うと感じたところは、こちらから助けてあげて、元に戻してあげようと努力するんです。個人的には、この仕事をしていて、わたしが一番、感動するのもその時です。」
「……。」
「生身の人間も、複雑ですけど、心だって、結局は物理的な仕組みですから。VFは、コミュニケーションの中では、限りなくご本人そのものです。」
「──心はないけれども、ですよね?」
「はい、そう申し上げましたが、感じるんです、やっぱり。心って何なんでしょう?」
彼女は、これまでになく、本音を語っている風の口調で言った。そしてそれは、生身の人間らしく、まったく矛盾しているのだった。
結局、僕は、その日のうちに母のVF製作を正式に依頼した。
見積価格として、三百万円という額が提示された。以前の僕には、とても手が出なかったが、母が残してくれた生命保険から、どうにか捻出するつもりだった。
*
母のVF製作を依頼した翌日から、僕は、小樽に出張することになっていた。
興奮のせいか、一種の疚しさに似た気持ちのせいか、或いは、「高い買い物」の決断に急に不安に感じ出したせいか、ともかく、前夜はなかなか寝つかれず、朝も目覚めが早かった。
クーラーをつけ、水を一杯飲んで、汗ばんだ体に涼気を受けながら、リヴィングの南向きの窓を見つめた。
母の後半生の労働が、この小高い丘の上に建つマンションのローンの支払いに捧げられたという考えは、僕を少し憂鬱にさせる。それは他でもなく、この僕との生活のためであり、感謝の気持ちだけでないのは、僕の生計が最後まで母に依存していて、現に今も、母の遺したこの部屋のお陰で住む場所に困らずに済んでいるからだった。
母の生命保険の一部を、VFの支払に充てると、僕は、値上げが続いている管理費と修繕積立費を、いずれ支払えなくなるかもしれない。遠からず、ここも退去すべきだろうかと思うと、街の眺めも、急に惜しくなる。
蟬の力強い鳴き声に、古い建物の全体が浸されていた。
静寂の中にも、特別な静寂がある。人が鍵を掛けて出て行った部屋にだけ、こっそり姿を現す、臆病な動物のような静寂が。──しかし、この時には、なぜかまだ、僕がいるというのに、その静寂が部屋に忍び込んできたのだった。それで僕は、しばらく息を潜めて、朝の光が、大きな首をゆっくりともたげるように高くなってゆくのを見ていた。
きっと、僕の体が感じ取れないほどの小さな地震でもあったのだろう。リヴィングのドアが開いた。昨日の経験が、僕の現実を瞬く間に乗っ取った。ドアの陰には、母が立っている気がした。そして、今にも姿を現して、「おはよう。」と僕に声をかけるのではないかと想像した。
僕は、半開きのまま止まっているドアを見つめた。その裏側で、銀色のノブに触れようとして躊躇っている手を思った。
「お母さん、……」
こういう時には、万が一のためのことはすべてすべきだった。
僕は、母を招き入れるために呼びかけた。けれどもドアは、僕の期待に困惑したように、いつまでもただ、じっとしているだけだった。
*
羽田から小樽へと向かう飛行機の中で、僕は、今日の仕事の確認をした。
所謂〝リアル・アバター〟として働くようになってから、もう五年、──いや、六年近くが経っている。
個人事業主としての契約で、その間、登録会社は二度変わったが、僕はこの世界では、例外的な古株だった。
今でも人間が求められ、且つ、特別な技能を必要としない職業の中では、最低限よりも、大分マシな報酬の部類だと思う。世間的には蔑まれてもいるが、依頼者からは感謝されることが多く、僕はやり甲斐を感じていた。
それでも多くがすぐに辞めてしまうのは、肉体的にも、精神的にも、保たないからだった。
母は、この仕事を好まなかったが、それでも、僕がどうにか続けてこられたのは、母の存在があればこそだった。
依頼者は、八十六歳の男性で、手配したのはその息子夫婦だった。「最後の親孝行に」と、要望書の中で説明していたが、実際に面会した折に、その言葉を文字通りに受け止めるべきであることを察した。
病床に座って僕を出迎えた「若松さん」という老人は、顴骨ばかりがふっくらと目立つほどに瘦せていたが、目の底にはまだ力があり、意思は明瞭だった。ただ、僕の仕事については、今ひとつ吞み込めていないようだったので、
「簡単に言えば、この体を丸ごとお貸しする仕事です。僕が装着するカメラ付きゴーグルの映像を、若松さんには、このヘッドセットで見ていただきます。ご自分の体のように、僕の目を通じて見て、僕の耳で聞いて、僕の足で歩いていただきます。」と説明した。
自転車や電車で物を運ぶこともあれば、依頼者が行けないような遠い場所、危険な場所に行くこともある。感染症が流行ると仕事が増える。何かのリサーチを頼まれることもあるし、旅行の代理を頼まれることもあった。時間がなくて、行ってきたことにしたい人、行きたいが、病身で行けない人──若松さんのように──というのは、少なからずいるのだった。僕が旅先で撮影した写真を、自分が撮ってきたものとしてネットにアップするのは、依頼者の自由だ。それについては、こちらに守秘義務がある。
若松さんは、「人間ドローンですか?」と笑って言ったが、ふしぎと嫌味がなかった。
「ええ、飛べませんけど。基本的には、依頼者の指示通りに動きますし、遠隔で操作するだけでなく、僕の体と一体化して活動したい、現地を体験したいという方も多いです。外国からの依頼者もいます。」
仕事中は、依頼者の体になりきっているが、珍しい、面白い体験もあるし、行ったことのない場所に行って、現地で多少、自分の時間を持てることもある。それも、僕が必ずしも、嫌いな仕事でない理由の一つだった。
若松さんは、長年、小樽に住んでいたが、今は僕が訪れた小田原の施設に入っている。
死ぬ前に──と彼自身ははっきりと言った──どうしても、昔住んでいた小樽の家を見たい、そのあと、家族でよく足を運んだ、町の外れの断崖に建つホテルから海を眺めたい、というのだった。
承諾すると、彼は握手を求めた。乾燥した木の棒がスッと持ち上がるような動作だったが、長く入院している人らしく、掌の皮には繊細なやわらかさがあった。埋もれていた彼のまだ少年だった頃が、肉が落ちて露わになったかのような感触だった。
死が近づくと、人の思念の中では、過去の川が、一筋の流れであることを止めて、氾濫してしまうのかもしれない。堰を切ったように、誕生から現在までの存在の全体が、体の中に満ちて来る。肉体には、その隅々に至るまで、懐かしさの気配が立ち籠める。
いずれ、この世界から、諸共に失われてしまうなら、肉体が記憶と睦み合おうとするのも当然かもしれない。
旅程のすべてを、若松さんのアバターとして辿ることも可能だったが、長時間は、体力が保たないというので、二箇所の目的地だけに絞ることにした。
新千歳空港から小樽までは、電車で一時間ほどだった。北海道とはいえ、特段、涼しいわけでもなく、日中は、三十度を超えるという予報だった。ポロシャツにチノパンという恰好だったが、僅かな駅の移動の間にも汗が兆した。
僕は、動き出した電車の窓辺で、アカエゾマツの林が視界を掠めていくのを、見るともなしに眺めた。そして、母が僕に、唐突に〝自由死〟の意思を伝えた日のことを思い返した。
あの日、母は初めて僕に、一人の依頼者として、仕事を頼みたいと言った。伊豆の河津七滝に行って、自分に見せてほしい、と。
「一度、朔也がどんな仕事してるのか、よく知りたいと思ってたのよ。お金も、他のお客さんと同じようにちゃんと払うから。」
僕は、喜んで応じた。母が、僕の生き方を認めてくれたようで嬉しかった。
なぜ、河津七滝なのかは、訊ねても曖昧だった。ただ、滝が見たくなって、昔、『伊豆の踊子』を読んだのを思い出したと言った。母は、趣味のはっきりした読書家だった。僕は、あの小説の主人公の起きては鎮められる性欲の波に、悪酔いした記憶しかなく、どこかに滝が出てきただろうかと曖昧だった。
それでも、僕自身の前後の予定も詰まっていて、日帰りできる距離は丁度良かった。どこに行くかということ自体は、あまり重要ではなかった。
僕は、はりきっていた。初めての場所だったので、十分に下調べをして、プランを立てた。せっかくなら、母をアバターとしてではなく、手を引いて連れて行ってやりたい気持ちにもなったが、嬉しいけど、それだと意味がないと笑われた。
アバターになっている間は、話し相手になってほしい人もいれば、完全に自分の肉体であるかのように、ただ指示だけを出し、返事をされることさえ嫌がる人もいる。
母も最初は、僕と同化して遠隔操作することを試みていたが、熱海で新幹線から特急に乗り換える時に、僕に注意を促した辺りから我慢できなくなったらしく、いつもの口調になった。しかし、いかにも言葉少なだった。
車窓から眺めた伊豆半島の景色は、今ではもう、何度も遊んで印刷が擦れ、順番がバラバラになってしまったカードのようになっている。
椰子の木が並び、海が見え、民家が視界を遮り、伊豆高原近くになると、深い緑の木々に覆われた。しかし、その順番に見たのではない気がする。
近くに人が座っていたので、声を出して母と会話することは憚られた。母もそれを承知していたが、晩春の光を浴びた海が煌めく先に、大島が見えた時には、思わず嘆声を漏らして、「ほら、見える?」と語りかけた。
東京から、二時間近くかけて運ばれた母の沈黙が、今では僕の記憶に永い旅の荷物のような重みを残している。
距離に換算される沈黙という考え方は、きっと正しいのだと思う。なぜなら、その一五六・八キロを辿る間に、母のそれは、ゆっくりと変質していったであろうから。そして、母がその時、何を思っていたのかという僕の想像は、どんな一瞬にも辿り着けないのだった。
*
河津駅に着くと、バスで水垂という停留所まで行き、そこからゆっくり山を下りつつ、七つの滝を見ていった。一キロ半の道のりだったが、途中で座って眺めたりと、一時間ほどかけたと思う。
木製の階段や橋が設置されていて、案内も親切だった。
それでも、ところどころ、木の根が隆起し、苔が生した足場の悪いところがあり、母は、やっぱり、自分ではここに来られなかったと思うと僕に言った。
「木下路」という『伊豆の踊子』の言葉通り、山道は、鬱蒼とした木々に覆われていたが、川の真ん中にまでは、両岸からの枝が伸びきれず、その先端が触れ合えないまま開いていた。次々と視界に現れる滝に、空からまっすぐに光が注がれ、滝壺には、目を射るような煌めきが満たされ続けている。
間近で霧雨を浴びるような大きな滝もあれば、その激しさを足許に見下ろす滝もあった。
水は、底が見えるほどに透徹していたが、全体に分厚いガラスの断面のような深緑色をしていた。
少しあとになって、僕は、川端康成ではなく三島由紀夫の初期短篇の中に、こんな一節を見つけた。
「これほど透明な硝子もその切口は青いからには、君の澄んだ双の瞳も、幾多の恋を蔵すことができよう」
僕が思い出したのは、ガラスではなく、この滝の水の色だった。必然的に、「君」の役割は母に宛がわれることになった。実際、母は、歳を取って瞼が落ちてきてからも、目の綺麗な人だった。
僕は母と、何を話しただろうか?
母は、「瀬を早み岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ」という、百人一首の崇徳院の和歌を、少し戯けた風に諳んじてみせて、その通りね、と言った。
「誰か、再会したい人がいるの?」と、僕は訊ねたが、母は笑って何も答えなかった。
奇妙に孤立した会話の一往復だった。
岩間を抜けて流れる浅瀬の水は、川底の起伏をなめらかになぞって、周囲の岩のかたちと親和的だった。
水に近づけばひんやりと感じられ、離れれば如実に気温が上がった。
七つ目の「大滝」と名づけられた滝がハイライトで、僕は母の勧めで、その傍らにある温泉宿で休んでから帰ることになっていた。
滝は、見上げるような大きさで、僕たちは、轟音の直中で、小さな静謐を分かち合っていた。
水は、緑に覆われた岩間から、宙に向けて勢い良く吹き出していた。ガラスの器に落ちてゆくかき氷のように白いその滝は、途中に迫り出した岩にぶつかり、更に大きく荒々しく開いた。
僕は陶然とした。
「滝壺に虹が架かってるの、見える?」
そう言おうとしたが、先に母が口を開いた。それで、その言葉は、一生外気に触れることがないまま、今も僕の中に、小さな虹の断片のように留まっている。
「やっと、朔也の仕事がわかった。あなたのお陰で助かる人がたくさんいるでしょうね。」と母は言った。
僕は、何と返事をしただろうか? 虹から視線をモニターの中の母に移した。
「疲れたね? ご苦労様。ありがとう。」
「ううん、僕も楽しかったから。」
「お母さん、本当に満足。これで安心。……ありがとう。もう十分。」
僕は、滝の前を離れて、道路に出るまでの長い急な階段を上り始めた。
「朔也にいつ言おうかと思ってたんだけどね、……」
母は、そう切り出したあと、躊躇うように間を置いた。
「お母さん、もう十分生きたから、そろそろって思ってるの。」
「──何が?」
僕は、足を止めた。少し息が上がっていた。咄嗟に母が、施設に入る決心をしたのではないかと考えた。──そんな余裕はないはずだったが。そしてそのことに、当惑しつつ、少し腹を立てた。
しかし、次いで、母の口から洩れたのは、まったく予期せぬ言葉だった。「お母さん、富田先生と相談して、〝自由死〟の認可を貰って来たの。」
僕は、動けなくなってしまった。何か言おうにも口が開かず、呼吸さえ止まっていた。苦しさからようやく一息吐き出すと、心臓が、棒で殴られた犬のように喚き出した。
僕は明らかに、母の言葉を理解できていなかったが、体の方は既に恐慌に陥っていた。多分、母と僕の体は、その時一つだったから。……
後ろに続いていた家族連れに声を掛けられ、僕は端に避けて先を譲った。「──よく聴き取れなかったんだけど。」
「ごめんね、急に。でも、お母さんも、じっくり考えてのことだから。」「だから、何を?」
「自由……」
「どうして?」
僕は、モニターの全面に母を映し出した。困惑したような、許しを請うような微笑で、こちらを見つめていた。僕は愕然とした。それは、既に決断し、相手をどう説得するか、様々に想像しながら、時間を掛けて準備してきた人の顔だった。
そもそも僕は、〝自由死〟などという欺瞞的な言葉が大嫌いだった。それは、寿命による〝自然死〟に対して、言わば、無条件の安楽死であり、合法的な自死に他ならなかった。それを、よりによって母の口から聞かされるとは。──
「どうして? 何かあったの?」
「ずっと考えてたことなのよ。この歳になれば、」
「この歳って、まだ七十前だよ? 何言ってるの?」
「もう十分なのよ。……もう十分。」
「とにかく、すぐに帰るから。それからゆっくり話し合おう。おかしいよ、急に。……早まったこと、しないでよ。とにかく、僕が帰るまで待ってて。……」
なぜなのか?──なぜ?……
しかし、その晩、遅くまで続いた母との話し合いを、僕は、若松さんとの仕事の前に思い出さなかった。脳裡にちらつくその光景を堰き止めて、小樽駅に到着しようとする車窓の風景に吞まれるに任せた。アイスクリームを食べている観光客に目を留めた。ホームの柱がそれを断ち切り、別の一群に繫ぎ直して、また断ち切った。自動販売機や広告など、つまらないものが一通り視界を過っていった。そうした平凡さこそが、追想から逃れるためには、是非とも必要だった。
若松さんの家は、駅の裏手の高台にあった。富岡聖堂という小さな教会の少し先で、地図で見ていたより、その坂道は急で、僕の自宅マンション前の道を更に何倍にもしたほどに長かった。
僕は、駅から彼と一体化していたが、あの病床の老人も、若い頃はいつもここを上り下りしていたのだ、というようなことを、少し息を切らしながら考えた。
平日の白昼は、見慣れぬ余所者の闖入に、ひっそりと息を凝らしていた。僕が実は、若松さんだと知れば、景色が一変するくらい驚くのではあるまいか。
あの老体を満たしていた幼少期の記憶が、今は僕の体に打ち寄せている。そして彼は、僕を通じて、束の間、懐かしい過去へと駆け出してゆくのだった。
教会はこぢんまりとして、ヨーロッパのゴチック建築のファサードを、一部こっそり引き抜いて、持ち帰ってきたかのような風情だった。
街は既に眼下に遠く、若松さんの自宅は、そこから歩いて五分ほどである。
二階建ての大きな洋風の家で、屋根はピアノの鍵盤のふたを、開きかけて、そのまま止めたようなかたちをしている。積雪対策なのだろう。
白い外壁の一角には、ダークブラウンの装飾が施されていて、建てられた時には、立派な、趣味の良い家だと評判せられたに違いない。
庭の大きな貝塚息吹はよく手入れされていて、玄関先には、子供用の自転車が二台、置かれている。
若松さんは、僕の耳元で頻りに、「ああ、……」と、懐かしそうな、言葉にならない声を漏らしていた。僕は、今の居住者に、中を見せてもらう交渉をするかどうか、提案のメッセージを送ったが、「いえ、いいです。」という返事だった。
周辺をしばらく散歩し、小樽公園にまで足を延ばしたあと、無人タクシーを拾って、岸壁のホテルに移動した。僕の視界の映像は、若松さんの息子夫婦にもシェアされているようで、「お父さん、よかったね、家が見れて。ねえ?……」と何度も声を掛けるのが聞こえた。
ホテルに行く前に、僕は磯辺に向かった。船着き場があり、ニシンの焼き魚定食やいくら丼を出すような店が軒を連ねている。
駐車場のアスファルトの先は、僕の足よりも少し大きいくらいの丸い石が積み重なっていて、時折、不意によろめいては、石同士が軋み合うのを足裏に感じた。
そして、全身に響く大きな潮騒。
波打ち際には、「人」という字を組み合わせたような四脚の消波ブロックが、ぎっしりと並べられている。
遊泳エリアではないが、子供用の青い浮き輪が一つ、足許に落ちていた。少し先にあるビーチから流れてきたのだろう。
風が強く、汗ばんでいた僕には心地良かった。
青空には、薄い雲が、今にもゆっくりと、音もなく引きちぎられてゆくように棚引いている。その裂けて飄った縁は、時間が止まったかのようにかたちを保っている。
水平線は、白く打ち烟って曖昧だった。
僕は、雲の隙から降り注ぐ無数の光が、海原一面に煌めいて、波と共に打ち寄せてくる様を眺めた。若松さんに、その規模を伝えたくて、ゆっくりと頭を巡らせた。彼は、黙っていたが、その息遣いだけは耳に届いていた。
病室にいる彼の許に届く波は、きっと、過去から折り重なるようにして、層を成しているのだった。買ったばかりの折り紙を開封して、その中から、好きな色を一枚だけ抜き取ろうとしては、一緒に他の色まで引き出してしまうように、若松さんの記憶の中の波は、今、幾年も隔たった景色を、続けざまに見せているに違いない。
波は、磯の直前まで潜っていて、唐突に顔を上げると、飛びつくようにして消波ブロックにぶつかり、高く砕け散った。
噴水のように跳ねた飛沫が、次々と波の中へと落ちてゆく。そのうちの幾つかは、悪戯めかして、僕の顔にまで飛んできた。眩しさに、僕は下瞼を無意識にずっと緊張させていた。
ホテルまでの一本道は、急勾配だった。若松さんは、「きついでしょう? 冬はこの辺は真っ白ですよ。車も、4WDじゃないとね。」と、僕に初めて語りかけた。そういう時は、会話に応じた方が良かった。
「ええ、大丈夫です。この辺の人は、そうなんですね。関東に住んでると、そんなことさえ思い至りませんけど。」
道の途中には、古い水族館があったが、その駐車場に停まっている車も、確かに4WDが多かった。
何度か後ろを振り返ったが、先ほどまで見ていた海が、眼下に見る見る遠ざかっていって、定食屋の屋根も、僕が立っていた磯も、もう、細密画の一部になっている。
体そのものが大きくなったかのように錯覚した。
ホテルは、白い瀟洒な建物で、若松さんが行きたがっていたのは、展望テラスがついた、芝生とタイルの広い庭だった。
平日の午後なので、人影はなく、僕は、若松さんに確認して、見晴らしの良さそうな場所の手すりの前に立った。
風は麓にいた時よりも更に強かった。磯とは方角が違い、遠くに小さく灯台が見える。
手すりの向こうは草木に覆われていて、その先は、唐突に何もなかった。実際に草を踏みしめてゆけば、ふっくらと膨らんでいる草叢の中ほどから、切り立った絶壁となっているはずだった。ヘッドセットのARをONにした。クマザサ、オウシュウヨモギ、ホオズキ、ブタナ、ホッカイヨロイグサ、……と、それぞれの名前が表示された。
身を乗り出して下を覗き込むと、遥か下方に、岩場に打ち寄せる波が見えた。「危ないよ。」と、若松さんに注意されたが、この一言が、奇妙に僕の心に残っている。
視界は、海と空とに力強く二分された。
頭上は群青色のように濃い青だったが、水平線に向けて、その色が薄らいでいく。
潮の流れが、広大な海面に、細かな模様を描き出しているが、それは寧ろ、風の手が撫でつけて出来た皺のようでもあった。
至るところに、白浪がちらめき、どんな僅かな水の起伏にも陰翳が伴っている。
若松さんは、また、「ああ、……」と嘆息を漏らしたきり、無言になった。その静寂の向こうで、僕は彼が泣いているのを感じ、モニターの小窓を見ないようにした。
風が、潮でべたついた僕の額を涼しく撫で、前髪を掻き上げた。恐らく僕の体は、若松さんの亡くなった妻の傍らに立っているのだった。
人生の最後に、思い出の場所の景色を見つめる目。──この空と海が、若松さんという一人の人間の瞳に像を結ぶことは、もう永遠にないのだった。
そして、僕の目は、別のもう一人の目を、否応なく、引き寄せてしまった。──母の目を。
あの日、帰宅した僕は、生まれて初めて、母を酷く責め、何かあったのなら話してほしいと詰め寄った。母は、「もう十分に生きたから。」と繰り返すばかりで、終いには、穏やかな、ほとんど冗談でも口にするような面持ちで言った。
「何にも不満はないのよ。お母さん、今はすごく幸せなの。だからこそ、──だから、出来たらこのまま死にたいの。どんなに美味しいものでも、ずっとは食べ続けられないでしょう? あなたはまだ若いから、わからないでしょうけど、もうそろそろねって、自然に感じる年齢があるのよ。」
「違うよ、それはお母さんの本心じゃない。お母さんは、子供や若い世代に迷惑をかけないうちに、人生のケジメをつけるべきだっていう世間の風潮に、そう思わされてるんだよ。お母さんの世代は、若い時からずっとお荷物扱いされてきたから! けど、長生きすることに、疚しさなんて感じなくていいんだよ! 僕にはまだ、お母さんが必要なんだよ。どうしてそんな悲しいこと言うの?」
「違うって。……違うのよ。これはお母さんが、自分の命について、自分で考えたことなのよ。お母さん自身の意思よ。」
「じゃあ、考え直して。僕のお願いだよ。そんなこと、……どうして?」
正直に言えば、母でない赤の他人であるなら、僕はその考えを、理解し得たかもしれない。それこそ、今ではよくある、平凡な話だと。けれども、母がそうした心境に至るには、何らかの飛躍が必要なはずだった。
僕は当然に、それを精神的な不調のせいだと考えた。実際、かかりつけ医が、母の意思の確かさを認めるまでに時間を要するのは、そのためだった。
しかし、母はその後も、まったく落ち着いていて、抑鬱的な気配は微塵もなかった。熟考しており、医師との対話にも積極的に応じ、その他、〝自由死〟の認可を出す条件を完全に満たしていた。ひょっとすると、認知症の兆候などが見つかり、将来を悲観しているのではないかとも疑ったが、医師はその見方を否定した。
取り乱していたのは、僕の方だった。母がこの世界からいなくなってしまうという想像に、僕は深甚な孤独を感じた。しかも、母が自らの意思でこんなことを考え出したのは、病気でないとするなら、僕のためを思ってなのではないのかという不安を拭えなかった。
母は僕の手を乱暴に振り解くつもりはなく、僕を納得させてから、死にたいと願っていた。
そして、僕にこう言った。
「お母さんはね、朔也と一緒にいる時が、一番幸せなの。他の誰といる時よりも。だから、死ぬ時は、朔也に看取ってほしいのよ。朔也と一緒の時の自分で死にたいの。他の人と一緒の時の自分じゃなくて。──それが、お母さんの唯一のお願い。あなたの仕事も、家を留守にしがちだから、お母さん、万が一、あなたがいない時に死ぬと思うと、恐いのよ。わかるでしょう、それは?」
僕は虚を突かれた。それは、僕自身の死の瞬間を思ってみても、慄然とさせられる考えだった。僕が死ぬ時には、一体、傍らに誰がいるんだろう? そもそも誰か、いるんだろうか?……しかし、だからといって、今すぐ〝自由死〟したいというのは、幾ら何でも、理解を絶していた。
「だけど、お母さん、まだ若いんだから。それだって、まだ十年も二十年も先の話だよ。──本当は、どうしてなの? 何かあったんでしょう?」
──僕が、悪かったのだろうか? 責めるつもりではなく、ただ、母の本心が知りたかっただけだった。
母は、僕から、人生の最後の希望を奪われてしまった。僕は、母の〝自由死〟を絶対に認めなかった。そして結局、母は僕が、上海に出張していた時に、事故死してしまったのだった。搬送先の救急病院で、若い、見知らぬ医師たちに取り囲まれて。
病院に着いた時、母にはまだ、辛うじて意識があったらしい。
母は、僕を恨んだろうか? 僕と一緒の時の自分でなく、赤の他人の目に曝されながら死ぬことを、最後の瞬間、酷く嘆いただろうか? だからあれほど言ったのにと、僕を責めただろうか? 母がこの世界に遺した最後の感情は、そんな後悔だったのだろうか?……
「──もう十分です。」
青い大きな海と空の前で、微動だにせずただ立ち尽くしていた僕に、若松さんはそう言った。僕はやはり、その言葉に、感情を搔き乱された。なぜそう思えるのだろう? 五秒前でも、五秒あとでもなく、なぜ今この瞬間だったのだろう?
それは、疲れてしまったからだろうか?
「ありがとうございました。最後にこの風景が見られて、本当に良かった。あっちにいる家内に、いい土産話が出来ました。」
僕は、丁重に挨拶をして、若松さんの希望通り、そこで通信を切断し、仕事を終えた。
東京に戻って二日後、若松さんの息子からメッセージが届いた。そこには、感謝の言葉とともに、「穏やかに眠りにつきました。」という、彼の訃報が添えられていた。
📘📙
続く、第二章「再会」は、5月21日(金)noteにて公開いたします。
📘📙
平野啓一郎の最新長篇『本心』、5月26日(水)の発売に向けて、予約受付中! 発売日に確実に手に取っていただけますよう、お馴染みの書店さん、電子書店さん、Amazonをチェックいただけましたら幸いです!
📨
「平野啓一郎 公式メールレター」でも『本心』先行配信をお届けしています。noteでの公開を待ちきれない方、ぜひこの機会にご登録ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

