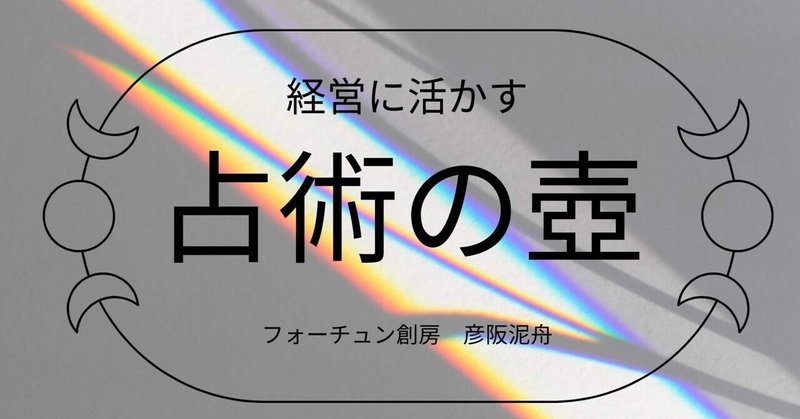
易経をベースにした東洋運勢学
五行説には万物の生成順に配当された、「生成の五行」(水火木金土)と、四季の循環を取り入れた「五行相生説」(木火土金水)があります。
この陰陽五行説は、現代にも様々な形で生活に根付いています。その典型的な例が囲碁や大相撲、あるいは薬膳料理や懐石料理です。
占術を活用してきた代表は、三国志時代の軍師・諸葛孔明をはじめ、中国の春秋時代の帝王や官僚、武将などで、占いを戦略戦術に用いてきました。日本でも中世の武将や軍師が実戦の場で活用してきました。
運勢学には「命・卜・相・医・山」の5種類があって、占い(卜)は、その一つに過ぎないのです。

東洋運勢学のベースになっているのは、四書五経の一つ易経です。四書五経は、大学、中庸、論語、孟子の四書と、易経・書経・詩経・礼記・春秋の五経から成り立っています。人の上に立つものの倫理の規範として、現在にも受け継がれています。
秦の始皇帝が、国を収めるのは武力であり、他の教養書は要らないと言って焼き捨てましたが、易だけは占いの書ということで焚書を免れました。
今でも易は、閣僚経験者の政治家や、中堅企業の経営者に愛読されている、ロングセラー書籍です。占いと言うよりも、トップの人格を磨く哲学・思想として読み継がれているのです。
易の思想を、そっけないほどシンプルに表したのが「易経三義」です。宇宙の万物は絶え間なく変化する(変易)が、そこには一定不変の法則が貫いている(不易)、その法則とは、陰と陽の対立・転化と言う、簡単明瞭な形式で表される(易簡)と言うものです。
簡単明瞭な形と言うのは、韓国の国旗にも用いられている、東洋の運命観のシンボル「太極図の」のことです。

四書五経は、中国のキャリア官僚試験「科挙」の問題に供されてきましたが、一国のリーダーとしての資質として、詩や音楽などにも精通する情操豊かな人格か否かを審査したのです。
#四書五経 #陰陽五行説 #科挙
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
