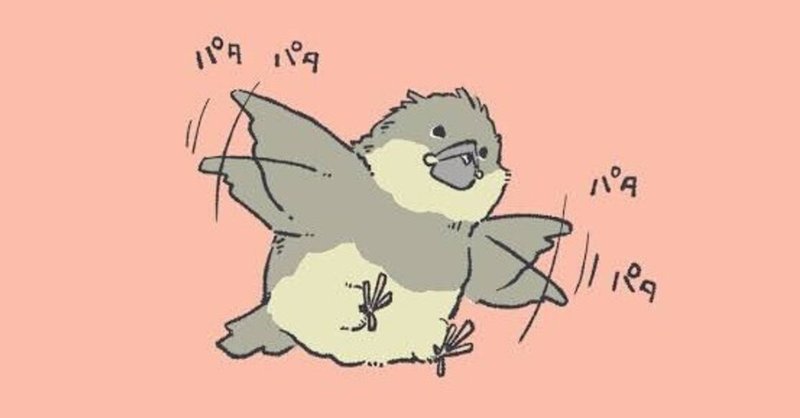
第1947回 気になる鳥 ⑶
①https://birdstory.net/illust/7560より引用の飛ぶごとを悦ぶ鳥のイラスト
どんなに飛ぶことができる鳥でも、卵から孵化してヒナになり、幼鳥となって、生まれて初めて空を飛ぶ時がきます。いざ飛ぶとなり、尻込みをするものもいたりします。しかし、何とか親鳥に飛ぶことを促されて、恐々と飛び立ち生まれて初めて翼を①のイラストのように、羽ばたきます。そして、飛ぶごとに成功したときに、私たち人間もその様子をはらはらドキドキして見守る反面、鳥だから飛べて当たり前だと思ってしまいます。飛行に成功した幼鳥のその仕草は愉快な光景です。
②-1.https://blog.goo.ne.jp/franny0330/e/280115bebf28e07c0af80a784e7c1ff4より引用の怖い顔のハシビロコウ(体長約120㌢)

②-2.https://ganref.jp/m/ogamasa/portfolios/photo_detail/3126869より引用の笑っているハシビロコウ

②-3.https://www.saiyu.co.jp/itinerary/new/GLGY12/より引用の笑っているシロフクロウ(体長約50〜65㌢)

②-4.https://www.navita.co.jp/s/11127501/より引用の怒った表情のシロフクロウ

テレビやなんかで、よく中継されますのが、長時間餌である水中にいる肺魚が近づくのを動かずに待っています②-1.と-2.の写真のハシビロコウは主に中央アフリカの熱帯部に生息し、鳥類最大といわれる長い指を持っていて、沼の多い湿地帯で沈まないためのようです。そんなモアイ像の如くいごかぬこの鳥はいつも-1.のように怖い顔かと思いましたら、何の-2.のように角度が変われば、笑っているような表情にも見えるのです。こんな大きな鳥には負けじと、②-3.と-4.の写真のシロフクロウも、人から見ましたら表情豊かな鳥です。もともとふっくらした身体に丸顔ということもあり、人にとっては癒し系の鳥かもしれません。ハシビロコウとは正反対の笑っている様な表情が多いですが、-4.のようなたまには怒った表情もします。
③-1.https://www.saiyu.co.jp/itinerary/new/GLGY12/より引用のオウギワシ(体長約99㌢)

③-2.https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A4%E3%82%A2より引用のギリシア神話に登場する女面鳥身の伝説の生物であるハーピーの想像図

何か③-1.の写真を見ていますと、私には大仏様がこちらをご覧になっておられるようにしか見えないのですが、この人のような顔をしています鳥らしき生き物は、中央アメリカから南アメリカにかけた新熱帯区に分布しています大型の猛禽類であるオウギワシです。体の大きさはフィリピンワシやオオワシと並び、猛禽類では最大の部類に入ります。写真の角のようなものこそ、扇のようで、この冠毛が名前の由来となっています。この鳥の顔を見ましたら、どうも人の顔に似ていますので、英名を単にHarpy eagleといい、“Harpy“はギリシャ神話の上半身が女で下半身が鳥の怪鳥のことを指すようです。こんな鳥が伝説の鳥です。
④-1.https://blog.goo.ne.jp/dream_019/e/b9aa6e48ba3bc2d216e5956887deb321より引用のキンケイ(左側 体長オス約95㌢、メス約70㌢)とギンケイ(右側 体長オス130~170㌢、メス:60~70㌢)

④-2.https://arkpet.ocnk.net/product/3357より引用のつがいのカンムリシャコ(左がオス、右がメス共に体長約25〜27㌢)

キジの仲間といいますと、あの小さなウズラやコジュケイもその仲間で、雌雄同色です。しかし本家本元の国鳥キジをはじめ、日本固有種のヤマドリなどキジの仲間の殆どが、オスが派手な出立ち、身体もメスより大きく、メスはその反対に地味な体色と身体もこじんまりとした感じです。これを同じ種ながら雌雄違った容姿のことを性的二型と言います。上の④-1.の写真の左がキンケイで、右がギンケイの二種のキジの仲間をご覧になられたら、なぜ故に性的二型のオスだからと言って、こんなに派手な出立ちをしなくてはいけないのかと思われた方も多いはずです。キジの仲間は地上採餌が種ですから、外敵は凄く多いのです。また④-2.の写真はやはり同じくキジの仲間のカンムリシャコです。標高のそれほど高くない熱帯雨林の中に生息するやはり地上採餌が種な鳥です。シャコというよりウズラに近い体型をしています。気になりますのは、性的二型だからオスは派手な出立ちですが、メスはメスで目立ちます。
⑤-1.https://www.navita.co.jp/s/11127501/より引用のアオアシカツオドリ(体長約80㌢)

⑤-2.https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%84%E3%82%AA%E3%83%89%E3%83%AAより引用のアカアシカツオドリ(体長約75㌢)

この⑤-1.の写真は、何か二人で肩を組み、青い長靴をステップを踏んで、歩いているのは、中央アメリカおよび南アメリカの西海岸沖に生息していますアオアシカツオドリです。求愛行動時、オスが足を交互に持ち上げ、メスの周りをダンスします。猛禽類のように少しですが、メスの身体の方が大きいのです。また、現在は巣を作りませんが、過去に作っていた頃の名残で、小枝や小石を求愛相手に指輪のように差し出す行動を致します。負けじと同じくカツオドリの仲間の⑤-2.の写真のアカアシカツオドリは、インド洋、大西洋、太平洋の熱帯および亜熱帯の海域に分布します。向こうが青ならこちらは赤だと言わんばかりに、赤い長靴を履いています。このアオアシやアカアシにしてもなぜこのように青赤の色分けになるのか。まずはアオアシカツオドリはなぜ青い足なのかは、これはエサとなる魚に含まれるカロテノイド色素を足に蓄えているために青くなるのだといわれています。またアカアシカツオドリは名前にもある赤い足の理由は求愛行動で引き付けるためだという説が最も有力と思われます。なんか釈然としないけど、それで赤いようです。また可哀想にこの二種のカツオドリの英名の後ろについています“〜-footed booby"は間抜けということです。
⑥-1.https://www.google.co.jp/amp/toricago.net/chinese-little-bittern.html/ampより引用のろくろっ首のヨシゴイ(体長約36㌢)

⑥-2.https://www.google.co.jp/amp/toricago.net/chinese-little-bittern.html/ampより引用のガニ股すぎるヨシゴイ

最後の⑥の項になって、日本に生息しています鳥が登場します。⑥-1.の写真はこれでもかというくらい首を伸ばして獲物を捕獲しようとしているところで、⑥-2.の写真は首を縮めて身を低くして脚を曲げたところが凄いガニ股に写ってしまっているヨシゴイの二枚の写真です。種類が多いサギの中で、天敵から身を守るために擬態するサギの仲間がいます。普通シラサギと呼ばれるサギは色が白いので擬態はできませんが、葦の葉や茎の色に似ているのが名前の由来となった写真のヨシゴイやサンカノゴイ、笹の葉の色にそっくりなササゴイ、木々の色や枯れ葉の色にそっくりなミゾゴイと、体の色が生息域に溶け込みようになっています。人間から見ますと笑えますが鳥たちは必死。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
