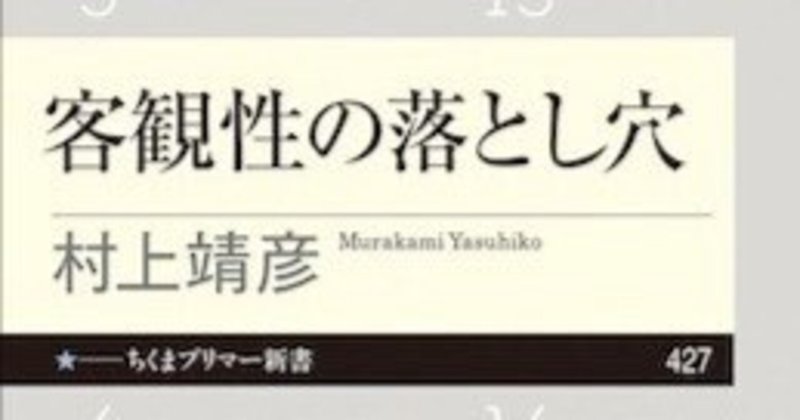
『客観性の落とし穴』を読んで、思いがけず小説について考えることになった
意図せず、昨年ベストセラー新書である『客観性の落とし穴』を購入し、読んだところ、これはまさに小説についてのことが書いてある!と思ったので、客観性というキーワードから、小説について考えてみることにした、というのがこの記事を書こうと思った理由である。
と言いながら、私自身、どこがどう『客観性の落とし穴』と小説が結びつくのかをスパッと一言で言い表せるほど考えを纏めきれていないので、章ごとの私なりの要約のメモを辿りながら考えていきたいと思う。
第一章 要約
19世紀から20世紀にかけて、人々の間で客観性が真理であるかのように考えられるようになった。
測定、数値化、法則化(論理的整合性)により、自然を客観的に捉えるようになった。(自然の客観化)
第二章 要約
社会学者デュルケームは社会をデータ化して、モノとして捉えられるようにした。(社会と心の客観化)
客観化が進むことにより経験そのものをそのまま言葉で語ることができなくなるのでないか、というのが著者の問題提起。
第三章 要約
昨今、あらゆる事柄が数値で示されるようになり、人間を数値で表して比較できるようになった。それは、一見いいことのように捉えられている節があるが、数値化されることで、社会や未来がリスクとして認識されるようになった、と著者は書いている。
第四章 要約
その例として、障がい者への差別が挙げられており、生産性という物差しで人間の価値を数値化したときに、障がい者は生産性の低い人、として扱われることになる。客観性、数値化が弱者をつくり出しているような構造がある。
というのが、(かなりざっくりだが)前提となる分析で、ここからは私の連想を含んだ理解として、客観的に説明できたり、わかりやすいことばかりを追求していくと、数値化できないもの、イレギュラーなもの、偶然によるもの、などの個別の体験の中にある客観視できない面白さを、見逃してしまうばかりか、遠ざけてしまうことになるのではないか、ということだ。
サラリーマンをやっていると、(やっていなくてもかもしれないけど)客観的な視点で物事を見たり、判断したりすることが、そうあるべきことだ、とされるような状況が本当に多い。というかそれが常識となっている。
だから、逆にそれができないと、非常識な人間と捉えられることもある。
あらゆる場面で、私たちは、客観性の名のもとに弱者を踏みつけにしているのだ。
と、書くと、あまりに感傷的かもしれないけど、それほどまでに、客観性というのはもはや現代人にとって、空気ぐらい当たり前のものとして身近に存在していて、もはや私たちは客観性を吸い込み、客観性を吐き出して呼吸をしながら生きている。
前置きが長くなったけど、要は、それら客観性の外にあるものについて考えたり表現したりすることが、小説を書くことだったり、あらゆるアート作品なのではないか、ということだ。
第五章以降で展開される、固有の経験の”語り”の中に客観性に回収されない、個有の生き生きしたダイナミズムを見出す取り組みだったり、時間という切り口から、”偶然性”(因果関係では説明できない出来事に対峙したとき、それをどう意味づけるか)や、”変化”(主観的な、時間の流れ、計測できない時間の流れ)が、科学では捉えられない、リアリティを持つというようなことが書いてあり、この辺はまんま小説を書くうえで大事なことだな、と思った。
つまり私は、小説は主観的なものであり、”個の手触り”を持っているべきものだという、保坂和志『書きあぐねている人のための小説入門』の一節を思い出したのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
