
【映画】アグニエシュカ・ホランド監督『人間の境界』
昨日は用事が立て込んで一日都内にいたのですが、合間を縫って日比谷でアグニエシュカ・ホランド監督の『人間の境界』を観てきました。
ホランド監督の映画は、『太陽と月に背いて』、『ソハの地下水道』、『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』等、出来るだけ観ていますが、どれも私の国際政治観に大きな影響を与えるものばかりでした。
どれも重く辛い内容で、実は最初に『ソハの地下水道』を観たときには、半日ほど寝込んでしまったぐらいでした…
『ソハの地下水道』は、第二次世界大戦中、現在ウクライナのリビウとなっているポーランド東部で働いていた男が、ユダヤ人達を地下水道にかくまう話です…もしご関心のある方は以下からどうぞ。
それでは前置きが長くなりましたが、今回の『人間の境界』です。
ロシアによるウクライナ侵略のインパクトが強すぎて、いまではヨーロッパでもあまり報道されなくなっていますが、この映画は2021年9月以降にベラルーシのルカシェンコ大統領がシリアやアフガニスタンから「難民」を募って一度ベラルーシに集めたあと、難民をポーランド国境からEU圏に送り込むという、いわゆる「人間/難民の武器化」を題材としています。
2022年2月のロシアの全面侵攻以前は、私は実はウクライナよりもこちらの件でコメントを求められることが多く、たとえばこのようなインタビュー記事を朝日新聞に掲載していただいていましたし、
Yahoo!コメントも出来るだけ書くようにしていました
(このnoteの最後に、過去私がこの問題について書いた全記事のコメントのスクリーンショットを掲載していますので、ご関心のある方はご覧下さい)。
朝日のインタビューでもYahoo!コメントでもそうだったのですが、私(といいますか当時のヨーロッパの主要な報道)の分析は、難民を武器化するという「ルカシェンコ政権の非道性」に焦点を当てたものになっていました。
こうしたルカシェンコ政権の手法にこそ、第一義的な問題がある、という私の主張は今でも変わりません。
一方、今回の映画『人間の境界』は、ルカシェンコ政権に問題があるのは当然の前提として共有しながらも、難民を送り込まれた側の当時のポーランドの「法と正義(PiS)」政権の対応にも、深刻な問題があったことを厳しく告発するものです。
ポーランド側に文字通り「投げ込まれた」難民達は、ポーランド内での庇護やスウェーデンへの移住を目指すのですが、まずはベラルーシ・ポーランド国境地帯の自然は、難民達が自分の足で安全なところまで移動するにはあまりに過酷です。
この映画の原題はGreen Borderなのですが、この自然豊かな国境線(border)が、難民達にとっては脅威でしかありません。
映画ではこの国境地帯の沼地で、重要な登場人物が命を落とします。
その国境地帯を命をかけてポーランドに向けて進んでいると、ポーランドの国境警備隊に見つかり、容赦なくベラルーシ側に再度「投げ込まれ」ます。ポーランド側の措置も、難民を人間として尊重するものとはとてもいえないのですが、一部の国境警備隊員はその状況で、激しい自責の念に駆られます。
ポーランド側の住民も多くは難民流入を怖がるのですが、映画では少しずつ、難民保護に立ち上がるボランティアが増えていきます。
しかし難民に協力したことが政権に知れたり、あるいは政権の指定する「立入禁止地域」に立ち入ったことが判明し次第、こうしたボランティア達は苛烈な弾圧を受けます。
映画の演出なのか、それとも事実に基づいているのかは明らかではありませんが、一人のボランティア女性は難民を助けようとした疑いで、文字通りの丸裸にされて取り調べを受けます。21世紀のこの世の中で。
個人的には、アフガン人女性難民のレイラに共感しながら観ていました。
レイラは、一緒にEU圏内を目指していたシリア人難民家族の子供達を、自分の子供のように慈しむ愛情深い女性なのですが、物語後半でポーランド国境警備隊にメガネを奪われてしまい、半狂乱になりながら連れ去られてしまうのです。
レイラの度数の強いメガネは踏みにじられ、ボランティア達の「メガネだけは返してあげて」という必死の願いも聞き届けられません。
実は私自身、コンタクトで言えば度数-7.5の強い近視でして、メガネやコンタクトがなければ研究はおろか、日常生活を送ることもままならない状態です。それもあり、数ある辛いシーンのなかでも特に私が心をえぐられたシーンでした。
痛烈な政権批判だけでなく、EUの難民政策の欺瞞・偽善に対する指摘が随所で行われています。
この映画が公開された当時、PiS政権がこの映画に対する強烈なアンチキャンペーンを行ったのも、理解できるというものです・・・

この映画のエピローグは、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略で、ウクライナからの避難民がポーランド国境に押し寄せてきていた場面を扱っています。
物語を通じて、強い葛藤と良心の呵責を覚えながら難民達をベラルーシ側に押し戻していた国境警備隊の若者は、今度はウクライナからの避難民をポーランド各地に送り届けようと全力で働くのですが、
ボランティアからは
「その優しさがベラルーシ国境でもあったらよかったのにね」
という言葉をかけられます。
ベラルーシ政権によって送り込まれた難民と、ロシアによる侵略でポーランドに逃げてきたウクライナ避難民。
理不尽な運命を突きつけられ、困窮している立場は一緒なのに、なぜポーランドにおいては両者の扱いがここまで違ったのか。人種差別という以外に説明が付かないのではないか…という点は、購入した映画パンフレットに掲載された監督のインタビューによれば、監督が強く主張したかったポイントのようです。
こうした「ダブルスタンダード」批判は、ポーランドとEUだけではなく、ヨーロッパ国際政治を観る者すべてにつきつけられたものでもあります。
また、そのポイントからは少しずれるかもしれませんが、私自身もこの映画を観て、この2年間の自分の研究上の力点の置き方を、反省を持って見直しました。
ベラルーシによる「難民の武器化」問題は、(ポーランドの政権が交代した今でも)解決したわけでも、また送り出し・受け入れ側の問題の全容が判明したわけでもない以上、継続して可視化し、提起し続けなければならなかった問題でした。
しかし果たして私自身は、この問題に対して十分な注意を払い続け、十分な発信を行ってきたか。
ロシアによるウクライナ侵略に目をとられるがあまり、この問題を疎かにはしていなかったか。
「時間がない」という甘えはなかったか。全てを一人の人間がカバーすることは出来ないことは当然にしろ、もう少し継続的に取り組めなかったのか。
様々な思いを抱きながら劇場を後にしました。
まだ『マリウポリの20日間』も観ることが出来ていませんし(油断していると終わってしまいそうなので、来週中にはなんとか…)、今月末に公開される『関心領域』も、ヨーロッパの歴史を理解する上では絶対に外せませんが、今後もヨーロッパの国際関係に関わる映画は出来るだけ観て、皆さんに共有していけたらと思います。
(本当は恋愛映画も観たいんですけどね…)
以下では、私がこの問題に関してYahoo!エキスパートコメントに書き込んだコメントをすべて掲載しています(新しい順)。
残念ながら記事本体はすでに削除されたものが多いのですが、コメントを見ていただけるだけでも、ベラルーシによる「難民の武器化」問題をざっと理解していただく一助になるのではないかと思っています。
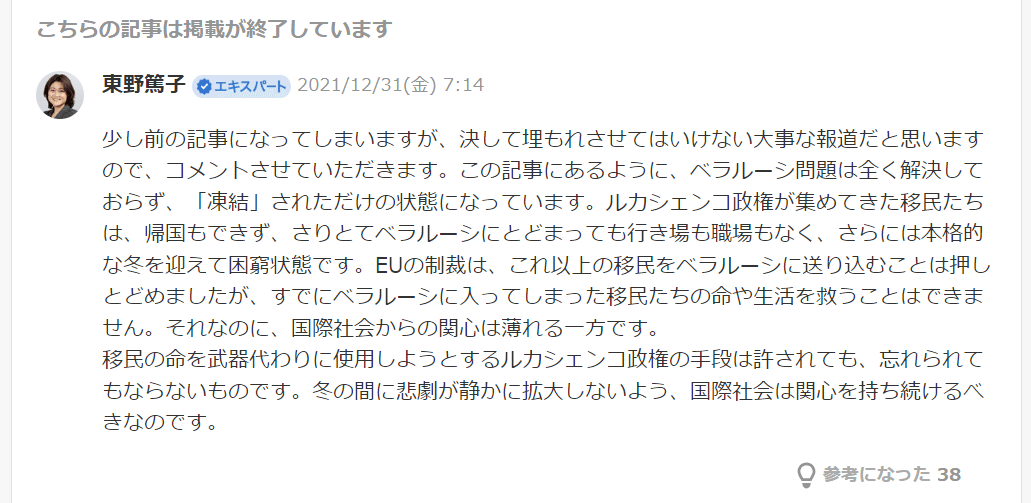






なお、これらのコメントを見て私のYahoo!のコメントに関心を持って頂けた方がおいででしたら、リンクはこちらになりますのでよろしくお願い申し上げます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
