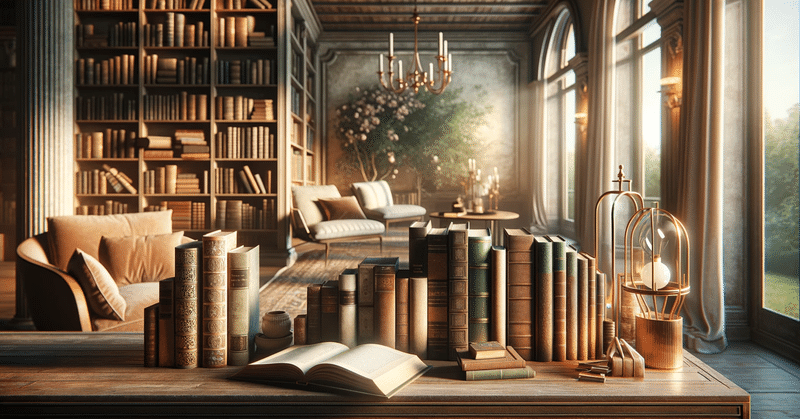
書評:ネガティブ・ケイパビリティ
今回ご紹介の書籍は、
ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力
ネガティブ・ケイパビリティとは?
・ネガティブ ケイパビリティとは「どうにも答えの出ない、どうにも対処をしようのない事態に耐える能力」
なぜ、ネガティブ・ケイパビリティが大切なの?
・ わかったつもりの理解がごく低い次元にとどまり、より高い次元まで発展できないことがある(想定外に対するあやまった管理を実行する危険性)
・ 何かが決定的に抜け落ちている可能性。世の中にはそう簡単には解決できない問題がみちみちているという事実が伝達されていないのです。人が生きてゆく上では解決できる問題よりも解決できない問題の方が何倍も多いはずなのに
・小学校から大学大学院での試験、そして就職試験に至るまで、(答えが用意された問題を)試験では問題の解決能力が測定されます。つまり、答えの出ないような問題は初めから用意されていません。(現代はこういった答えのあるものを解くという、ポジティブ・ケイパビリティが支配的な世界)
・現代の教育の現場が視野狭窄に陥っていて、親はそれ以上に視野が狭くなっている。学校の課題だけを早くこなすように強制しがち、「早くやりなさい」、「ぐずぐずしないで宿題を先にしなさい」、というのが口癖
・ 今の時代は こうすれば苦労なしで簡単にお手軽に解決しますよの方が受ける
・ The answer is the misfortune or disease of curiosity - it kills it.
・ 目の前の事象に、拙速に理解の帳尻を合わせずに、解決できない状態を不思議だと思う気持ちを忘れずに、持ちこたえていく力が要請される場合がある
具体的にはどう「対処」すればよい?
・ 解決できない問題への対処として、「日薬」と「目薬」があります。何事もすぐには解決しませんし、数ヶ月、数年と処置が続くことがあります。しかし、なんとかしているうちに、何とかなるもの。例えば、自己治癒能力が高まり自然と回復してくる。このアプローチが「日薬」。もう一つの「目薬」は、あなたの苦しい姿は主治医である「私がこの目でしかと見ています」というメッセージが伝わること
・祈祷師や自然療法を行う場合、この「目薬」と「日薬」を非常にうまく使っている。生物にもともと備わっている自然治癒能力に頼らざるを得ない場合はかなりの年月の時間が治療に必要になってくる。
その場合に、例えば患者の家族が病気のために苦労をして薬などを手に入れることは、日にちを稼ぐ「日薬」的な効果があるし、これだけ努力したんだから効果があるはずだというプラセボ効果も見込める。また苦労したからこそ、ここまで頑張ったんだから、これ以上のことはできなかったよなという納得感を得る効果も見込める。
また、治療者が病気の苦しみから目を背けずに私はあなたを見守っているという「目薬」の効果ももちろんある
・分かりたがる脳は何やらわけのわからないものを前にして苦しむことがあるが、音楽と絵画でそれが特に見られる ⇒拙速な判断や答えを求めないために芸術に触れる
・分かりたがる脳がわかるために欠かせないのが「意味づけ」。意味がわからないままだと心が落ち着きません。人は不可解なものを突きつけられるとなんとか意味づけしようとするもの⇒これに耐える
・ プラセボ効果を生じされる必要条件は「意味付け」と「期待」。治療を受けているのだと患者が意義を感じ、病気が軽減されると「期待」を持った時、脳が希望を見いだすことで回復の方向に導く
・ 小説を書くのは、暗闇を懐中電灯を持って歩くのと似ています。星の位置から目指す方向はおおよそこの道だと分かります。しかし、道がこの先まっすぐなのか曲がってるのか、行き止まりなのかは見当がつきません。⇒プロセスを楽しむ
ネガティブ・ケイパビリティと教育
・ 教育は一見すると分かっている事柄を一方的に伝授すれば済むことのように思えます。保育園や幼稚園の勉強や遊戯にしてもそうです。保育士や先生が全てをお膳立てして幼児はそれに乗っかっていればいい。本当にそうだろうか?
・ 「早く早く」を耳にするたび私は90歳の高齢者に息子と娘が早く早くとせかす光景が重なります。足元もおぼつかない高齢者に早く早くというのは 早く死ねというのと同じだからです
・ 江戸時代武士の師弟が小さい頃から返り点をつけただけの漢籍を内容がよくわからないまま素読させられたのは、現在の教育とは正反対の極にあります。子供は何のために素読をするのか分かりません。ただ 声を出すだけで意味もわからないままです。しかし何十回と繰り返していくうちに漢文独特の抑揚が身についていきます。漢字の並びからぼんやり意味 が掴めるようにもなります。この教育には教える側も教えられる側にもわからないことの苛立ちがありません。わからなくてもいいのです。子供は言われるがままに 何回も音読を繰り返します
・学べば学ぶほど未知の世界が広がっていく、学習すればするほどその道がどこまでも続いていくのがわかる。峠だと思って坂を上り詰めても、またその後ろにもう一つ高い山が見える。そこで登るのをやめてしまってもいいが見えたからにはあの頂きにたどり着いてみたい、それが人の心の常であり、学びの力、つまり、答えのない問題を探し続ける挑戦こそが教育の真髄。
【読後に思ったこと】
ネガティブ・ケイパビリティの定義を読んで、ぱっと思ったのが、え〜私、エンジニアの端くれだし、元々、米国留学時代にブルケーベン国立研究所で研究してたし、答えの無い問題に粘り強く取り組むって研究活動そのものじゃないって思ったんです。ただ、反射的にこの反応が出てくるのは実はポジティブ・ケイパビリティに思考が支配されているのかもしれない…という気づきも
ネガティブ・ケイパビリティは本質的には、仏教哲学でいうところの「空」に近い、「研究」を粘り強くして答えのない問いに取り組むということよりもより広い意味があり、その点では、まだまだネガティブ・ケイパビリティを全然身につけられていないなと感じました。特に、心(人間の内面)に関わる部分で、どうしようもないことが起きたときに、「目薬」「日薬」をうまく活用して「対処」していくというのは、全然できていないなというのが気づきでした。
【かぴばら書店さん】(対話のある本屋さん)
一流ビジネスマンの高橋さんと文通ができてしまうすごいサービス
来店できる場合:980円/月
地方の方向け:1,540円/月
正直、この値段ならまずは調べてから、、、というよりもとりあえず申し込んでしまってOKな値段設定だとおもいます。超お得。
サポートを検討いただきありがとうございます。サポートいただけるとより質の高い創作活動への意欲が高まります。ご支援はモチベーションに変えてアウトプットの質をさらに高めていきたいと考えています
