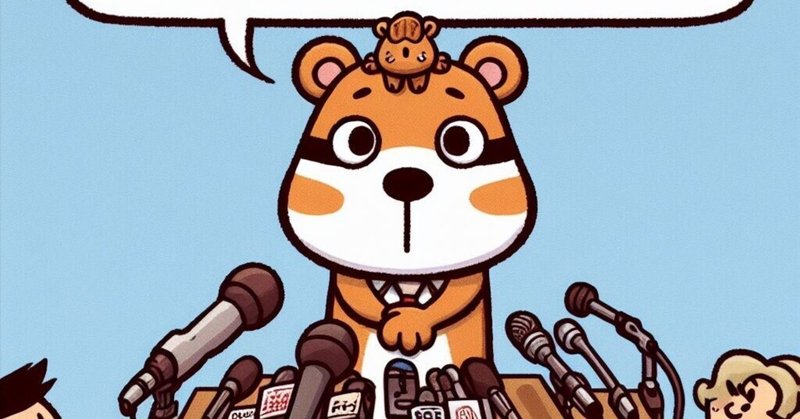最近の記事
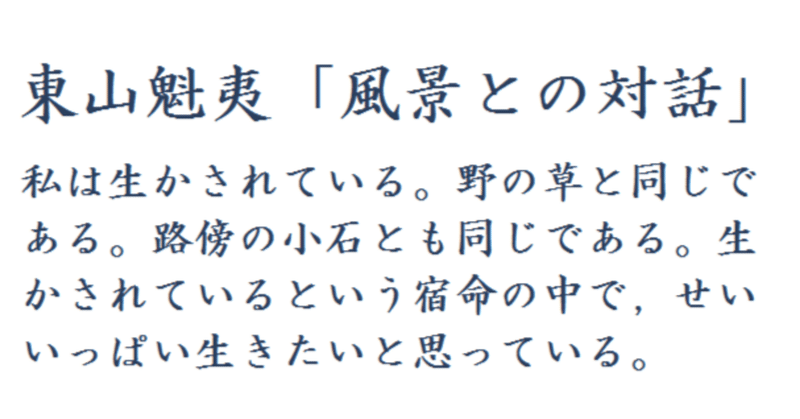
言語によって「世界の見え方」は変わり、日本人の「世界の見え方」は日本語によってのみ表現が可能であり、翻訳不能であることを「私は生かされている」という表現から検証する。
思考は言語によって形成される。日本人は日本語によって思考を形成していき、アメリカ人は英語によって、そして、中国人は中国語によって、思考を形成している。 わかりやすいところで言えば、アメリカ人にとって、神は明確な意味をもつが、日本人にとっては、神という概念は神道的な「八百万の神」だと説明できる。同じ神という言葉であっても形成される思考は異なる。もちろん、たとえ日本人であっても、子どもの頃から洗礼を受け、聖書が座右の書であれば、その限りではないかもしれない。 また、「中華」と