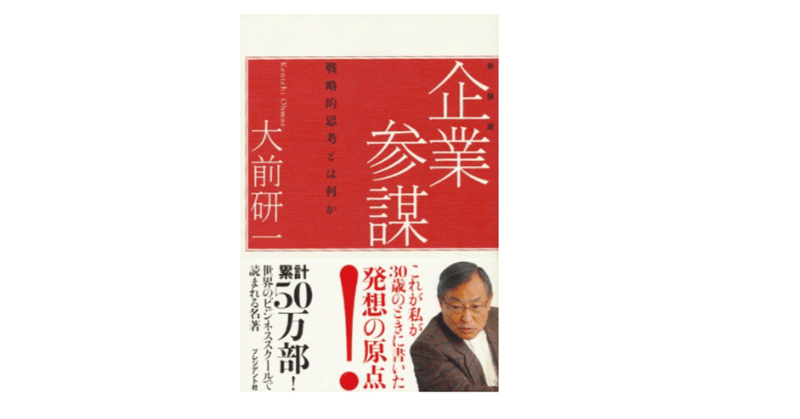
【書籍】『企業参謀』(大前研一著)で問題解決の基本を学ぶ
大前研一氏の『企業参謀』をご存知でしょうか。1975年と1977年に刊行され大前氏の著者の出世作となった『正・続企業参謀』の新装版です。経営戦略の基礎が盛り込まれており、中身が非常に濃い本です。
ここでは、その中でも私が最も気に入っており、常時使っている「問題解決の基本」に係る部分を取り上げたいと思います。この部分を学ぶだけでも、すぐに実践に使うことができると思っています。
「問題解決の基本」のプロセス
大前研一氏『企業参謀』は、問題解決の基本が盛り込まれています。特に以下、「問題点の抽出と解決のプロセス」をマスターし、繰り返し演習をしていくことによって、「本質的問題」の抽出→課題設定→方向性(案)を出すことができるようになります。
3 問題点の摘出と解決のプロセス
設問を解決策志向的型にすることによって、物の本質に迫る解決案というものを出す場合、設問が的を射ているためには、問題点そのものがすでに正しく把握されている必要がある。
(中略)
このため問題点のしぼり方、すなわち摘出方法が問題解決の一つの決め手となる。私は、この段階で重要なことは、
「問題点の絞り方を現象追随的に行うこと」
であると思う。
「問題点の絞り方を現象追随的に行う」ということが非常に重要です。ここで「現象」ということについて注意が必要です。後述もしますが、誤りがちなのは、これを「問題点」あるいは「本質的な問題点」としてしまいがちなことです。そうすると、単なる現象に対して解決策を立案してしまうことになります。付け焼き刃、または問題点でないところに対してケアをしてしまうということになってしまいます。これは本当によるあること、というよりも、このようなことも多いのではないかと思います。
まず現象の摘出にあたっては、ブレーンストーミングでも、オピニオンポルでも、あるいはその他のどんな方法でもよいから、当該企業が新鋭企業に対して、劣っていると思われる点を集め、箇条書きにする。次に、これらは必ず何らかの共通項に整理されるはずだから、例の同類項をくくる誰でも知っている初等数学の要領で、グルーピングを行う。そのうえで、もう一度グループとしてまとめてみた場合に、共通していえる問題点とは何か、ということを考えてみる。
このプロセスを抽象化のプロセスと呼んでもよい。
こうして、初めてこの企業の直面する真の問題というのが、取りこぼしなく摘出され得るのである。
事象に飛びつかず、抽象化を行う
現象抽出→グルーピング→抽象化→アプローチ(必要な手段)設定です。
まずは、現象を抽出する。何度もいいますが、これはあくまでも現象であって、問題点ではありません。そこに飛びついてしまうと、問題点が異なった状態で解決策を出そうとしてしまいます。
グルーピングを行うことで、バラバラであった各現象がある程度の塊になります。その状態で、そこからいえることは何なのか、ということを考察し、アプローチの設定を行います。抽象化することで、現象を俯瞰して見ることができるようになります。
私が今までに見、あるいは聞いてきた限りでは、企業内でルーチン化している業務内容改善計画やプロジェクト活動というものは、えてしてこの抽象化のプロセスを踏んでいない。したがって、解決策と問題点が短絡してしまっているのである。
例えば〈図7〉、
「問題」=事業部間人事交流の欠如
「対策」=事業部間人事の流出入を容易にし、人事交流を図る
といったたぐいの短絡した解決である。しかし、現象として表れている問題点が何に帰属する問題であるのか、何に深くかかわりあいがあるのか、ということの理解なしには真の解決策は得難い。
私もまさに人事として長く企業活動に従事しておりますが、「人材交流がない」→「人材交流を行う」というった類の解決はいくらでも見られますよね。人材交流がないという事象と、問題点を一色淡にしてしまっています。人材交流がないことが、必ずしも、問題というわけではないです。人材交流がなく、人材を一事業部に長く集中させた方が業績もよくなるかもしれませんね。深掘りが必要なのです。
もう一つ例を。昨今は、人材採用に難しくなっていますね。ではどうするか、ということを検討するときに、エージェントを使う、広告を出す、リファラル採用(紹介採用)を使う、などとなっていないでしょうか。いきなり、採用の手段に入ってしまっているわけです。そう考えると、こういった現象は、至るところにあるというのが分かるでしょう。
さて、ひとたび抽象化がすめば、問題解決のアプローチについては、既成の問題解決法がかなり使えるのである。
(中略)
さて、〈図6〉の抽象化プロセスは、アプローチの設定で終わるのではない。問題解決はこれからである。このときの大きな方向として、一度抽象化し、アプローチを決めたら、今度は具象化に向かって実行計画書をまとめてゆく。どんなに有能なラインマネジャーでも、抽象的な計画は実行できないし、どんなに本質をついた解決策でも、実行されなければ実効は出てこないからである。この間の例は、二、三後述する機会もあるので、今は〈図7〉を再度ながめて、この抽象化と具象化のプロセスが、本質的問題解決の一つの特徴である、ということを覚えておいていただければ十分である。
具象化、解決策の方向性を見出す
抽象化までいったら、今度は具象化に向けて進めていきます。1回だけではなくて、何回も「抽象化」と「具象化」を行き来させて確度を高めていきます。「抽象と具象」って現在では当たり前のように言われていますけれど、大前氏は早い段階から気づいていたとすると、すごいですね。
BBT大学大学院の教科書にもなっている
なお、当書籍は私も終了した、ビジネス・ブレークスルー(BBT)大学大学院でも、教科書として取り扱われています。また、非常に中身の濃い本ですので、何度でも読み返し、実践として当ててみる書籍です。是非ご一読ください。
問題解決の事例
問題解決のプロセスで短絡的なアプローチを採るとは、問題の根本原因を詳細に分析することなく、急いで表面的な症状のみに対処することを意味します。このような方法は一時的な解決策にはなり得るものの、問題が再発する可能性が高く、結局はより多くの時間とリソースの浪費につながることがあります。以下に、この問題解決スタイルの具体的な例を挙げ、より効果的なアプローチについても考察します。
具体例:企業の顧客サービス部門でのクレーム対応
状況説明
ある企業の顧客サービス部門で顧客からのクレームが急激に増加している状況が発生しました。クレームの内容は主に製品の不具合に関連しており、顧客の不満が高まっています。
短絡的な解決策
この問題に対処するために、部門のマネージャーはクレーム処理のスタッフを急遽増員することを決定しました。目的は、クレームに対する応答時間を短縮し、顧客の即時の不満を迅速に解消することにあります。この対策により、表面的には顧客からの直接的な不満は減少するかもしれません。
問題点の深掘り
しかし、このアプローチは製品自体の品質問題というクレームの増加の根本的な原因には目を向けていません。スタッフの増員は一時的な解決に過ぎず、製品の欠陥が解消されない限り、クレームは持続する可能性があります。この結果、組織は無駄なリソースを消費し続け、顧客満足度の長期的な低下を招くことになるでしょう。
より戦略的なアプローチの提案
より効果的な解決策としては、まず製品の品質管理プロセスを全面的に見直し、製造から出荷に至るまでの各段階での品質チェックを強化することが考えられます。さらに、クレームのデータを詳細に分析し、特定の問題が発生している製品ラインや製造ロットを特定することも重要です。これにより、具体的な製品改善策を講じることが可能になり、問題の再発防止につながります。
このように、問題解決においては短期的な対応だけでなく、長期的な視点を持って根本原因を特定し、それに基づいた体系的な対策を講じることが重要です。これにより、再発を防ぎ、組織全体の効率を向上させることができます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
