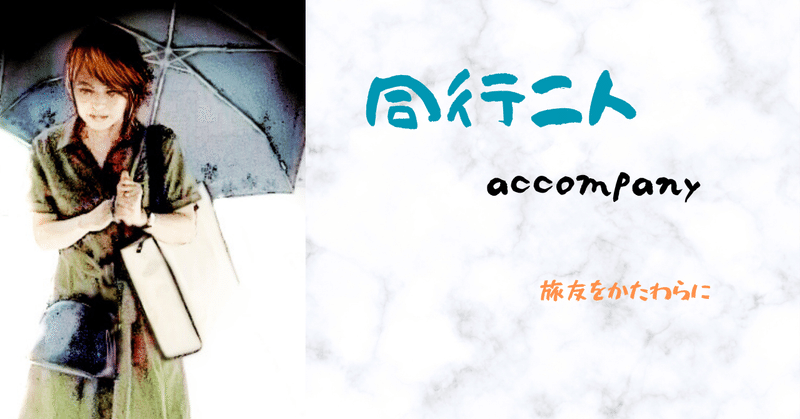
湯島聖堂~良き世は、良き秩序にあり・・か
中央線御茶ノ水駅。
懐かしい響きだ、学生時代この界隈は良くほっつき歩いたものだ。今はそんな面影はないが、かつてはここは「学生街」だったし、当時の学生たちは、一時この界隈を占拠し、「カルチェ・ラタン」を夢見た過去があった。
そんな、幻を夢見た場所でもあった。
だが、その後いわゆる「学生運動」も下火になり、マチからはそういう記憶もなくなっていった。
そんな妙な記憶があるこの界隈。彼女は不思議そうに言う
「え?だってあなたの大学って、南の方でしょ?」
「そうだよ、だけど、この辺は良く古本買いに来てたんだ。」
「へぇ~。」
「アルバイトもこの辺が多かったからかな。」
「どんなことやってたの?」
「小さな印刷工場。」
考えれば、当時の学生運動は、ある意味「秩序への挑戦」だった。
そんなつまらないことを考えながら、私たちは湯島聖堂に向かった。これも徳川綱吉が建てたものだ。
綱吉の治世、「文治政治」がメインになった。すなわち、武力に頼らない政治である。
その契機は、慶安4年 におこった由井正雪の乱 だった。
戦国の名残でもある統合の条件「総無事」が、強権によって保たれるという武断政治は、この乱の原因となった社会矛盾だったのだ。
家康から家光へと続いた政治は、強大な幕府の武力と、それを背景にした「法度」に基づいた支配体制だった。だが、それはある意味「恐怖」を拠り所にした統治だ。
その結果は、各藩の取りつぶし、改易などの生殺与奪の権を、幕府が合法的に行使出来た事を意味する。その結果が主を失った武士=牢人の急増だった。
彼らが不満を爆発させ、叛乱を起こしたのは、こういった社会情勢の変化による。
やはり、「秩序」は大事なのだ。しかしそれ以上に、「力」を持つものは弱いものに慈しみを持たねばならぬと言うのが儒教の考えなのだろう。綱吉が理想としたのはたぶんこういうことなのだろうと聖堂の伽藍を眺めつつ思った。

湯島聖堂はまさに大都会の真ん中にある。その中にあって、凜とした佇まいを保っている。これはいったい何なのだ。そうか、ここは「学問の府」なのだ。その雰囲気が漂っているのだ。民間信仰とは一線を画している。

「なんかお寺さんと雰囲気違うねぇ・・。」
彼女は実にピュアな感覚でいきなりものを言う。そうだよ、ここはお寺さんじゃないから・・。しかし、その無理のないスタンスが魅力的なのかもしれない。
「おバカでゴメンね。」
彼女はよく言うが、おバカであると言う事を自分で言える事が尊いのだ。そういう面で「莫迦」の境地にいるのだからだ
日はすでに傾き始めていた。

「ちょっと、一杯引っかけていく?」
彼女は待ってましたとばかりの笑顔で大きくうなずいた。
「うん!、いこいこ!。知ってるいい店あるんよ~。」
・・・はいはい。
これも、「酔い秩序」ってやつだな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
