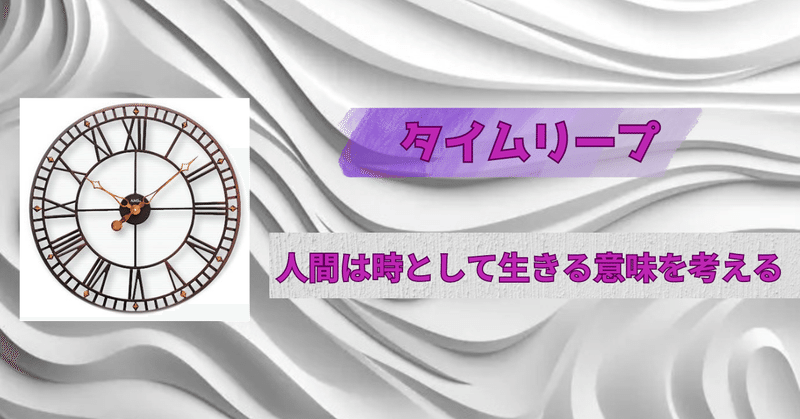
「偉大なる魂」マハトマ・ガンディーの闘い

「マハトマ・ガンディー」という人をどれほど正しく知っていますか。今日はガンディーの生涯を通して、「人間の大きさとは何か」について、考えてみたいと思います。
子ども時代のモハンダス・ガンディ―は、内気で、神経質な面を持っていました。彼は『自伝』に、「かつての私はとても引っ込み思案で、人と親しくつきあうのをさけるような少年だった」と記しています。
若くして結婚したガンディーは、単身ロンドンに留学し、1891年に弁護士資格を得ました。ガンディーは、ヒンドゥー教徒として育てられましたが、イギリスに行くまでは、宗教についてあまり深く考えたことはありませんでした。彼は生涯を通して、ヒンドゥー教徒でしたが、キリスト教やイスラム教など他の宗教をも学び、そのすべてに敬意を抱くようになりました。他人を理解するためには、彼らの宗教を理解することが大きな助けになると確信したのです。
インドで弁護士の仕事を依頼されましたが、あまりに内気なガンディーは、法廷で立ち上がり、人前で弁護をすることができませんでした。困っていたガンディーに、1893年、南アフリカでインド人の商人が経営する会社の法律顧問の仕事がまいこんできたのです。当時の南アフリカは、人種差別が激しく、日が落ちてからは、有色人種は外出することさえできない程でした。
ガンディー自身、汽車の一等切符を持っていたにもかかわらず、一等車から放り出された経験を持っていました。以来、彼は南アフリカのインド人を助けたいと強く願うようになったのです。
この南アフリカでの経験をガンディーは、「生涯におけるもっとも創造的な経験」と述べていますが、不条理な差別に対する怒りをどのように効果的に表明すべきかについて、ある意味悟りをひらいたのです。
ある時開いたインド人の集会で、不当な差別をなくすための演説をしたガンディーは、まるで別人のようでした。口ごもることも、緊張のあまりその場に座り込むこともなく、力強い言葉は彼の口からよどみなく流れ出て、人々の心を動かしました。
ガンディーは、インドの民衆のために生きるという使命を自覚したことによって、わずかな間に「怖れなき心を持った闘士」に生まれ変わっていたのです。後にガンディーは、「たとえ体は小さくとも、自分の使命に対して、信念を抱き、決然とした心を持つ者だけが、歴史の流れを変えることができるのです」と述べています。
ガンディーは、差別をしている白人たちを罵るのではなく、インド人たちに「誇りを持て」「勇気を持て」と訴えました。臆病だった青年は、一夜にして優れた民衆指導者となったのです。
しかし、ガンディーの努力も虚しく、1906年、トランスバール政府はインド人の入国を制限し、すべてのインド人に登録と指紋提出を義務付ける法案を作りました。登録証を携帯しないものは追放処分や罰金刑となり、従わなければ投獄されるというものです。
ガンディーは、この法案の成立を阻止するため、組織的な抵抗運動を始めました。多くのインド人が運動に参加し、政府への登録を拒否しました。登録者は全インド人の五%にも満たなかったため、政府は登録を拒否した者への弾圧を開始し、1908年には、ガンディーを含め、多くのインド人を逮捕しました。それでも彼らはガンディーの教えの通り、固く結束し、暴力で対抗することなく、権力の横暴に徹底的に抵抗したのです。
ガンディーたちの運動は、じっと暴力に耐えるだけではありませんでした。彼らは銃のような武器を持つかわりに、「非暴力」という武器を手にした戦士でした。ガンディーは、この運動のあり方を「サティヤーグラハ」(真理をつかむこと)と名づけ、明確な非暴力の抵抗闘争となったのです。ガンディーが収監されていたヨハネスバーグ刑務所には、わずか2週間で155人ものインド人が収監されてきました。彼らは「われらのガンディーが投獄されている刑務所を、われらの仲間で満員にしてしまおう」と誓い合っていたのです。
1910年、トランスバール共和国が南アフリカ連邦(現在の南アフリカ共和国)に吸収されると、新たに「インド式婚姻無効法」が制定されました。インド式の結婚式による結婚は無効で正式な夫婦と認められず、その子どもたちには財産相続も認められませんでした。
これには女性たちも妻としての尊厳を守るため立ち上がりました。わずか16名で始められたデモ行進は、瞬く間に数千人になり、参加者はガンディーをはじめ次々に逮捕されました。
しかし、デモ行進は止むことなく、増え続けました。「サティヤーグラハ」の勢いは止まらず、イギリスやインドをはじめとする国際世論も南アフリカ政府を非難し始めたのです。その結果、1914年には、「インド人救済法」が成立し、ガンディーたちの要求はほとんどすべて、この法律によって実現しました。
22年に及んだガンディーの「サティヤーグラハ」という「愛によって憎悪に打ち勝つ」闘いは、見事にその方法の正しさを証明し、勝利したのです。「サティヤーグラハ」とは、要するに、すべての人の心の中にあるに違いない真理や正義、愛を喚起するということなのです。使命を終えたガンディーは、1914年、祖国インドに帰りました。
すでに「戦う闘士」としてインドでも有名だったガンディーは、インド西北部に小さな活動拠点を作りました。しかし、帰国後しばらく、表舞台に姿を見せなかったガンディーが、インド全土を舞台に闘いを始めるきっかけとなったのは、1919年にイギリス政府によって作られた「ローラット法」でした。
イギリスの政策に反対するインド人を令状なしで逮捕し、裁判で弁護を受けることもなく牢獄に入れるという悪法です。ガンディーは他のインド人指導者たちに4月6日に全国民が、集団で仕事や学校を休み、祈りを捧げたり行進をしたりする非暴力のストライキを提案しました。
ガンディー自身、果たしてその提案にどれほどの民衆が参加してくれるか、不安でした。しかし、その日、インド中の商店や工場がいっせいに仕事を休んだのです。1919年4月6日は、インドの全民衆が歴史上初めて民衆運動に参加した記念すべき日となったのです。
ガンディーが民衆運動に大きな影響力を持っていると確信したイギリス政府は、それらしい理由でガンディーを逮捕しました。民衆は不当な逮捕に怒り、暴動を起こしました。「サティヤーグラハ」が非暴力に徹した抵抗運動であることを、インドの民衆はまだ十分理解していなかったのです。
罪滅ぼしの意味を込めて、ガンディーは三日間の断食を行いました。ガンディーにとっての断食は、抗議ではなく、自己浄化であって、これに共感する人々を自己浄化させることが目的なのです。
ガンディーが3日目の断食を終えようとしたまさにその日に、悲劇は起きました。パンジャブ地方のアムリッツァルでは、この日シーク教徒を中心とする大規模な集会が開かれることになっていました。
パンジャブには急遽、集会禁止令が出されましたが、女性や小さな子どもを含む約2万人の民衆のほとんどは、集会禁止令について、何も知りませんでした。会場となった公園の広場には、ダイヤー准将率いる90人の、イギリス軍兵士が待ち構えていたのです。兵士たちはいっせいに銃をかまえると、群衆めがけて発砲しました。逃げまどう人々の叫び声が銃声と重なって、見るも恐ろしい地獄と化したのです。インド人の暴動に対するイギリスの仕返しは、1200人以上もの犠牲者を出しました。
ガンディーが非暴力を貫いたのは、暴力がさらに大きな暴力を生むことを良く知っていたからです。だからこそ、たとえ正義のためであっても、暴力を用いてはならないと考えたのです。この大虐殺はインドの民衆の怒りを燃え上がらせ、「何が非暴力だ。何が不服従だ。やつらは、おれたちを虫けらのように殺しまくった。」怒りを爆発させた人々は、各地にあふれ、電車のレールをはがしたり、電線を切断したり、駅になだれ込んだり、役所に押し入って役人を殺したりしました。
ガンディーは、民衆に向かって、怒りを鎮め、暴力の連鎖を断ち切ろうと何度も何度も訴えましたが、各地の暴動は広がるばかりでした。ガンディーは言いました。「仲間や身内を殺されて、相手をやつざきにしてやりたいという気持ちはわかります。しかし、敵をゆるすことは、敵を罰するより、ずっと気高い行為だということを、どうか忘れないでほしい。」「力は、腕力からではなく、不屈の意志から生まれるのです」と。
しかし、各地の暴動は広がるばかりで、1922年には、ある村で、警察官の発砲に怒った約3000人の民衆が、警察署を襲撃し、建物に放火し22人の警察官を焼死させたのです。
ガンディーは、静かに言いました。「確かに、運動はいま最高に盛り上がっている。ここでやめることは、イギリス政府を喜ばせることになるだろうし、政治的には間違っている。だが、宗教的には決して間違っていない。わたしが求めるただ一つの徳は、真理と非暴力なのだから…。」非暴力という信念を曲げてまで運動の成果をあげることは、ガンディーの良心が許さなかったのです。
こうして、「サティヤーグラハ」運動は中断され、民衆は戸惑うばかりでした。イギリス政府は大いに喜び、さらに追い打ちをかけるようにガンディーを逮捕しました。ガンディーが投獄されている間に、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立は深刻化していきました。
獄中でガンディーは、どうやってインド独立の運動を「非暴力・不服従」の信念のもとに実現するか、その具体的な方法をずっと考えていました。
禁錮6年の刑に処せられたガンディーでしたが、重い虫垂炎にかかり、わずか2年で釈放されました。インド人の生活をよくするためには、イギリスの統治を終わらせるだけでは不十分で、カースト制度の枠組みにも入らない最下層の不可触民に対する差別や深刻な地方の貧困、宗教対立など解決すべき国内問題はたくさんあり、イギリスに対する抵抗運動と、インド自体の変革を両立させていかなければなりませんでした。
そんな折、ガンディーは、新しい抵抗の方法を思いついたのです。それが有名な「塩の行進」です。当時、イギリス政府は、塩の製造・販売を独占し、インド人から高い塩税を取り立てていました。ガンディーは、自らの手で塩を作ることを思いついたのです。

行進は1930年3月12日にガンディーが自ら選んで集めた78人でダンディーという海岸を目指して390キロの道のりを行進し始めたのです。運動の意義をわかりやすく伝えながら、4月5日に目的地の海岸に着いた時には、行進は数千人に膨れ上がっていました。
翌朝ガンディーは海岸に行き、祈りを捧げたあと、身をかがめて、小さな塩のかたまりを拾い始めました。行進をしてきた人々もガンディーにならって塩のかたまりを拾いました。400人の警察官が棍棒をふりおろし、25人のライフル部隊が一斉に発砲しても、民衆はたじろぐことなく、非暴力の抵抗運動を続けました。数週間で、じつに10万人もの男女が製塩法違反によって投獄されました。
アメリカのジャーナリストによって、この事実は世界に知らされ、イギリスと世界の良心に訴えかけられました。世界中の新聞もきそって記事として取り上げ、ガンディーの名は、世界中に知れわたり、運動はさまざまな形で拡大し、500万人規模の大衆運動に発展していきました。
イギリス製品の不買運動、税金の不払い運動、工場労働者のストライキ、ハルタール(閉店、休業、断食、祈り)など、いよいよ盛んになってインド全土に広がっていきました。
獄中にあってもガンディーは闘いました。南アフリカ時代に2回、インドに帰ってから16回の大きな断食を行っています。もちろん命がけであり、「われらのマハトマ・ガンディー」に万一のことがあれば、彼を崇拝するインドの民衆は何をするかわかりません。イギリス政府もガンディーを交渉相手として、インドの独立・自治を真剣に考えなければならない時期がきていたのです。
そんな中、1939年に第二次世界大戦が始まると、しばらくして日本の東南アジア侵略の波が、インドにも迫ってきました。ガンディーらは、独立運動を一時停止し、イギリスと協力して、日本の侵略という、より巨大な暴力と戦うことを決意しました。
戦後、国際情勢は大きく変化し、1947年8月15日、ガンディーが長年夢見てきた、インドの独立がついに認められました。しかし、独立した国家は、ヒンドゥー教徒が多数をしめるインドと、イスラム教徒が多数をしめるパキスタンに分かれてしまい、その後も両教徒は激しい宗教対立を繰り広げ、多数の血が流されました。宗教的和解を求めて断食に入ったガンディーに対して、「ヒンドゥー教徒の国でイスラム教徒の味方をするのは、祖国への裏切りだ」とささやく者もいました。
1948年1月30日の夕刻、首都ニューデリーのビルラー邸という屋敷で、数人の従者とともに夕べの礼拝に向かっていたガンディーに、一人の青年が近づいてきました。
「やあ、こんばんは。きみは?」両手を合わせ、親しく声をかけたガンディーに向かって、3発の銃弾が撃ち込まれました。青年は、イスラム教徒との融和を嫌う、狂信的なヒンドゥー教徒でした。ガンディーは述べています。「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」と。
インドの国民的詩人タゴールが「偉大なる魂」という意味から「マハトマ」と呼んだガンディーの葬儀は、あらゆる宗教の壁を超えて、国をあげて行われました。
若い頃、引っ込み思案で、人前で話すのもままならなかった臆病者が、なぜ「インド独立の父」と呼ばれる偉大な民衆指導者となり得たのか。ガンディーは確信をもって、こう述べています。「人間は、その人の思考の産物にすぎない。人は思っている通りになる」と。人間の大きさとは、思想の高邁さ、魂の偉大さに裏打ちされた勇気ある行動によって決まるのです。
ガンディーが私たちに教えてくれたことは、何か。それは、不可触民も同じ人権を持つという「人間の尊厳」、暴力にたよらなくとも軍隊にも負けない力をもてるという「非暴力主義」、命令されても従わない「不服従という抵抗」のあり方、イギリスの力なくして祖国を繁栄させられるという「独立自治の精神」、宗派を超えて、信仰によって精神が満たされると、誰に対しても悪意や憎しみを抱くことができなくなるという「人間主義の宗教の重要性」です。
参考文献 前原政之『ガンディー伝~偉大なる魂・非暴力の戦士』(第三文明社)
フィリップ・ウィルキンソン『ガンディー』(BL出版)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
