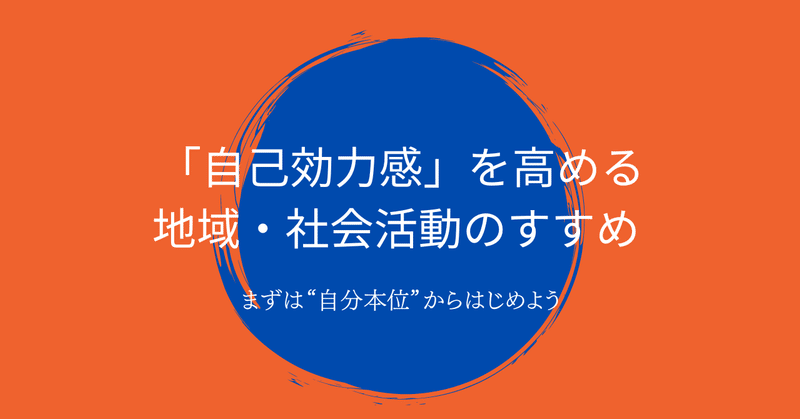
「自己効力感」を高める地域・社会活動のすすめ -まずは“自分本位”からはじめよう-
はじめに、本noteの想定する読者を書いておくと、
若手のビジネス実務従事者
地域・社会活動に関わってこなかった人
という方々です。
もう少し補足しておくと、1点目については、歴戦のビジネス経験者ではなく、現役で若手の実務従事者を想定しています。業種・職種は問いませんが、特に筆者と同じD2Cビジネスに従事している人に読んでもらえると嬉しいです。
2点目については、既に地域・社会活動に関わっている(関わっていた)人にも共感して欲しいですが、より深く刺さって欲しいのは、これまで地域・社会活動に関わってこなかった人に気づきを与えられたらと思っています。
また、「地域・社会活動」というと社会課題の解決や公益性があるような高尚な活動をイメージしてしまうかもしれませんが、ご近所や町内会、子供会、学校などの取り組みでも良いです。
「営利目的が弱い、会社以外の活動」くらいの緩い定義で捉えてみてください。
今回のnoteの趣旨は、このような読者に対して、「自己効力感」(“自分ならできる”と、目標達成のための能力を自身が有していると認識すること。簡単に言うと“自信”に近い)を高めるために気軽に地域・社会活動を始めてみませんか?と伝えたいということと、その結果、自身の仕事に対しても自信や成長意欲が芽生えるという好循環が生まれたら良いなぁというものです。
また、もし地域・社会活動に関わっている団体の方が読んでくださった場合、身近なところに様々なプロフェッショナルがいて、きっかけさえあれば地域・社会活動に参加してもらえますよ(特にD2Cビジネスに従事している人って色々役に立ちますよ)ということを伝えられたら幸いです。
本noteのきっかけになった地域食堂の立ち上げ活動
さて、これまでCX(Customer Experience)やD2Cを取り巻く概念的な事象について屁理屈のようなnoteを書いてきた私が、なぜ本noteを書こうと思ったかというと、2024年4月に妻が団体代表として立ち上げた地域食堂に関わったことがきっかけです。
【参照】筆者が関わっている地域食堂についての地域情報誌の取材記事
https://www.townnews.co.jp/0103/2024/04/18/729108.html
地域食堂やこども食堂は、ライフスタイルの変化に伴う地域のつながりの希薄化や、子どもやお年寄りの個食、生活困窮など、様々な事情・社会情勢によってニーズが高まってきているものの、その担い手の多くは行政ではなく民間の個人・団体です。
しかし、個人がいざ地域食堂を作ろうとすると、超えなくてはいけないハードルは非常に多く、もはや「起業」に近いことをやらなくてはいけません。
私の妻の場合も、既存の地域食堂にボランティア参加しながら話を聞いて手探りで情報を収集し、団体として活動するための立ち上げメンバーを集め、町内会や民生委員さん等の地域の方々との繫りを作り、団体としての活動実績と書類を整えて銀行口座を開設し、助成金を申請し、チラシを制作・配布し、ボランティアさんを募集し、開催告知をして・・・個人として強い意志と根気、時間、体力を注ぎ込むとともに、本当に多くの方々の協力を得ないと、立ち上げが難しいのが現実です。
私も微力ながら、何か手伝おうとしますが、これまで地域との関りをほとんど持ってこなかった上に、地域食堂に関する知識も乏しく、なによりフルタイムで働きながら手伝えることは限られます。
そのため、必然的に自身が業務で得た知識を活かせる領域で関わることになります。
ビジネスの実務経験は、地域・社会活動に活かせるのか?
それでは、ビジネス実務従事者が、その経験をどのように地域・社会活動に活かすことができるのか?
それほど難しく考える必要はありません。自身がこれまで業務で関わってきた内容について、端的なキーワードにして“私の得意分野は●●です”と掲げてみましょう。
また、これまで地域・社会活動に関わった経験が無くても、気にする必要はありません。“関わってみたい”という気持ちが大事ですし、かく言う私も社会人になってから20年以上、地域・社会活動への関りはほぼありませんでした。
私の例を書いてみます。
私の場合、ビジネス経験で得た知識を活かせる得意分野は、「IT」、「Web」、「SNS」、「CRM」、「会計」といったキーワードになります。
キャリアのスタートはSEでしたし、その後も初期のキャリアで情報システム部門に在籍していました。また、実は大学時代(2000年前後)にHTMLを手書きして個人でHPを作っていました。現在もECを主要チャネルとするビジネスに関わっていますので、「IT」や「Web」については、それなりに理解をしているレベルであると思っています。
そのため、団体のHPの制作は難なく行えました。
また、ECビジネスに関わっていれば、「SNS」の運用についても知識と経験が備わります。FacebookページやInstagramアカウント、LINE公式アカウントの立ち上げと初期設定、運用ノウハウなどの基本的な経験がこれに当たります。また、日々これらのプラットフォームの事例や情報に触れていますので、手段としてどのような活用ができるのかは、検討がつきやすい状態にあります。
団体の情報発信のためのFacebookページやInstagramアカウントの設定・運用、参加者募集のためのLINE公式アカウントの立ち上げなどに、この経験が活かせました。
そして個人的には最も応用の効く汎用性の高い経験は、「CRM」だと思っています。CRM:Customer Relationship Managementは、対象となるお客さまとの関係性をコミュニケーションを通じて構築するものです。対象となる方の年齢等の属性や、媒介するモノ(サービスや製品)は異なったとしても、相手の方に対して、“どのように感じるか?”、“どのように感じてほしいか?”、その結果、“どのように行動して欲しいか”を考えて施策を行うことがCRMの本質であり、この概念はあらゆる業界・業種・商材で通用します。(これは私が副業で行っているスポットコンサルでも実感していることです。)
団体の発信内容をお客様起点で見ることができるだけでなく、わかりやすいユーザーインターフェースとしてQRコードの活用やアンケートフォームの設計、LINEの応答メッセージのシナリオなどに活かせました。
もう一つ、地域・社会活動においても何らかの“団体”として活動をする以上、必要になってくるのは「会計」に関する領域です。企業・団体のあらゆる活動は、その結果が会計情報に反映され、報告する必要があります。団体を通じて行う社会活動においても、その活動の経済状態を記録し、報告する必要性は生じるので、会計の知識は重要になります。私は事業活動に関わるお金の処理を正しく理解するために簿記の資格を取ってみたり、ビジネススクールのゼミではアカウンティングとファイナンスを専攻しました。
団体の会計処理は、簡単な出納帳や元帳の起票が出来れば、十分に対応出来ます。
このように、キャリアのどこかで(或いは学生時代に)少々かじっていたり、ちょっと勉強をした分野やキーワードを、“私の得意分野”として掲げてみるだけで、良いのです。
それが、自身が地域・社会活動に活かすことができる経験や能力です。
ビジネス経験を地域・社会活動に活かすことで得られる「自己効力感」
ビジネスで実務に従事している人であれば、それぞれ何かしらの「得意分野」と呼べるものがあると思います。
そして、それを活かした業務を通じてお給料をもらえているということは、「その道のプロ」と言えます。
ですが、ビジネスでこれらの「得意分野」を活かしていたとしても、会社においては目標達成や売上・利益への貢献といった「成果」をもって評価されるのが常ですし、周囲に相対的に経験が長い先輩や知識量の多い同僚がいたりすると、特に若手は胸を張って「私は●●のプロです」と言える人は少ないかもしれません。
しかし、その「得意分野」に関する知識と経験は、それを持っていない社外の人からすると、十分に有益で有用なものです。特に地域・社会活動に取り組む団体や個人にとっては資金や人材が限られる中で、何よりも一緒に取り組んでくれる仲間を求めていますし、それぞれの領域に専門知識を有する人のサポートが得られることはとてもありがたいはずです。
試しに、ご近所や知り合いで、何か地域・社会活動を行っている人に、自分の「得意分野」で役に立てることが無いか、聞いてみてください。
その際、冒頭でも述べましたが、「地域・社会活動」を難しく考えたり、社会課題の解決に取り組むような高尚なものに限定する必要はありません。例えば、ご近所や町内会のお祭り、子供会の催し物、学校等の見守り活動、地域の少年スポーツチームのスタッフ、マンションの理事会などでも構いません。
これらの地域・社会活動に、プロとして自身がビジネスで培った「得意分野」を持ち込むとどうなるか。もちろん、その分野に対するニーズの有無や程度、タイミングなどにもよりますが、プロとして「得意分野」の力を発揮することで、何かしら貢献できている実感と喜びが得られると思います。
前述の通り、同じように「得意分野」の力をビジネスで発揮しても、すぐには事業上の成果が伴わなかったり、周囲との相対的な比較によって、必ずしも評価に直結するとは限りません。ですが、ひとたび会社の外に出て、地域・社会活動に自身の「得意分野」を活かすことで、“自分ならできる”という「自己効力感」(自信)を得られる機会は、実はいっぱいあるのです。
そして私の経験上、「自己効力感」は仕事に対して自信や成長意欲といった前向きな気持ちが芽生えるという好循環を生み出します。社外の活動で得られた「自己効力感」であっても、それがビジネス実務によって培った得意分野を通じて得られたものなのであれば、自身の業務に対する「自己効力感」へと繋がります。
まずは“自分本位”から始めよう
このように、地域・社会活動への参画が結果として、
地域・社会へのちょっとした貢献
会社では得難い「自己効力感」
自分の仕事への好循環
という3つをセットで生み出します。
それならば、行動を起こす最初の目的は「地域・社会への貢献」といった崇高なものや、「仕事への好循環」といった会社員として優等生的なものではなく、「自身の自己効力感のため」という「自分本位」なものでも良いのではないかと思うわけです。
このような会社員の地域・社会活動について調べていると出てくる言葉に、「プロボノ」というものがあります。
※「プロボノ」についての説明は、下記の朝日新聞さんの記事がわかりやすいので、ご参照ください。
https://www.asahi.com/sdgs/article/14928258
上記の記事の通り、プロボノ(pro bono)とは、
職業上のスキルや経験を生かして取り組む社会貢献活動のこと
です。
定義・解釈としては、ここまで私が書いてきたものととても近いのですが、私があえて「プロボノ活動をしよう」と言わないのは、「プロボノ」と言うとどうしても、参画する活動の社会貢献度や、所属する企業側のメリットや意義など、ハードルが上がってしまうなぁと感じているためです。
前述の通り、地域・社会への貢献や、自身の仕事への好循環は、結果としてセットで得られるものであると考えており、それよりも、「自身の自己効力感のため」という「自分本位」な理由で気軽に始めてもらった方が、活動への参加者のすそ野が広がり、結果、活動の総量としての「社会貢献」や「本業ビジネスへの経済効果」が生まれると考えています。
これが、私が本noteで書きたかったことの核心です。
このnoteを読んでいただいた方が、まずは自分自身のために「ちょっと活動してみようかな」と思っていただき、その結果、地域・社会の困り事が少し減ったり、仕事に対するモチベーションがほんの少しでも上がったりしてもらえたら幸いです。
おわり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
