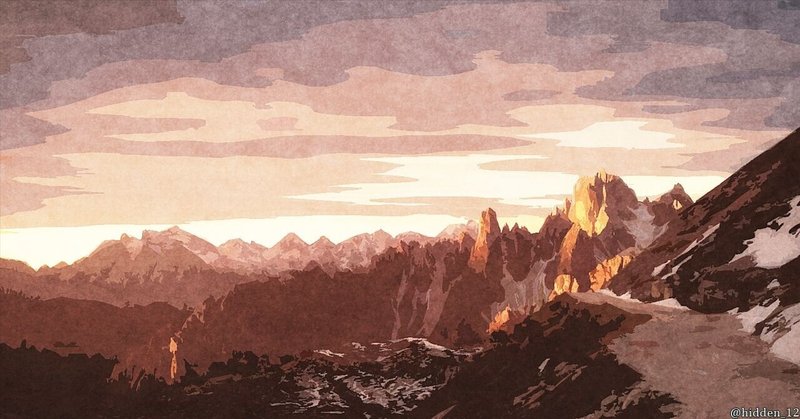
17:棒か縄か
4歳ごろ。
両親は、車で30分ほどの場所にある「寺」に足を運ぶようになった。
祖母も行くとすれば当然、幼い姉と私も行くことになる。
周囲は大人ばかりで、みなが同じ場所を見つめ、胸の前で手を合わせ、声を合わせている。
託児所とまではいかないものの、子供が好きに過ごして待つ部屋もあったようだが、そちらで過ごした覚えはない。
大抵は大人しい姉弟であったので、同席していても邪魔にはならなかったのだろう、とは思うのだが「場所をわきまえる」といった感覚は、このころに身につけたのかもしれない、とも思う。
「喜んでもらいたい」という根底にある気持ちが加わって、努めて行儀よくしていた部分もあると思う。
両親がこの寺に縁を設けたことにより、幼少期から、ある種の「縛り」があった。
実際に縄で縛られているわけではないが「かくあるべし」が、いつの間にか幼心に染みついていた。それはときに「道理」でもあり、ときに杓子定規による「横暴」と感じることもあった。
***
サルがヒトになる段階で最初に発明したのは「棒と縄」である、といった話がある。
「棒」は、いらないものを遠ざける攻撃のために。
「縄」は、いるものをそばに引き寄せ置いておくために。
どれだけ時代を進めても、この「棒と縄」にあてはめられる、という。
銃などは「棒」で、スマホなど他者と繋がるためのものは「縄」。
ならばインターネットは、縄を編んだ網といったところだろうか。
繋がりがオンラインになっても、ヒトはSNSやゲームで「棒」を持ち、攻撃/口撃を続けている。
幼少の心に染みついていた「かくあるべし」は、果たして「棒と縄」のどちらだったのか、と思う。
「正しく生きよ」という教えのもとにおいては、親から子に対する「縄」の意味合いが強いように感じる。親は子に、間違った道へと進んでほしくはないものだ。我が子を守るために、繋ぎとめておく。程度の差はあるにしても、その心にあるのは「縄」だろう。
しかし「◯◯でなければならない」といった具合に「正しさ」の強制へと転じた場合はどうだろうか。
よその教えを排斥する傾向がある集団であればあるほど「正解はひとつしかない」という価値観に陥りやすいと想像できる。
よそはすべて間違っており、自分たちだけが唯一正しい、という考え方である。
そのほうが統一しやすい、目的をひとつに団結させやすいからだという側面もあるだろう。浮気をされないように囲いこむための詭弁だったりもするのだろう。
私は宗教の専門家ではないので、唯一神教がとか、拝一神教や多神教がとかいうカテゴリーでああだこうだと論じることはできないのだが「自分たちだけが正しい」として、よそに矛先を向ける宗教にろくなものはないと思う。
世のあらゆる戦争は「自分たちだけが正しい」同士の衝突で行われてきたのではなかったか。信仰は自由だが、争いごとは嫌いだ。
しかしながら、このあらゆる情報が手に入るようになった現代社会でも、そういう宗教は多いようだ。
固執して周囲を見ない。「縄」のつもりが視野が狭くなり、いつの間にか、はみ出た者に「棒」を振りかざすことにはならないだろうか。
***
細かい話はさておき「正しく生きよ」と「◯◯でなければならない」は、微妙な違いのようで、言っていることは「棒と縄」のように違う、と思う。
『心を解放するのが「宗教」。心を縛るのが「カルト」』
いつだったか、宗教問題の専門家によって分類された画像を見た。
つまり「◯◯しなければ不幸が起きる」と詰め寄るのは、分類的にもきっぱり「カルト」ということである。
心の置き場を失って救いを求めている人を、さらに追い詰めるやり方である。
「◯◯でなければならない」には「棒」を突きつけられているような高圧的な印象を受ける。そして「◯◯」でなければ、そこに「怒り」が生まれるのだ。
強制することが、人の心を救うことはない、と私は思う。
世界や世間を騒がせている宗教問題は、少し見聞きしただけでも根深いものが多い。
私がこの世を去るときにも、なにひとつとして解決していないだろう。
それでも世のなかは先へ進んでいくしかないので、未解決のまま混沌としたものを、混沌としたものだとして受け入れるしかないのだ。
と、今回はべつにこんな話をしたいわけではなかった。
なんだっけ。
***
そうそう、記憶の話である。
両親が足を運ぶようになった寺では、近場だけでなく、遠方へ出向く機会もあった。
幼少の私が飛行機やフェリーなどで他県へ行ったのは、そういう機会がしばしばあったからである。
母に確認したところ、初回は寝台車だったらしい。意外なチョイス。
新幹線やバスなど、そのときどきで移動手段はさまざまだった。
お座敷列車などというレアなものも。
それぞれに、思い出もある。
新幹線でゲームボーイをしながら「アンバサ」を飲んで、盛大にくしゃみをして画面にぶちまけたあの人は、元気にしているだろうか。
そういえばアンバサって見かけないけどまだあるのかな、と思って調べたら、いまも販売されているようだ。(コカコーラ/乳性炭酸飲料)
これまでの記事にも何度か書いているが、私は筋金入りの出不精なので、家を出る前から「早く帰りたい」モードだった。
家族が一緒だといっても、そんなことは関係なく、遠出をしている間中、まったく心が落ち着かないのである。人も多い。聞きたくもない話し声も、方々から耳に飛びこんでくる。
記憶に刻まれる情報が多すぎる、と感じるのかもしれない。
それに加えて乗り物酔いもあったので、なかなかに苦難の旅路であった。
道中の思い出もいろいろだ。
***
とりわけフェリーは印象深い場面が多い。
非日常感が強かったからだろうか。
船に渡るためのタラップの隙間から見える、船と岸の間の海。高所恐怖症というわけではないが、なにか足もとがふわりと浮くような感覚。
乗りこんだときの、潮と機械用の油が混ざったような独特なニオイと低い駆動音。
滑り止めが施されているのか、と感じるくらいの床のベタつきを靴底で感じながら、いささか急な階段をのぼり、ロビーのような場所に出る。床はオレンジ色~茶色の暖色系。
そのロビーには食堂があり、隣接する小さな売店ではキーホルダーや、なかにイルカを閉じこめたスノードームなどの船や海っぽい土産物、旅先で遊ぶためのトランプやパズル的なゲームなども置かれていた。
少し狭い場所に自動販売機が並び、記念メダルの販売機などもあった。
記念メダルは金色で、チェーンも売られていたように記憶している。金色のメダルやチェーンには、少年心がくすぐられたものだ。なんの記念だったのかは知らない。
ロビーにはゲームセンターに置かれているようなアーケードゲームもいくつかあった。麻雀やテトリス、ぷよぷよなど。
ゲームセンターで遊んだことのない私は、特にテトリスをやってみたかったが「遊びに来たのではない」と、一蹴されていた。
船が動き出す。
小学生くらいのころには、重い扉を開いて、姉と一緒に甲板へ出たこともあった。
ベタついた甲板の床は深緑でプールサイドのように水溜りができている箇所もあった。白く塗装された柱や手すりはどこもかしこも潮でベタついている。
甲板から、船の後方へと流れては消えていく白波を眼で追う。
なにかふと、もの哀しくなる。そんな子供だった。
夜になって、父親が食堂へ行く。
家で夕食を食べる時間よりもずっと遅い時間だったと思う。
店じまいで明かりを落とした、薄暗い売店の横へ向かう。
ひと際まばゆく輝いて見える自動販売機で父が買ったのは、カップヌードル。小腹が空いたのだ。
食堂の隅の席で、父から少し分けてもらって食べたオーソドックスなカップヌードルは、やけに美味しく感じられた。
割り箸ではなく、プラスチックのフォークというのも、特別感を演出していた気がする。
フェリーでは、雑魚寝の大部屋だったことも、二段ベッドの部屋だったこともある。
雑魚寝の大部屋では、低い段差のところで靴を脱いであがるのだが、段差の縁がステンレスで補強されており、靴の爪先をそこにぶつけて大きな音をさせる人がいて、音をさせる人が現れるたびに私はちょっとイラッとしていた。やはり当時から音に敏感だったのだろう。
薄く毛羽立った硬めの毛布と、合皮のこげ茶色カバーで覆われた四角い枕。横には丸い金具があって、穴が開いており、枕に頭を置くとそこから空気が抜けるようになっている。
暗めの青いカーペットも、毛足が短く縮れたような感じで、昭和の民家のような感じだった。いや、使い古したキッチンマットかな。
一泊したフェリーの翌朝は、揺れに馴染んだのか馴染んでいないのか、中途半端で気持ち悪い。
テトリスの台を横眼で見ながらトイレに行く。強烈なミントのニオイ。
早朝から、知らないオジサンが歯磨きをしている光景を見るというのも、なかなか珍しい経験だった。
セルフサービスの朝食。
プラスチックのトレーを持って、一品ずつ取って席に着く。
白ごはんに味噌汁、焼き鮭に個包装の海苔。和食の見本のようなセット。
最後にフェリーに乗ってからかなりの歳月が経つが、いまでも変わらずあるサービスなのだろうか。
***
目的地に着いてからは特に、あまりいい思い出がない。
苦手なことばかりである。
一度寝てから中途半端に深夜に起きなければならず、畳に布団を敷いて大勢で寝るのも息が詰まった。誰かがトイレなどで廊下に出るたびに眼が覚める。
慣れない手触りの布団や枕なども「知らない人が使ったもの感」が強くて苦手だった。
当時は分煙などはされておらず、煙草を喫うオジサンも多かった。
裸足でスリッパを履かなければならないトイレも、できれば行きたくなかった。誰が座ったかわからない便座も避けたくて、大は行かなかった。ずっと緊張状態で、途中でもよおしもしなかったのだ。
トイレ前の廊下には給湯器のコーナーがあり、お茶も飲めるようになっていた。だが、幼少の舌にはちょっと渋すぎた。
朝食は配られた弁当。
父はわさび漬けが好きで、弁当に入っていると喜んだ。知り合いに苦手な人がいると、もらったりもしていた。
そういえば、バスなどで弁当と一緒に配られた、プラスチックの容器に入ったお茶は、いまでもあるのだろうか。
お茶パックが入っている、蓋付きの半透明の容器である。
子供のころはあまりお茶が好きではなかったので、なぜ弁当にこういうお茶をつけるのだろう、と思っていた。
幕の内弁当のご飯が、なぜ俵型を寄せ集めたようなカタチに型をつけられていて、なぜ梅干しと黒胡麻なんだろう、などとおかしなところに注目していた。おかしな子供だ。
***
旅先で土産店を覗いたのは、少し楽しい記憶だ。
幼い私は「忍者」が好きだったらしく、なにかの戦隊モノの人形を買ってもらったことがある。外見は覚えているが、名前に覚えがない。
「テレビ番組」をまったく把握していなかった私は、タイトルを意識せずに1~2話だけ観たのだろう。
調べてみたら『世界忍者戦ジライヤ』という作品だったらしい。
当時の私が、刀や忍者を好きになったルーツ的番組なのかもしれない。
タイトルを把握していなかったことは自分でも驚きだ。
ほかにも当時、記念に買ってもらったキーホルダーが、いまでもいくつか残っている。
すぐに壊れてしまって処分したが、黒い小さなリモコンのようなもので、カラフルなボタンが並んでいるものがあった。それぞれのボタンに効果音が対応していて、押すと「ちゅどーん」といったような音が出る。ボタン電池2個を入れて使うやつだった。懐かしい。
1~15までの数字をスライドさせて縦か横に並べるパズルも、一時期熱心にやっていた。私はこれが得意で、バラバラになった状態から50秒以内に完成させていた。披露する機会もなく、なんの役にも立たない特技である。
そして、どういうわけか少年は日本刀のキーホルダーに惹かれがちだ。
箸くらいのサイズだが、鞘から抜き差しできて、しっかり縄でさげられるようにもなっていた。
確か「ちょっといいお値段」で買ってはもらえなかったが、記憶にはしっかり残った。
船を降りても身体が揺れて感じることを「陸酔い」と呼ぶが、あのころに見た光景が、ずっと陸酔いのように残っている。手に入らなかったことも、いまではいい思い出だ。
なにかと闘うわけでもないのに、日本刀や忍者に惹かれる。
刀は「棒」なのに「縄」で繋ぎとめておきたいとは、これいかに。
少年の眼には「棒と縄」どちらに見えていたのだろう。




▼この記事のシリーズはこちらから。
いつもありがとうございます! ひとつひとつのリアクションに元気を貰っています。 寄せられたサポートは、頭痛対策のバファリンや本の購入に使用され、それらは記事の品質向上に劇的な効果をもたらしています。 また、小説の文庫本作りや、新しいことに挑戦する際に活かされています。
