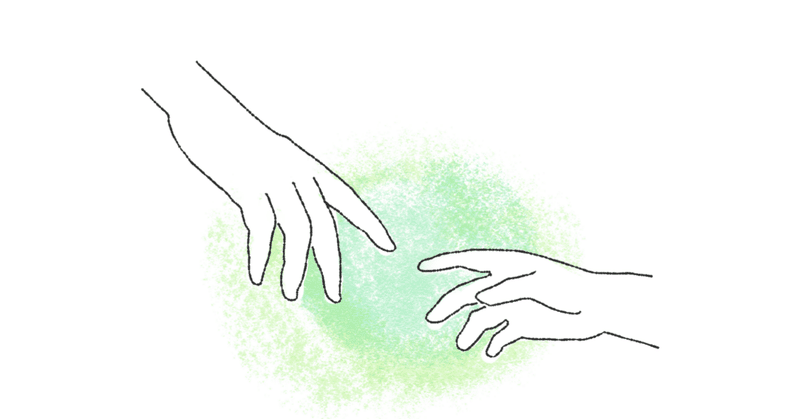
〈毒親〉の呪いから解放されたら
〈毒親〉とは、支配したり傷つけたりネグレクトしたりして、子どもが大人になってからも負の影響を与え続ける親のことを言う。私もまあまあな毒親に育てられた。それを聞いたら、きっと母は「どこか毒親だ、私なんてもっとひどい育てられ方をした!」と怒ると思う。ここに毒親の呪いの全てが詰まっている。
毒親は〈自分基準〉で考え、子どもを「分かろうとしない」。毒親に育てられた子どもは〈親基準〉で親を「分かろう」と顔色をうかがい疲弊する。子どもが辛いとき「私の方が辛い」と言ってしまう、子どもに寄り添わない態度が毒親の最大の特徴だ。逆に子どもは「こんなこと言ったらお母さんは怒るかな?」「お母さんはどうしたら喜んでくれるかな?」「お母さんはどう思うかな?」と、頭の片隅に親を住まわせ、親の気持ち抜きに物事を考えられなくなる。物理的な距離をおいてもなお心的な支配下を逃れることができなくなるのだ。
小さい頃は「お母さんの言うことは絶対」であっても、高校生くらいになると「お母さんはおかしい。私を分かってくれない」と幻滅することも少なくない。しかし簡単に〈幻滅さえもさせてくれない〉のが呪いの根深さでもある。これまで分かってくれなかったのに、分かってくれなかったからこそ「もしかしたら今度こそお母さんは分かってくれるかも」という一縷の望みが捨てきれず、苦しい時に親を求めてしまう。そうしてまた親から裏切られてしまうのだ。
〈毒親に育てられたこと〉を自覚し、〈お母さん〉という判断基準を捨て去ろうとする時も〈無自覚に〉罠にはまっていく。なぜなら親に支配されてきた人間には「私はこう思う」「こうしたい」という自分の基準が育っていないからだ。「これは一般的におかしい」とか「常識的にはこうすべき」といった〈一般論〉とか〈正義感〉が、〈お母さん〉に代わる〈自分の軸〉になってしまうからだ。正義感倫理観に依存して、腹を立てたり他人と衝突したりする。生きていくなかで常識は大切だが、それを分かった上で「自分は何を選択するか」のほうがもっと大切なのである。動かしようのない一般論を〈私〉と取り違えたままでいると柔軟な考えができないので精神を病みやすい。
「毒親の呪いを解く」というと、解放されれば解決のようなニュアンスだが、呪いは解いたあとが大変で、「私はどうしたいのか」という判断基準を探していく必要がある。まともな親に育てられていたら、子どもの頃から少しずつ積み上げてこられた〈私〉を、大人になってから〈再構築〉しなければならないのだ。「お母さんのせいでこうなった」と恨むのなら、それはまだ呪いの延長線上にいることになる。私は「何が好きで」「何を思って」「何がしたいのか」を見つめる時間をたっぷりとって、私を可愛がるところから始めてほしい。
最後に〈毒親育ち〉の人が陥っているかもしれない〈愛着障害〉について話しておく。愛着障害とは、虐待などが原因で、親子の間で愛着が形成されず、情緒面や対人関係に問題が現れてしまうことをいう。私がみてきた愛着障害の子どもは、いつもどこかソワソワしていて、失敗をおそれていて、衝動的な行動をとりやすく、大人を「敵か味方か」で判断していたように思う。多くの子が〈発達障害〉らしさをもっていた。多動や不注意のせいで育てにくかったのか、きちんと愛着が形成されなかったせいで多動になってしまったのか、判別が難しいところではあるが、〈毒親〉に育てられた人が「多動や不注意といった発達障害と類似した生きづらさを感じやすい」というのも周知されるべき事実だろう。
私の「毒親エピソード」を話す文字数が足りなくなってしまった。失敗すると叩かれたりライターの火で脅されたり裸足のまま外に締め出されるなど色々大変だった。でも、やはり母が「自分が一番辛い」と主張することや、「自分が一番愛されている」状態じゃないとダメな未熟な精神だったことがまずかった。私のことをブスだのデブだのダサいだの言いすぎたのが良くなかった。子どもの前で性の話題を持ちだしすぎるのも虐待の一種だったと思う。だからといって、母に愛がないわけではなく、「私には合わない育て方をされた」(合う人が存在するのかは疑問)という認識のもと、母とはそれなりに距離をとりながら〈今現在は〉仲良くやっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
