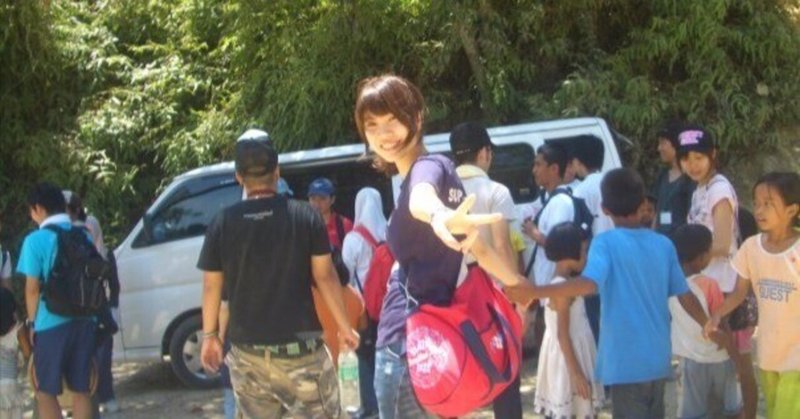
大丈夫、全てはちゃんと繋がってる
初めまして
8月1日付で入社しました、久保絵里香と申します!
(とか言って入社前日にコロナ陽性判定を受け、熱にやられて入社早々3日間欠勤し、メンバーの皆さんにお会いできたのは8月11日という出鼻くじかれまくりスタートだったのですが……とほほ)
リテール部門でもっともっと多くの人に異彩を届けるため、店舗運営の仕組みづくりなどを担当することになりました。
売り場に立つ機会も多いので、ぜひお店でお会いできたらうれしいです!
私は、実は精神保健福祉士という資格を持っています。
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく名称独占の資格であり、精神保健福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいいます。
とはいえ福祉系の大学を出ているわけでも、前職で福祉のお仕事をしていたわけでもありません。へラルボニーメンバーの多くの方のように、身近に障害のある方がいたというわけでもありません。
そんな私がなぜこの資格を取るに至ったのか、なぜへラルボニーに入社することになったのか、そして“くぼえり”ってどんなやつなのか、ご紹介させていただければと思います。
ちょっと長くなりますので、お時間のあるときに気軽に読んでいただけると嬉しいです!
生い立ち
私は千葉県市川市という微妙に知名度のない街で生まれ育ちました。
ディズニーランドの浦安市と、ふなっしーの船橋市の隣です。
働き者の父と、働き者の母の間に長女として生まれ、7歳年下の妹がいます。
私の人格を形成する上で影響のあったのは、この7歳下の妹と、アメリカ人の従姉妹たちです。

従姉妹たちはアメリカ人の父と日本人の母(母の姉、私の叔母です)の間に生まれており、生まれも育ちもアメリカという、いわゆるハーフです。
日本語は話せますが敬語は苦手。お父さんや姉妹同士では英語で話し、お母さんや私たちと話すときは日本語を話すバイリンガルです。
小学生の頃までは、毎年夏休みになると日本に遊びに来て短い期間でしたが私と一緒の小学校で体験授業を受けたりしていました。
見た目も話し方も、若干他のクラスメイトと異なる彼女たちは学校中の注目の的で、一緒に通う私はなんとなく誇らしい気持ちになったのを覚えています。
彼女たちのおかげで、“違う”ということは“カッコいい”という価値観が形成されたように思います。
もうひとりの重要メンバーは7歳下の妹です。彼女が生まれたことによって、私は“お姉ちゃんである自分”という人格が形成されました。
私が小学校に入学してから妹がバブバブ爆誕したので、母は妹にかかりきりになり、私は早々に身の回りのことをほぼ全部自分でできるようになりました。
(私は小学校1年生から自分の上履きを自分で洗っていましたが、妹は「とと洗って!」と父になんでもやらせる要領の良いプリンセスに育ったので、若き日の私は妹を甘やかす父と自由奔放な妹にブチギレていました笑)
高校生になる頃には、自分のお弁当は当然自分で作りますし、なんならみんなの夜ごはんも私が作りますよ?的な貢献ドリブンな人間に成長しました。
なぜか勉強が好きだったことも相まって、両親の手を煩わせない“しっかりもののお姉ちゃん”が出来上がりました。
しっかりもののお姉ちゃん、国際協力に目覚める
そんな私がはっきり将来のビジョンを意識したのは高校1年生の時。
たまたま家庭科の授業で見せられた児童労働に関するビデオを見て衝撃を受け、同じ人間でも生まれた環境でこんなに人生が違ってしまうのか、と憤りを覚えました。
そこから、教育を通じて社会を変えたいと考えるようになり、大学では教育社会学を専攻します。
大学では海外ボランティアサークルに所属し、マレーシアに住む無国籍のフィリピン人移民を支援する活動をおこなったり、国際協力系NPO法人で10ヶ月間の長期インターンを経験するなどの活動をしていました。

意識高い系お姉ちゃんと発達障害の出会い
そんななか、単位取得のためにたまたまとった“発達障害児者教育”の授業が私の運命を変えます。
その先生は授業のなかで、発達障害のある人への教育というより、そもそも「発達障害とは何なのか」を説明することに時間を割きました。
講義を通して私は、発達障害や知的障害という障害は、健常発達の人と感覚野の発達が異なることに起因する世界の捉え方の違いがマジョリティの世界と何らかの不適合を起こしてしまっている事象で、“障害”とはマジョリティ側が便宜上ラベリングしたに過ぎないのだと学びました。
何だかちょっと硬い言い方をしてしまいましたが、要はみんなそれぞれ別の目や耳を持ってるんだから当然感じ方は異なるよ、その感じ方が世間一般の“普通”と違う人たちを、不便だから“障害”という枠組みでくくるよ、というイメージです。
うーん、、障害って何なんだ?という気持ちが膨らんでいきます……。
発達障害の特徴として、特定のこだわりを持ったり、常同運動と呼ばれる特徴的な動きを繰り返すなどが挙げられることがありますが、これは「見えすぎる・聞こえすぎる・肌や鼻が刺激に敏感すぎる」といった違いから生まれるのだと、授業を通して学びました。
正直授業でこの話を聞くまでは、ブツブツ何かを唱えながら歩いていたり、電車の中でワーワー言いながら耳を塞いでいる人を見かけたとき、怖いな、近づかないでおこう、と思っていました。
でも今は、あの時出会った人たちは、それぞれの感じる世界と折り合いをつけるために自分で編み出した工夫をしながら生きていたんだな、ということがわかります。
人はみんなそれぞれ見え方、聞こえ方、感じ方が異なる世界があって、それぞれが自分の心地よいリズムを保つために工夫しながら生きている。
でも考えたらそれって誰にとっても当たり前のことですよね?
当事者からしたらこれが“普通”の世界なのに、マジョリティの常識が当てはまらないからって“障害”とラベリングするのってどうなのよ?
と強烈な違和感を覚えました。
そこから発達障害が“障害”として診断されるようになった歴史とその背景をゼミの研究テーマとして扱うようになります。
みんなが自分らしく生きられる世界、世間一般の"普通"と自分を比べて劣等感を覚えたり、人を見下したり憐れんだりせずに済む世界、誰もがあるがままの自分で「生まれてきてよかった!!」と思える世界を作りたいと思うようになりました。
そんなこんなで就職活動
そして就職活動の時期を迎えます。
サークルやNPO法人でのインターン、そしてゼミでの研究を通じ、人がありのままで“しあわせ”だと(主観的に)感じられるためには、周囲の人との対等であたたかな関係性が何より大事だとなのではないかと感じるようになりました。
自分は愛されている、自分のことを大切に思ってくれる人がいる、という感覚はどんな状況下においても生きる力を与えてくれるはずです。
そこで私が就職活動の軸に据えたのが“思い出”というキーワード。
「あの時楽しかったね!」「次の機会が楽しみだね!」と語ることが生きる活力となるような、家族や友人、大切な人と楽しい思い出を作れる場所や機会を提供できる仕事を軸に就職活動を行いました。
結果私が辿り着いたのは……みんな大好き夢の国!!

レストランでのある経験
さあやっと精神保健福祉士の話がでてきます!!(前段の自分語りが長い長い……)
入社後私はレストラン運営を行う部署に配属されました。
多くの"キャスト"の皆さんと、"ゲスト"の皆様に快適で楽しいお食事体験を提供するお仕事です。
たくさんのキャストのなかで、あるときひとりのメンバーがリーダーにこんな相談をしている声が聞こえました。
「わたしは発達障害かもしれない。やろうとしていたことを急に忘れてしまったりするんです。みんなと同じようにうまくできないんです……」
その方から詳しく話を聞くと、同時にいろいろなことをこなさなくてはいけないポジションの時、パニックになってしまうことに悩んでいるとのことでした。
私は医師ではないので障害の診断はできないし、この話だけでは発達障害とは判断できないと思いつつも、その方が困っていて、不安を抱えていることはわかりました。
そこで、「体調に不安があったら相談してくださいね、ポジションの配慮は検討しますからね」とお伝えして、このことを社員間で共有しました。
ちょっと間をはしょりますが、結論、これがあまりうまくいきませんでした。
その時の私にはどうすることもできず、悔しく、申し訳なく、情けない思いを抱えたまま、異動のタイミングがやってきて、そのお店から離れることになりました。
戦うための武器を身につけたい
異動先は顧客満足度向上をミッションとする部署。
海外からお越しのお客様や、障害のある方など、マイノリティとなるお客様に向けた施策も統括していました。
これはチャンス!!
異動直後の面談で、上司にその時抱えていたモヤモヤを吐きだしつくしました。
こういった障害のことをしっかり理解する人間が内部にいることは、組織として大事なことだと思う。
改めて専門的な勉強をしなおして、研修などを通じて社内に広めていく活動をしたい。
自信を持って語れるようになりたい、自分の話を聞いてもらえるだけの力がほしい。
「私は精神保健福祉士の資格を取りたいです」
精神保健福祉士の資格を得るためには座学、試験の他に実習が必須です。
精神科病院や診療所などの医療分野で12日間、生活介護や就労継続支援を行う施設、地域活動支援センターなどの地域分野で16日間の計28日間の実習のため、職場を離れる必要があります。
そのため、働きながら資格を取得する人の多くは元々障害のある方の支援を行う機関や、クリニックに勤務している方がほとんどです。
業務上必須の資格ではないため、有給休暇を使って実習に行く相談をしました。
当時の上司は快く承諾してくれました。
そして私は約2年間、通信制の専門学校で学び、2回の実習と試験を経て、晴れて精神保健福祉士の資格を取得しました。
さてこれから武器を片手におらおらと研修やら制度やらに手を入れていくぞ!!と思った、そんな矢先…。
そしてコロナがやってきた
私が資格を取得したのは、2020年3月です。
4月に初めての緊急事態宣言が発令され、世の中は自粛モードまっさかり。
私の職場も閉鎖となりました。
色々はしょりますが(すぐはしょる!)、まあとにかく大変で、せっかく取った資格を活かそうにも本当にそれどころじゃない状態におちいりました。
そうこうしている間に1年が経ち、世の中の状況は改善されず、まだまだ職場も通常運転にはほど遠く、どうしたもんかなあとこの先の自分の人生について考える時間も増えました。
異なるフィールドへ
ここでやりたいことはある、そのために勉強して資格もとった、でもやりたいことはいつになったらできるかわからない……。
そんな状況で私は翌年30歳になる年で、年齢的なボーダーも意識するようになってきました。
もやもやしつつも、これができたらこの会社で頑張ろう!と思っていたことがありました。
でもそれが叶わなかった。
私は転職を決めました。
そこで私はヘラルボニーと運命的な出会いを果たし……たわけではありませんでした。
ものすごく異なるフィールドへ
転職先は人材業界の営業職。
今までとは全く異なるフィールドでした。
きつかった。覚悟はしていましたが、きつかった。
思っていたきつさの100倍、1,000倍、いや10,000倍きつかった……。
未経験業種、未経験職種。
未熟な自分が大切なお客様の期待を裏切るわけにはいかない。
「あれを聞かれたらどうしよう」「これもわかってないと不安だし」と自分に課すタスクはどんどん増えていき、やってもやっても終わらない仕事が四六時中浮かんで食べ物が喉を通らなくなりました。
明日が来るのが怖くて、眠れなくなりました。
その割に、いざ机に向かうと、何から手をつけていいかわからなくなって涙が出てくる。
新しい仕事に適応しようと必死で食らいついていた私の中で、”精神保健福祉士”の私がささやきました。
いや……これ……あかんやつやん………。
「転職したらどこに行ったって半年くらいは辛いもの」
「大丈夫、新人にお客様だってそんな期待してないよ、もっと気楽にやればいいじゃない。」
色々な方からいろいろなお声がけをいただきましたが、自分の元来の真面目さと心配性が災いして、手を抜くことができず、体力的・精神的に削られていき、辞めるしかないという気持ちが大きくなっていきます。
”たった数ヶ月でこんなことになってしまって、根性なしやんけ。”
”啖呵切って大企業飛び出してきたのに情けな……”
なのに、もうここには居られない、という結論にかたむくと、自分のなかのよくわからんおっちゃん(誰やねん)が呆れ顔で責め立ててくる。
完全に、自分で自分の思考や感情をコントロールできなくなっていました。
ああ、もう、これはあかんやつや……。
緊急避難的にお休みをいただきました。
(ああなるほど、こうやって人は突然病気になってしまうんだな、と客観的に自分を観察している自分もいました)
何事もそつなくこなせてきた。“しっかりもののお姉ちゃん”の自分がまさかこんなことになるなんて。
一大決心で転職したのになぜこんなことに……。
お休みの間もぐるぐると自分を責めるばかりで打開策が見いだせず、「何も考えず楽しめそうなものを摂取せねば!」とネットフリックスでのだめカンタービレをずっと見てました。笑
そしてあるべきフィールドへ
お休みをいただいたのち、前職を退職することにしました。
本当に短い期間での退職となり、前職で関わった皆様には心から申し訳ない気持ちでいっぱいです。
短い期間ではありましたが、本当にお世話になりました。
申し訳ございませんでした。
ちなみにこの時点ではまだへラルボニーにジョインすることは決まっておらず、「しばらく専業主婦やるか〜」という覚悟でおりました。
しかしほんの少しの間お休みしただけでも、私は仕事をしてないとダメな人間だな〜というのは感じていました。
私は何に私の人生をかけたいと思えるのかな。
どんな働き方であれば私はいきいきと仕事を続けていけるのかな。
私はどんな思いを持った人と仕事をしていきたいのかな。
そして辿り着いたのが、一番最初に仕事を選ぶうえで考えたこと。
みんなが自分らしく生きられる世界、世間一般の“普通”と自分を比べて劣等感を覚えたり、人を見下したり憐れんだりせずに済む世界、誰もがあるがままの自分で"生まれてきてよかった!!"と思える世界を作りたい。
いくつかの企業や団体のことを調べるうちに、岸田奈美さんのツイッターやnoteを通じて知っていた“へラルボニー”という企業を思い出しました。

へラルボニー Mission
“普通”じゃない、ということ。
それは同時に、可能性だと思う。
この言葉にアドレナリンが身体中を駆け巡りました。
うっわー!!そうだよね!!!私と同じことを思ってる人がいた!
しかも株式会社として、ビジネスとして戦おうとしている!
支援ではなく対等に、“違う”ことの価値をリスペクトを持って世に発信しようとしている!
ここで働きたい。
ただただその衝動で、カジュアル面談を申し込みました。
この時はまだ自分がどんなポジションでどんな貢献をできるかの具体的なイメージはないままでした。
カジュアル面談で担当の大田さんとお話ししてみると、
私が一社目で培ってきた店舗運営の経験や多くの人が気持ちよく働くための仕組みづくりの経験にものすごく食いつきが良く(!)
私が大学での学びを通して感じてきた“障害観”をベラベラ喋り倒して意気投合し(!!)
大田さんの推し作家である岡部さんの紹介を受けて、私が初めてアール・ブリュットの魅力に衝撃を受け(!!!)
おや、もしかしてこれは私へラルボニーと出会えたのって運命じゃね?
と感じるようになりました(なんっておこがましい…!!)
その後、面接までの間にnoteを隅から隅まで読みつくし、働く皆さんの魅力を通してへラルボニーに惹かれ、面接で代表お二人から伺った今後の事業の目指す姿に惹かれ、面接の結果を待つ間にどんどん愛が高まっていきます。
内定通知をいただいた時は、にっこにこのガッツポーズで夫に報告です。
「いや〜なんか、ここにたどり着くためにこれまでの人生があった気がするよ」
最後に
入社後1ヶ月が経ち、これまでの人生は全てここにたどり着くためだったという気持ちは確信に変わってきています。
生い立ち、大学での学び、1社目、2社目での経験、周囲の人たちの支え、どれが欠けていても今私はここにいないと思います。
特に夫には本当に心配をかけてしまいました。
ずっと側で支えて応援してくれて、あなたがいなかったらどうなってたことか。ほんとにありがとね。
もっともっと多くの人に“異彩”を届け、障害の概念を変える。
一人でも多くの人が、違うって面白いよね、と思ってもらえるように、一人でも多くの人に素敵なプロダクトを届ける。
それが今の私が人生をかけてやりたいことです。
素敵なアートを素敵なプロダクトに落とし込むプロフェッショナルたちと、本気で作り込んだ商品たちです。
これを読んでくださった皆様に直接お届けできる日を楽しみにしています。
ぜひお店でお会いしましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
