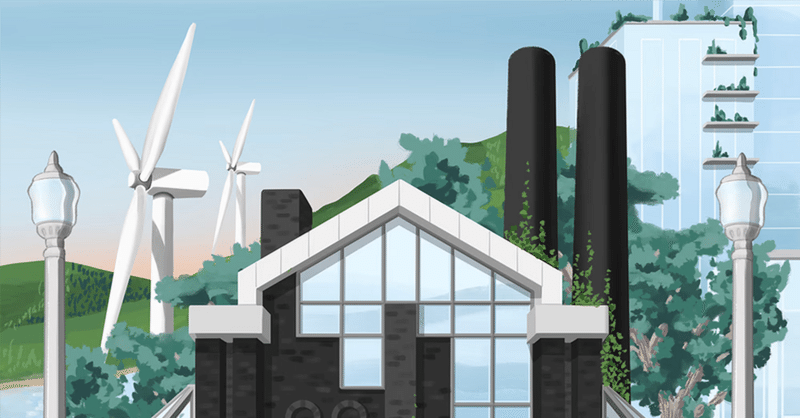
家計収支のあれこれ
こんにちは。返済レスキューです。
ご相談内容に多い、家計収支に関する記事を書いていこうと思います。
家計収支の必要性
①家計状況の改善と可視化
破産手続きを依頼するまで、家計簿をつけたことがないという方は、とても多いです。そのため、家計状況を聞き取りしても、曖昧な金額しか分からず、とにかく次の給料日まで凌ぐことを家計のやりくりとしていることが多いです。
それもそのはずで、クレジットカードのリボ払いやキャッシングの返済は、いつの支出が含まれているか分からないので、単純に計算すると、何かしらが二重計上されてしまい、数字がほぼ間違いなく合わないです。
これをクレジットカードやローン等の支払いを停止し、新たな借入もできなくなり、現金生活を始めることで収支を単純にして、純然な1ヶ月の家計収支を作成、可視化することで家計の改善を容易にすることができます。
②債権者の調査
破産手続きではすべての債権者を例外なく裁判所に申告して、すべて平等に破産手続きの対象にする「債権者平等の原則」があります。
携帯キャリア決済、後払い決済、家賃や水光熱費の遅れなども債務に含まれるため、家計収支を提出してもらうことで新たな債務を発見することも目的の1つとなり、この調査を怠って申立てをすると、ライフラインに影響が出たり、スマホが使えなくなったり、破産管財人にお金を組み入れることになったりします。
③資産の調査
給与以外の入金があれば、請求権が存在する可能性があったり、支出には保険解約返戻金のように資産性があることがあります。これも申立後に破産管財人の調査によって発覚した場合、破産管財人にお金を組み入れることになったりします。
家計収支の期間
①作成する期間
事務所によりますが、依頼してから免責許可が出るまでが原則です。
裁判所に提出する家計収支は申立直前の2〜3ヶ月分ですが、いきなり家計収支を作成しても上記のような調査の結果、申立てを延期することにもなりかねないですし、申立代理人にも管理する役目があるので、逆に「直前だけでいいですよ」のパターンはあとから苦労するかもしれませんね。
②1ヶ月分は何日から何日までを記入するのか?
家計収支の質問では、何日から何日までを書けばいいの?といった質問を多くいただきます。
パターンとしては「給料日始め、給料日前日締め」、「1日始め、末締め」の2択かと思います。結論としては、どちらでも1ヶ月分が記載されていれば問題ありません。私のおすすめは「1日始め、末締め」ですね✨
▶ 給料始め、給料日前日締め
支給された給料をどのように使ったが、明確に分かる利点がありますね。
一方で明確になりすぎるのも困りもので、収支がギリギリまたは赤字の場合、一目瞭然で分かってしまいます。
▶ 1日始め、末締め
副業をしている、給与とは別に年金や児童手当などの収入がある場合には、こちらの方がいいかもしれませんね。
また、収支がギリギリまたは赤字の場合に誤魔化すことができるので、私はおすすめしています。私は依頼者さんから家計収支を受け取ったら、パッと以下の3つを確認します。
定期的な収入(給与や年金等)以外の収入がないか?
高い支出や気になる項目がないか?
繰越金がいくらあるのか?
この時に繰越金が少ないと、どこか支出が高いんじゃないか?収入に返送があったのかなど、他の項目を再確認します。おそらく、この行動は弁護士や管財人も同じで繰越金が少ないと他のところが気になってしいます。
例えば、給料日が25日の場合、末日時点の繰越金は給料日後なので潤っていることかと思います。また、10日が給料日でも前日よりはお金があるはずです。 このような点で私は、1日始め、末締めをおすすめしています。
家計収支の範囲
家計収支の目的として、「申立人ないし破産者のお金の流れが適正か?」を検討する資料になります。上記の債権者や資産の調査に関わる部分で細かいところですが、生活費の負担割合についても考えることになります。
例えば、夫婦ともに収入があり、健常者にも関わらず、申立人がほとんどの生活費を負担し、配偶者が生活費の負担をせずに貯金をしている場合、申立人から配偶者に対し、不当に破産者の財産が流出したとして、請求権が成り立つ場合があります。
このような場合は、適正でないことが明らかですが、夫婦で収入がと支出が混同している場合、その金額が適正であるかを判断することが申立人の収支だけでは判断できないため、同居人を含めた家計収支の提出が原則になっています。
①お一人暮らし(仕送りなし)
依頼者さん一人の収入と支出を記録するだけでOKです。
②夫婦または同棲中の2人暮らし
配偶者または同居人の収入と支出を含めて記録する必要があります。
③二世帯(夫婦&父母の同居)
夫婦と父母の間に金銭の受け渡しや食費・日用品等をシェアしている場合は配偶者及び父母の収入と支出を記録する必要があります。
一方で夫婦と父母の間に金銭の受け渡しや食費・日用品等をシェアがない完全に分離している場合は、②と同じでOKです。
a.同居の子供がいる場合
子供に収入がある場合は、子どもの収入と支出の状況も記録します。
学生のアルバイト程度であれば、不要と判断してくれる弁護士もいるので相談してみましょう。
b.仕送りをしている場合
仕送り相手の収支状況を報告する必要があります。理由としては、仕送りする必要があるのかを検討するためです。
◆家族に内緒の方は必見
もしかしたら、許される「家計分離型」を紹介します。
家族バレに協力的な弁護士であることが前提となりますが、ざっくりと説明すると、負担割合が適正かを考える検討材料が、より少ないほど、同居人の家計までは提出しなくて良いと考えやすいです。
➤検討材料が多い例
「家賃は配偶者が払い、水光熱費は私が払っている、食費や日用品は、二人でその都度払っていて、携帯と保険料は各々払っている。」
「お互い給与が入ったら、全部同じ口座に入れて管理している。」
検討材料が多い例の特徴として、負担している具体的な金額が分からないことがあります。金額が分からないと、まずその金額を算出しなくてはいけませんので、個人のお金を追うのにとても不便なため、全部ひっくるめた収支を出してほしいと考えると思います。
➤検討材料が少ない例
「私は同居人に5万円を渡して、残りは自由に使っている。家のことは同居人にはやりくりしてもらっている。」
「私が同居人から15万円をもらって、やりくりしている。」
検討材料が少ない例は、やはり、具体的な金額が出てくることです。上記の5万円や15万円の妥当性のみを考えればいいので、非常にシンプルに比較できます。
例えば、家賃が10万円の場合、5万円渡して同居人が水光熱費も負担してくれているなら、申立人が払い過ぎていることはないだろうと推測されます。
また、15万円受け取っている場合も、家賃の半分を差し引いて10万円が生活費に充てられる場合、生活費合計額が20万円以下であれば、同居人の負担が多いことが明らかです。
以上のように具体的な金額が分かり、申立人の負担が少ないことが分かる根拠があるととても良いです。
支出の目安
赤字にならないことを前提に支出の割合は、画像のように考えています。
裁判所としては、毎月ギリギリで生活することを望んでおらず、毎月多少の余裕をもって、不測の事態に備えられるようにしてほしい(いざとなった時に借金に頼らないでほしい)と考えているので、最低限この比率を超えてはいけないと考えてほしいです。ここまでなら使えるといったラインではないです。
なお、貯金や積立など、使えなくなるだけで自分の資産である場合は、支出には含めません。

◆支出の目安の考え方
趣味等のぜいたくの支出15%
節約できる支出35%
致命的な支出50%
注意点として、1の支出がオーバーしている場合は、2や3から補うといった考えはしません。この比率から、はみ出す部分が「収入に見合わない過大な支出」と考えるからです。つまり、食費や日用品の支出を削れば、趣味にお金を費やせるのではなく、削ることができた部分は、貯蓄にすると考えるのが望ましく、代理人弁護士に支払う報酬をこの削れた部分から支出し、破産手続終了後は余裕をもって生活ができるようになるといった考え方になります。
注意点
◆賞与について
よくある質問で賞与を毎月の収入に割り当てる考え方(1カ月あたり○○万円等)をすることがありますが、原則、この考え方はありません。
裁判所の考え方として、賞与は特別な支出であり、特別な支出に充てるべき収入と考えられているので、毎月の生活費に消費することは、収入に見合わない過大な支出ともとらえられるので、賞与は自由に使えないお金と考えましょう。
なお、特別な支出が想定されない場合は、手続費用に充てるのが一番無難な使用方法です。
◆退職金、保険の解約返戻金や契約者貸付について
賞与同様に特別な収入であるため、特別な事情が無ければ、使用することはできません。使用したい事情がある場合は、ご依頼中の弁護士に相談することをおすすめします。
◆支出の項目に迷ったとき
家計収支をつけていると、これってどの項目に当てはまるのか分からないことが、多々あると思います。そんなときは、「その他(〇〇代)」と書き足したり、欄外に内訳を書いておくと良いと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか?少し長文になりましたが、家計収支について思い当たるところを書いてみました。自己破産や個人再生では、特に依頼している弁護士に説明することが多いと思いますが、大切なことは、行動に根拠や一定の規則があることだと思います。
弁護士と一緒に働いていると「なぜ?」をよく気にしてきますが、その時に何の考えもなくやっているよりは「こう思ってこうしている」と答えられた方がスムーズに会話ができるイメージです(もちろん、依頼者さんに合わせろよって思いますが笑)。
もともとは7,000文字(公開時は約4,200文字)でしたが、ちょっと削ったりしているので、何かありましたら、いつでもSaimsやDMでご相談ください✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
