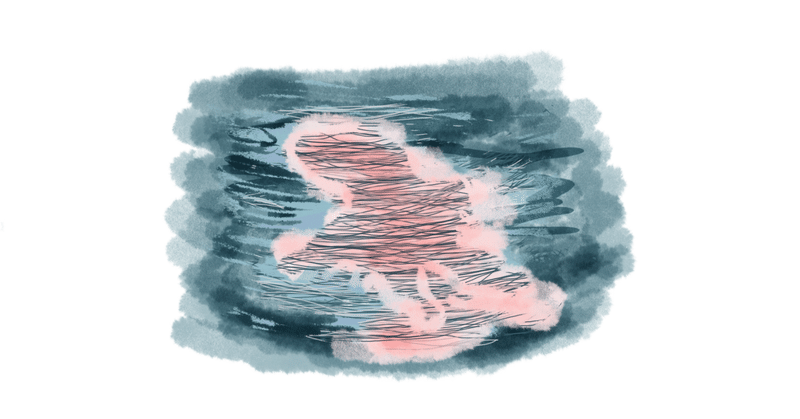
「第四間氷期」(安部公房)を読む
この本を読み、考えたことは次の四つだ。
・AI(人工知能)との関連性
・水棲哺乳類の魅力
・現在と断絶した未来
・自分は未来に対して保守主義者だろうか
AI(人工知能)との関連性
内容については何も知らずにこの物語を読み始めたのだが、登場する予言機械は、まさに今でいうAIのことを描いているように思えて驚いた。書かれたのは一九五九年だそうだ。冒頭、こんな言葉が登場する。「電子計算機とは、考える機械のことである。機械は考えることはできるが、しかし問題をつくりだすことはできない」。
この「考える機械」の使用目的が未来予測であることをまず意外に思った。例えばソ連で開発された予言機械モスクワ2号は、三十二年以内に最初の共産主義社会が実現する、という未来予測をする。私にはAIを人類社会という大規模の未来予測に使うイメージがなかったので新鮮味を感じた。
それは安部公房自身が人類の未来の姿に大いに関心を持っていたからだろうし、またその時代の関心事でもあったのだろう。未来予測は人類の夢であり、それが機械によって実現できるという期待や予感があったことを思わせる。
一方で、今は世の中が高度に複雑化したように見え、さらに機械の技術的な限界がある程度想像できるからか、機械による未来予測にはリアリティを感じにくいように思われる。少なくとも私はAIを人類史レベルでの未来予測に使うイメージはなかったため、意外だった。
この予言機械は、必ずしも未来予測だけに使用されるのではない。例えば物語中で死体の脳波等のデータを分析することで擬似的に死者を再生させ喋らせたりする。これはまさに今のAI技術の延長上に実現しそうな状況であり、作家の想像力に驚かされる。また、登場人物の次のような発言も、AIを巡って昨今よくいわれる話で、昔に書かれた小説とは信じ難い。
つまり、予言機械は、質問をうけなければ、答えることはできないわけでしょう。自分から質問を考えだすことは出来ないわけね。だから、予言機械を本当に使いこなすためには、むしろ質問者の能力が問題になってくる。
予言機械は、大量のデータを読み込ませることで複雑な問題に対応できる電子頭脳である。しかしいわゆる意識を持つわけではない。機械に意識が宿るか、といった哲学的な話は登場せずあくまで計算機として描かれてる点も現代的だ。
水棲哺乳類の魅力
後半、水棲哺乳類という怪しげなモチーフが登場し、物語は意外な方向に展開する。胎児を用いて人工的に生物進化を作り出す技術によって生み出された水棲豚や水棲牛、そして水棲人。読後、この作品を頭の中で思い浮かべる時に真っ先に出てくるのが、私の場合はこの水棲哺乳類のイメージである。生物進化の神秘性、科学の一側面としての自然改造技術の恐ろしさ、水という存在の美しさと曖昧性…、それらの要素が絡み合った独特の光景が脳内に広がる。
現在と断絶した未来
安部公房はあとがきで、この作品において未来というものを肯定的にも否定的にも表現しなかったといっている。「はたして現在に、未来の価値を判断する資格があるかどうか、すこぶる疑問だったからである」。
真の未来は、おそらく、その価値判断をこえた、断絶の向うに、「もの」のように現われるのだと思う。たとえば室町時代の人間が、とつぜん生きかえって今日を見た場合、彼は現代を地獄だと思うだろうか、極楽だと思うだろうか? どう思おうと、はっきりしていることは、彼にはもはやどんな判断の資格も欠けているということだ。この場合、判断し裁いているのは、彼ではなくて、むしろこの現在なのである。
物語の最後で描かれる、一人の水棲人の少年を中心とした未来のイメージは、だから理想的世界でもディストピアでもない。その世界がよいのか悪いのかを判断する我々はそこにもう存在しない。いるのは、私たちの現在知る意味での「心」を持たない水棲人である。
私たちとは異なる心的構造を持つ存在を中心に世界が描写されると、私たちはその解釈に戸惑う。人間の心を描く文学という地平の、果ての光景に私には思えた。
この未来のイメージは、作中では主人公の死の間際に予言機械によってなされる語りとして書かれている点に注目したい。この未来は、ある意味でAIによって作られた小説であるともいえるのだ。当然、実際にはAIではなく安部公房という人間が書いているわけだが、作者が成り代わる、断絶した未来の描き手として心を持たないAIというのは相応しい存在ではないか。AIは、価値判断を超えた、ある意味でそれ自体が断絶した存在なのだから。そう考えると断絶した未来の語り手がAIであることには必然性があるように感じられた。
飛躍するが、安部公房がいう真の未来とは、もしかしたらある種の芸術作品に当てはめて考えてみても成立するのではないだろうか。
ある種の芸術とは、断絶の向こうから現代の我々を裁くものである。
であるならば、芸術家とは断絶の向こうをを作り出すことができる人のことである。
そしてAIは、断絶の向こうを作り出し現代の我々を裁く、もう一つの存在になり得るのかもしれない。
AI技術が実現し日常に浸透しつつある今、私たちは現在進行形で、AIの作り出す「もの」に裁かれつつある。
そんなことを考えてみる。
自分は未来に対して保守主義者だろうか
主人公の勝見博士は、予言機械の開発者でありながらも、断絶した未来を受け入れることのできない保守主義者として描かれている。
「つまり先生は、やはりその未来には、耐えられなかった。結局先生は、未来というものを、日常の連続としてしか想像できなかったんだ。その限りでは、予言機に大きな期待をよせていらっしゃったとしても、断絶した未来……この現実を否定し、破壊してしまうかもしれないような、飛躍した未来には、やはりついて行くことが出来なかった。(略)」
この作品を読みながら、どことなく違和感がずっとあった。その理由を考えてみるに、それは私がこの物語の中心的なテーマである「未来」というものに、興味が薄いからではないかと思った。
私は勝見博士のように、未来に対して保守主義者であるということかもしれない。そう思って少しショックだった。
「でも、先生は、駄目でした……先生は、未来が現実を裏切るかもしれないという可能性は、まるで考えて見ようともなさらなかった。ということは……そうね、どう言ったらいいのかしら……つまり、予言機械は、質問をうけなければ、答えることはできないわけでしょう。自分から質問を考えだすことは出来ないわけね。だから、予言機械を本当に使いこなすためには、むしろ質問者の能力が問題になってくる。その点で、先生には質問者としての資格が、ぜんぜん欠けていたように思うんです」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
