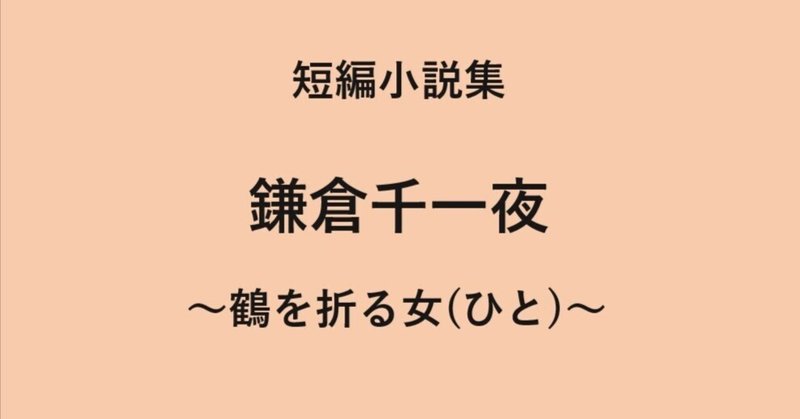
【短編小説集vol,12】鎌倉千一夜〜鶴を折る女(ひと)
第59夜 母娘托生
「 今年の花は大きい気がする」
母と鶴岡八幡宮まで朝の散歩をするのが日課になって何年になるだろう。朝5時に二の鳥居で落ち合って段葛をゆっくり歩いて八幡宮を目指す。源氏池の島にある旗上弁財天への太鼓橋上から蓮を眺めるのが母のお気に入りだ。かつては源氏池には白の、参道を挟んだ平家池には赤の蓮の花が咲いていたそうだ。何もそんな血生臭い演出をしなくてもいいのにと思うが、天下双璧の両者には和のゆとりなどなかったのだろう。
「ひなちゃん、この大きな花もお昼になると閉じてしまうのよね。何故かしら? そうやっていろんなものには閉じる時がやってくる」
「やめてよお母さん。お母さんはこうして毎日しっかり歩いてここに来ているじゃない」
「ううん。呼ばれているのよここに。ハンカチでも風呂敷でも広げ使い切った後は畳み仕舞うでしょ。そんな風に自身の意識も夢を広げてがむしゃらに動き回った後は、いろんなところに散らかした諸事を片付け、そして仕舞うの。そのタイミングは人それぞれよ。でも50はいい目安になるんじゃないかしら。人生は広げて畳むのよ」
「50って私はとっくに過ぎているわ。まだまだ広げてるわよ人生」
「何を言ってるの。元気な時に畳み始めないと、体が動かなくなったらみんなそのまま放りっぱなしになっちゃうわよ。ああ、あの人は突散らかしたまま逝っちゃったのねって思われるわ」
「それでもいいじゃない、生きてるうちに死に向かうなんて私できない」
「別にそれは死に向かうことじゃないわ。あなた寝る前にリビングもキッチンもきちんと片付けてからベッドに向かうでしょ。それと同じことよ。人生の場合何年もかけて広げたわけだから、片付けるにも時間がかかるの。50年なら少なくとも5年はかかるわ」
「5年! それじゃあ80なら8年、90なら9年ってこと? お母さん83よね?」
「そうよ、80になって片付け始めたわ」
「88で死ぬってこと?」
「米寿は立派な長寿よ」
「じゃあ私も80になったら始めるわ」
「それじゃあダメなの。片付けの準備を始めなくっちゃいけないの」
「えっ? 何よその準備って」
「本当に片付けようって思うその意識づくり。何故綺麗に片付けなきゃいけないと思う?」
「残された人に手間をかけさせないため?」
「違うわよ。人間って細胞が分化して出来上がったものでしょ、だからそこに戻るの。何もなかった状態にね。臨終には死装束だけになるの」
「また縁起でもない。それって終活みたいな考え方?」
「そんな言葉が言われる前から大体の老人は悟っていくわ。棺に個人の遺物を入れたりしてるけど、私の時は入れないでね。最初の細胞だったころにそんなもの持ってなかったじゃない。元に戻りたいのにお荷物になっちゃうわ」
「それは生きた証とも言えるんじゃないかしら? この世に生を受けた証」
「ひなちゃん、考えてみて。死んだお父さんがよく言ってたじゃない、地球なんて宇宙の中では砂浜の砂粒より小さな存在で、そこで生きている100年間にしても宇宙誕生からしたら瞬きの瞬間にも全然満たないって」
「そりゃあお父さんは物理学者だったんだからそうなるかもしれないけど、今この時って大事じゃないかしら?」
「そうとも言えるわ、でも必ずやってくる死に近づいたら先を見るの。先が長いのよ」
「死んだら終わりじゃないの?」
「だからねひなちゃん、細胞の前はなんだったと思う? なぜあなたは私の元から生まれたの?」
「そんなのわからない」
「私が願ったからよ。私の人生にあなたがやってきてくれたの。そして私の人生ずっとあなたは一緒にいてくれたわ。それが何よりうれしくて」
「お母さん、そんなの当り前じゃない」
「ひなちゃん、一蓮托生って言葉知ってる? いい行いをすれば極楽浄土で同じ蓮の花の上に生まれ変わる、というものなの。私は先に逝くけどずっと先もまた一緒に居ましょうね」
「また何を言ってるの! でも、そうやって先々までお母さんと一緒に居られる気がしてきたわ。ついでに言うと死への怖さも少しだけ減った気がする。」
「そうよ。いつ死が来たって怖くないから堂々と毎日を楽しめるの。それにお父さんのところにも行けるしね」
7時。白い蓮の花はまだもう少し開いているようだ。
第60夜 フィールドワークの幻光
翡翠、水晶、砂金…、日本には数多の宝が自然に放置されている。しかしそれらを取り合うことに血眼になる者はいない。理由は埋蔵量の乏しさだ。全ての時間を捧げてもそれで食べていけるほどの採掘量にはならないのだ。が、佐々木翠は違った。翠にとっては鉱物そのものではなく、それらが眠る大地が魅力的だったのだ。鉱物が掘り出される前の、鉱物が地表や川にあるその姿が最高なのだ。ときにはその場所は山奥だったり海岸だったりする。そして何日かけたらその姿に出会えるかは全く不明だ。翠は初めは中古車に寝泊まりしていたが、いつしか夏の暑さにうんざりし(窓を開けると蚊やアブにうんざりする)、テントを張るようになりかなり快適になった。が、女子のひとりテント泊というのも心配で不眠気味になり、決断した。キャンピングカーだ。20年落ちの中古だが、つてで安くリストアしてもらったらかなり快適になった。クーラーだけは新品にしたので、もはやホテル並みだ。それでも翠はなるべくキャンプ場、それがなければ人里近いところに野営地をとった。長ければ2週間は滞在する。だから新鮮な食材は現地調達する。資金は乏しいから採取し捕獲する。野を歩き山菜を取り釣りをする。初年度は空振りが多かったが、2年目は結構確保できるようになった。例えば岩魚の塩焼きとウルイのおひたし、デザートはサルナシ。アクは強かったりするが野生味のある濃く深い味は野外食ならではで満足だ。
鉱物を採集するのは控え、撮影を主に行う。日中は各所で撮影をしまくり、夜はそれを整理する。その瞬間に起きている現象をデータとして収める手段は加速度的に進化した。かつては撮影ごとに撮影地を別にノートに記したのだろうが、今はGPSで各カットのデータにタグづけされるから撮影に集中できる。常に頭に装着したGO PROで録画もしているので後の作品整理がかなり楽だ。しかも画期的な発見は録画され残っているから、それを編集すればエビデンスに利用できる。そのうちに五感で感じ脳に記憶するという最速な手段を凌ぐ日がやってくるだろう。
栃木の山中は印象的だった。渓流にヤマメを追っているときだった。山肌を削るように流れるせせらぎが左にカーブするその角に、ちょっと見には気がつかない洞があった。私は閉所は苦手だがその洞は人を寄せ付けない空気は発しておらず、むしろおいでおいでと呼んでいるような気配すらあった。時間はまだ朝7時だ。しかもここからどんどん晴れていく予報なので心細さも薄い。翠は中へ入ってみることにした。案の定そこに踏み込んだのは自分が最初ではなく、タバコの吸い殻や食べ物の包み紙が散らかっていたりはしたが、入口から差し込んだ光は洞の先の鍾乳石をほのかに照らしていた。洞の天井は翠の背を遥か超え3mほどはあるので先に進んでいくのは容易だった。外からの光は徐々にその範囲が狭く低くなり、足元にもその光が届かなくなったところで翠は息を呑んだ。乳白色の鍾乳石が自然発光している。いや発光しているのではない。先ほどとは違うもっと狭い洞口があるのだろう、そこからの一筋の光がピンスポットライトのように鍾乳石を眩しいほど強烈に際立たせる。奇跡的にそこにはA3サイズほどの雲母の塊があり金鉱のように輝いている。鍾乳石の乳白色と対比をなし、かつてパリで見た王宮の装飾のように場違いな気高さを露わにしていた。おそらくこの状況は太陽の軌道が合致する瞬間にしか出会いないだろう。翠はこの邂逅にすべてを捧げ居続けた。次第にその光は短くなり惜しむように途絶えた。皆この幻想に身を置きたくてやってくるのだろう。その時翠は何も機器に納めていないことに気づいた。ヤマメが目的だったからだ。だがいいのだ、出会えたのだから。
第61夜 GO PROLOGUE
父はある時から散歩の時はネックストラップでGOPROを常に回していた。そして1週間前にあの世まで歩いて行ってしまった。葬儀を終え書斎を整理していると使い込んだGOPROが引き出しから出てきた。前に使っていたHERO8だ。メディアはそのまま入っていたので再生してみる。
そこに映っていたのは、
ゴミを片付けたり
人の犬を撫でたり
橋からせせらぎを眺め続けたり
生垣の花の香りに鼻を近づけたり
声をかけたりかけられたり
自販機で迷ったり
掲示板に近づいたままいつまでも読み終わらなかったり
鼻歌歌ったり
水たまりで跳ね上げだ車に文句言ったり
私たちにはあまり見せない姿だった。
メディアを抜き私のPCに落とす。父の声は生かし、スケジュール帳に父が書いていた書き込みを下段に小さくテロップで入れていった
5月1日 社休日 ジャガイモの芽かきをする
5月2日 令通澤田さん打ち合わせ
5月3日 憲法記念日 母さんの秋冬物を押し入れに
5月4日 みどりの日 吉郎の誕生日 カニを解凍しておく
5月5日 こどもの日 孫たちとみなとみらいへ
父の毎日は自身のためでないことばかりだった。それでも父の散歩の足取りは軽快だ
手ブレ軽減機能でも水平維持機能のせいではない。なぜなら被写体が笑顔だからだ。誰も花も猫も父を心配なんかしていない。皆笑顔で父に挨拶をしている。こんな生き方がいい。いやこの瞬間から始めなくてはいけない。あんな風に被写体を向く人生を。
第62夜 鶴を折る女(ひと)
地下鉄丸の内線のドア脇に寄りかかりながら手を動かす女性が何故か気になり、しばらく横目で観察した。飴の包みでも小さくしているのかと思った。しかしその人はマニキュアの施された長い爪で2センチ四方ほどの小さな紙を丁寧に折り続けている。私が少し目を離した間にその紙は仕舞われたようで手には無かったが、女性が手首に掛けていた小さな紙袋を開いたところで状況が掴めた。同じサイズの紙が幾つものジップロックに色とりどりたくさん詰まっていたのだ。
これで856羽目。往復2時間の通勤で40羽が折れる。家で頑張れば明日には千羽を終えられるはず。間に合って、いや絶対に間に合う。そしてまた一緒に毎日を過ごすの、絶対。
赤いマニキュアは千羽鶴にどこかそぐわない。何故か? それはマニキュアを塗る時間は人生の中でいちばん不要不急な気がするからだ。まあ私がマニキュアに縁のない男だからかもしれない。だがどう考えても後回しでいい行為だ。
この爪の長さじゃないとこの小さい鶴は折れないの。もっと大きなのを折れたらいいんだけど、集中治療室では許されない。マニキュアだって不似合いなのは分かってるけど、長いだけの爪って切り残しみたいでだらしない。というより、あの子が私のマニキュアをいつも「ママの爪かわいいね」って言ってくれてたから。
あれ,一つ足元に落ちている。「あのー、すみません…」拾うのは避け声をかけて知らせた。スカートだったからだ。女性は丁寧に御礼を返し、拾った黄色の鶴を紙袋にしまった。疲労を感じさせる表情に、私は鶴の意図について聞くことは出来なかった。
第63夜 ベランダ方丈記
浮かぶ雲は次から次へと北へ運ばれ、椎の最頂部の枝葉を揺らす風は、日光浴に微睡む私の火照った肌を優しく癒す。ベランダは洗濯物を干すだけの場所にあらず。とくに二階の角に設えられたここは3×3mの方丈空間。プランターのスナップエンドウのツルや、まだ収穫には程遠いミニトマトの苗の隙間にビーチリクライニングチェアを置き、屋根に真っ直ぐ切り取られた空と半年以上ぶりに対面すると、お互い少しはにかみ瞳を逸らす。
紫外線は私を劣化させようと差すが、若かりし夏の日とはこちらの知恵が違う。夏を待たず盛春の柔光で、まるで遠火で渓魚を炙るが如くゆっくりと、そしてSPF値の高いサンオイルというタレを乾いては塗りじっくり仕上げるのだ。夜の輩のような黒光りではなく、あくまで飴色。そう、フィンカビヒアで思惑するヘミングウェイの肌の色だ。
老犬ベティが私の周りを訝しげに彷徨く。コパトーンのココナッツフレーバーが気になるのだろうが、私以外に何もない。諦めて方丈端の日陰にフテ寝する。呼び寄せ耳裏を撫でてあげると機嫌を直して私の足の甲に腹を乗せ満足そうに寝そべる。
太陽の下ではいつだって全てが平等だ。だがその日差しが激化する時、逆にうんともすんとも言わない時、物理的差異が不平等を生み出す。細工が出来る知恵や指先、移動出来る機能や熱力。しかしそれらも、太陽系という都合のいいゾーンの均衡の中のみのことで、ひとたび圏外に出たならば全て素粒子に帰す。ある意味平等に帰す。
5月の方丈は思惑に寛大だ。暑さに居た堪れず水に飛び込みたくなることもなく、喉が疲労するほど水を飲みたくなることもなく、ただただ空との対面が叶う。生まれたままの姿と心で。
第64夜 青い土俵にて
呼び出しは土俵を掃いて平す
勝敗を決する行為ではないが
荒れた土俵は新たな闘いには不向きだ
力士はさらに塩を撒き清めなおす
幾度もの闘い そして儀礼
蹲踞 四股 力水 塩 仕切
神聖な土俵では心して闘う
お互いに敬意を払いながら
奪取 蹂躙 挑発 威嚇
神聖な土俵上にはない言葉たち
ではそれらが存在する闘場とは?
聖戦という言葉は微かに存在はしているが…
陽光に浮かび出された宙の青い土俵
呼び出しもないまま戦い始める非礼
飛び交うミサイル 放置された瓦礫の山
敬意なき 拍手なき 希望なき 天覧試合
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
