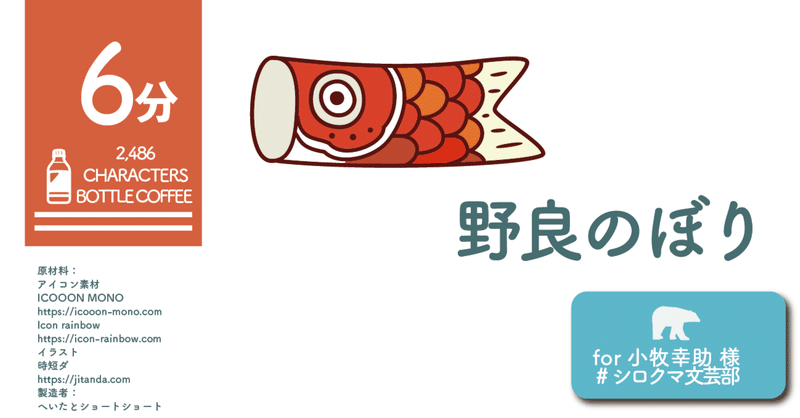
北極日記 野良のぼり(#シロクマ文芸部)
子供の日、というのはすっかり大人になってしまった今では縁がないが、せっかくなのでちまきぐらいは食べておきたい。中華ちまきではない。葉っぱに包まれた白いやつだ。あの、うすら甘いもちもちした甘味を存分に味わえるのは年に一度、子供の日くらいにしかないのではないだろうか。
おもち原理主義とでも言おうか、小さい頃から餅好きのあまり他の和菓子に厳しい子供だった。牛皮はお餅の偽物、くらいには思っていた。不必要にびよびよと伸びる牛皮菓子に冷ややかな視線を浴びせてきたが、不思議とちまきだけは好物である。あんこすら包んでいない地味なお菓子なのに自分でも解せない。甘いだけなんだけどなあ、と笹の葉を開いた時が一番わくわくする。幾つになってもあの爽やかな香りを嬉しく思う。
ご存知かと思うが、ちまきは極めて腹の膨れる食べ物である。近所の和菓子屋で柏餅と一緒に買い求めたはいいものの、二種類買ってしまった時点でお茶菓子の範疇を超えている。セットなので何本も入っているのだ。誰かとわければいいようなものだが、「子供の日を満喫したいから柏餅とちまきを一緒に食べてほしい」などとしょうもないことを誘えるご近所さんもいないので、これは食事だ、ということにする。おはぎを食事にすることだってあるではないか。
五月晴れの風が気持ちよく、ベランダを網戸にして、ちまきを食す。コーヒーも入れた。あんこをコーヒーと一緒に食べるのが気に入っている。どっちも黒くて、どっちも豆というのがいい。ちまきにあんこは入っていないが、それもまたいい。
ベランダでは連休だからと張り切って片付けた洗濯物がはためいている。景観と実用が両立しないのは困ったものだ。休日に家でゆっくりする日にこそ、外の景色を楽しみたいものだが、休日に家でゆっくりする日にこそ洗濯物がしたいのである。
シャツやらタオルやらが風に揺れる。私の衣類はどれもこれも木綿で、白いものばかりだ。波打つ布地の中に、赤色のものがのぞいた。あんな服あったっけ。イベントTシャツか何かだろうか。鱗の模様がついている。勢いで買ったにしても派手すぎる。
立ち上がってベランダに出てみると、鯉のぼりが物干し竿に引っかかっていた。小さな緋鯉だ。風でどこかから飛ばされてきたのだろうか。洗濯物を引っ掛ける部分に、鯉のぼりの口から出た紐がからんでいる。外そうとすると怯えてイヤイヤと体をくねらせた。布地があたって、くすぐったい。
「じっとしていないと、外せないよ」
顔にかかる布を払いながら緋鯉に言う。なおも緋鯉は抵抗する。困った。子供がいるわけでもないのに、物干し竿に鯉のぼりをぶら下げておくわけにもいくまい。机の上にのったちまきが見えた。思いつきで言ってみる。
「外れたら後でちまきあげるから」
途端に緋鯉がおとなしくなった。現金なやつだ。紐を切らないように注意深く外すと、萎んでぺちゃんこになった。約束なので家に入れてやる。窓から部屋に入った途端にまたうねうねとくねって、机の前に体を曲げておさまった。
「悪いですね。ご馳走になっちゃって」
うきうきした声でそう言った。
鯉のぼりに胃はあるのだろうか。少なくとも手はなさそうなので、和菓子屋のパックから新しいちまきを一つ出して、皮を向いた。半分皮に包んだまま、ぷりぷりとした中身を緋鯉に差し出すと、丸い口をいっぱいに開けて、私の腕ごと口の中に入れた。歯はない、とわかっていても一瞬身がすくむ。どうするのだろう、と思っていたらすうすう音がした。
「ああ。いい匂い」
鯉のぼりが嬉しそうに言った。匂いを食べているのかもしれなかった。ちまきを持ったままじっとしておこうと思った。
「どこからおこしになったんですか」
鯉のぼりに聞いてみる。
「どこからも。わたし、家なんてないの」
返事を聞いて、びっくりした。家のない鯉のぼりなんているんだ。どの鯉のぼりもどこかの家の柱に家族と繋がってるもんだと思っていた。野生、と言ってもいいのだろうか。野良のぼり、とでも呼ぶのか。
「本当よ。家なんてないんだから」
拗ねたような声で鯉のぼりが繰り返す。嘘だな、と思った。人(?)はやましいことを繰り返すものだ。聞いてもいないのに繰り返してくるのは気にしている証拠である。
「家出でもなさったんですか」
聞いてみると、鯉のぼりの口がきゅっとしまった。思わず喰われていた右手を抑えてしまう。痛くはないが、びっくりした。
「だって」
鯉のぼりが私とちまきを口から取り出して、わなわなと震え始めた。泣いているらしい。
「だって、せっかく年に一度の遊泳なのに、家の人たち、出かけちゃっていないんだもの!」
今度は床にうねうねくねくねのたくりだす。よほど口惜しいらしかった。
「家の人が見てなくても、周りの人が見てますよ」
仕方がないので慰めてやる。なるべく優しい声で付け加えた。
「こんなに綺麗な鯉のぼりなんて、そうないでしょうしね」
玄関のチャイムがなった。同じ地区の長谷川さんだった。廃品回収の当番であったことがある。
「あのう」
申し訳なさそうにインターホン越しに話しだす。
「うちの鯉のぼり、お邪魔していないでしょうか」
床でのたうちまわっていた鯉のぼりが途端に静かになった。さっきより赤くなったような気がする。
「いますよ」
インターホンに返事をした。
「今、お持ちしますね」
動かなくなった緋鯉をそっと畳んだ。ついでに綺麗なちまきと柏餅を箱にしまい直した。
鯉のぼりと和菓子を押し付けられた長谷川さんはびっくりした顔をしていた。申し訳ない、と恥ずかしそうに頭を下げた。「いんですよ」と私は言って「買いすぎちゃったので」と和菓子のパックを押し付けた。
部屋に戻って、コップに牛乳を注いだ。和菓子に牛乳も乙なものだ。食べかけのちまきを齧り、鯉のぼりのために開けたちまきに手を伸ばす。笹の匂いはすっかり消えていた。
※この文章はお題(「子供の日」)から始まる嘘の日記です。
小牧幸助さんの「#シロクマ文芸部」に参加しています。
今週のお題は「「子どもの日」から始まる小説・詩歌・エッセイなどを自由に書く」です。
