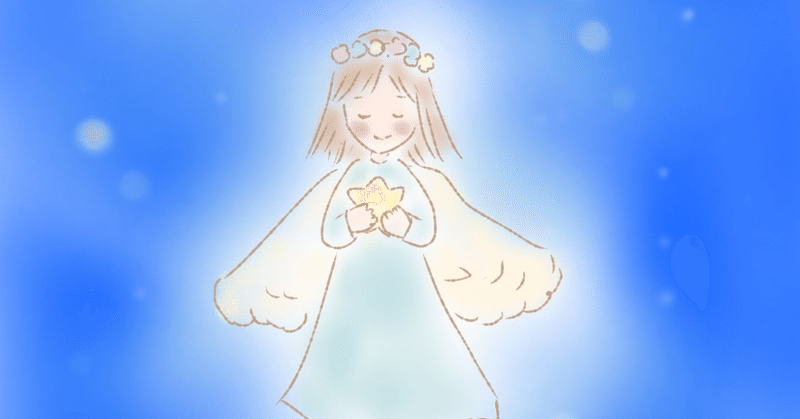
Ami Ⅲ 第7章 宇宙のおばあちゃん
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
リビングでヨガの練習をしながら、おばあちゃんが僕を待っていました。
「ペドロ、何か良い事でもあったの?
朝出かけた時と顔が違ってるうだけど。
アミとビンカには会えたの?」
と僕に尋ねてきたのです。
僕は、まるで、夢でも見ているような気分でした。
あまりに驚かされて、何も答えられず、ただ目玉焼きのような大きな目でおばあちゃんを見つめました。
「あのね、お前の本に書いてあることは、全部本当だと思うの、息子よ。
今朝、庭で洗濯物を干していたら、銀色の丸い宇宙船が、空を通過するのが見えたの。
それは視界から消えるまで、空高く昇って行ったのよ。
それで、その船には、翼のあるハートがあったから、お前の本を再びめくってみたの。
やっと点と点が繋がったわ。
あとね、体調に気をつけてビタミンを摂っているから、いつかお前が持ってきてくれたおいしいエイリアンのナッツを、なんとか思い出せたのよ。
今、お前は久しぶりに幸せそうに見えるわ。
以前は、アミがまだ帰ってこないからと、悲しんでいたのよね?
そうよね。
本当に彼とビンカと一緒にいたんだと思ってるのよ。」
その言葉に僕は唖然としたのです。
怖いと思う反面、やっと自分の世界の誰かと秘密を共有できる、しかもそれが、この地球上で最も愛されているおばあちゃんなのです!!
大きな希望が湧いてきました。
「本当にそう思ってるの?おばあちゃん?」
「もちろんよ、息子よ。」
彼女は正直な目をして答えまた。
「誰にも言わないつもりなの?」
「どうしてそんなことを考えるの?
もちろん、言うはずないじゃない。
誰もこんな不思議な現実を信じないし、こんな話題に触れるとお前が錯乱していると思われてしまうじゃない。」
「もし僕が、おあばちゃんが見たあの船に乗っていたって言ったら、信じてくれるの?」
「もちろんだよ、ペドリート。
あの船を見たとき、そのことが頭をよぎったんだもの。
お前はとても幸せそうに去っていったわ。」
「じゃあ、宇宙人は怖くないの?」
僕は、ますます興奮して言いました。
「だって、宇宙の主な力は愛なんでしょう。
だから、私が見たような幻想的で高度な船を操る宇宙人は、私たちよりずっと進化してて、愛への道を歩んできたに違いないと思うのよ。」
僕は彼女を抱きしめ、馬鹿のように彼女の肩で泣き始めました。
新しい喜びの可能性が開かれたのを感じたからです。
「ペドリート、ひとつだけ、大切なお願いがあるの。」
「おばあちゃん、僕にできることなら、何でもするよ。」
「次に戻ってきたら、アミに会わせてね。」
僕は、また彼女を抱きしめて、幸せに浸っていました。
「明日会えばいいよ!」
「明日って、前は1年間も空いてたじゃない?」
彼女は、少し戸惑いながら尋ねました。
こんなことを、祖母とオープンに話せるのは、とても素晴らしいことだと思いました。
その上、彼女はもっともっと知りたがっていたのですから。
最近の出来事を話してあげると、祖母はとても喜んでくれたし、ゴローがビンカに許可を出さないかもしれないという不安も少しあったようだけど、きっと上手くいくと信じていると言ってくれました。
その夜ほど幸せに眠れたことはありませんでした。
第一に、僕に祖母という理解者ができたからです。
第二に、僕の最大の夢である「二度とビンカと離れ離れにならない」ということが実現間近だったのですから。
(第三は忘れてしまいましたが...。)
翌日、祖母は僕と同じように興奮し、アミに会うために森まで一緒に行こうと言いました。
僕は、それは年寄りには遠すぎるからダメだと言い、アミに直接会うことが可能かどうか聞いてみることにしたのです。
僕は森に到着しました。
今回は長く待つ必要はありませんでした。
頭上に突然、黄色い光が見えたので、僕がその中に身を任せると、船の中にたどり着いていたのです。
そこには微笑むアミとクラトの姿がありました。
「ビンカは?」と僕が尋ねると、「クラトの大陸よりあなたの大陸の方が近いから、先に彼を迎えに行きました。
もうそろそろ彼女も立っているはずです。
さて、私たちはキアに戻って、向こうの新情報を見ることにしましょう。」
「そんな何百万キロも、何でもないかのように、往復するなんて。
すごいね、アミ。」
「何十億キロもです。ペドロ。
もし、コロンブスが見たら驚くでしょうね。
彼のあの有名な旅が、たった数時間の飛行時間でできるのです。
あなたたちが使っている、再生不能な燃料を使い、汚染し、ひどい音を立てる、あの遅い機械を使ってるのですから。
さあ、出発です、みんな。」
「でも、その前に聞きたいことがあるんだ、アミ。」
「あぁ、あなたが考えている事は、わかっています。
おばあちゃんは、全て知っていたのですね。
私に会いたがっているなんて、嬉しいです。
このままだと何もかも上手くいきますね。
もちろん私も会いたいと思っています。」
それを聞き、僕は飛び上がるほど喜びました。
「一緒に歩いていきましょう。ペドロ。」
「それじゃ、行こう。」
とクラトは自分を誘うように言いました。
「そんなことを考えないでください。
その耳とその外見で見られたら、牢屋に入れられて、その半分ピンクの髪の根元まで調べられますよ。」
アミは彼に警告しました。
「まあ、わしの美しさに見とれて喜んでもらえばいいんじゃが。
ほっほっほ!!。」
「彼らは、メスを使って、あなたの内部も調べるでしょう。」
「ふむ、足が痛いから、こっちで待ってようかの?
おばあちゃんによろしくな。”べトロ”。
「さて、船のことはクラトに任せます。
バカなことをしてアンドロメダ星に辿り着いたりしないように、すべての制御は無効にしてあります。」
と、星の少年は笑いました。
「テレビをつけておいてくれんかの?
この世界のスポーツを観たいんじゃ。」
「どんなスポーツがいいですか?クラト。」
「ロコトコみたいなものはないかい?」
「ロコはキアの小動物で、アルマジロに似ているけど、もっと速いのです。
そして、トコは赤を意味しています。」
とアミが説明してくれました。
「クラト、それは、どんなスポーツなの?」
と僕は尋ねました。
「”ベトロ”、スポーツに興味をもってくれてうれしいよ。
ほら、各プレイヤーは先端にネットがついた棒を持ってるんじゃ。
ロコが放たれると、ネットでキャッチするんだけど、動物と一緒には、3歩以上走れないんじゃよ。
じゃからな、相手にキャッチされないように気をつけながら、空中で味方に投げて、ゴールまで行って、そこに入れてGOAL!
素晴らしいじゃないか〜。」
「もし、パートナーがキャッチできず、生き物が地面に落ちてしまったら?」
「そうすると、生き物は逃げてしまうし、キャッチするのは簡単じゃないから、間違って投げた人に対する減点ポイントになるんじゃよ。」
「でも、落ちてたらかわいそうだよね...。」
「いや、ロコは、空中から落下するときは硬い装甲球になるんじゃよ。
それ以降は『捕まえられるものなら捕まえてみろ』」だ。
ほほう、そうですか。
わしは『ウトナの猛者たち』のスター、レッドロコと呼ばれとったんじゃ。」
「どういう事?」
「それはな、わしがロコを投げるときによく失敗して、その足のついた硬い鎧が、最も危険な相手の頭にさりげなくぶつかり、わしのロコを赤く染めて、相手をノックアウトしとったんじゃ。
ホ、ホ、ホ!
じゃから "レッドロコ "と呼ばれとったんじゃよ。」
「それじゃあ、汚なすぎてプレイできないよね!」
「柔らかい頭が、わしのロコの邪魔をしたのは、わしのせでいはないからの。
ホー、ホー、ホー!」
「彼が、キアの最もスピリチュアルではないスワマだと言ったでしょう。」
アミはモニターのスイッチを入れながら言いました。
「しかし、あまり彼の妄想を信じないでください。
ほら、これです。
あなたが見ているのはサッカーと呼ばれるもので、この地球上で最も人気のあるスポーツです。
足と頭だけでプレーします。」
「白塗りの哀れなロコを蹴るなんて...。」
「あれはロコではなく、柔らかいボールです。
手が触れることは禁じられています。
青はここのゴールに、白は反対側のゴールに入れなければならないのです。」
クラトには、それ以上の説明は必要ありませんでした。
彼は、一瞬でこのゲームを理解したようでした。
それに、彼はすでに一方の味方になっていたのですから。
「白、行け!
わしのロコのチームと同じ服を着てるんじゃ。
やっつけてしてしまえ!
それはなんの画像なんじゃ?
アミ?白いのは?」
「ルーマニアのブカレストから来た”ラピッド”です。
彼らは何のためにプレーしているか。。。」
「ゴールの前に一人いるぞ。
今だ、強く蹴るんだ!こうやって!
あー!ダメだこりゃ。
入ったけど、青くない奴が手でボールを掴んだんじゃ...。」
「彼は青いチームのゴールキーパーです。
クラト、彼だけが手を使ってボール取ることができるのです。
少しずつ、わかってきますよ。
このキーを押すことで、他のチャンネルも見ることができるようになります。
それでは、またお会いしましょう。 」
「またな... なんていいトラップなんだ!
青いのはどうやって飛んだんだ!
ホ、ホ、ホ!...どうした?
赤い紙を手に持ってやってきて、トラップした奴に怒ったような顔をする黒服は誰だ?」
「あれはレフェリーです。
彼は審判なのです。
ゲームの警察官のようなもので、そのレッドカードはその選手が試合から追放されることを意味するのです。
ここでのキックはカウントされないのです。」
「えーっ!
触りさえしなかったら….. 青いのは芝居がかっとるんじゃよ、アミ。
芝生の上でオカマみたいに文句言って、レフェリーの気を引いとるんじゃ... いくらもらったんだ、この売れ残りレフェリー!
あいつはルールを知らないのか、アミ!
レフェリーカードはくじ引きで当てたのか!」
「クラトが地球に来たら、僕の世界の習慣にすぐに順応しそうだね。」と、森に降りながら笑いました。
「テリスだったという彼の過去を考えると、それは決して良い習慣とは言えませんが。」
僕とアミは、二人でビーチタウンに向かって歩きはじめました。
2年前と同じように、今回も「アミ」の格好をした美少年だと思われ、ちょっと親近感を持たれ、仮装パーティーに向かう少年だと思われ、時折、頭を撫でられたりもしていました。
彼も僕も、その状況に満足していました。
なぜなら、僕は前回よりもずっと、アミと彼の能力について多くのことを知っていたのですから。
この子が本物のアミだとは、誰も思いもしませんでした。
幸い、本の絵に描かれている顔などは、現実と違うように気をつけていましたから。
家の中に入ると、祖母がニコニコしながらこちらに向かってきました。
祖母はアミを見るなり、感激して抱きしめたのです。
「アミの表情はなんという優しさと明るさなんでしょう!
そうね、この子は、地球の子ではないのよね。
神のご加護がありますように、いつも守ってくれますように、良い子だね!」
彼は笑い始めました。
「いつも守られています。おばあさん。
でも僕はそれほど若くもなく、そんなにいい子でもありません。
ハハハ。」
「あなたのような高度な存在、別の世界の住人を受け入れることができるなんて、なんという喜びでしょう。
神よ、この素晴らしい機会を与えてくれてありがとう。
ありがとう、アミ。
孫の先生になってくれて、ありがとう。」
僕はおかしくなってきました。
祖母は、アミを僕の「先生」だと思ってたんだね。
男の子なのに...。
僕は笑い出してしまいました。
祖母は何もわかってなかったので、「おばあちゃん、アミは僕の先生ではなく、友達なんだよ。
彼が、特別な目で彼女を見ると、彼女は何かを理解したようで、こう言いました。
「ああ、そうだね、お前の言う通りだよ、息子よ。
孫の友達でいてくれることに感謝します。アミ。」
「私はこの仕事をするのが喜びなのです。
愛情を込めてやっています。
親愛なるおばあさん。
では、そろそろ出発します。
お誘いしなかったことをお許しくださいますか?」
「もちろん、とんでもないことだわ。
誘われても行かないわよ。アミ。」
「どうして、怖いの?」
「恐怖じゃないのよ、アミ。
ただ、あまり不思議なものを見たくないだけなの。
その後、この世界がとても悲しいと感じるかもしれないでしょ。
ペドリートは、時々、この世界のものが、ほとんど原始的だと思って怒り歩くからね。」
僕は罪悪感を抱きました。
「おばあちゃん、それは個人的なことだから......。
ただ、どうしてもオフィルと比較してしまうんだよ...。」
自分を正当化しようとしました。
「ペドロ、あなたは、自分自身を向こうの人たちと比べたりしないんですか?」
と彼は僕に尋ねました。
「それは....。」
「だから私は行かないのよ。
私は多くの良いこと、そして多くの悪いことから目をそらせたいの..。」
「その通りです、おばあさん。
このような旅には、心理的な危険性があることを、私たちは知っています。
それが、私たちが誰にでも堂々と自己紹介したり、誰かを私たちの世界に連れて行ったり、私たちの素敵な生活を知ってもらったりできない第18の理由です。
素晴らしい進化した世界を知っていながら、愛が支配していない、人々があまり良くない別の世界に戻って生活しなければならないのは、簡単なことではありません。
それが、このような出会いが少ない理由でもあります。」
「今朝、私が作ったケーキをどうぞ。
ビンカ譲と紳士のクラトさんにもどうぞ。」
「紳士のクラトさんだって?
は、は、は、は なんてことを言うの、おばあちゃん。
クラトは山の老人だよ。」
「クラトさんは紳士だわ。ペドリート。
彼があの巻物を書いたのですから。
私の尊敬と称賛に値する方なのよ。」
「何だって!?
いつか彼に会った時に言わないでよ。
クラトのエゴが膨らむからね。
でも、彼は、とても優秀で、とても面白い人であることは確かだけどね。」「ペドロ、おばあさんに何か言うのを忘れていませんか?」
「いや... 何について?」
「クラトのことです。」
「いや、何も... 。
ただ、彼はかなり醜い老人だってこと以外はね。
ハ、ハ、ハ、ハ それじゃ、またね、おばあちゃん。」
「ペドロ、彼からよろしくと伝えてくれと言われたのを忘れています。」
「ああ、それは... そうだ...。
よろしくって言われたよ。
じゃあ、またね。」
「本当なの?
ああ、なんて親切なの!
なんてスリリングなんでしょう!
こんなにも美しい魂が...別世界から... 。
ありがとうございますと伝えてね。
私からもよろしくと伝えてね。
そして...いつこっちにお茶を飲みに来てくれるのかしら...彼の星と私の星の話をしましょうとね。」
祖母はこの戯言にあまりに感動していました。
「お茶?もし来ることがあっても、お茶はないだろう...。」
と僕。
「じゃあ、何を飲むっていうの、ペドリート?」
「ワインか何か...わからないけど、お茶は、きっとない。」
「じゃあ、彼が来たときのために、いいワインを買っておくわね。
アミ、気をつけて運転してね。
ルールも信号も、全て守ってね。」
「心配しないで、おばあさん。
私は何年も前にパイロットの運転免許を取ったのですが、一度も罰金を取られたことはありません。
信号も速度制限も横断歩道も尊重します。」
白い服の小さな存在が笑いながら答え、僕たちは別れを告げました。
おばあちゃんが「ビンカと戻ってこれる事を祈ってるわね。」
と遠くから声をかけてくれました。
僕たちが、船にもどった時には、サッカーの試合は終わっていて、クラトは他の番組を見ていました。
彼は、とても興奮して僕たちのほうにやってきたのです。
「勝ったんじゃよ。
ホッ、ホッ、ホッ、ホッ、ホッ、ホッ、ホッ、ホッ!
ペナルティをとったんじゃ!」
もちろん、レフェリーは悪党じゃったんじゃが。
エリア外で青い奴が顔へキックしたんじゃよ。
フリーキックで充分だったんじゃが、あいつはPKを取って、その上、ターゲットマンを退場させてしまったんじゃ。
じゃが、わしらがのチームがそれを止めたんじゃ。
2人外れた状態でプレーしなければならなかったんじゃよ。
レフェリーは青い服を着るべきじゃ。
なんと哀れな事か。
さらに、あいつは、”チリ”の素晴らしいゴールも却下しおったんじゃ。
ターゲットとなった選手は、ボールがきてから2人のディフェンダーを抜いたんで、完璧にクリアしてたのにじゃ。
じゃが、レフリーとゴールキーパーは、『足の速い”ラピッド”のストライカーは前進した位置にいた』と言うんじゃ、ゴールを認めなかったんじゃよ。
それで3点対2点で勝ったんじゃよ。
どうじゃ、わしらにはアフリカのスター選手がおるからの。
そいつが、3つのゴールのうち2つを決めたんじゃ。
(アフリカからの選手ではなく、日焼けオイルを塗りすぎて、全身が真っ黒になっただけなんですが。)
僕はポカンと口が開いたままになりました。
クラトはサッカーのルールをすべて覚えていたのです!
僕が理解するのに時間がかかった「オフサイドポジション」の複雑なルールでさえ、彼はただ試合を見て、理解できない言語で話を聞いただけで理解していたのです!
「何かを本当に好きになると、脳はそれに全力を注ぐのでよりよく働きます。
その集中力は非常に強力なものなのです、ペドロ。
それに、この老人は馬鹿じゃないのです。
もっと重要なことに注意を払わないのは残念ですが...。」
「サッカーはとても美しいの。
キアにも似たようなスポーツはあるけど、こんなのはないの。」
「僕も好きだけど、反則があると、どこかに行きたくなるんだ。
残忍なことは嫌いなんだよ。」
「あのスクリーンで見た他のスポーツ、男が怖い角のある巨大な獣に挑む...ようなスポーツに比べれば、わしはこのスポーツを男らしく、強く、残忍ではないと思うんじゃ、”ベトロ”。
赤い布で獣を挑発し、だまされた獣がそれに続くんじゃ。
その角は男の数センチ先を通過する...。
勇気が要るじゃろうな...。
じゃが、彼らは可哀想な動物に何でもするんじゃよ!
そして、冷酷に殺す... 残酷じゃ。」
「その通りです、クラト。」
とアミは言いました。
「バンデリージャという小さなナイフで動物を刺し、少しずつ出血させ、弱らせるのです。
揺れるたびに傷口が開き、より酷い痛みとなって、獣たちは激怒するのです。
背中に長いナイフが刺さったまま走り回るとか、想像できますか?」
山男でさえも同感したようでした。
「確かに、アミ、この辺りには、かなり荒っぽい奴もおるな。
この世界の別のスポーツも、ワイルドすぎるように思えたんじゃがな。」
「どういうこと?」
「2人の男が殴り合ってたんじゃよ。
片方が地面に倒れ込んで半死の状態になるまでな。」
「ああ、それはボクシングかな?
そういうスポーツがいくつもあるからね。
本当に倒れて死んじゃった人も沢山いるんだよ。
それで頭が悪くなっちゃった人もね。」
と僕は言いました。
「これらのスポーツは悪い例ですね。
その上、振動がとても低いのです。」
とアミが口を挟みました。
「観客の興奮と暴力的な感情は、精神的な振動となって街全体に届き、他の人は無意識でもそれを感じてしまうのです。
振動は『磁気』なので、他の人にも同じ振動、つまり同じ種類の思考や感情を誘発し、世界はその振動で泥沼化するのです。
これこそが暴君に合った振動なのです。」
すると、クラトが「だからサッカーを好きになったんじゃ!あれはスポーツじゃよ!あのキックを思い出してみろ!」と言いました。
「しかし、時にはかなり汚いプレーもあります。」
「汚いのは青い奴らだ!」
とクラトは相手チームだけを非難して抗議したのです。
「もっと有益な話はないのですか?」
と、アミは少しイライラしながら聞きました。
「その”ベトロ”って書かれた袋は何じゃい?」
「あ、ケーキだよ。」
「一切れ味見させてくれんかの。
うーん、パクパク... ふぅー!これは甘いな。
お前さんたちが食べるものは全部甘いのかい?」
「全部じゃないよ、おいしいものだけだよ...。」
彼を困らせようと、僕は言いました。
「そのケーキは、ペドロのおばあさんが、私たちのために作ってくれたものです。クラト。」
「 ああ... 、おいしいな。
よろしくと伝えてくれたかい?」
「うん。伝えたよ。」
「で、何か言ってたのかい?」
「『ありがとうございます、ゴロー。
ゴローにはもっと優しくなってほしいな』って言ってたよね、アミ。」
「ペドロ、あなたは正直ではありません。
真実を隠す者は、嘘つきです。」
「いや、アミ、ゴローにはもっと優しくなって欲しいって心から思ってるよ...。」
「話題を変えるのが上手ですね。
まるで...何か知ってるようですよね。」
「何を言ってるの...もう伝えたよね... おばあちゃんは『ありがとうございまる』って言ったよね。
「それは、もう言いましたよね。
他にはないのですか?”ベトロ”?」
「あ、そうだ、『彼女にもよろしくと...。
ビンカに会えるのを楽しみにしています。』とも言ってたよ。」
「他には何もないのですか?”ベトロ”さん?」
「それだけだよ。
ちょっと暑いな...。」
「ペドローーーー。」
とアミが咎めるように言いました。
「そうそう、アミに『信号機を守るように』って...。
はは、はは、宇宙の信号機だって。
ビンカについて話してもいい?」
アミは爆笑しました。
「進化してない人にとっては、本当のことを言うのは難しいのでしょうね。
」
「もう言ったよ、アミ。言ったよね。」
僕は動揺していました。
「大体の事は、でも、全てではありません。」
「僕は、おばあちゃんが話したことをすべて話したよね、アミ、もう充分だよ、お願い。」
「あなたは、彼女が巻物の作者に大きな敬意と賞賛を示したたことだけを言い忘れていました。
また、クラトがよろしくと言ったと知ったときの彼女の興奮を隠し、家に招待したこと、クラトが好きな飲み物を買うつもりだと言っていたことも言いそびれましたね。」
「そんなことまで言ってたのかい?
なんて温情のあるおばあさんなんじゃ...。
なぜ隠したんじゃ、”ベトロ”?」
「僕は何も隠していないよ。
象のように大きな記憶力がないだけだよ。
もう充分だよ。お願い。」
クラトは混乱していました。
「この子はどうしたんじゃ、アミ?」
「嫉妬です、クラト。
ちょっと独占欲が強くて、センチメンタルでわがままなのです。」
「あぁ......あぁ......。」
「嫉妬...?おばちゃんに?
僕が好きなのは、ビンカだよ。」
「そうです、ビンカはパートナーとして、おばあちゃんは、おばあちゃんとして。」とアミが言いました。
「それ、それ、何がそんなに酷いのかわかんないよ。」
「あなただけのおばあちゃんとして。
あなたは、彼女を他の誰とも共有したくないんでしょう。
彼女を独り占めするために、彼女の可能性をすべて閉ざしてしまうのです。
彼女の幸せはどうでもよくて、自分の幸せだけを考えているようなものです、ペドロ。」
前回もそうでしたが、自分が気づかなかった自分の欠点を指摘され、僕は座席に倒れこみました、が、今回は少し違っていたのです。
今回は、アミの言うことが正しいとはっきり理解できたので、以前のように自分から真実を隠すことはありませんでした。
今、アミは僕にとって、不当な悪党や中傷者ではなく、僕が自分自身を知る以上に僕を知ることのできる友人であり、祖母を自分だけが独占し、祖母のことや彼女自身の私生活を気にかけない、利己的な人間であることを教えてくれたのです。
僕は目を閉じました。
恥ずかしさで頬が赤くなっていたと思います。
僕は立ち直るまで、しばらくの間、何も言わないことに決めたのでした。
https://note.com/hedwig/n/nea337086b7cb
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
