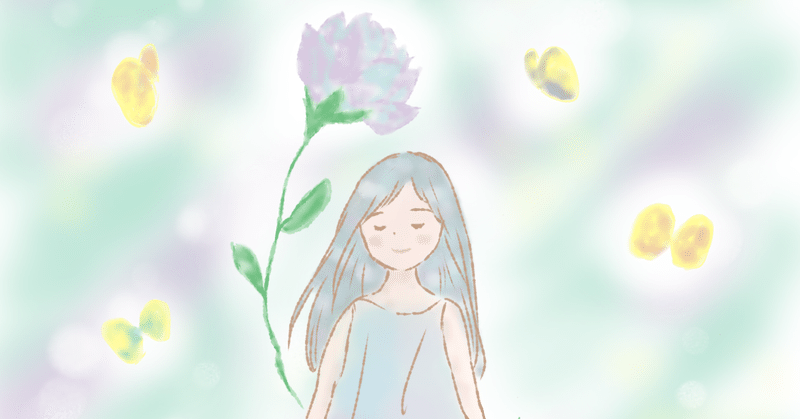
Ami Ⅱ 第17章-船上の反乱②
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
今となっては、どのようにして、何をしたのかすら覚えていませんが、その瞬間、僕は過去、現在、未来、そして、僕と宇宙のすべてを知っていました。
それ以上に、僕は、宇宙の中心であり、司令塔であり、銀河や魂は,僕から発せられ、僕に戻り、また僕から出ていくという、絶え間ない脈動での一種のリズム、まるで僕自身の呼吸であるかのようでした。
僕の中心には、至福と充足と叡智に満ちた大きな静けさがありました。
そこには僕の平和があったのです。
表現するのはとても難しいのですが、どこもかしこも正しくて、すべてが完璧で、何のかも素晴らしい事なのだと知っていました。
その高い視点から観ると、苦しみさえもOKだと理解したのです。
長い目で見れば、というか非常に高い所から観れば、それは良いことで、教えであり、浄化であり、誤りの結果であり、強化であり、内面の成長であったのです。
苦しみとは、忘れること。
忘れることによって引き起こされることを理解することができた気がしたのです。
すると、僕の意識はいつものレベルに戻り、通常の知性がその疑問とともに現れたのです。
僕は答えを見失ってしまったのでした。
何を忘れたのでしょうか?
自分の体を感じ、座布団の上で膝が重くなるのを感じていました。
この小さな体に戻りたくないという思いがありましたが、別の部分では戻りたいという気持ちもありました。
その場にいるのをやめて、司令部、つまり無限の知識に満ちた中心点に戻って答えを得たいと思ったのです。
『苦しみは、忘れ去ることによって引き起こされる...。何を?』
しかし、ある力が僕をそこから引き離し、宇宙船にいる重い体に戻したのです。
『自分の使命を忘れないでください。』
と声がしたような気がしました。
『あなたの使命は下にあります。』
わかっていても、思い出したくない、抗いたい、上に行きたかったのです。
『上がるためには、まず下がらなければなりません。』
と、また、内なる声がしました。
苦しみの原因となった「忘れること」とは、何だったのか、思い出せなくなりました。
「本当の自分を忘れてしまう事です。」
と、隣のアミが言いました。
それは、僕が必要としていた答えでした。
僕に、物質的な宇宙へ、宇宙船へ、瞑想のホールへ、自分の体へ、忘却へ、無知へ、平凡へと永久に戻ることを決意させたのです。
すべては順調でした。
目を開けると、崇高な色彩は消え、目の前に小さな光だけが残っていました。
ビンカは、アミの隣で、興奮で目を潤ませながら僕を待っていたのです。
僕は、徐々に、いつもの現実に、いつもの無知に、いつもの間違いに、自分を適応させていきました。
「本当の自分を忘れること。」
僕は、自分にとって意味を失いつつある、その言葉の意味を思い出そうとしながら呟きました。
「それが、失敗の原因です。」
とアミが言いました。
そして、上手く行かない時に、その失敗の代償を払わなければならないのです。
「よくわからないんだけど。
本当の自分とは何なの?」
「ある意味、神性です。」
と彼は答え、僕が起き上がるのを助けてくれました。
しかし、これらの考えはもはや、僕が本当に理解できるものではなくなっていたのです。
宇宙の礼拝堂を後にしながら、僕は自分が体験したこと、無限の至福と叡智の中心を思い出そうとしました。
「決して忘れないようにしてください。
それが本当の自分なのです。
もし、常にその部分から行動することができれば、間違いを犯すことはなく、したがって、苦しむこともないでしょう。」
「そうだね、アミ。
僕は本当の自分を経験したんだね。
全部わかったよ!」
「私はすべてを愛していたのよ。」
と、ビンカがあの礼拝堂での内なる体験に感動しながら言いました。
「知的な中心と感情的な中心です。
ほら、だから相補的なペアなのです。
あなた方ひとりひとりが、叡智の一部を顕在化させているのです。」
アミは船のコントロールバーに目を向けました。
「ほら、キアに着きました。
また暴動を起こさないようにしてください。ハハハハ!」
その言葉は、僕たちが彼に対して不快感を抱いていたことと、彼が普通の少年から光り輝く少年へと変化したことを思い出させました。
「どうやって変化したのか教えて貰えない?」
「最大の変化は、あなた自身の中で起こったのです。
外見を越え、一瞬でも、ありのままの姿が見えるようになったんですね。
私たちは皆、見かけ以上の存在であり、光り輝く存在です。
しかし、ある瞬間にだけ、自分や他人の真の次元を把握することができるのです。
あなたがとても悪い行動をしていたので、本当の自分が間違った行動をしていることに気づかせたのですが、あなたは愛を守りたいだけで、別れたくはないのです。
愛が暴力の最大の原因の1つであるというのは、こういう事なのです...。」
その言葉に、僕とビンカは顔を見合わせました。
「愛ゆえに、子オオカミは、自分の子供を襲うかもしれない者たちに対して獰猛になります。
自分のことを愛するがゆえに、人は往々にして他者に対して残酷で利己的です。
そのような愛のために戦争が起こり、その愛のために彼らの世界は危険にさらされるのです。」
「それは偽りの愛だよね。」
と、僕は理解したつもりで言ったのですが、
「それは偽りではありません。
それも愛なのです。
ただより低いモードで、より低いレベルだという事です。
私たちはそれを『愛着』と呼んでいます。
愛着とは、盗むこと、嘘をつくこと、そして殺すことです。
生き延びたい、それ以外のことは、どうでもいいというのは、愛の形ではありますが、自分自身、自分の小さな家族集団、自分の属する側に対してのみであり、それ以上のものではありません。
しかし、残念なことに、多くの人が、互いに戦いあうという、人生の戦いに、囚われてしまっているのです...。
これらは、誇張された愛着の結果です。」
「アミの言う通りだわ。」
ビンカは目を瞑って言いました。
「テリでさえ、悪ではなく、そういう愛に突き動かされていると思うのよ。」
「素晴らしい、ビンカ。
その理解があってこそ、激しく争う側ではない、高い視点から、物事を変えていくことができるのです。」
「残念なことに、テリ間の争いは、私の仲間であるスワマを危険にさらしているんだけど。」
「キアの民はただ1つ、テリとスワマの民なのです。
それがあなたの仲間です。」
ビンカにとっては、その発想が腑に落ちませんでした。
「何を言ってるの!」
と、思わず彼女は叫びました。
僕は、彼女の言う通りだと思いました。
「スワマに傾倒するのは当然だよ、アミ。
彼らは、彼女の仲間なんだから......。」
「ここでも、劣等な愛、執着、他者に対する自分の側面が見て取れます。
愛着は限定された愛ですが、真の愛には限界がないのです。
これまで、あなた方の世界の人々は、愛着によって生き延びてきました。
それゆえ、すべての領域で戦争が起こったのです。
しかし、今、第3から第4進化レベルに移行しようとしています。
もし、あなたが上昇したいのなら、執着を捨て、真の愛に導かれ、自分の小さな派閥の利益だけでなく、全人類の善に目を向けなければなりません。
そうでなければ、これ以上前進することはできないでしょう。
これが普遍の法則です。
愛着は、分裂した世界では、多かれ少なかれ上手くいくのです。
その分裂が、人類全体を危険にさらさない限り、また科学的レベルがそれほど高すぎない場合に限りますが。
そして、あなた方の世界のように、とてつもない破壊力を手に入れた彼らは、愚かさと暴力をあきらめるか、自らを滅ぼすかのどちらかなのです。
執着というアンバランスで利己的な愛を手放さずに、公正で平和な世界を築くことは、不可能なのです。
同時に多くの破壊的な能力があるのですから。
「なぜ愛はアンバランスなの?」
「愛には、自分に対するものと、他者に対するもの、という2つのタイプがあるからです。
呼吸と同じで、空気は行ったり来たりしています。
執着があると、息を吸う量が、吐く量より多いのと同じです。
『すべては自分のため。
自分と、家族に対してより多く、他に対してはより少なく』
となるのです。
それはバランスが悪いと思いませんか?」
「汝の隣人を汝自身のように愛せよ。」
と、僕は宗教の授業で習ったことを繰り返してみました。
「それは『エル・フスト』が言ったことだわ。
どうして知ってるの?」とビンカ。
「『エル・フスト』って誰?」と僕。
「キアの歴史の偉大な巨匠よ、ペドロ。」
「それは普遍的な法則なのです。
全て私が説明しようとしていることと同じです。
それは、真の愛なのです。
バランスのとれた愛、自分に対しても、他人に対しても、アンバランスなく、いつも同じ尺度でです。」
僕は、他者への愛が多く、自分への愛が少ないとどうなるのか、と尋ねてみました。
「それもアンバランスです。
空気を吸わずに全部吐き出してしまうようなものです。
数分後には硬直してしまいます。」
「バランスというのは、進化する上でとても重要な言葉だと思うのよ。
感情の中心と知的中心のバランスをとる。
愛と愛着のバランスをとるということね。」
とビンカが言うと、
「テリもスワマと同じように愛しなさい。ということです。」
と、アミが答えました。
「やってみるわ。努力してみるわ。」
とビンカ。
スクリーンには、この船が、キアの人々の目には見えていない、と示されていました。
僕たちは、地球上のどの都市にもあるような郊外を漂っていたのです。
別れる時間が迫っていたため、僕は、何も観察する気になれませんでした。
「いつまで続くか誰にもわからないよね。」
と、胸が締め付けられるような思いで、悲しく言いました。
「次の本が完成するまでです。」とアミ。
「『また戻ってきたアミ』のようなタイトルになるかもしれません。」
「君は、多くの知識と力を持っているかもしれないけど、どうやら文法は得意じゃないんだね。」と僕。
「どうしてですか?ペドロ?」
「「戻ってきた」には、「また」を付ける必要ないんだからね。
『戻ってきたアミ』って言うだけで十分なんだよ。」
「確かに、話し言葉や文法は得意ではありません。
それは、あなたが既に見たように、私たちは実際、話さないからです。
テレパシーの方がより安全で正確なのですから。」
「でも、ご両親とはよく話してたよね?」
「はい、でもそれは、あなた方への礼儀としてです。
私たちの言語を話さない訪問者が来た場合、訪問者の言語を知っていれば、それを使わなければならないのです。」
今となっては、どうして僕が会話の詳細を覚えていたのかすら、わかりません。
僕の関心は、悲しい別れにあったのですが、ビクトルに口述すると、何故か記憶がよみがえるのです。
まあ、アミが、テレパシーで助けてくれていたのでしょうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
