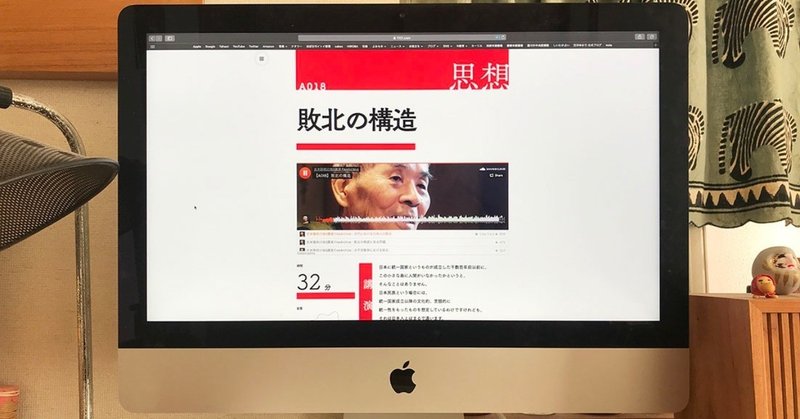
講演「敗北の構造」
ふと思えば、12月も、
28日になっていてもう年末なんだわ。
そんなことし中にね、
なんとかブログ書きたいと思っていたのが、
このごろ数ヶ月に1度ぐらいでブログ申しております
ほぼ日の講演フリーアーカイブ集「吉本隆明の183講演」より、
吉本隆明さんの講演のことなのでして。
前回、吉本さんの講演のことをブログ書いたのは、
今から4か月まえの8月18日、
【宗教としての天皇制】という講演なのでしたが。
つぎに聴きたい、という講演はすぐに決まったものの、
吉本さんの講演、ぼくにはいろいろむつかしかったりして。
同じ講演を何度か聴くうちに、すこしずつ、
馴染んでゆく、と申しあげますか。
そうしたら、いつのまにか4か月経っていた。
そして、こんかい聴きました講演は、
【A018 敗北の構造】です。
この講演は1970年6月10日、つまり、
ぼくが前回聴きました【宗教としての天皇制】の
約1か月後、会場は明治学院大学で行われた、
とのことなのですが。
両講演とも、開催日時が近いからか、
似ていることをおっしゃっている場面もあって。
それはたとえば、「天皇制」についてのこと。ですので、
ことしは「天皇即位」の年でしたので、
なんとか、ことし中にブログ書きたいと思っていたのよね。
さきほどは「何度か聴くうちに」とは申しましたが。
講演時間は32分と他の講演よりも短いのですが、
まだまだ、わかっていないことも多くて、
なかなかうまくは申せないけれども。
たとえば、吉本さんが講演冒頭でおっしゃる、
「現代の敗北」とはちがう
「大昔の敗北」というのは、
これまで全く考えたことなかったと感じまして、
興味ぶかく思いました。
つまり、かつて日本が統一国家になる以前には、
現在のことばで言えば「なになに郡」と言うぐらいの
小規模の国家が郡立して日本列島に存在していて。
そしてそこから、天皇制権力というものが、
国家的に制圧して統一性国家を成立させた。
という説があるらしくて。吉本さん曰く、つまりは、
そのとき、統一国家が成立する以前に在った
「日本の全大衆」が「総敗北」した。と。
吉本さんがおっしゃるこの「敗北」とは、
郡立状態の国家の中で決められていた法律みたいなものが、
吸い上げられるようにして、おおいかぶさるようにして、
交換、または、混合されて、統一国家が制定された。
えーっと、ぼくには、ちょっとむつかしいのですが。
でも、なんだか、ちょっと
わかるような気もするのですが。
今まで信じられていたもの、とか、
ふつうに信じていたことが、
スッとべつのなにかが登場することによって、
人々が、自然と何気なくそちらのほうへ導かれてゆく。
みたいな感じでしょうか?????
やっぱり、うまく言えないんですが。
あたらしく登場したものを、あたかも、
自分が以前から持っていた考えのように錯覚する。
と、吉本さんはおっしゃっておりますが。
でも、そういうことって、
じつは、たぶんにありそうにも感じられる。
講演のそのあとでは、
吉本さんご自身が体験なさった「敗北」として3つ、
・太平洋戦戦争における敗北
・労働運動における敗北
・60年安保における敗北
のことを挙げておられますが。とくには
「60年安保における敗北」についてのことで吉本さんが、、、
自分は、物書きとしてシャットアウトされるに違いない。
そうだとしたらば、おれは、書くということに対して、
そういうふうにシャットアウトされても、
「書くべきもの」あるいは「書きたいもの」は書く。
というそういう場を、いかようにしても、
獲得しなければならん。と。
(吉本隆明さん講演【A018 敗北の構造】、チャプター05「60年安保における敗北」0:45〜)
‥‥ということばを、力強くおっしゃっていたのが、
とても印象的でした。
そして、この講演の最後のほうでお話しされていた
「国家権力や法権力というのは、
首のすげかえができる、横すべりができる、
スッと上にかぶさることができる。」
というのは、でも、内容はむつかしいのですが、
それでも、「敗北」のなかの救い、と申しあげますか、
ひとつの希望のように感じました。
おそらくは、かつてから、
上にかぶさるようにして成立されてきた事柄というのは、
いつか、また、さらに上にかぶさるようにして、
つぎの段階が成立してゆく。的な?!
いや、どうか、よくわからないけれど。。。
そして吉本さんがいちばん最後でおっしゃっていた
「現在においても、ある種の迷信を打ち破るには、
たいへん有効じゃないか。
っていうふうに、僕には思われます。」
のこと、ぼくは案の定、まだよくわかっていないのですが、
よくよく思っていたいです。
そんなこんなでぇ、さて、つぎは、
吉本隆明さんのどの講演を聴こうかねえ???
令和元年12月28日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
