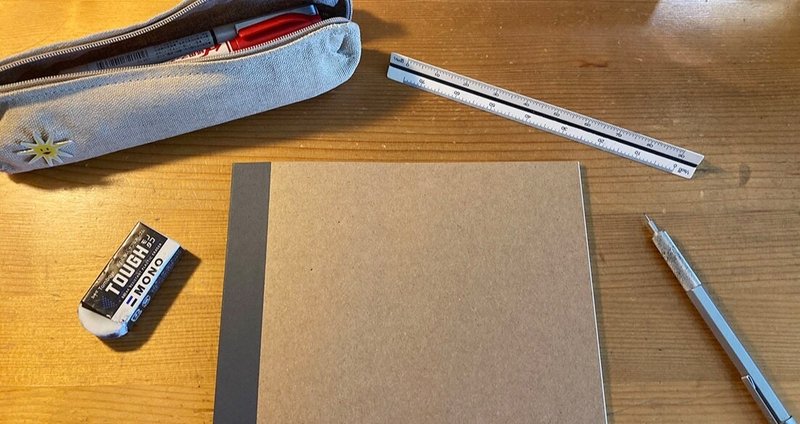2023年7月の記事一覧
七月の名古屋市の街へ。
一昨日は、名古屋市の街へゆきました。
ぼくが住んでいる愛知県豊橋市より、
県庁所在地の名古屋市までは、
今回はJRに乗りまして快速電車で約五十分、
「名古屋駅」で地下鉄に乗り換え、
最初の目的地は東山線「伏見駅」下車、名古屋市美術館にて
「マリー・ローランサンとモード」展を鑑賞いたしました。
思えば、名古屋市美術館へ来るのも
ひさしぶり、と申しますか、たぶん
コロナ下以後では初だったやもしらな
質か、量か、もう一つか。
「質よりも、量。」であるとか、その逆に
「量よりも、質。」であるとか、という議論は、
ネットでもよく見かけたりするけれども、
「質」なのか、「量」なのか、って、
ぼくにはよくわからないな。
たとえば、前者の
「質よりも、量。」と言うならば、
質のわるいものをたくさんつくる、
という意味としても受け取れそうだし、
そしてまた、後者の
「量よりも、質。」と言うならば、
質は申し分ないけど、それは
一
革命はパッと一瞬に。
先日のブログの中で申しあげました
B'z・稲葉浩志さんの作品集『シアン[特装版]』を、
読み終えました。書籍読みながら、
やっぱり、ぼくはB'zが好きだし、
稲葉さんのソロも好きだし、そして、
稲葉さんの歌われることばが好きだなあ〜。
ぼくがB'zを聴き始めたのは、中学生のころ
『love me, I love you』がリリースされたときだった、
と存じますが、B'zを聴くことで
知ったこと、
日々の変化について。(「見えにくい」ver.)
前回noteでは、「明日は明日の風が吹く」と言われても、
明日の風と今日の風と昨日の風のちがいって、
ぼくにはあんまりわからない、でも、
たとえば、今吹く真夏の風と
半年前吹いていた真冬の風とのちがいは、
ぼくでもわかるだろう、的なことを書いたけれども。
このことって、案外、じぶんの中では
すごい発見なんじゃあないか! って、
ひとりでちょっと小躍りしたい気分になった。
つまりはさ、
とある「変
その日の風に吹かれながら。
明日は明日の風が吹く、と言われても
明日の風と今日の風と昨日の風のちがいって、
ぼくにはよくわからないな。
でも、たとえば、
この今の「夏」の風と、
半年後の「冬」の風を比べたら、
そのちがいはぼくでもわかるだろう。
半年前の日に吹いた真冬の風を、
そのまま袋に詰め込んでおいて、
今日、その袋を開いて
その風に吹かれたい。その同様に、
今日吹く風と日差しをね、
そのまま袋に詰め込んで、
半年後
明日、縄文時代が終わったら。
縄文時代というのは、紀元前1万4千年ごろから
紀元前10世紀ごろまでつづいたらしい。
つまりはさ、その時代は
1万年以上つづいて、そして
今から約3千年前に終わった、
とのことなんだけれども。
そんな「1万年」とは、どんな時間だったんだろう?
ってゆうのを考え出すと、なんだか、
頭がぼーっとしてくるのよね。
でも、おそらく、一言で
「縄文時代」とは言えども、
その時代の中にも区分はあるとも思うけ
比喩について。(「似ている」篇)
きのうのブログではね、比喩のことについて
考えていることを書いてみたのですが、
今回ももうすこしだけ、そういうような
比喩について書いてみたい。
きのうもすこし申しましたが、
比喩にはいくつかの種類があって、
そのうち代表的な比喩を挙げるとすれば、
「直喩(明喩):シミリ」と、
「隠喩(暗喩):メタファー」があると存じます。
前者の「直喩」とは、たとえば、
【のような】や【ごとく】や【あたかも】
「わからない」とは、メタファーだから。
テストとか受験とか学校の問題とかだったら、
「わからない」というのはダメなこと、つまり、
よくないことではあるけれども、
ならば、すべての場合において
「わからない」がダメなわけでもない。
誰しもが、すべてのことを
「わかる」わけでもないし、逆を言えば、
「わからない」ことなんてえのは
たくさんあり過ぎるし、そして、
「わからない」からこそ、
どうするか? って、
考えることもできるよ。
はた
ごくごく飲み干すかのごとく。
昨日のブログではね、本を読むこととは、
そのほかのどのような鑑賞よりも、
いちばんおもしろいんじゃあないか?
とも思っている、ってゆうのを記したのですが。
そう言われてみれば、でも、ぼくはさ、
昨日もすこしだけ書いたのですが、
20代半ばごろより本を読むようになって、
なので、子どものころ、つまり、
その以前までは読書が大の苦手だった。
現在41歳のぼくは、小学生のとき
学研の「学習」と「科学