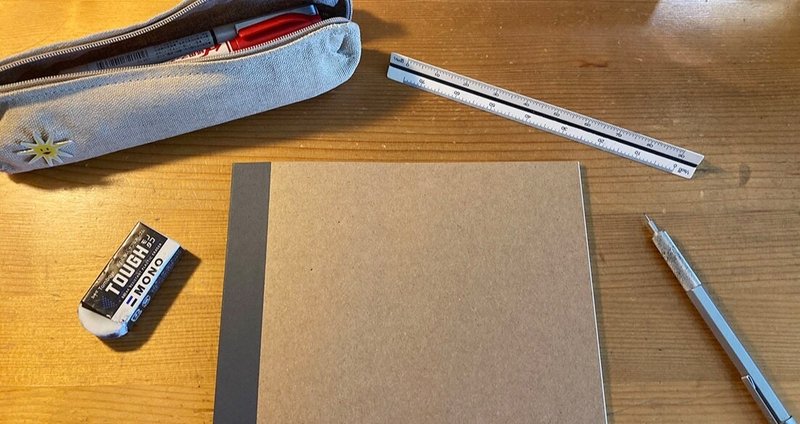2023年2月の記事一覧
消極的にブログを書くこと。
ぼくは日々、このnoteにて、
ブログを書いているんだけれども。
そのぼくが思っている
「日々、ブログを書く方法」とは、
日々の生活において、スケジュールとして
「ブログを書く時間」を組みこむ、
みたいなことなのでして。つまりはさ、
日々、この時間でブログを書く、とゆうのを、
あらかじめ予定で決めておく。
とは言えども、ぼくの場合では、
ぼくは現在パート契約の短時間の仕事なので、
フルタイムでは
無題。(令和5年2月24日の独り言)
ある重大な出来事が起きたことによって、
その出来事の起きた日にちが、
記念日、及び、祈念日になることがある。
たとえば、
「8月15日」であったり、
「8月6日」であったり、
「8月9日」であったり、
「1月17日」であったり、
「3月11日」であったり、
「9月1日」であったり、
「9月11日」であったり、また、
「2月26日」や「5月15日」という日も、
そのような日とも言えるやもしらないし
「がんばる」ということばについて。(「健闘を祈る」篇)
「がんばる」ということばは、
ぼくは、案外、きらいじゃあなくって、
日常的でも使ってはいるんだけれども。
でも、たとえば、漢字で記すと
「頑張る」になるけど、つまり、
「頑なに張る」というのが、
ちょっと強硬的、というか、
頑固さや堅さみたいなことも感じられたり。
もしくはね、たとえば、
こころのやまいをわずらわれている方には、
「がんばれ!」とは言ってはいけない、などなど、
使い方のむつかしい
ひとりの時間をもつということ。
ぼくは、20代半ばごろから30代半ばごろの数年間、
仕事もせず、半引きこもり的に、つまり、
お買い物などで自宅から外へ出ることはあるとしても、
基本的には、家と部屋で居る、
という日々を過ごしていた。
そこまでへ至る経緯を簡単に書いてみると、まずはさ、
ぼくは大学新卒で就職した会社を約半年で辞めて、
その次の春からは専門学校へ二年間通いまして、
専門学校卒業後には就職したけれども、
その会社もま
ことばはどのようにして生成されるのか?
言ったり、書いたり、思ったりするときの
「ことば」とは、この
ぼくのあたまやこころの中で、
どのようにして生成されているんだろう?
ってゆうことはさ、なんだか、
たまに考えてみるんだけれどもね、
よくわからないちゃあ、よくわからない。
たとえば、
なんにも思ってなかったようなときに、
なにかを思いつく、というときもあるし。
また、相手との会話や対話のときでは、
それまで考えたことのないことを
考
艶やかないいおやすみの日。
昨日はおやすみの日で、
一日中、家から外へと
一歩も出ずに過ごしておりました。
元来、ひきこもり気質のあるじぶんとしてはさ、
そういうおやすみのときこそ、
最高の至福な過ごし方なのですが。
とは言えども、とくべつ、
ゆっくりもしていられなくって。
昨日はね、まずは
部屋や押入れでたまってしまっている
新聞&段ボールをビニール紐でしばったんだった。
新聞をしばるときにはね、ぼくはいつも
イヤホン
四つの国名とドーロムービー。
「アメリカ」「ジャマイカ」「インドネシア」「エチオピア」
の共通点とは何か? と問えば、
その答えは、奥田民生さんの
『CUSTOM』という曲で歌われる国名だ。
あらためて考えてみるとね、この
四つの国名が歌われる、ってえのは、
かなり唐突な感じも受けるけれども、
でも、この国名のシーンがあるからこそ、
歌がさらに感動的になる、と申しますか、
とくにとくに大好きな箇所なんだなあー。
つまりはさ、