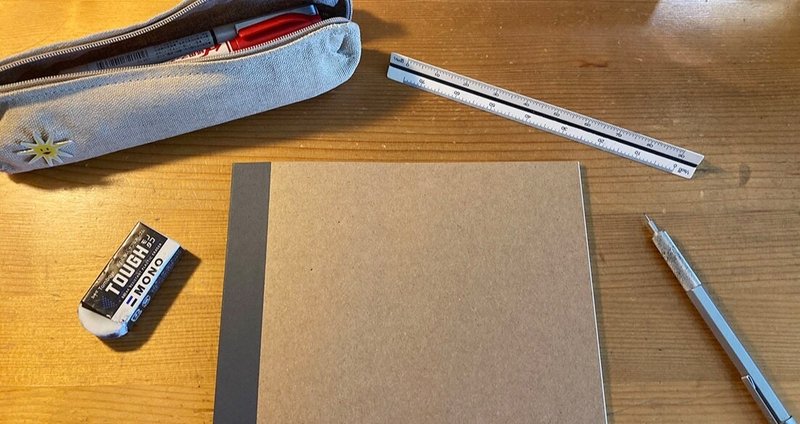2022年9月の記事一覧
義務という鉄板の上で。
さくじつのブログでは、義務教育とは、
「教育を受ける義務」ではなくって、
「教育を受ける権利」があること、そして、
日本国憲法では、保護者が
子供(子女)に普通教育を受けさせる義務を負う、
と定められていることをね、あらためて記しながら、
ふと、思ったのは、
このことを学校で習うのはさ、
義務教育も終わりに近づいた
中学3年生の「公民」の授業なのだとすれば、
逆にね、義務教育がスタートする
小学1
義務教育のイントロダクション。
日本国憲法の第26条第2項では、
義務教育について記されているけれども。
義務教育とは、
子供が教育を受ける、つまり、
子供が学校へ行く義務、
なのではなくって、保護者が
子供(子女)に普通教育を受けさせる義務を負う、
ってゆうのをね、ぼくが知ったのは、
いつごろだったか憶えてないけれども。
たとえば、ぼくが義務教育を受けていたときには、
義務教育のことを知っていたかなあ〜。
当時を思いだして
なぜ、勉強はおもしろいのか?
ゲームって、なぜ、
こんなにもおもしろいんだろうか。
たとえば、なんだろうかなあ、
そのゲームがさ、
むつかしかったとしても、
むつかしいからこそ、
クリアしたくなって、
なんども、なんども、なんども、
プレイしてしまうのか。
つまりはさ、困難を
乗り越えようとすること、そして、
困難を乗り越えたときの達成感を、
ゲームによって感じられるから、
おもしろいのかもしれないなあ。
高ければ高い壁
うさぎか、かめか、どちらでもないか。
「うさぎとかめ」のお話しで言えば、
ぼくは、どっちのタイプなのだろう?
って考えながら、でも、
結論としては、おそらく、
うさぎでも、かめでも、
どちらでもないんだろう。
まずはさ、
うさぎのように、
早かったり、出来たり、つまり、何かの
特別な能力があったりするわけでもない。
かと言って、
かめのように、
こつこつと着実に進んでゆく、
ってゆうのもね、ぼくには、
なかなかできがたい。
たぶん
速度について考えるときに僕の考えること。
現在、ぼくがパート契約で勤める学習塾にて、
小学生や中学生たちへ、
算数及び数学を教えようとするときにね、
彼らが、苦手、というか、
むつかしそうだなあと感じられるのは、
たとえば、食塩水の割合の問題とか、
原価と利益と定価と割引の問題とか、
円周率とか、もしくは、おうぎ形の面積とか、
などなどの単元なのだとは存じますが。
そのなかでもね、いちばんは、
速度の問題かなあー。
速度の問題が、
どう
タイムマシンを思いながら。
フィクションの物語として、
「タイムマシン」って、好きだなあー。
たとえば、
『ドラえもん』だったり、
『ドラゴンボール』の人造人間編だったり、
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』だったり。
あとはさ、ぼくの中で
めちゃくちゃ印象的だったのは、
2002年公開の『タイムマシン』の終盤のシーンにて、
タイムマシンの外側に居る悪役が、
タイムマシンの内部に居る主人公の身体を腕でつかみ、
そのまま、主
考えられない、わからない、言えない。
安倍晋三さんの国葬儀について、
ずっと、考えている。
ぼくとしては、
「賛成」とは申し上げられず、
とは言っても、きちんとした
「反対」の意見を言えるかどうか、
ってゆうのも、むつかしくって、
ネットやニュースやコメントでSNS等で、
調べたりもしながら、でも、
どう考えたらよいのやら、
まだ、よく、わからない。
たとえば、
内閣の持つ行政権とは、
「法律に沿って政策を実行する」
ということな
なんだって言えるか。
ことばを、
言おうと思えば、
なんだって言える。
それは、たとえば、
思想のことでも、
哲学のことでも、
経済のことでも、
社会のことでも、
事件のことでも、
善悪のことでも、
身体のことでも、
流行のことでも、
情勢のことでも、
宇宙のことでも、
どんなことでも、
言おうと思えば、
なんだって言えるだろう。
でも、やっぱり、
ぼくには、それらのことを、
言おうと思っても、
かんたんには言えな
そのときに授けられたことばを言え。
そもそも、人間は、
どうしてことばを話すんだろう?
いや、「どうして」とは言ってみても、
人間がことばを話す「理由」を
考えたいんではなくって、それは、
「どうやって」と言ったほうがよいかな。
つまり、人間は、
どうやってことばを話すんだろう?
たとえば、相手と会話をするとき、
じぶんが何かを言うためには、
ことばを言う前の段階で、頭の中で
これから言おうとすることばを思いついて、
その思いつ
忘れ物を思い出すこと。
出かけるとき、ふと、玄関先で
「あ、そうだ。あれを持ってゆかなくちゃ!」って、
忘れ物を思い出すことがある。
もしくは、出かけるときの玄関先で、
忘れ物を思い出さないこともある。
そういうような忘れ物のことをね、
「思い出すとき」と、
「思い出さないとき」では、
どういうちがいがあるんだろう?
ぼくとかは、事前に
どんなにチェックしていたとしても、
忘れ物をしてしまうことはあって。
それを、ふ