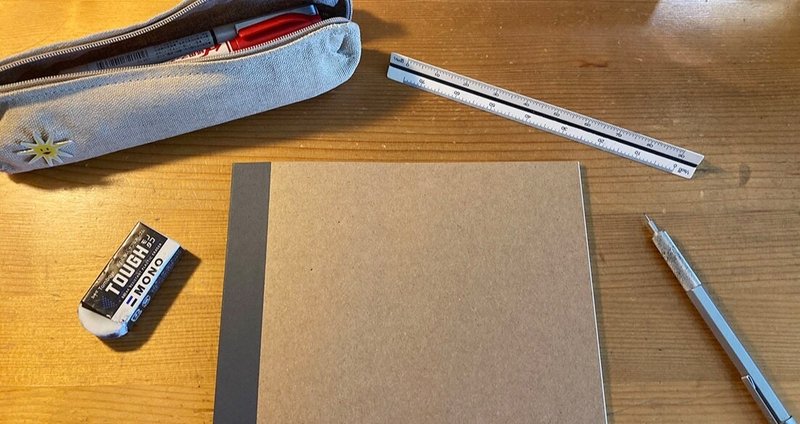2022年2月の記事一覧
ビー、オールライト。
なんだか無性に、
ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの
『No Woman, No Cry』を聴きたくなって、
昨日、Spotifyで聴いていた。
ぼくは、でも、
ボブ・マーリーのこと、そして、
レゲエのこと、ジャマイカのことについて、
知識として何も存じないけれど、でも、
『No Woman, No Cry』を聴くと、
なんだか、気持ちが落ちついてくる。
そして今、さっき、YouTubeでね、
until we meet again 生きなければ
昨日は、くるりの配信ライブ
「くるり結成25周年記念公演『くるりの25回転』」
観ましたー。
なんとゆうか、この今、
観ることができて、ありがたかったー。
25周年記念のライブとして、セットリストが
これまでの各アルバムから2曲ずつ選曲されていて。
本編25曲、および、アンコール2曲、という、
いろいろな曲、歌、演奏が聴けて、
すばらしかったなあ。
そのなかでもね、ぼくとしては、
『every
無題。(令和4年2月25日の独り言)
「正義」というのは、
とっても大事なことだとは思うけれど、
なんだか、ちょっとこわいなあ、
と思うこともある。
たとえば、
「正義」は
「悪者」をやっつける。
なのだとして、
「正義」とは、
「正しい」からこそ、その
「悪者」を「やっつける」ときのふるまいとは、
たとえどんな手段を使おうとも、
すべて「正しい」ものである。
と、思うようになる。
つまりはさ、
「正義」の「正しさ」を、
信じて、
思考の迷路の闇の中。
すぐに頭の中で考え込んでしまうぼくは、
「考える」という行為が、
ちゃんとできているかどうか、ってえのは、
じぶん自身の死活問題であるとも言える。
「考える」が、
ちゃんとできていない、ってゆうことは、
思考の迷路の闇の中で、
迷い込むことを、意味する。
そのようにならないためにも、
すぐに頭の中で考え込んでしまうようなぼくは、
「考える」とは、何か?
を考えることによって、じぶん自身が
「考え
ほんとうの考えが分かれば。
「考える」とはどういうことか?
ってゆうのは、けっこう、
じぶんの中で考える。
けれど、いまだに、
「考える」について、
じぶんなりの考えは持てていない。
「考える」について考えるときにね、
ぼくがよくイメージするのが、
吉本隆明さんのおっしゃっていた
「ほんとうの考えと嘘の考え」
のことばのことなのでして。
このことばについて、
以前、ほぼ日刊イトイ新聞にて、
吉本さんと糸井重里さんとの対
複雑なことを解釈するための練習として。
数か月前、パートで勤めている学習塾にて、
とある中学生の生徒さんが、
数学の問題を解いているときに
「こんな問題解いて、将来の何の役にたつの?」
と訊ねてきた。
こういう質問って、
たびたび訊かれながら、その都度、
ぼくはなかなかうまく答えられていないんですが。
このときはさ、
父が亡くなってから数か月が経ち、父に関する
もろもろの手続きのことをしていたころで、
そのことをずっと考えていたので、
「学ぶ」とは何か?(『素敵じゃないか』ver.)
ぼくがこのじぶんのブログのなかで、
「学びたい」とか言ってみても、
「学ぶ」とは何か? について、
じつはあんまりわかっていない。
「学ぶ」って、たとえば、
テキストや参考書で記されている
語句や知識を覚える、
だけにとどまらない、とは思っている。
けれど、それ以上は、
どういうことがあるのか?
ってゆうのは、うまく言えないの。
「頭が良い」という言い方もあるけれど、
たとえば、テキストの知識
大学の「図書館」の隠し部屋。
このごろはさ、先日読み終えました
内田樹さん著『複雑化の教育論』を読みながら、
教育のこと、そして、ぼく自身の
大学生のときのことを考えていた。
『複雑化の教育論』の冒頭では、「学びの場」として、
大学の「校舎」のことが書かれていて。
内田さんが勤めておられた神戸女学院の校舎は、
ウィリアム・メレル・ヴォーリズという建築家の設計で、
この校舎とは、配慮と、居心地のよさと、
ミステリアスさが兼ね備
「卒業論文」と「後輩」について。
前回noteでは、大学生のころのぼくは、
ダメ学生ではあったけれど、それでも、
全く何も学んでいなかった、
というわけでもなかった。
みたいなことを書いたのですが。
かと言っても、それでもやっぱり、
じぶんはいろいろダメ学生で、
そのなかでも、いちばんダメだった、と、
今でも思い出すと、申し訳ないと思うことがある。
それは、卒業研究のことでして。
卒業研究ではさ、昨日も書いたのですが、
先生の
お豆富と失敗と工夫について。
先日のブログでは、
大学生のころのぼくは、勉強もせず、
だらだら過ごしていたようなダメ学生だった、
というのを書いたけれど。
とは言ってみても、当時4年間の大学生活の中で、
まったく何も学んでいなかったか、というのは、
そうではなかった。って思っている。
たとえば、
建築学科だったぼくは、1年生のころかな、
「建築構造」の授業のときに、
先生のおっしゃっていた
「人間は、豆富のようにやわらかい。
「何をもって憶えられたいか」と「受動態」のこと。
さくじつのブログでは、
「何になりたいか」的なことを、
あらためて考えていたら、ふと、ドラッカーの
「何をもって憶えられたいか」
ということばを思い出したことを記しました。
「何をもって憶えられたいか」
ということばとは、
ドラッカー著『非営利組織の経営』や、そして、
上田惇生さん著『ドラッカー入門』等でも、
書かれているとぞんじますが。
『非営利組織の経営』より引用を申しあげますと、、
‥‥