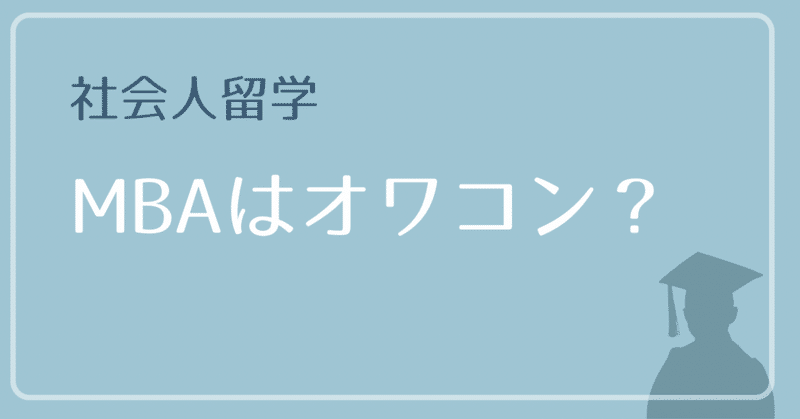
パート②「オワコン」と散々聞いていたMBAに40歳を過ぎて行くことにした理由を整理してみました。MBAでないと達成できないこととは。
前回、パート①では、いまの自分の課題感について書きました。
今回は、それが「MBAでないといけなかった理由」につながるまでの話です。
カリキュラム(学びの話)
わたしは20代の頃から、いつか大学院に戻りたいと思っていました。MBAではない、大学院です。人事系か教育系で学びたいと思っていました。
でも、その頃は金融でフロント(収益を生む部署)におり、かけ離れた業務をする中で、具体的に、大学院で何を掘り下げたいのか定まらず。それ以外にも、結婚・出産など控える中、実際に行動に移すまでにはなりませんでした。
そして今回。色々なタイミングがあい、「そうだ、大学院に行こう!」とようやく大学院計画が始まる。
大学院を調べていくと、確かに面白そうなプログラムはたくさんあります。でも、どれも、インスピレーションに響かなかった。
(わたしの決断の思考回路として、決めるまでは色々ロジックで考え、調べるのですが、最後は直観で決めるタイプ。心に響かないと絶対に行動しないタイプです。イメージ、「せっかく色々事前に調べるくせに、最後は衝動買い」みたいな感じ。頭と心で違うことを考えていて、最後は必ず心でいく。行動と心はつねに一致しており、気持ちとの矛盾が少ないので、比較的、ハッピーに過ごせるタイプだと思います。時に「自分勝手」と言われるリスクを背負う。)
確かに、プログラムとしては面白い。でもなぜ自分には響かないんだろう?
そう考えた時、1つの仮説は、「1つに絞りたくないから」でした。
人事系、教育系のプログラムは、中にはそのまま博士へいく人もいくような、アカデミックで「深掘り系」なものが多い。実践というよりも、いかにも「学校」という感じで、専門性を磨くイメージです。
もちろん、それがいいところでもある。学問にどっぷり浸かりたい気持ちもあるので、それに惹かれる部分もありました。
でも、なぜいくんだっけ?と目的に立ち戻ると、「卒業した後にどうしたいのか」に行きつく。
とくに、大学院だと、論文を書く必要がありますが、書きたい内容がなかった。
勉強はしたい。色々深めたいテーマはたくさんある。でも1つ絞れと言われると、なんだか違う。
全身全霊を捧げたい、特定のテーマがあるわけではない。
とすると、この勉強したいという気持ちはなんなんだろう? わたしは何を勉強したいと思ってるんだろう?
この漠然とした「勉強したい」「大学院に行きたい」という気持ちを掘り下げたとき、1つの結論に辿り着きました。
わたしは学問に浸りたいわけではない。ビジネスに身を置き続けたいんだと。
しかしここで、もう一つの迷路に入ります。
世の中には、学問系ではなく、ビジネス系の人事向けプログラムもたくさんあります。それこそ、組織論、リーダーシップ論、制度設計など、人事の専門を磨けます。
そういうのも学びたいし、もっと深掘りしたい。
でも、それとも、何かが違う。
それは最悪本を読めば済む話だし、日本で仕事をしながら、近くの大学院に通うか、3ヶ月とかの集中コースだっていい。
そうではなく、わたしは学校に行きたい。そして卒業後はビジネスに戻りたい(企業人に戻るかどうかは別として)。
そうすると、その得た知識を「どう使うのか」も深めたいし、使うためには自分自身の幅(リーダーシップスタイルなど)を広げる必要がある。
知識だけでなく、自身のビジネスパーソンとしての成長も大きな目的の一つになる。
そうなってくると、ただ人事のことだけを学びたいわけではなくなってくるし、人事の人たちと集まって1年間過ごしたいわけでもない。
そもそも、このままずっと人事「だけ」でいくつもりも全くない。
人事はつねに自分の軸になるだろうけれど、「人事の専門」を突き詰めることは、少なくともここ数年の自分のワクワクではなかった。
だから、うまく言葉にはできないけれど、学問系だろうがビジネス系だろうが、「人事のプログラム」にいきたいわけじゃないんだ。。。
だとしたら、私に合ってるプログラムは何なのだろうー!
(この状態で、実は3ヶ月くらい迷走し、とりあえずMBA、学問系、人事系、の願書をほぼ同時進行で進めていました。)
学問とビジネス、両方の切り口で悩む中、同時に、学問の世界とビジネス世界の、大きなギャップや、その関わり方の違和感を感じていました。
人事の世界にいると、人間の行動心理や、リーダーシップ像など、学問の世界とビジネスの世界は、切っても切れない。
学問ででた結論や提唱が、ビジネスの世界に投げ込まれる。そうすると、それに、わーっと、みんなが飛びつく、群れる。メディアも、そういうキーワードが好きで、同じようなキーワードが「はやり」のように使われる。ネットは、そういうインタビュー記事で溢れる。
人事は、「それ」を、「それっぽく」語れることが求められ、一度社会的に受け入れられてしまったものは、疑問を投げかけることも、難しくなる。
疑問を投げかけるまで行かなくとも、単純に「ちゃんと理解したいから」という理由で基本的な「そもそも論」なことを質問をすると、「人事なのに、この考えに賛同できないんですか」でもいうかのような反応で、ものすごいセンシティブ。
いや、そういうことじゃない。ただちゃんと自分が理解して、咀嚼できた方が、現場でどのように活用できるのか、影響できるのか、分かるから。だから知りたい。向かっている方向は同じはず。
こちらは、ただ、もっと知りたい、と思っているから質問をしているにも関わらず、知りたい=疑っている、と防御的に受け止める人が多いことに気がついた。
「一般的にこう言われているんだから、それでいいじゃない。なぜそれをわざわざ疑うの」と。
もっと面倒なのが、そこに、「人事なのに」という、のにのにがつくこと。
いや、人事「なのに」でなく、人事「だから」こそ、でないのか。人事が、自分の言ってることの論理や根拠を理解しておらず、それっぽく語ることこそ、無責任だし、世間体の横流しでないのか。
このやりとりを何年も、やってきて、みてきて、やっと気がついた。
あ、もしかして、世の中には、そこまでちゃんと掘り下げて発言したいと思っている人ばかりではないのかもしれない、と。
「あの偉い人がそう言ってるんだから。Googleがそう言ってるんだから。それでいいじゃない。なんでそれを疑うの?」
(しつこいですが、こっちは疑ってるわけではなく、ただ知りたいだけなのですが。。)
以前、ファッションの「今年のトレンド」ってどうやってできるのか、詳しそうな人に聞いてみたことがあるのですが、「あれはブランドが作ってる」と。
誰かが「今年は緑だ!」といえば緑だし、誰かが「今年はロングコートだ!」といえばロングコート。毎年トレンドを変えることで、毎年買ってもらえるから。
結婚指輪はダイアモンド、バレンタインはチョコレート、というように、企業のマーケティング戦略に消費者が乗っかってる結果だよ、と。
とすると「なんで今年は緑なんだっけ?」と考えてもあまり意味はないかもしれない。
「でも緑ってこういう風に、いいよね、こういう緑もあれば、こんな緑もある。こういう時は、この緑がいいんじゃない?昔は、こういう緑も、はやった。それにはこういう歴史的な背景があって。お年寄りはこういう緑が好きだけど、若い人は、こういう緑が好きな傾向がある。こういう場面では、この緑が合うんじゃないかな。」
こんな風にトレンドに流されずに、自分の軸を持った上で、取捨選択し、組織や環境にとって最適と思える施策を提言し実行できるようになりたい。
そのためには、何か人事テーマを一つ掘り下げるのではなく、人事×ビジネスの、掛け算と、その見せ方、その裏側など、単なる学問としてではなく、ビジネス視点の実践で、人事を「解体」して、咀嚼して、自分なりに「組み立て」直したい。
すると、そこでもう一つの壁にぶち当たる。
提言し、実行できるようになったとして、人事を組み立て直すとして、そもそも人事の存在意義は何なのだろう。
各論では、採用、教育、DEI、労務など挙げられる。それは良い。でもそれはあくまで機能であり、存在意義ではない。別の言い方をすれば、手段であって、目的ではない。
一つずっと不思議なことがある。
世の中には人事コンサルという職種がある。戦略コンサルの一種で、男性が多い。当然だが、事業として成り立っていて、収益を上げる。給与もそこそこ高い。れっきとしたビジネスだ。
一方で、世の中の企業人事は、一般的には管理部門と言われる。男女比率も女性が圧倒的に多い。外資では、収益は上げずに人件費だけかかる部門なので、コストセンターと呼ばれることもある(人事に限らず他のバックオフィス全般的に)。
わたしは、企業人事は、企業の内部コンサルだと思っている。内部営業から始まり、提案、そして執行。執行まで自分たちでやるので、外部コンサル以上の責務だと思っている。と言うか、思いたいし、そうあるべきだと思っている。
内部の業務なので、収益は上げないが、外部コンサルへの委託料の削減に検討したと言う意味で、結果的に利益に貢献しているともいえる。
何をコンサルするのかと言うと、それは単刀直入に、ビジネスの成長。
ビジネスが成長するために何が必要なのかを見いだし、たまたまそれが人事の領域なら、人事がやる、という思考。見つけたペインポイントが、例えば人事ではなく経理の領域なら、経理がやる。それだけのこと。
人事だからダイバーシティを提唱しなきゃ、という思考は、私から言わせれば順番が逆なのだ。
ビジネスの成長のために、例えばダイバーシティが必要なら、それは人事の専門ですね、では人事がやりますね。というのが、あるべき順番だと思う。
自社の成長、ビジネスの発展のために何ができるのか、ビジネス思考で人事も考えなくてはいけない。だから「社内コンサル」だと私は思っている。これは、いわゆる「人事ビジネスパートナー」と呼ばれる、外資では当たり前の人事のあり方でもある(必ずしもできているとは限らないが)。
にもかかわらず、人事は事務、と言う印象が世の中には強くある。海外でもそうだが、日本は特にそうな気がする。
確かに、労務など事務系の仕事はある。でもそれは一部で、本来は事業の成長に直結した成果を出すことが、人事にも求められ、人事にある社員もそう言う意識を持たないといけないと思っている。
にもかかわらず、この現状との差は、なぜだろう。。
そう考えた時、1つの結論を改めて「思い出した」。
人事にいると、「人事は何をすべきか」に頭が行きがち。でも本来必要なのは、ビジネスに何が必要なのか。あくまでその結果、初めて人事が何をするのか。
人事がしたいことをするわけではなく、耳触りの良い旬なキーワードを叫ぶのではなく、あくまでビジネスに必要なものを人事は提案し、動く。
それは十分理解していたつもりだったが、長年ビジネスを離れて、すっかりわたしも人事にどっぷり浸かってしまっていた。
今わたしに必要なことは、人事を深掘りすることではなく、ビジネスという土俵の上で、今後どう戦うのかという、戦略と方向性だ。
だから、私は、今回学校に行くことで、人事としての学びというよりも、ビジネスパーソンとして、収益部門やビジネスサイドのシニアメンバーと、対等に議論し、ビジネスマインドで、人事課題やバックオフィスの課題を考えられるよう、自分を鍛え直したい。
そう考えた時、あれ、これって、もう完全にビジネススクールじゃない…?と、ストンと自分の中で全てが腑に落ちた。
だからこそ、人事系の大学院ではなく、MBAなのである。
学問の世界に入った上で、ビジネスとのギャップに取り組むことも少し考えたが、学校に戻る時点で、半分は学問に足を突っ込むのと同じなので、であればもう片足はビジネス側(つまりビジネススクール)に置いておいた方が、両方との接点が持てて良いのではないか、と感じたのも、最終的にビジネススクールを選んだトドメだった。
ネットワーク(人の話)
ネットワークも、カリキュラムの話に似ている。
人事同士のネットワークは大切。でも私は、あえて多種多様なビジネスパーソンと切磋琢磨したかった。人事にどっぷり浸かるのではなく、ビジネス視点での交流を経て、自分なりの「人事」「バックオフィス」のあり方の落とし所を見つけたい。
ほかにも、起業家、エンジニア、マーケター、教育関係者、福祉関係者など、自分とは全く違う専門やパッションを持った人と交わることで、自分の中での色々な「掛け算」の発想が広がることも期待している。
また、今回通うプログラムは、15-20年の社会人経験があり、経営者、管理職などそれなりの立場の人がメインだ。彼らのグローバルな経験と実践から学べることは、計り知れない。
これら全て、人事系のプログラムでは得られない、クラスメイトからの学びになると期待したい。
「あえての」このタイミングでいくMBA
これは、実は完全に後付けで、色々な人生計画の中で、結果的に、たまたまこのタイミングになったのだが、今となっては、むしろこのタイミングまで「待って」良かったと思う。
ビジネスサイドでやっていきたい人は、MBAで学ぶ内容が、すぐに活きる場面もあるかもしれない。だからこそ、行くなら早めの方が良い気もする。
一方で、人事の道で進みたい自分が、もっとキャリアの早いタイミングでいってしまっていたら、頭でっかちになったり、ビジネスの一般論で終わってしまったり、そもそも何を学んだら良いか分からず、とりあえず満遍なく学ぶ、と言うことになっていた気がする。
また、MBAという発想にならずに、おそらく人事系の大学院に行っていたと思うので、今とはまた違うキャリアになっていたと思う(それはそれで、どうなっていたかは良くも悪くもわからない)。
人事のキャリアがある上でのMBAにいくことで、なぜ学ぶのか、何を学ぶのか、が明確で、単なる就活のためとか学位のためでなく、自分の中に残るものにできるような気がする。
なお、「なぜMBAなのか」の回答にはならないが、子供を連れて行けるのも、費用対効果に対してかなりメリットになっている。
正直、自分の学びのためだけだったら、わざわざ大金をかけてアメリカのMBAにはいかなかったかもしれない。
子どもに、生の海外生活を体験してもらえるのも、この年で、子どもがそこそこ大きくなっているからとも言える。
だとすると、MBAはなぜ「オワコン」と言われているのか
いざ自分が行くことにして、これが逆に不思議になったので考えてみた。
プログラムとしては、かなり良きものだと感じるため。
日本以外の事情は知らないので、あくまで日本に限ったことになってしまうが、いくつか仮説がある。
仮説①
JTCからあまりにも多くの企業派遣がされ、しかしその方々のその後の活躍に関しては、そこまで派手には語られない中で、日本の不況が続き、なんで社費派遣してるんだっけ?と言う平成のイメージだけが残ってしまった?
(例えば、リクルート卒とかGE卒の方は、ビジネスの世界でも目立って活躍している人が多いので、なんだかすごい会社なんだろうな、という漠然とした印象を持つが、MBA卒だからさすがのご活躍ですね、みたいな話はあまり聞かない?)
MBA卒の方が活躍してない、と言う意味では全くなく、単にあまり耳にする機会がない、という意味です。
仮説②
20-30年前は、今でこそ有名な外資系企業も、まだまだ日本に進出したばかりで、新卒採用も大々的にはしていなかったため、入るなら中途採用→つまりはJTCから企業派遣されたMBA卒業生がメインだった。
しかしその後、新卒でも普通に東大などから入社できるルートが確立されると、かつこれら企業は新卒入社の社員をとても大事にするので、社内の勢力図的にも、MBA卒で入る方より、新卒で入る方が主流になった。新卒の方が活躍すると、MBAって必要なくね?と言う感覚が広がった。正しいかどうかは別として。
(少なくとも、外資金融に身を置いていた自分としては、これが一番しっくりきている仮説です。)
仮説③
アメリカの学費の高さが全般的にここ数十年で半端なくなり、例えMBAが良いものだったとしても、そこまでの大金かけて行く価値あるの?という、費用対効果でのオワコン感覚が広がってきた。
色々な理由が考えられますが、いずれにせよ自分が何を学べるかの話だと言うところに尽きます。
現時点での自分の知識だけで言うと、かなり濃いプログラムなのではと期待はしていますが、「本当にオワコンだった」可能性は、全然あるとは思っていて、まずは自分で行って確かめてみたいと思います!
🌷ここまで読んでくださりありがとうございました!🌷
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
