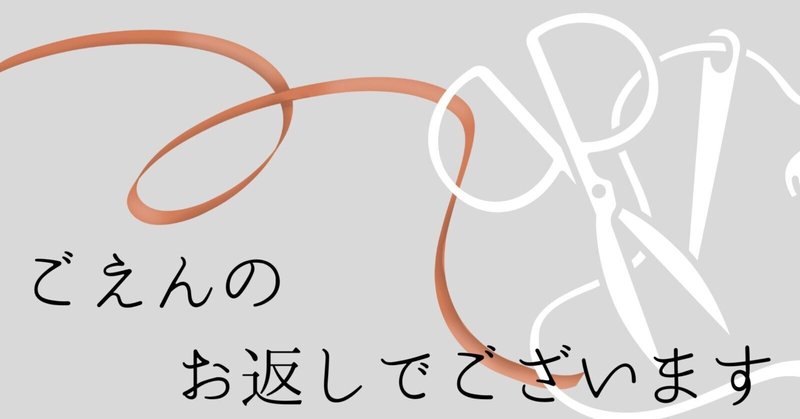
「ごえんのお返しでございます」2話 紅薔薇、白百合⑥
病院へ行こうとした僕のもとに、着信があった。相手を見て、バスに乗る前でよかったと思う。
電話に出なかったら、機嫌を損なうことになる。そうなれば、今度電話をくれるのは、いつになることか。
以前、怒らせて、長期間連絡が来なかったときは、姉が倒れているのではないかと、やきもきした。
最近は、美空の見舞いや糸屋の監視で忙しく、あまり気に留めていなかった。
「もしもし、姉さん?」
くぐもった声で応答があった。目の前の車道を走る車の音にかき消されてしまうくらいの小さな声に、何度か聞き直したところで、要領を得なかった。
ここで勝手に「切るよ? いい?」とやってしまえば、姉はいじけてしまう。女子というのは、えてして扱いが難しいものだ。
そう思い出すのは、美希のことだった。
同じ顔をした双子の姉妹のことを、「最低最悪」と罵るその心の内は、いかほどか。
他のことを考えていることは、なぜか電波を通じて姉にすべて伝わってしまう。
紡、何考えてるの。
さっきまで不明瞭だったのに、やけにはっきりと届く声。
導火線に火がつく限界まできていることを察して、僕はとっさに、
「リボンをもらうなら、何色がいい?」
と、最近頭の中から離れない問題のアドバイスを求めた。
リボン? なんのために?
「そりゃ……髪をまとめたり、とかさ」
そんな古風なこと、イマドキしないわよ。
女ってリボンやフリルが好きなんじゃないのか? 美空はいつも、お姫様みたいなパジャマを着ているし。
美空は、僕が遊びに来てくれるだけでいいと言う。実際、病室に持っていける見舞いの品は、たかが知れている。病人に、自分の勝手で食べさせるわけにもいかない。
これが篤久だったら、毎週週刊少年ジャンプを手渡せば、事足りる。女の子へのプレゼントって、難しい。
僕の頭を最近支配しているのは、美空への見舞いだけだ。
糸屋にいるときも、何かあげたいなあ、という気持ちでいた。僕の目に入ったのは、色とりどりのリボンだった。柄がついていたり、キラキラしていたり、唯一店の中で楽しいアイテムである。
美空は基本的に、いつも長い髪を下ろしている。ベッドの上で過ごす時間がほとんどだから仕方ないだろうが、もったいないなあ、と、常々感じていた。
顔がそっくりな美希は、学校によく、派手なヘアアクセサリーをつけてやってくる。校則はゆるいから、注意はされない。
先生も、「今日もキラキラだなあ」と、やんわりと授業前に言うだけだ。怒っているわけじゃない。
髪を結んだときのうなじや、ちょろりと垂れる後れ毛は、ときにセクシーで、入学したての頃の僕の目を惹きつけた。
美空のそんな姿も、見てみたい。
きれいなリボンを贈ったら、その場で髪をまとめてくれるだろうか。
「まぁ、どうでもいいじゃん。何色?」
姉はしばらく考えた末に、赤、と応えた。
その心は、運命の赤い糸みたいでしょう、だった。
その日は、美空の体調が悪くて会えなかった。母親が来ていて、「ごめんね」と言ったが、謝ってもらうような話でもない。お大事に、で帰って、それから三日後、再び僕は彼女のもとを訪れた。
美空はベッドに腰掛けた状態で、スマホを弄っていた。開いたままのドアをコツコツとノックすると、こちらを向く。パッと明るい笑顔になる。
「紡くん!」
片手を挙げて、入室する。頬には適度な赤みがあって、無理はしていないようだと判断する。
「今日は体調、よさそうだね」
「うん……」
おや、と思った。返答に元気がない。
「美空さん?」
ハッとした表情で、彼女は苦笑した。本音を滲ませた小さな溜息に気づかれたことを恥じらっているのか、長い髪の毛先を指にくるりと巻いて、きゅっと引っ張っている。
「今日は元気でも、ね。明日はどうなのかわからないし。もしかしたら、一年後には……」
窓の外を眺める。三階ということもあり、枝の先が見えている。あまり背が高くないこの木は、桜の木だ。
青々と繁る葉の形から判断したわけじゃない。ただ、僕自身が姉のかわりに病院に通うようになったのが、春だった。その光景をありありと思い出した僕は、彼女の言わんとしていることを察した。
来年の桜を、見ることができるかどうか。
視線の先、彼女は淡い色合いの花を幻視している。
大丈夫だよ。絶対治るよ。
無責任な慰めの言葉は、胸の内に堆積する。そのまま腐らせてしまった方がマシだ。
口にしたときの彼女の反応を、予測することができない。「ありがとう」と、微笑むのか。それとも、「あなたに何がわかるっていうの!」と、怒りをむき出しにするのか。
医者ではない僕ができるのは、何も言わず、神妙な顔をしてみせることだけだった。
しばらく窓を眺めていた美空は、ふとこちらに目を向けた。
「ねぇ、紡くんのバイト先って、赤い糸を売ってるんだよね?」
「う、うん」
ドキッとした。赤い糸、だって?
彼女の顔をまじまじと見つめ返す。その表情が示すところは、明らかだった。美空は、紡が働いている店が、都市伝説のあるいわくつきの店であるということを、知ったのだ。
「私、病院からは出られないから。だから、紡くんに代わりに買ってきてほしいんだけど、いいかな?」
「……赤い糸を?」
小首を傾げておねだりする仕草は可憐だった。願い事をなんでも聞き入れてあげたくなるほど。
だが、赤い糸を買ってきてほしいという頼みは、僕の心情的に叶えたくない。いったい誰と縁を結びたいのか。この病院で会ったのは、濱屋姉妹の両親だけだ。僕以外にも通っている男がいて、美空はその男に恋をしているのか。
「だ、誰と?」
上擦る声での問いかけに、美空はきょとんとしたのちに笑った。からかいが混じっている声色に、僕は青くなる。
やっぱり他に、男がいたんだ。
「やだぁ。美希ちゃんともっと仲良くなれるように……っていうおまじないだよ」
なんだ。
どっと肩から力が抜ける。
縁=恋愛と結びつけるのは、短絡的だ。有名な縁切り神社には、ブラック企業から抜け出したい人たちが書いた絵馬で溢れているのだと、前にニュースで見たことがあったのに、つい。
あからさまに安心した顔、ひょっとすると間抜けな顔をしている僕に、彼女はいよいよ笑いが止まらない。
「私、男の子の知り合いなんていないよ。紡くんだけ、特別」
特別。スペシャル。いい響きだった。
ふっと表情を改めて僕を見つめる美空は、どこか儚げで、透明だ。無垢な彼女は、どこまでも白い。
純白でできた少女を彩るのにふさわしいリボンは、やっぱり。
「ね、お願い。赤い糸、私のために買ってきてほしいの」
篤久のこともある。僕は一瞬、やめた方がいいのでは、と戸惑う。
けれど、美希と美空は家族だ。恋愛沙汰じゃない。篤久だって、美希ひとりを対象にしていたときは、うまくやっていたじゃないか。めったなことは起きないだろう。
僕は請け負った。赤い糸で姉妹の絆を結ぶという大役を、胸を張って。
美空は「さすが、紡くん」と褒めてくれる。僕の両手を握りしめ、「絶対、絶対だよ!」と念を押してくる。
美空の手は小さくて、すべすべとしていた。離れていくと、名残惜しくなってしまう。
赤い糸を渡すときにも、もう一度握ってくれないかな。
いただいたサポートで自分の知識や感性を磨くべく、他の方のnoteを購入したり、本を読んだりいろんな体験をしたいです。食べ物には使わないことをここに宣言します。

