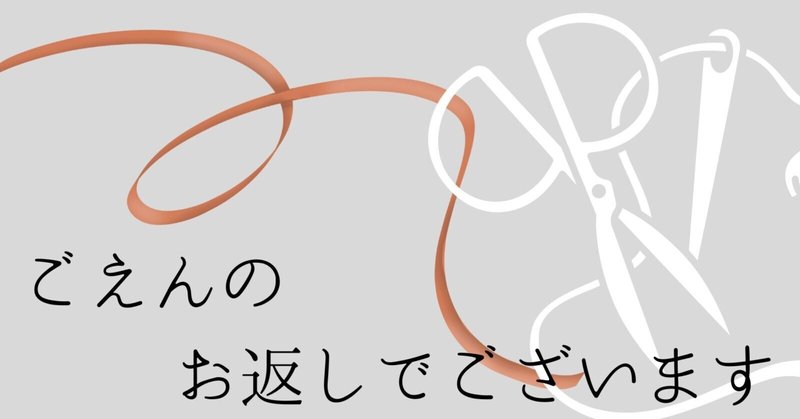
「ごえんのお返しでございます」2話 紅薔薇、白百合⑤
とうとう、見つかってしまった。
「あれ、紡くん?」
総合玄関から入って西棟へ向かう途中、冴木医師に声をかけられた瞬間、足が竦んだ。
「今日はどうしたの?」
医者だから、なのか、彼だから、なのか。冴木は僕のことを上から下まで観察し(なんなら目をライトで照らされそうにすらなった)、どこも悪いところはなさそうだ、と首を傾げた。
別にやましいことはしていない。なのに、彼への苦手意識が、自然と手を前で組んで、腹をガードする姿勢をつくる。
そっぽを向いて、「友達の見舞いです」と一息に言えば、一度は「ああ」と、納得してくれた。
しかし、すぐに思い直して、
「でも、篤久くんのところは面会謝絶だし、それにこっちじゃないよね」
と、さらなる追及をしてくる。篤久のことを忘れていた自分に、少しショックを受けた。
結局僕も、友情より恋を取る男だったということなのか。
無言でいるのも居心地が悪い。冴木は僕の返答を待っている。
「篤久以外にだって、友達はいます」
視線を外してぼそぼそと言う僕とは対照的に、彼はにこやかだった。
「そうかぁ……女の子?」
まったく、精神科の医者というのはこれだから。なんでもかんでも知りたがり、質問をよこす。
思わず睨みつけて、「先生には関係ないでしょう」と言えば、彼は両手を上げた。
「そうだね。ここは診察室でもなんでもないし……君がお姉さん以外に仲良くできる女の子がいるとしたら、僕が嬉しいっていうだけだよ」
確かに、僕の交友関係は狭い。親友は篤久しかいないし、そのほかは一言、二言喋ればいい方。両親とは食卓をともに囲んでいても会話はほとんどないし、女の子で友達といえる存在は、生まれてからこの方、いたことがない。
「仲良くね」
それだけ言って、冴木はひらひらと手を振り、西棟へと向かった。僕はぼんやりと見送って、ハッとする。時間をロスしてしまった。
美空の身体のことを思えば、長時間無理をさせるわけにはいかなかった。病院内を走るわけにいかず、早歩きをした。
病室に着いた僕を待っていたのは、第二の試練だった。言わずもがな、第一の試練は冴木医師である。
彼女のベッドの傍に立っていたのは、中年の男女。年頃からいっても、美空と美希の両親にちがいない。
突然の親との遭遇に、僕は一度固まった。
いやらしい気持ちを態度に表していたわけじゃない。堂々とすべきだ。
気を取り直して、会釈をした。
「またあとで、出直します」
家族の団らんの時間を邪魔することはせず、退出しようとした僕を止めたのは、美空だった。
「待って。別にいいよ。もうすぐお父さんたちも帰るから。ね?」
娘に早く帰れと言われたも同然の父は、苦笑しつつもうなずき、それからこちらを向いた。
「美空の父です」
「あ……切原紡です。美空さんとは、その、仲良くさせていただいています」
こういうとき、どうしたらいいのかわからない。
とりあえず笑ってみた。笑顔をつくるのは上手じゃなくて、媚びへつらうみたいになっていないか、不安だった。
そんな内心が出ていたのだろう、父親は、「まぁそんなに硬くならずに」と、言ってくれた。
「切原くん、その制服……」
美空の母は、めざとく尋ねてきた。嘘をついたりごまかしたりする必要もなく、「はい。美希さんのクラスメイトでもあります」と、僕は応えた。
「美空さんと初めて会ったときは、びっくりしました。美希さんと同じ顔だったので……」
自分が精神科に通っているということは、言わなかった。姉の代理とはいえ、印象がよくない。美空の両親が受ける僕の印象は、好青年であってほしい。
イメージのことを気にするなんて、僕らしくもない。
朗らかに笑って雑談をどうにかこなした僕に、ふたりは頭を下げて出て行った。
「これからも美空のこと、よろしくお願いします」
と。
「いえ、こちらこそ」
僕も深々と頭を下げて、イーブン。最後まで見送ってから、肩の力を抜いた。背後からは、忍んだ笑い声。美空だ。
「美空さん」
「ん、ごめんね。紡くん、無理してるなあって思ったら笑えてきちゃって」
クスクスと、口を両手で覆い隠して笑う美空は、病気がちで他人との交流を十分できなかったせいもあるのか、子どもっぽいところがあった。ずっと笑いが止まらない彼女を見ていると、僕の唇も、次第に震えてくる。
「ぶはっ」
とうとうこらえきれなくなって、噴き出した。すると、美空はさらにけらけらと声を上げる。
僕たちはひとしきり笑い合った。僕の胸の中には、美空へのあれこれの気持ちが浮かんでは消えていく。シャボン玉みたいにキラキラと輝いた想いの泡に触れると弾け、優しさが広がっていくのだった。
「ねぇ、ちょっと」
名前すら呼ばないあたり、不機嫌さが丸出しだ。自分の機嫌は自分で取れって、昨今よく言われているが、実践する気は皆無だ。
気分が悪いのは全部、誰かのせい、僕のせい。
焦らしはさらなる激高を生む可能性があるため、諦めて振り返る。
せめて、教室にたどり着くまで待てなかったかな。
「どうしたの、濱屋さん」
僕のことが気に入らないのに、どうして話しかけるの。
彼女は周囲を注意深くうかがった。そんなに僕といるところを見られるのが嫌なら、人の少ない時間にするとか、考えればいいのに。無策のまま行動に移して、困るのは自分の方なのに。
少々辛辣になるのは、美空の方が大事だからだった。
篤久に恋愛相談をもちかけられたときは、「濱屋さん、可愛いもんなぁ」と思った。あのときは僕も、ほんのりと美希に憧れていた。
しかし、美空の存在を知った今、彼女とは似て非なる美希のことは、割とどうでもよくなっていた。
「あんた、病院であの子に会ってるって……」
ああ、この間、両親に会ったときに口止めするのを忘れていた。
舌打ちをしそうになる。美希が親の仇を射殺しそうな目で、こちらを見ている。あまり刺激するものではない。野生の勘が、そう訴えている。
美少女と名高い美希に、こんな顔を向けられるのも、自分くらいじゃないか。
ギラギラと粘つく視線には、憎しみがこもっているような気がする。手負いの獣の眼だ。相対するものすべては敵で、ほんのわずかに怯えも混じっている。
僕はなるべく淡々と聞こえるように、言葉を紡いだ。
「学校で話をするなとしか、言われていないから」
だから、病院で僕が誰と交流しようが自由だし、美空も同じだ。姉妹だからといって、美希にどうこう言われる筋合いはない。
ここで声が震えたら、つけいる隙を与えることになる。罪悪感を抱いていると勘違いされては困る。
「個人で仲良くするしないは、君には関係ない」
正論で追い打ちをかけた。案の定美希は、歯噛みして悔しがっている。他人をコントロールできるものではないと、知っているのだ。
「それだけなら僕はもう教室行くけど……濱屋さん」
「……なによ」
ぎゅっと握りしめた拳。丸まった背中。ちっぽけな彼女。
「どうしてそんなに、美空さんのことが嫌いなの」
そんなことを聞かれるとは思っていなかったのだろう。彼女は顔を上げ、目を見開いていた。絞り出した声は、低くて小さい。
「あいつは、最低最悪な奴よ」
そういう彼女の方こそ、醜悪極まりない顔をしている。
いただいたサポートで自分の知識や感性を磨くべく、他の方のnoteを購入したり、本を読んだりいろんな体験をしたいです。食べ物には使わないことをここに宣言します。

