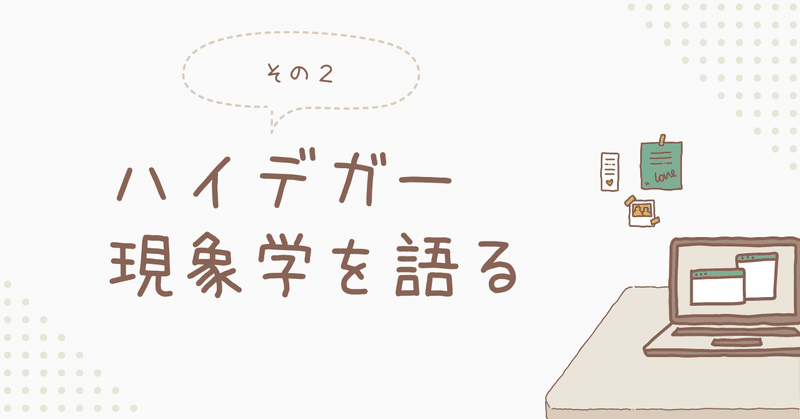
ハイデガー、現象学を語る その2
3. ハイデガー、少年の恋の仕方を語る
(下の続きです)
少年のような恋をしたい。
いつもそう思っている。
小学校6年のとき、絵本を読んだ。子供がお母さんに質問をする。
「お母さんはお父さんのこと、本当に好きなの?」
「大人になると、そういう気持ちはなくなるのよ」
「大人になると、女の子を好きだと思わなくなっちゃうのか」
「なら僕は、一番好きな⚪︎⚪︎ちゃんと結婚しないことにした」
「好きじゃなくなっちゃうなんて嫌だもん」
ハイデガーは現象学を「なにか立ち現れてくるもの」を観察する学問と語る。
出会った瞬間、あの子に立ち現れてくる何かを感じた。
だから恋に落ちた。
恋だけではない。
夏の祭り。
秋の道に落ちているどんぐり。
夕暮れのサイレン。
いつかの朝食。
母の味噌汁。
蜃気楼のように立ち現れてくるもの。大人になるにつれ感じなくなった。
4. 現象学の本質
フッサールは、現象学の本質を
「ものそのものへ」 "To the things themselves!!"
とした。存在の本質は、目に見えているものでなく立ち現れてくるものにある。
ハイデガーの『存在と時間』の解説を著したH.ドレイフェス。
彼は「存在は相似物」だと語る。
「桜・松・杉から木」
「木、草、苔から植物」
「植物、生物、物質から存在」
「存在は究極の抽象物だと捉えられるが、そうではない」
「類推や相似、寓喩物である」
神に似せて人は作られた。存在は客観的な何かではない。
世界とは見えるものだけれど、それでも僕たちは、世界を見ることを学ばねばならない。

遥奈さんの詩を思い出す。
「夜の新幹線って綺麗だな」
真っ暗な田舎の夜を光が駆け抜けていくんですよね。
どこか遠くへ行くんだろうな
その行き先とかは別にどうでもいいのに、
「今、この世で一番綺麗なものが
遠くへ離れていっちゃうんだ」
と思わず感じたんですよね。
”刹那”って言うのかな、こういうの、わかんないな
でも「綺麗だな」って感じてる時
みんなこの一瞬の中にしか生きてない気がするんですよね。
現象学は、会話を促すためにある。
近代を動かしてきた因果論をハイデガーは否定する。主従関係を導き、争いを誘発し、会話を許さないからだ。
因果論と対置するものに縁起論がある。二つの根本的な違いは、同一と相違だ。

因果は自己と他者を同じと捉え、手足を動かすように指示可能だと考える。
縁起は自己と他者を違うものとする。人に指示することも相手を解明することもできないが、傍にいることはできる。そう考える。
5. hurly-burly
ウィトゲンシュタインはこう述べている。
「判断、反応や態度を決定づけるものは、法則や論理ではなく、激動や無秩序な爆発の総体(hurly-burly)である」
と。
人は会話や感覚、イメージによって行動するのであって、合理的な判断には寄らない。合理で人が動機づけられるなら、学生はみな東大に入ろうと躊躇なく勉強に取り組むだろう。
「解明するのではない」
「受け入れることだ」
「難しいとしても」
ウィトゲンシュタインは、hurly-burlyをシステム化、理論化することに強く反発した。
人は会話し、受け入れられたと感じたとき行動する。合理性にもとづいて動くわけではない。
学校とて同じである。合理的だから学び始めるわけではない。
最先端を走るとされる哲学、「正統的周辺参加」でも会話せずコアを掴もうとする学びを否定する。ワークブックの学習は実践では役に立たない、として。行為につながらないからだ。

正しさを掴もうとする学びは、常に軋轢を生む。会話やhurly-burlyによる学びは、一見遠回りに見えるが永続する。
超短期決戦に見える大学受験ですら、3年ものあいだ学び続けねばならない。他者に否定され、自ら納得もせず続けることは困難を極める。
良い環境にいる生徒が良い成績を上げると言われるのはそのためだ。会話がある場所には永続的な行為がある。その会話は、一見無駄なものでなければならない。
6. 意味は縁から生まれる
合理主義では、人の存在意義や人間関係の文脈を考慮できなかった。人生の無意味さに我らは抑圧される。アドラーが語るように「すべて悩みは人間関係の悩み」で、「すべて喜びも人間関係の喜び」であるのに。
『存在と時間』の原題は、"Sein Und Zeit".
「存在」を意味するsein(ザイン)の語源は、「何かの傍らにとどまるもの」だ。
因果のように直接影響を与えるのではなく、隣人の傍にとどまる。会話が生まれ、「立ち現れるもの」を感じ取る。
神話や音楽、愛や妖の類もこうして生まれる。
事実でなく解釈が必要になる。神話や音楽を作るには。また、人生の意味を知るにも。ゆえにハイデガーの現象学は解釈学的現象学と呼ばれる。

ハイデガーは、法則や原理を否定した。日常的な技能、実際的な知識、実践こそが人を社会化し、主体となり人生を理解するために必要だと考えた。
「上手く行かないこと」「苦闘」が生活のメインである必要がある。
推定とか計画とか予想に間違いがないと考えてしまうと、内省しなくなってしまう。
なにより、実践に真剣味がなくなってしまう。
ハイデガーは問う。
「計画がメインなのか、実践がメインなのか」
と。
計画がメインでは、生きることに真剣でなくなってしまうのだ。
正しいことを直接掴もうとする学びは、多くの哲学によって否定されている。だが、苦悩の渦に飛び込むことは奨励される。
本来の自分へ至ろうとする者は、腹を括り苦悩の渦に飛び込めばいい。
作り出すのでも、広めるのでも、好きになるのでもないとき、
内なる存在には何ができるのか。
ただ隣にいることだけが残される。
なにもせず傍にいると、彼女を明瞭に見つめられる。
人間存在は慈悲だ。
見つめることが人生を決定づける。
隣人を愛する者、聖者へ。
師匠の橘川幸夫が 7月13日のニュースレターで、こう語った。
「最近、10年ぶり、20年ぶりの人から連絡があって、ランチなどしてます」
「時間って面白い」
「人をデザインするクリエイターですね」
時間を自分自身のデザイナーにする。そんな時間は計画的な時間にはない。苦難の渦に飛び込み、夢中になった刹那の連鎖に立ち現れる。
ホームズが『赤毛連盟』で述べた言葉で、論を括ろう。
奇妙な出来事や異常事態に出会いたいなら、人生の渦に飛び込め。
どんな想像力も及ばない冒険で溢れている。

お読みくださいまして、誠にありがとうございます!
めっちゃ嬉しいです😃
起業家研究所・学習塾omiiko 代表 松井勇人(まつい はやと)

下のリンクで拙著の前書きを全文公開させていただきました。
あなたの墓標には何を刻みたいですか。
「死」があなたを目覚めさせる。
そんな主題。是非ぜひお読みくださいませm(_ _)m

どん底からの復活を描いた書籍『逆転人生』。
大河内は中学の時からの親友で、中二の時に俺が陸上部全員から無視された時「もう松井を無視するのはやめた」と、皆の前で庇ってくれた恩人である。
5名の仲間の分も、下のリンクより少しづつ公開させていただきます。
是非お読みくださいませ(^○^)

こちらが処女作です。
テーマは、、、
トラウマを力に変える起業論
起業家はトラウマに陥りやすい人種です。
トラウマから立ち上がるとき、自らがせねばならない仕事に目覚め、それを種に起業します。
起業論の専門用語でエピファニーと呼ばれるもの。エピファニーの起こし方を、14歳にも分かるよう詳述させて頂きました。
書籍紹介動画ですm(_ _)m
追記:ハイデガーがナチスに加担したことについて。
ハイデガーは、"hurly-burly"を説いたウィトゲンシュタインよりは合理的でした。人が判断を下すための何らかの型があると考え、明らかにするために『存在と時間』を著しました。
そんなある種の権威主義が、ハイデガーを合理主義の権化である全体主義に加わらせたと、個人的には感じます。
間違いを犯したとしても、彼の論は傾聴に値すると確信していますけれども。
サポートありがとうございます!とっても嬉しいです(^▽^)/
