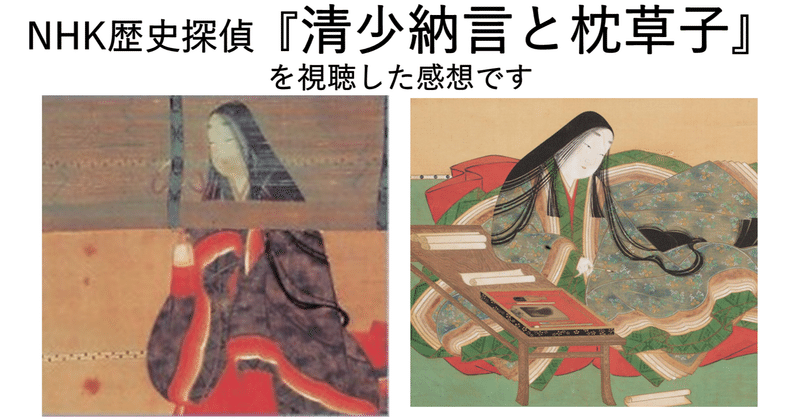
【感想】NHK 歴史探偵「清少納言と枕草子」を視聴しました
2024年5月15日(水)22:00~22:45 歴史探偵「清少納言と枕草子」を視聴しました。
<NHKのあらすじ>
光る君へで注目の清少納言と枕草子。春はあけぼのだけじゃない!
その先に記された秘密のメッセージを調査。
紫式部が清少納言に向けた痛烈な批判!?
平安女子の深い物語。
■プロローグ
●スタジオで
今日は、清少納言と枕草子です。
清少納言のプロフィール
・名前:清少納言(清原氏+少納言)
・職業:藤原定子の女房
・代表作:枕草子
春はあけぼの
実際どんな季節なのでしょうか?
■春はあけぼの
●相愛大学(大阪)春曙文庫
・鈴木徳男さん(相愛大学)
『弥富本』
藤原定家が鎌倉時代に写したものが元になっています。
原文に最も近いとされ、教科書にも採用されています。
『枕草子』「嫁入本」
中にはあの有名な言葉が。
春はあけぼのやうやう白くなりゆく山ぎわすこしあかりて
むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる
実際に「春はあけぼの」はどんな景色だったのでしょうか?
宮中からみたものと考えられます。
●登華殿
清少納言が仕えた定子の住まいです。
そこから眺めた京都東山の景色がそれに当たるだろうと考えられます。
●京都御苑
・梅林秀行さん(京都ノートルダム女子大学)
平安時代はここから西に約2km離れた場所に登華殿がありました。
「平安宮内裏内郭回廊跡」
9年前の発掘調査で、柱の痕跡が見つかり、ここに登華殿があったことが確定しました。
東の方角は遮られています。
そこで向かったのは船岡山
・吉村晋弥さん(気象予報士)
『枕草子』にも「岡はふなをか」とあります。
いい眺めです。
ここは建勲神社の境内です。
左に比叡山、右に大文字山
あけぼのは、山の稜線がうっすら見えてくる時間帯で、航海薄明です。
日の出直前町が明るくなるのが常用薄明です。
航海薄明は5時23分
常用薄明は5時52分の30分が勝負です。
●3月8日撮影当日
朝は晴れ出次第に曇る予報、春はあけぼのには良い条件です。
5時23分航海薄明
雲がたなびいています。
空の青に朝日の赤みが混ざり、紫色になりました。
●スタジオで
完璧な春はあけぼのを撮影しました。
佐藤所長「THE春はあけぼのだね」
河合先生「それまでは春といえば桜、梅、うぐいしでしたので、清少納言のセンスです」
枕草子の内容まとめ
①日記(宮中での出来事)
②テーマ(「かわいらしいもの」など)
③エッセー(自然や人間について)
河合先生「順番がばらばらで、晩年のことがはじめに出てきたり極めて珍しい形の本でした」
枕草子に清少納言の秘められた深い目的は?
■枕草子の深い目的
●滋賀大学データサイエンス学部
・佐藤健一さん(滋賀大学)
枕草子の10万字を解析、どのような単語が多く使われているのか解析しました。
ワードクラウド:出現頻度の高い言葉を視覚化するシステム
・赤間恵都子さん(十文字学園女子大学)
形容詞に注目しています。
平安の女性たちの心情や性格の違いがわかるといいなと思いました。
さらに、特別な舞台、VR空間です。
●バーチャル空間
ポジティブな形容詞は、ゆかし、をかし、めでたし
ネガティブな形容詞は、あさまし、にくし、心もとなし
好き嫌いをはっきり言う清少納言だとわかります。
清少納言が枕草子を書いた目的がわかります。
をかしを見てみましょう。
■をかし
定子の兄の藤原伊周が訪ねてきました。
雪がとてもすてき(をかし)
伊周様が雪に映えて非常にすてき(をかし)
それ以上に素敵だったのが2人のやり取りでした。
雪で「道もなし」と思ったのにどうしていらっしゃったのですか?
これは有名な和歌「山里は雪降り積みて道もなし今日来む人をあはれとは見む」
の前半を引用した問いかけでした。
それに気づいた伊周は、「あはれ」と思って下さると思いまして
先程の歌の後半の、こんな日に来る人こそあはれ=真心があるのですという意味を懸けた言葉でした。
清少納言はふたりの教養とその機転に感激します。
「定子後宮をアピールしています」
■めでたし
大層すばらしい、非常に立派だという最高の褒め言葉です。
めでたいが出てくるのはこの場面。
中宮様は紅梅色のお召し物を紅の打衣の上に重ねていらっしゃる、大層すばらしい(いとめでたし)
どのような衣装を着ていたのでしょうか?
・野呂佳代さん
これが十二単です。
・岡本和彦さん(風俗博物館)
試着させてもらいました。
12枚ではなく、9枚前後が一般的です。
17kg、実際に歩いてみると、歩くのが難しいです。
色の組み合わせ、「かさね」といいます。
例えば紅梅色を使ったかさねです。
つぼみからだんだん咲いてくるグラデーションです。
他にも、袖口からちらっと見える指先が薄紅梅色に輝いて見えたというを「限りなくめでたし」と表現しています。
枕草子を書いたのは定子を褒めるということにあったと思えます。
●スタジオで
佐藤所長「定子を褒め称えるために枕草子を書いた」
河合先生「サロンのようなとことで、定子のすばらしさを書かずにはいられなかったでしょう」
河合先生「主人というより恩人という信頼関係でした」
”春はあけぼの”の描写が、定子を表したのではないかと指摘されています。
河合先生「紫雲は天皇や中宮を表していて定子を暗示していて明るく照らす」
紫式部
二人の仲ってどうだったのでしょうか?
■意外なコメント
●『紫式部日記』
「寒々とした状況の中でも『あはれ』とか『をかし』とか感動ばかりしてその内容はうそっぽい」
・山本淳子さん(京都先端科学大学)
清少納言の漢文のレベルは低いとか、なれの果てを転落と決めつける恐ろしい言葉で終わっています。
なぜ嘘つき呼ばわりするほど激しく批判したのでしょうか。
●斎宮歴史博物館(三重県)
藤原実資の日記『小右記』
・笹田遥子さん
「4月11日に入道関白殿昨夜の亥の時、入滅と云々」
藤原定子の父親の関白・藤原道隆が昨夜亡くなったことが書かれています。
さらに翌年、伊周が事件を起こし、大宰府に左遷されました。
後ろ盾を失った定子は宮中を出て、住まいを転々とします。
・梅林さん
平生昌が住んでいた邸です。
格式の低い板門屋だったのです。
中宮なので、四つ足門で迎えるのが通例でした。
小右記には板門屋を通るなど前代未聞と書かれています。
枕草子には定子の没落について記されていません。
■AIで分析
時期ごとに使う言葉が変わっています。
「めでたし」が小さくなり、「をかし」が使われるようになります。
をかしの使い方がこの頃から大きく変わります。
訪問客が手入れの行き届かない庭をみて、
「なぜこんなに草がしげり放題なのですか?刈り取らせたらよろしいでしょう」
すると定子は女房にこう答えさせます。
「葉に降りる露を見たいので刈らずにそのままにしているのですよ」
どんな状況でも風流を楽しむ定子をすてきだ(をかし)と思いました。
平生昌の訛を清少納言がからかったときは、
「あの人のことを笑わないほうがいいわ。真面目な方なのですから」
これに対し清少納言は、「気の毒に思っていらっしゃるのがすてき(をかし)」優しさを褒め称えました。
その後、定子を再評価する声が高まります。
そこで書かれたのが紫式部日記です。
紫式部は定子のつらさに触れない清少納言を現実的ではない、強がっているだけと批判したのです。
しかしそこにはもう一つ別の感情もありました。
・山本淳子さん
「貴族たちに強く働きかけて貴族たちが定子を懐かしむ、そのことが悔しかったんじゃないかと思います」
●スタジオで
佐藤所長「嫉妬の可能性はありますよね」
宮仕えした時期が5年ずれていたので対面したことはなかった考えられています。
河合先生「紫式部が仕えていたのは彰子で、道長の娘で、この頃定子は亡くなっていて、ところが彰子のサロンより、昔の定子のサロンのほうがすばらしかったと評価されています」
河合先生「晩年は京都の東山に住んで定子の菩提を弔いながら暮らしたのではないかと考えられています」
ーーーおわりーーー
次回は「首里城と琉球王国」5月22日(水)22時放送です。
■感想
なるほど、紫式部と清少納言は嫉妬があったというのは面白いです。
それに、面と向かったことはなかったというのも初めて知りました。
というか、文章で批判し合うということは、そうなんだろうねとは思いました。
「光る君へ」では友達のように描かれています(笑)
『枕草子』は、鴨長明の『方丈記』、吉田兼好の『徒然草』と並んで日本三大随筆と称されています。
一文章が比較的短く読みやすいらしいので、一度読んでみたいです。
ただし、定子後宮の記録なので、御用作家による称賛物語であることは確かで、そこはすこし割り引いて読む必要はありそうです。
それに対し、源氏物語はとても紫式部という女性が一人で書いたと思えない大長編物語。
おそらく為時とかとの共同作業でできたのでしょう。
そんな違いもあって面白いです。
https://www.nukumori1.com/murasakishikibu_genjimoongatari/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
