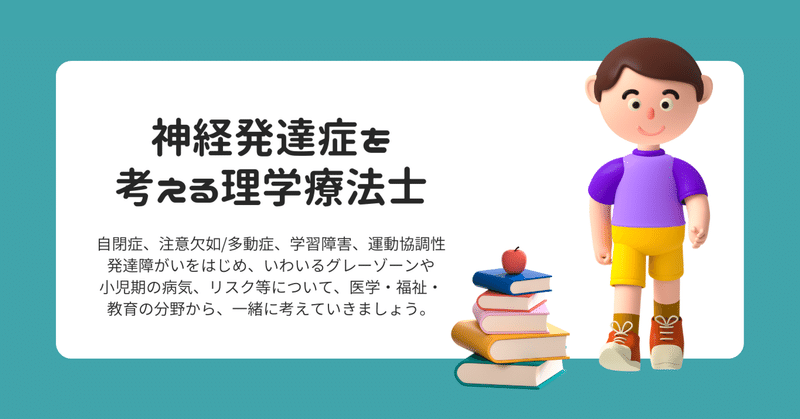
不安の正体
はじめに
不安という感情はどこからやってくるのでしょう。
漠然と、何が不安なのかもわからないけれどやってくる、不安。
その不安の正体を脳科学の視点から、探っていきましょう。
脳の三層構造

出典:大脳基底核の機能;パーキンソン病との関連において
旭川医科大学 生理学第二講座 高草木 薫
ポール・マクリーンという脳進化学者さんが考えた、脳の三層構造、または脳の三位一体仮説と呼ばれるものがあります。
人間の脳は、
【爬虫類脳】
生命維持のための欲求、反射的行動、身体反応としての脳
【旧哺乳類脳】
感情や情動によって社会とのつながりを示す脳
【新哺乳類脳・人間脳】
思考や論理、理性によって社会生活と人間関係を発展させる脳
の3つに分類され、それぞれ爬虫類脳は脳幹に相当し、旧哺乳類脳は大脳辺縁系に相当し、人間脳は大脳皮質、とりわけ前頭葉に相当すると考えられています。
爬虫類脳:身体反応
爬虫類は身の危険を感じた時、「こわっ」というような感情や、言葉をもって行動を選択するわけではなく、例えば逃げたり、身体を固めたり、丸めたり、噛みついたりするような身体の反応的行動をとります。
不安を感じた時、わたしたちの身体には変化が起こります。
たとえば、動機、息切れ、めまい、頬の紅潮、緊張など様々です。
この身体の反応は、爬虫類脳が反応しているのだと考えられます。
人間も、赤ちゃんの時にはこの爬虫類脳が主体となって働きます。
おなかがすいた、という本能的な欲求に対して泣く、という反応を取ります。
旧哺乳類脳:感情・気持ち
哺乳類の脳は、ある程度の情動を感じ取っているとされます。
猫や犬などに代表される哺乳類は、同種または家族に対しての愛情(または愛着)という感情を示し、哺乳類としての社会を形成しています。
不安、恐れや心配といった気持ちや感情、心の中でもやっとした何か漠然とした灰色の雲のようなものは、この旧哺乳類脳で感じていると考えられます。
ある程度赤ちゃんが世界に慣れてくると、お母さんの見えない不安から、泣くという行動を選択したりするようになってきます。
爬虫類脳の本能的欲求のみならず、感情によっても行動を選択するように成長していきます。
人間脳:考え・理性
爬虫類や哺乳類と明らかに人間が違うところは、大脳新皮質、とりわけ前頭葉の発達領域が他の哺乳類と比べて圧倒的に大きいところです。

前頭葉は、大脳の前側にある部分で、頭頂葉との境目の部分には運動をつかさどる部分もありますが、前頭葉の前側の部分は前頭前野と呼ばれ、人間で特に発達している部分です。
前頭前野では、理論的にものごとを考えたり、行動を計画したりする働きを持っています。
そして何より重要なのが、背外側前頭前野(DLPFC)と呼ばれる部分です。

これは以前、うつ病などのテーマでテレビなどにも取り上げられたことがあるので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
この背外側前頭前野は、大脳辺縁系の過剰な働きを抑制する力を持っています。
つまり、不安な感情を抑制し、軽減してくれる脳の場所ということです。
この力は、前頭葉の論理的な思考、考えなどによって強化されます。
不安に対する認知行動療法の根拠
ラベリング
認知行動療法では、不安な感情に対して、その気持ちは”不安”という感情だというように名前付け(ラベリング)をする作業から始めていきます。
これは、旧哺乳類脳の大脳辺縁系に対して、灰色のもやの正体がなんであるか、ということを頭で認識させることで、背外側前頭前野の働きを強め、不安の感情を抑えることができるようになるためだと考えられます。
身体反応
また、身体の反応にも着目します。
不安な気持ちを感じた時、身体はどのように反応しているかを見つめる作業は、爬虫類脳である脳幹レベルでどのような反射・反応が起こっているのかを考えることになります。
旧哺乳類脳の大脳辺縁系で不安を感じる前に、この爬虫類脳が反応することもあります。
特段不安な気持ちはないと思うのに、なぜだかめまいがするとか、胸がドキドキする、というような状態です。
そんな時、人間脳では「身体反応として、不安のサインが出ている」と気づき、認識することによって、早めに不安に対して対応するような行動を計画し、選択することも可能になります。
気持ちを言葉にして出す
そして何より強力なのは、気持ちを言葉にして出すことです。
不安なことを誰かに相談したり、聞いてもらったり、しゃべるだけで脳の前頭前野が活性化します。
脳の役割は、面白いくらいに縦割りになっています。
脳幹・脊髄より大脳辺縁系が強く、大脳辺縁系よりも大脳皮質、前頭葉の方が強い力を持っていて、下の脳をコントロールしています。
そして、脳は全体で働きのバランスをとっています。
一方が働くと、一方は下がるというような具合です。
これは左右の半球間でよく見られる現象で、右手を主に使っているときには左手の脳活動は低下する、という半球間抑制理論とも呼ばれます。
つまり、脳の前頭葉が働きを強めると、不安な感情を感じ取る大脳辺縁系や、身体反応を引き起こす脳幹の働きが弱まります。
この作用により、おしゃべりをしているとスーッと、不安な気持ちや身体反応が徐々に落ち着きを取り戻していきます。
大脳辺縁系や脳幹が力を持つと…
ここで、不安な気持ちや身体反応に目を向けすぎてしまうと、逆の現象が起きます。
前頭前野の背外側前頭前野の力は強力で、ある程度の感情は抑え込んでしまいますが、それがあまりにも長期にわたると、背外側前頭前野が疲弊します。疲れてしまい、力が弱まってしまうのです。
そうなると、大脳辺縁系や脳幹のやりたい放題。
不安な気持ちや、めまいなどの身体反応に埋め尽くされてしまいます。
そうなる前に、不安な気持ちや身体反応を、言葉にして出す練習をしていきましょう。
安心したい気持ちが、不安を産む
不安にさいなまれていると、どうしても安心したいという気持ちが強くなり、不安を回避したり、どのようにすれば安心できるか、と先のことばかりを考えてしまいがちです。
しかし、どんなに対策を打っても、究極の安心というものは存在しません。
安心したいと思う気持ちが、不安を産みだしているのかもしれないということに気づくことも、重要なことだと思います。
そんな時には、
「いま、ここ」を思い出してみてください。
そして、たくさんおしゃべりをして、気持ちや身体反応に支配されないようにしていきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

